「縁の下の力持ち」の意味(語源由来・類義語)

【ことわざ】
縁の下の力持ち
【読み方】
えんのしたのちからもち
【意味】
目立たないところで、人のために力をつくすこと。また、その人をさす。


スポットライト浴びてないけど、ちゃんと評価されるべき人たちのことやな、これは。
【語源由来】
縁側の下にある土台の石は、人の目につかないところで、柱を支えていることから。
【類義語】
・縁の下の掃除番
・縁の下の掃除人
・縁の下の舞
・陰の松の奉公
・簀の子の下の舞
・内助の功
・闇の独り舞い
「縁の下の力持ち」の解説

「縁の下の力持ち」っていう言葉は、見えないところでこっそりと大事な仕事をしている人たちを表すんだよ。
その元となったのが「縁の下の舞」なんだ。これは、大阪にある四天王寺っていうお寺で行われる、お経を読むための祭りで踊られる舞のことなんだよ。
この「縁の下の舞」、昔は誰にも見られずに踊られていたんだよ。演者の人たちは、誰も見ていないところで練習を重ねて、祭りのために踊りを捧げていたんだ。
このように誰も見ていないところで頑張る人たちを、「縁の下の舞」という言葉で表現するようになったんだよ。
でも、大阪周辺ではこの「縁の下の舞」の話が知られていたけど、他の地域ではあまり知られていなかったから、言葉が変わって「縁の下の力持ち」になったんだよ。
「縁の下の舞」の話は、大阪周辺で遊ばれていた、「上方いろはかるた」にもあるんだよ。
「縁の下の力持ち」の使い方




「縁の下の力持ち」の例文

- ともこちゃんは、いつも縁の下の力持ちとして、クラスのみんなが困っているときに手助けしてくれる。
- きれいな花は人の心をなごませるが、その下の根がなければ、きれいな花はさかない。根はまさに縁の下の力持ちである。
- どんなに能力の高い人気のあるスポーツ選手でも、縁の下の力持ちという存在がいなければ、その力をフルに発揮することはできないだろう。
- 我が社がここまで成長できたのは、優秀な人材があってこそだが、それ以上に、縁の下の力持ちとなり陰で支えてくれた多くの社員がいたからこそだ。
- 運動会などの学校行事も、お父さんやお母さんたちがお手伝いしてくれているよ。縁の下の力持ちだね。
- もうすぐ中学校の卒業式だ。こうやって無事卒業することができるのも、毎日お弁当を作ってくれた、縁の下の力持ちのお母さんのおかげだ。
- 彼は会社の縁の下の力持ちで、みんなが気づかないところで支えてくれている。
- 長い間、売れない小説家を続けていましたが、今回直木賞を受賞できたことは、縁の下の力持ちとなり家庭を支えてくれた妻の存在があったからです。
- 僕の奥さんは縁の下の力持ちだ。いつも僕を支えてくれる。
- 彼は会議ではあまり目立たないが、プロジェクトの成功のために裏でコツコツとデータ分析を行っている。まさに縁の下の力持ちだ。
「縁の下の力持ち」の文学作品などの用例
けれども私は、いちどだって、あの蔓バラ模様の考案者については、思ってみたことなかった。ずいぶん、うっかり者のようでございますが、けれども、それは私だけでなく、世間のひと皆、新聞の美しい広告を見ても、その図案工を思い尋ねることなど無いでしょう。図案工なんて、ほんとうに縁の下の力持ちみたいなものですのね。(太宰治の皮膚と心より)
「縁の下の力持ち」を英語で言うと?

「縁の下の力持ち」の英語表現をご紹介します。
※英語の声:音読さん
unsung hero
- 直訳:歌われない英雄
- 意味:すばらしい偉業を達成したのに、気づかれず賞賛されない人のこと。
behind-the-scenes support
- 直訳:シーンの後ろのサポート
- 意味:裏舞台で支えている人々のこと。
- 用語:behind:〜の後ろに / scene:現場、シーン
inconspicuous yet vital role
- 直訳:目立たないけど必要な役割
- 意味:目立たないけどなくてはならない存在のこと
- 用語:inconspicuous:目立たない / vital:必要な、欠かせない
thankless job
- 直訳:感謝されない仕事
backseat player
- 直訳:後部座席の選手

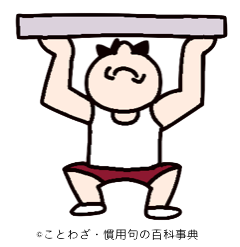







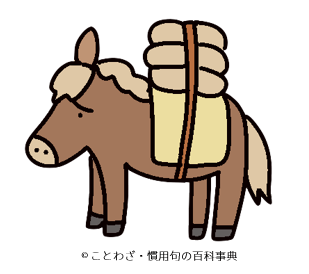


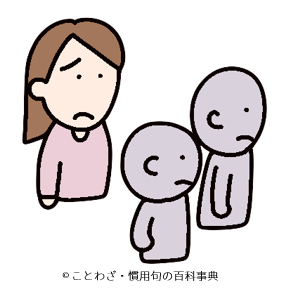









表には出てこないけれど、その人たちがいるからこそ物事がうまくいく、ということを表しているんだ。