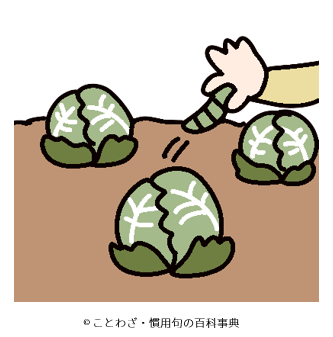「殷鑑遠からず」の意味(出典・類義語・英語訳)

殷鑑遠からず
【読み方】
いんかんとおからず
【意味】
失敗の先例は、遠くに求めなくてもすぐ目の前にある。


前の時代にあった失敗とか、間違いとかから学んで、自分たちは同じミスを繰り返さんように気をつければいいんやな。こういうことは身の回りにたくさんあるし、そこから学ぶことが大切ってことを教えてくれるんやな。
【出典】
「詩経・大雅・蕩」から。殷王朝は前代の夏が滅亡したことを鑑として戒めよの意。
【類義語】
・人の振り見て我が振り直せ
・人を以て鑑と為せ
・上手は下手の手本、下手は上手の手本
・他山の石
【英語訳】
Other’s failure is seen to make one’s warning.
「殷鑑遠からず」の解説

「殷鑑遠からず」っていうことわざは、学び取るべき教訓や注意すべき例が、とても遠くに求める必要はなく、すぐ近くに存在するという意味なんだよ。
たとえて言うとね、ちょっと失敗しちゃった友達の経験から学んだり、お兄ちゃんやお姉ちゃんが間違えたことから学んだりするようなことだよ。それは、遠くの過去や他の人の失敗から学ぶよりも、自分の身近な場所で起こった出来事から学ぶことの大切さを教えてくれるんだ。
このことわざの「殷」というのは古代の国の名前で、「鑑」は手本や教訓のことを意味しているんだ。「遠からず」は遠くない、つまり身近なところにあるという意味だよ。だから、「殷鑑遠からず」は「教訓は身近にある」という意味になるんだ。
つまり、このことわざは、「学ぶべき教訓や警戒すべき事例は遠くに求める必要はなく、身近なところに存在する」ということを教えているんだね。
「殷鑑遠からず」の使い方




「殷鑑遠からず」の例文

- そんなに昔の話を思い出さなくても、隣の会社が倒産したことは知っているだろう。殷鑑遠からずだよ。
- 殷鑑遠からずというけれど、大昔のことを持ち出さなくても、そばにいい例があるじゃないか。
- おばあちゃんは自分の失敗のことを教えてくれるけれど、私にとっては母を見ているとよくわかる。殷鑑遠からずだからね。
「殷鑑遠からずというように、あの会社は通販で売り上げを伸ばしているじゃないか。」と使うのは誤り。
まとめ
できるならば失敗はしたくないですね。
その為には、殷鑑遠からずというように、前例からしっかり学ぶことも必要ですね。