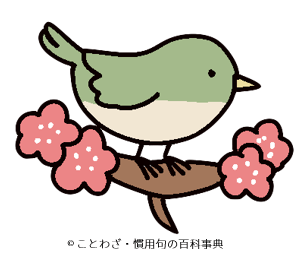「梅に鶯」の意味(語源由来・類義語・英語訳)

梅に鶯
【読み方】
うめにうぐいす
【意味】
とりあせわがよいこと。


梅と鶯みたいに、互いに引き立て合って、一緒にいると更に良さが増すってな感じやな。これは、相性の良さやバランスの取れた関係の大切さを教えてくれる言葉やな。
梅の花が咲く枝に鶯がとまってさえずるさまが、ぴたりと合っていることから。
【類義語】
・獅子に牡丹(ししにぼたん)
・竹に雀(たけにすずめ)
・波に千鳥(なみにちどり)
・牡丹に唐獅子(ぼたんにからじし)
・松に鶴(まつにつる)
・紅葉に鹿(もみじにしか)
【英語訳】
直訳では Plum blossoms and a Japanese bush warbler.
ただし、これだけではネイティブには理解されないでしょう。例えば It is one of the best collaboration and typical spring scene of Japan. などとひとこと説明が必要です。
「梅に鶯」の解説

「梅に鶯」っていうことわざはね、一緒にするとすごく合う、とってもよくマッチする二つのものを例えているんだよ。
例えばね、おいしいホットドッグにケチャップがついていたり、夏の日に冷たいアイスクリームを食べたり、そういう組み合わせがとっても良いと感じるときにこのことわざを使うんだ。
「梅に鶯」は、日本の早春によく見られる風景で、鶯が梅の花を咲かせる木に止まる光景を指しているんだよ。これがとても美しくて、自然の中で完璧にマッチしているから、よく合うものを例えるときに使われるんだね。だから、「梅に鶯」っていうことわざは、「とてもよく合う二つのもの」っていう意味があるんだよ。
「梅に鶯」の使い方




「梅に鶯」の例文

- 七五三のお参りですね。季節は違うけど梅に鶯、二人の着物姿がよく合っていますね。
- こんなに気が合う仲だとは思っていませんでした。今では梅に鶯のようです。
- 映像と音楽が梅に鶯のようにコラボしていて、どちらが欠けてもこの作品は成り立たなかったでしょう。
まとめ
梅に鶯といえば、思い出すのが花札です。松に鶴、紅葉に鹿も札の一枚にあります。いまではファミコンやスーパーマリオで有名な任天堂は、昭和の時代には花札といえば任天堂と呼ばれるほど有名な会社でした。花札のもとはポルトガルのカードゲームで、地方札として全国に普及します。主に賭博に使用されたことから、江戸時代後半から明治にかけて禁制となり、その中で花札が考案されたといわれていますが、花札もすぐに禁制となります。明治初期に解禁となり、花札は課税されるようになりますが昭和の中頃までは大流行しました。歴史的にみて大人の遊びですね。今では花札で遊ぶ人はほとんどみかけなくなりました。