「人口に膾炙する」の意味(語源由来・英語訳)
【ことわざ】
人口に膾炙する
【読み方】
じんこうにかいしゃする
【意味】
世の中に広く知れ渡っていること、評判になっていること。プラスのニュアンスで使われることが多い。


何かが大衆に受け入れられて、みんなに知られるってことは、それだけ影響力があるってことやね。こんな言葉もあるんやな。
【語源・由来】
膾炙の「膾」(なます)とは、魚や獣の生肉を細かく切って酢に漬けた料理。「炙」(あぶり)は火であぶった肉のこと。いずれも美味で万人に好まれるところから、この「人口に膾炙する」という言い回しが生まれた。唐の「林嵩」「周朴詩集序」の「一篇一詠、人口に膾炙す」に基づく。
【英語訳】
to be on everyone’s lips
to be well-known
to be famous
「人口に膾炙する」の解説

「人口に膾炙する」という表現は、人々の間で広く話題になり、もてはやされることを意味しているんだよ。この言葉は、「膾(なます)」と「炙(あぶりにく)」という二つの料理から来ているんだ。
「膾」とは、切り刻んだ生魚や生肉のことで、日本のなますや刺身のようなものを指すんだね。一方、「炙」は、火で焼いたり炙ったりした肉のこと。これらの料理は昔から多くの人に好まれ、広く人気があるものだったんだ。
「人口に膾炙する」という表現は、膾や炙が多くの人に受け入れられるように、何かが人々の間で広く受け入れられ、話題となる様子を比喩的に表しているんだよ。つまり、この言葉は、ある事柄やトピックが非常に人気があり、広く知られている状態を表現するのに使われるんだね。
たとえば、ある映画や本、出来事が非常に話題になり、多くの人々に注目されている時に、「それは人口に膾炙している」と表現することができるよ。このように、人々の間で広く知れ渡り、話題に上ることを表す表現なんだ。
「人口に膾炙する」の使い方




「人口に膾炙する」の例文

- 今では、その名は総理大臣より人口に膾炙しているのである。
- 彼は、人口に膾炙した面白い話を集めて日本中を旅して研究している。
- 日本食を口にするアメリカ人は、邪道から本格まで、種々であるが人口に膾炙し始めていることは否定できない。
- 「神ってる」という言葉が、昨年、人口に膾炙して、広く使われるようになった。
- 有名な作家が会見で使用した言葉が、人口に膾炙した。
「人口に膾炙する」の文学作品などの用例
秦の始皇が不老の藥を求めた話はもうあまりに人口に膾炙しているが、この不老とは単に長生きをすると云う意味でなしに、老いてなお色欲の享楽に堪え得る旺盛な体力を求めるのが根本である事は云うまでもあるまい。(南部修太朗の阿片の味より)
まとめ
人口に膾炙すると言えば、最も人口に膾炙した本とは何だろう。夏目漱石でいえば「吾輩は猫である」か「こころ」、芥川龍之介でいえば教科書にも載っている「羅生門」だろうか。それとも、本というより巻物だが「紫式部」の「源氏物語」か。今でいう、口コミで評判が広まり、みんなが好んで読み世に残る。こうして三世代(おばあちゃんから孫まで)残った本は本物だというが、そういう人口に膾炙し続ける本がこれからもどんどん出版されるといい。











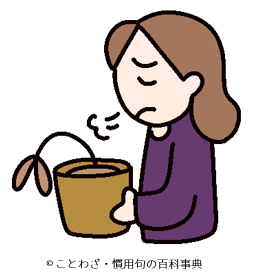
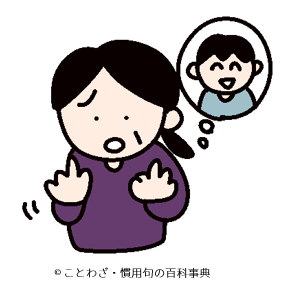

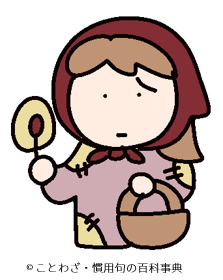








この言葉は、ある事物や人物が広く人々に受け入れられ、知られるようになる状況を表しているんだね。