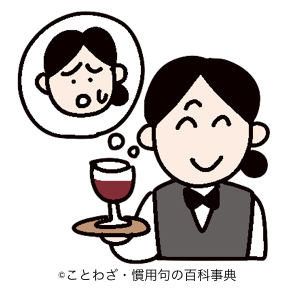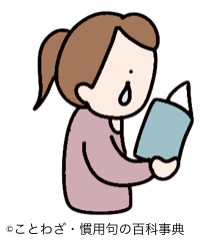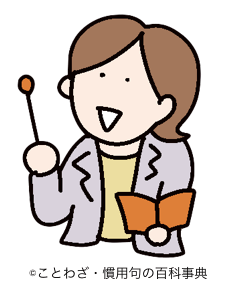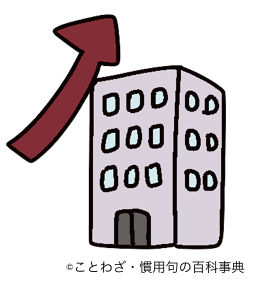「気骨が折れる」の意味(語源由来)

【慣用句】
気骨が折れる
【読み方】
きぼねがおれる
【意味】
いろいろと神経を使って、気疲れする。

「気骨が折れる」という表現は、たくさんのことを気にして精神的に疲れてしまう、つまり気疲れするという意味があるんだよ。

つまり、「いろんなことを気にしすぎて、頭がパンパンになる」ってことやな。
気を使いすぎて、精神的にへとへとになっちゃう状況を言うんやな。
【語源由来】
「気骨(きぼね)」が心づかい。気苦労という意味であることから。
「気骨」を「きこつ」と読むと、「信念を守りぬく強い意気」の意となる。したがって、「きこつがおれる」と読むのは誤り。
【スポンサーリンク】
「気骨が折れる」の解説
カンタン!解説

「気骨が折れる」っていう表現はね、いろんなことを気にかけたり、悩んだりして、心がすごく疲れてしまうことを言うんだよ。
「気骨」っていうのは、人に対する思いやりや、気遣い、あるいは心配事や気苦労のことなんだ。「折れる」っていうのは、困難なことに直面したり、苦労したりすることを指すよ。
たとえば、友達が悲しんでいるときに、どうやって励ますか、どんなことを言ったらいいかとずっと考えて、結局何も言えずに心配してしまったとか、テストでいい点を取りたくて、一生懸命に勉強したけど、なかなか思うようにいかないと感じて落ち込んでしまったとか、そういう時に「気骨が折れる」って言うんだよ。
つまり、「気骨が折れる」っていうのは、心配したり、気を使ったりして、心がすごく疲れてしまうときに使う言葉なんだよね。
「気骨が折れる」の使い方

今年の担任の先生は、神経質だから、気骨が折れるよ。

ああ、あの若い先生ね。

発言の一つ一つに気を付けないと、すぐ怒るんだ。

気骨が折れてクラス全体の成績が下がらなければいいけどね。
【スポンサーリンク】
「気骨が折れる」の例文

- 男も女も様々だったが、大抵、分別のある人たちで、古都の味をじっくりとたずねたいという客ばかりだったので気骨が折れたが、この仕事は性に合った。
- 久しぶりに休日は家でゆっくり過ごしたが、家の中をなごやかにするということは、気骨が折れる仕事だと思った。
- 大人数での食事は、愉しいテーブルになったが、慣れない人と食事をしたことで、自分で思うより気骨が折れたらしく、疲れが睡気を誘った。
- こんなところに橋を渡すなんて、危険であることは間違いないし、気骨が折れる仕事に違いない。
- こちらから何を言っても、すべて馬耳東風である、あんなひと相手では、あなたも気骨が折れることでしょう。