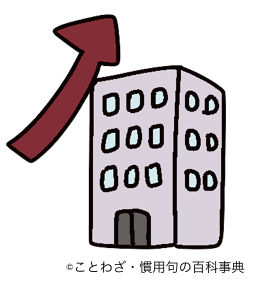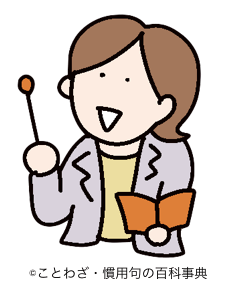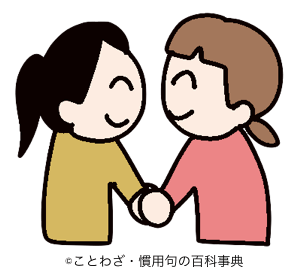「きまりが悪い」の意味(語源由来)

【慣用句】きまりが悪い
【読み方】
きまりがわるい
【意味】
他に対して面目が立たない。恥ずかしい。
きちんと整っていない。しまりがつかない。

「きまりが悪い」という表現は、自分が他人に対して恥ずかしい、または面目が立たない状況を指すんだよ。

つまり、「自分が恥ずかしい状況になってしまって、なんか顔が立たへん」ってことやな。
何かちょっとまずいことや失敗をして、他人の前で恥ずかしい思いをするんやな。
【語源由来】
「決まり」とは、動詞「決まる」の名詞形で、決着がつくこと、秩序の意味。それが「悪い」ということから、態度がきちんとしていなかったり、秩序が乱れていたりするため、他人に対して具合が悪く、面目が立たない、恥ずかしいという意味。
【スポンサーリンク】
「きまりが悪い」の解説
カンタン!解説

「きまりが悪い」っていう言葉は、ちょっと恥ずかしいなあ、みんなの前で顔が立たないなあ、と感じるときに使うんだよ。
例えば、学校で宿題を忘れて先生に注意されたとき、その場にいるみんなの前で恥ずかしいなあ、と思ったら、「きまりが悪い」って言うんだよ。これは、自分がちょっとした失敗をしたり、ちゃんとやるべきことをやってなかったりするときに使うんだね。
この言葉は、「決まらない」からきているんだ。「決まる」っていうのは、物事がうまくいく、きちんと整うという意味だよね。でも「決まらない」はその逆で、さらに「悪い」がついていることから、物事がうまくいかない、整わない状態を表すんだよ。
だから、自分が何か失敗をしたり、うまくいかない状況で恥ずかしいと感じるときに、「きまりが悪い」という言葉を使うんだね。
「きまりが悪い」の使い方

さっき、クラスで男子生徒が二人もめていたんだけど、クラスの生徒みんながシリアスな雰囲気で二人を見守っているときに、僕は急にしゃっくりが止まらなくなったんだ。

あら、それでどうなったの?

うん。雰囲気的にきまりが悪いし、でも、しゃっくりは止まらないし、あたふたしていたら、僕のことを笑う子が出てきて、喧嘩していた二人も馬鹿らしくなって、なんとなく解決したんだよ。

あらー、健太くんお手柄だったじゃない。
【スポンサーリンク】
「きまりが悪い」の例文

- 彼は、ほかの客たちの手前もあって、きまりが悪そうに、怒ったような声で言った。
- 恋人と一緒にいるところを生徒に見られてしまって、少々きまりが悪い思いをした。
- 自分ではない、同じ名字の人が呼ばれたのに返事をしてしまい、きまりが悪い思いをした。
- 実の息子から若い女性と歩いていたことを指摘され、さすがに父もきまりが悪かったようで、ごまかすように怒りの表情を作った。
- その女は、しきりに僕に話しかけるので、僕は少々きまりが悪くなって、急いでコーヒーを飲みこんでそこを出た。