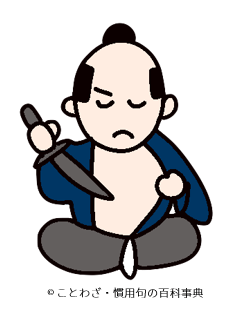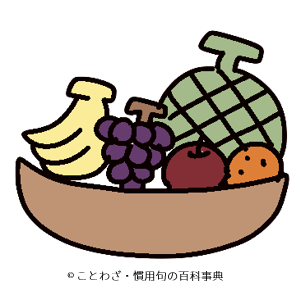「小田原評定」の意味(故事・英語)

【ことわざ】
小田原評定
「小田原評議」「小田原相談」「小田原談合」ともいう。
【読み方】
おだわらひょうじょう
【意味】
長引いてなかなか決定しない相談。
評定=相談。

「小田原評定」の意味は、長時間にわたって議論が続き、なかなか結論が出ない会議や話し合いを指す言葉だよ。

この表現は、話し合いがだらだらと長引き、決定事項についての合意が得られない状況を形容するのによく使われるんだ。
豊臣秀吉が小田原城を攻囲した時、小田原城内で北条氏直の腹心等の和戦の評定が長引いて決定しなかったことから。
【英語】
fruitless debate(実を結ばない討論、無益な討論)
【スポンサーリンク】
「小田原評定」の解説
カンタン!解説

「小田原評定」の由来は、日本の戦国時代に実際にあった出来事から来ているよ。
豊臣秀吉が小田原城を包囲していた時、城内で北条氏直と彼の側近たちがどうするべきかについての会議(評定)をしていたんだ。しかし、その会議はなかなか進まず、結論が出ないまま時間が過ぎていった。
そのため、「小田原評定」は長時間にわたって議論が続き、結論が出ない会議や話し合いを指す言葉となったんだよ。
「小田原評定」の使い方

明日の試合ではどうすれば勝てるのか、話し合いをしているんだ。

もう5時間も話し合っているようだけど。

これだけ人数がいて、長い時間をかけて話し合っているのに、ちっともいい作戦が浮かばないんだ。

そんな小田原評定をしていないで、練習したほうがいいかもしれないわ。
【スポンサーリンク】
「小田原評定」の例文

- 次の企画のアイディアを考えているけれど、会議は小田原評定になっている。
- これほど有能な人が集まっているのに、小田原評定をしていてはなんの足しにもならない。
- このまま小田原評定を続けていては、なにも決まらないじゃないか。
- 新商品について考えているけれど、小田原評定となっている。
「小田原評定」の文学作品などの用例
三時半に上井出を發する鐵道馬車に乘つて、四時四十分頃大宮町についた。蒸し暑い小さい車台の中でかんかん照りつける西日を受けながら、例の小田原評定をまた始めた。結局、大宮には登山客が雜沓するだらうから泊らないということだけをきめて、大宮から富士駅までの切符を買った。(野上豊一郎の湖水めぐりより)