「天下り」の意味

【慣用句】
天下り
【読み方】
あまくだり
【意味】
①天上界から地上界に降りること。
②官庁・上役などからの一方的な命令・おしつけ。
③高級官僚が退職後、勤務官庁と関連の深い民間企業や団体に優遇された条件で再就職すること。


ほうほう、色んな意味があるんやな。つまり、「天下り」は、一つは天から地に降りてきた人のこと、それから、上の人から押し付けられる命令のこと、それと、退職した偉い人が他のところでまた偉い地位に就くこと、の3つの意味があるんやな。
三者三様に使われるんやな。
【スポンサーリンク】
「天下り」の解説
カンタン!解説

「天下り」という表現は、「天下る」という言葉からきていて、神さまが天から人間の世界に降りてくることを指していたんだよ。これは、昔、奈良時代に使われてた言葉なんだ。
それが時代が進んで、明治時代になると「天下り」って言葉がちょっと意味が変わってきて、政府から民間へと一方的に命令が下されることを指すようになったんだ。それはつまり、天が政府のことを、地が民間のことを象徴していたからさ。
でも、それだけじゃなくて、さらに意味が進化して、今は「官僚が退職後に民間会社などの高い地位に就くこと」を意味するようになったんだ。つまり、政府の仕事を辞めた人が、普通の会社で大切なポジションをもらうことを指しているんだよ。
例えば、あるおじさんが長い間政府で働いて、退職した後に大きな会社の社長になるとき、そのおじさんは「天下り」したと言えるんだよ。
だから、「天下り」っていう言葉は、神さまが天から地上に降りてくることから始まったけど、今の時代に合わせて新しい意味で使われているんだよ。
「天下り」の使い方

塾の先生が、社会科の時事問題で、天下りの話をしていたけど、日本では多いんだね。

そうみたいね。高級官僚だった人が、退職してからも、民間企業に高い地位で再就職できるというのは、何かおかしくない?
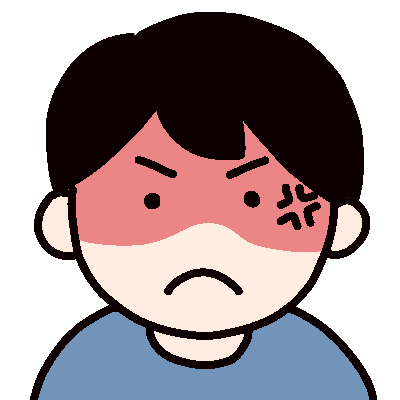
本当だよ。しかも、給料でも優遇されるというんだから。先生は、国会でも大きな問題になったと言っていたね。
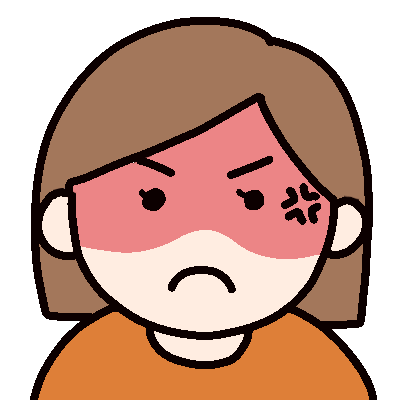
私は、いやだなー。受け入れる民間企業や団体も、何かプラスになるからというんでしょう。
【スポンサーリンク】
「天下り」の例文

- あの王子様は、貧しい土地に天下った天使である。
- 新聞は、天下り人事を大々的に取り上げている。
- 彼は、退職後、中央官庁から民間企業に天下りした。
- 公務員の天下りが、国民の批判にさらされています。
- ある省庁のOBは、天下りのあっせんをしたということで、国会で問題とされました。










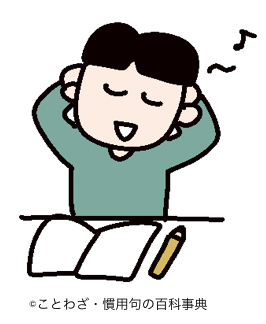

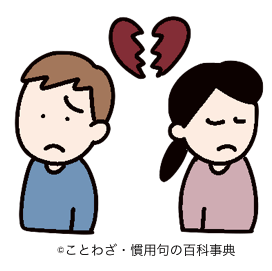



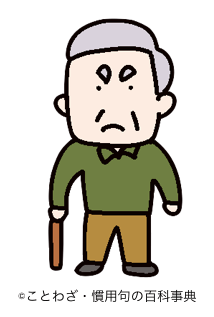





そして最後に、退職した高級官僚などが、外郭団体や関連の深い民間企業の地位に就くことを指す意味があるんだよ。