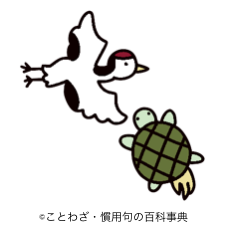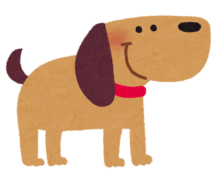「牛耳を執る」の意味(故事)

【慣用句】
牛耳を執る
【読み方】
ぎゅうじをとる
【意味】
ある団体や組織などの主導権を握る。

「牛耳を執る」ということわざは、団体や組織の中心となって、自分の意のままに物事を進める、つまりリーダーシップを取ることを指しているんだよ。

そやな、まるで牛の耳をつかんでどっちに進むかを決めるように、団体の方向性や決定を手中に持って、自分の思い通りに事を動かすってことやね。
要するに、大きな影響力を持ってるってわけやな。
「左伝哀公十七年」にある故事から。諸侯が同盟を結ぶ儀式で、盟主が牛の耳を割いて血を採り、これを順番にすすったということから。
【スポンサーリンク】
「牛耳を執る」の解説
カンタン!解説

「牛耳を執る」という言葉の由来は、昔の中国の習慣から来ているんだ。
昔の中国では、色々な国の王様たちが集まって、お互いを信じ合い、仲良くするために同盟を結ぶときに、特別な儀式をしていたんだ。その儀式では、牛の耳を切り、その血を飲むということをしていたよ。
そして、その牛の耳を切る役割を果たすのは、全ての国王の中で一番地位が高く、一番強い国の王様がやっていたんだ。だから、その強い王様が集団をリードする、つまり牛の耳を持つことが、「牛耳を執る」という言葉の由来となっているんだよ。これは団体や集団のリーダーになることを表しているんだ。
「牛耳を執る」の使い方

毎年、新しい学年になるたびに思うんだけど、なんでともこちゃんは学級委員にならないの?

えっ。私はそんな器じゃないわ。私は謙虚だから表舞台に出たくないわ。

ええっ。陰で牛耳を執ってクラスを操っているともこちゃんって、毎年恐れられているのに?
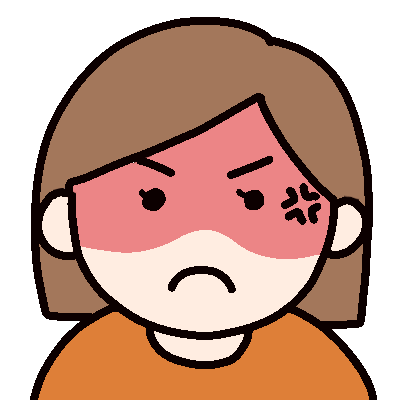
なんですって。そんなことを言われているの?あんなにみんなのために尽くしてきたのに、陰の番長呼ばわりだなんて。許さないぞー。
【スポンサーリンク】
「牛耳を執る」の例文

- 彼女は、夕方など、いつも商人の細君たちの輪に入って話しているが、大抵の場合、彼女がその雑談の牛耳を執っているらしいのである。
- この歴史研究会の牛耳を執っているのは、あなたが今、頼りなさそうとか儚げとか評した彼女です。
- 彼は、かつて、事業に失敗し、借金を抱えたこともあったが、今や同業者の間で牛耳を執るまでになった。
- 先生も君、あれでこの辺りじゃ、学者の牛耳を執ると言われて来た人ですよ。
- この部の部長は彼だが、実質この部の牛耳を執っているのは、マネージャー兼監督の彼女だ。
「牛耳を執る」の文学作品などの用例
そう云う次第だから創作上の話になると――と云うより文壇に関係した話になると、勢何時も我々の中では、久米が牛耳を執る形があった。(芥川龍之介のあの頃の自分の事より)