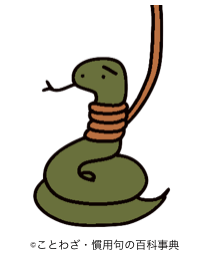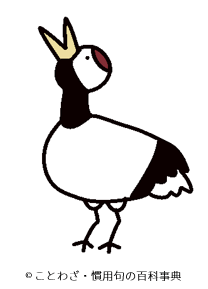「雀百まで踊り忘れず」の意味(語源由来・類義語・英語訳)

【ことわざ】
雀百まで踊り忘れず
【読み方】
すずめひゃくまでおどりわすれず
【意味】
子供のときに覚えた習慣やくせは、年を取っても直らないということ。


これは、若い時に学んだことの持続的な影響を示す言葉やわ。幼い頃に身につけた習慣や行動は、長く人生に影響を与えるってことやね。早いうちから良い習慣を身につける重要性を教えてくれるんやな。
【語源・由来】
雀は地面を歩く時に、ちょんちょんと踊りを踊るように飛び跳ねて歩く癖があり、その癖が死ぬまで抜けないように、幼い頃についた習慣は改まりにくいということから。とくに、若い頃に身についた道楽がいくつになってもやまないたとえにいう。日本の伝統芸能では、旋回運動を主体とすることを舞といい、跳躍運動を主体とすることを踊りという。ちょんちょんと、雀の飛び跳ねる動作は踊りということ。「上方いろはかるた」が由来。
【類義語】
・三つ子の魂百まで(みつごのたましいひゃくまで)
・頭禿げても浮気は止まぬ(あたまはげてもうわきはやまぬ)
【英語訳】
What is learned in the cradle is carried to the grave.
「雀百まで踊り忘れず」の解説

「雀百まで踊り忘れず」というのはね、雀が跳ねる動きをするのはその習性で、雀がどれだけ歳をとってもその動きを忘れないっていうことを表しているんだよ。
たとえば、子どもの頃にピアノを習ったり、サッカーをしたりすると、大人になってもそのスキルや楽しみ方を忘れないでいることが多いんだね。それが「雀百まで踊り忘れず」ってことなんだ。
このことわざは、子どもの頃に学んだことや習った習慣は、一生を通じて影響を与えるって教えてくれるんだよ。だから、幼い頃から良い習慣を身につけることが大切だっていうことを示しているんだね。
「雀百まで踊り忘れず」の使い方




「雀百まで踊り忘れず」の例文

- いい年をして、叔父はまだ女の尻を追いかけていると祖母が話していたけれど、雀百まで踊り忘れずというからね。
- 雀百まで踊り忘れずというが、小さいときに身につけたことは、大きくなってからも忘れないものだ。
- 小さい頃から朝が苦手だったという母は、今でも毎日起こされないと起きない。雀百まで踊り忘れずだ。
- 雀百まで踊り忘れずというが、あの年でまだギャンブラー気取りだよ。
【注意!】よい意味ではあまり使わない
「あのダンサーは、子供の頃からダンスが上手だったそうだ。雀百まで踊り忘れずだなぁ。」