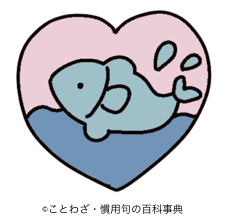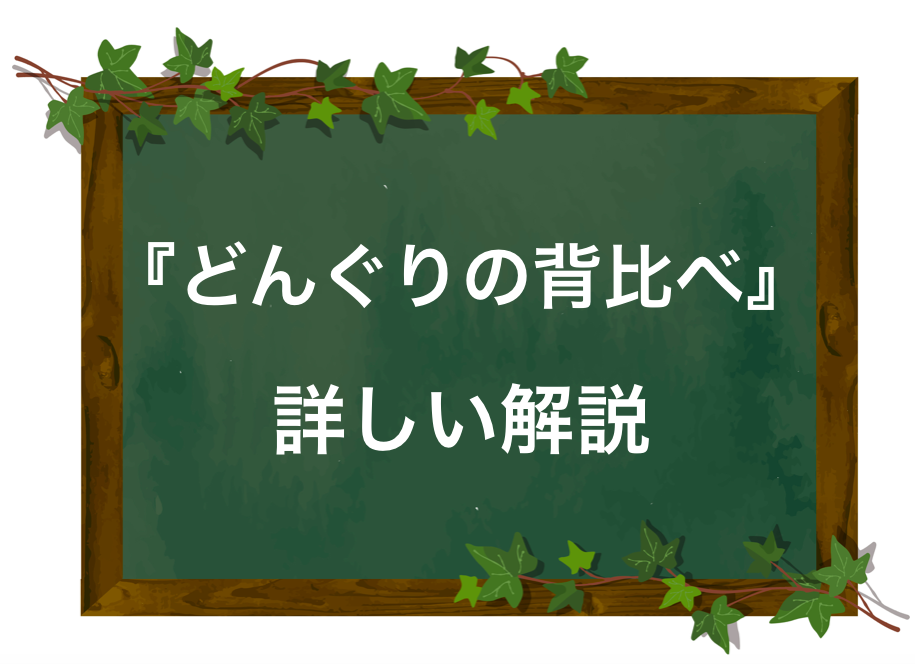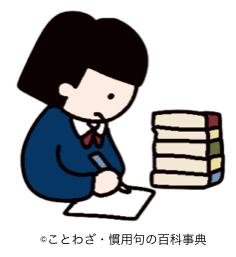【スポンサーリンク】
「か行」の小学校で習うことわざ

飼い犬に手を噛まれる(かいいぬにてをかまれる)
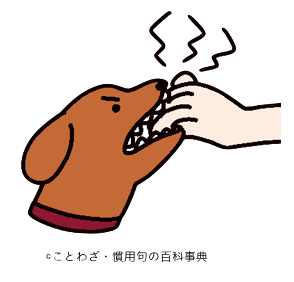
- 意味・教訓
信じていた人や、世話をしていた人から裏切られたり、ひどい仕打ちを受けたりすること。
人を信用することも大切だが、時には慎重になる必要があるという教え。 - 使用例
「ずっと面倒を見てきた後輩に悪口を言われるなんて、まさに飼い犬に手を噛まれるだよ。」
蛙の子は蛙(かえるのこはかえる)

- 意味・教訓
子どもは親に似るものであり、才能や性格、能力はそう簡単には変わらない。
親と子の関係を示すときや、平凡な親からは平凡な子が生まれるという意味で使われることが多い。 - 使用例
「彼のお父さんは運動音痴だから、彼が足が遅いのも納得だね。蛙の子は蛙だよ。」
蛙の面に水(かえるのつらにみず)

- 意味・教訓
どんなことを言われても、まったく気にせず平然としていること。
批判や恥をかかされても動じない様子を表す。 - 使用例
「彼に何を言っても全然気にしないね。まさに蛙の面に水だよ。」
学問に王道なし(がくもんにおうどうなし)
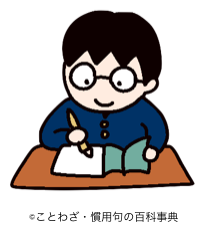
- 意味・教訓
学問を極めるには近道はなく、地道な努力と積み重ねが必要である。
一朝一夕で成果を得ようとせず、着実に学ぶことが大切だという教え。 - 使用例
「試験前だけ頑張っても意味ないよ。普段からコツコツ勉強しないとね。学問に王道なし、だよ。」
風が吹けば桶屋が儲かる(かぜがふけばおけやがもうかる)

- 意味・教訓
一見関係のないような出来事が、巡り巡って思いがけない結果を生むこと。
物事は意外な形でつながっているため、広い視野を持つことが大切だという教え。 - 使用例
「SNSで紹介された小さなカフェが、急に大人気になったんだって。まさに風が吹けば桶屋が儲かる、だね。」
ある事が起きるとそれが原因となり、巡り巡って全く関係ない所に影響が及ぶ長い長い因果関係を意味しています。また現代では、論理の飛躍・こじつけを意味することから、当てにならない事を期待する時にも使われます。
風邪は万病の元(かぜはまんびょうのもと)

- 意味・教訓
風邪は軽い病気に思えるが、放っておくとさまざまな病気を引き起こす原因になる。
健康管理を怠らず、早めの対策をすることが大切だという教え。 - 使用例
「ちょっとした風邪でも油断しちゃダメだよ。風邪は万病の元って言うし、しっかり休んでね。」
火中の栗を拾う(かちゅうのくりをひろう)

- 意味・教訓
自分の利益にならないのに、他人のために危険を冒して利用されてしまうこと。
安易に他人の頼みを聞いたり、リスクのある行動を取らないように注意すべきだという教え。 - 使用例
「上司のミスをかばって、自分が責任を取ることになったよ…。まさに火中の栗を拾うって感じだね。」
勝って兜の緒を締めよ(かってかぶとのおをしめよ)

- 意味・教訓
成功したからといって油断せず、最後まで気を引き締めることが大切だという教え。
勝利の後こそ慎重に行動し、次の挑戦に備えるべきである。 - 使用例
「試験に合格したからって気を抜かないで、次の勉強も頑張ろうよ。勝って兜の緒を締めよ、だね。」
鰹節を猫に預ける(かつおぶしをねこにあずける)

- 意味・教訓
欲しがる者にそのまま管理を任せるのは、非常に危険であるということ。
利害関係がある相手に重要なものを預けると、不正や裏切りにつながる可能性があるという教え。 - 使用例
「お金の管理を浪費癖のある彼に任せるなんて、大丈夫?まるで鰹節を猫に預けるようなものだよ。」
河童の川流れ(かっぱのかわながれ)
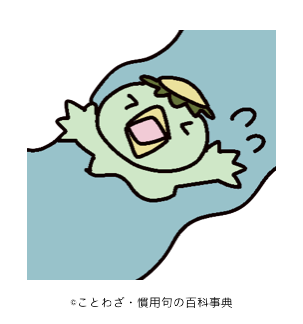
- 意味・教訓
どんなに得意なことでも、時には失敗することがある。
名人や専門家であっても油断するとミスをするので、慢心せず注意することが大切だという教え。 - 使用例
「料理上手な彼女が、今日は味付けを間違えたみたいだよ。河童の川流れってこともあるんだね。」
勝てば官軍、負ければ賊軍(かてばかんぐん、まければぞくぐん)

- 意味・教訓
戦いや争いごとは、勝った側が正義とされ、負けた側は悪とされることが多い。
結果によって評価が変わることがあるため、歴史や物事の見方には注意が必要だという教え。 - 使用例
「どんなに正しいことを言っても、結果を出せなければ評価されない。勝てば官軍、負ければ賊軍ってことだね。」
金は天下の回り物(かねはてんかのまわりもの)

- 意味・教訓
お金は一時的に手元にあっても、いずれは他の人のもとへ流れていくもの。
必要以上に執着せず、上手に使うことが大切だという教え。 - 使用例
「臨時収入が入ったけど、すぐに出費がかさんでなくなっちゃったよ。金は天下の回り物だね。」
壁に耳あり障子に目あり(かべにみみありしょうじにめあり)
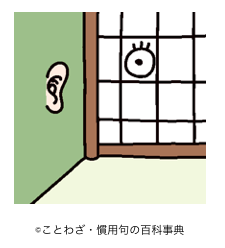
- 意味・教訓
どこで誰が聞いているかわからないので、秘密や悪口は慎重に扱うべきだという教え。
思わぬところで情報が漏れることがあるため、発言には気をつけるべきである。 - 使用例
「上司の悪口を話してたら、上司が聞き耳を立てていたよ!壁に耳あり障子に目ありだね。」
【スポンサーリンク】
果報は寝て待て(かほうはねてまて)
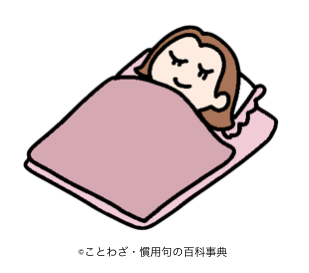
- 意味・教訓
良い運や幸せは焦らずに待つことで、自然と巡ってくるもの。
努力をしたあとは、慌てずに時機を待つことが大切だという教え。 - 使用例
「試験が終わったら、結果を気にしすぎても仕方ないよ。果報は寝て待て、っていうしね。」
亀の甲より年の功(かめのこうよりとしのこう)

- 意味・教訓
長年の経験は貴重なものであり、若さよりも年長者の知恵や経験が役に立つことが多い。
経験を積んだ人の意見を尊重し、学ぶ姿勢を持つことが大切だという教え。 - 使用例
「ベテランのアドバイス通りにやったら、仕事がうまくいったよ。やっぱり亀の甲より年の功だね。」
鴨が葱を背負って来る(かもがねぎをしょってくる)

- 意味・教訓
都合の良いことが、さらに良い条件を伴ってやってくること。
鴨鍋を作ろうとしていた時に、まさかの材料に必要な鴨がネギを背負って自らやって来たというように、利用しようとしていたモノが更に利用できるものを持ってくるという非常に都合の良い状況を表したたとえからきている。 - 使用例
「新規のお客さんが、最初から高額商品を希望してたよ。まさに鴨が葱を背負って来るって感じだね。」
鴨(カモ)=簡単に捕まえられる鳥ということから、お人好しで騙されやすい人という意味も含まれている。
烏の行水(からすのぎょうずい)

- 意味・教訓
風呂に入る時間が非常に短く、体を良く洗わずにすぐ出てしまうこと。
カラスが水浴びをするとき、数分で羽とくちばしを洗い整える姿からきている。 - 使用例
「彼女、シャワー浴びるの早すぎない?まるで烏の行水だね。」
枯れ木も山の賑わい(かれきもやまのにぎわい)
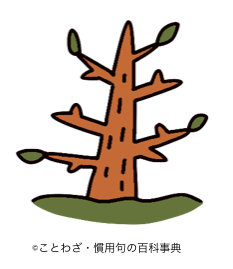
- 意味・教訓
つまらないものでも、ないよりはあったほうが良いということ。
また、何気ないものでも、集まれば場を賑やかにするという教え。 - 使用例
「発表会の観客が少なかったけど、僕たちが行ったおかげで少しは賑やかになったね。枯れ木も山の賑わいだよ。」
可愛い子には旅をさせよ(かわいいこにはたびをさせよ)

- 意味・教訓
子どもを甘やかすのではなく、あえて苦労や経験をさせることで、成長させることが大切である。
親の愛情とは、守ることだけでなく、子どもが自立できるよう導くことだという教え。 - 使用例
「留学に行かせるのは心配だけど、成長するためには必要な経験だね。可愛い子には旅をさせよ、だよ。」
眼光紙背に徹す(がんこうしはいにてっす)

- 意味・教訓
文章を読むとき、単なる表面的な意味だけでなく、その奥にある深い意図や真意まで読み取ること。
物事の本質を見抜く力を養うことが大切だという教え。 - 使用例
「この本はただ読むだけじゃなく、著者の意図を考えながら読むといいよ。まさに眼光紙背に徹す、だね。」
聞いて極楽見て地獄(きいてごくらくみてじごく)

- 意味・教訓
話に聞いていたときは素晴らしく思えたが、実際に見たり体験したりすると、ひどい状況だったということ。
物事は話だけで判断せず、自分の目で確かめることが大切だという教え。 - 使用例
「ネットの口コミでは最高のホテルって書いてあったのに、実際に行ったらボロボロだったよ。まさに聞いて極楽見て地獄だね。」
聞くは一時の恥聞かぬは一生の恥(きくはいっときのはじきかぬはいっしょうのはじ)

- 意味・教訓
分からないことを人に尋ねるのは一時的に恥ずかしいかもしれないが、聞かずに知らないままでいると、一生困ることになる。
恥を恐れずに学ぶ姿勢が大切だという教え。 - 使用例
「この用語の意味、今のうちに聞いておいたほうがいいよ。聞くは一時の恥、聞かぬは一生の恥だからね。」
雉も鳴かずば撃たれまい(きじもなかずばうたれまい)

- 意味・教訓
余計なことを言ったり目立ったりしなければ、災難を招かずに済むということ。
慎重な言動が大切であり、不用意に発言したり行動したりすると、自分の身を危険にさらすことがあるという教え。 - 使用例
「うっかり秘密を話してしまったせいで、トラブルに巻き込まれたよ…。雉も鳴かずば撃たれまい、だね。」
九死に一生を得る(きゅうしにいっしょうをえる)

- 意味・教訓
ほとんど助かる見込みのない危機的な状況から、奇跡的に生還すること。
絶体絶命の状態でも、最後まで諦めないことが大切だという教え。 - 使用例
「大事故に巻き込まれたけど、奇跡的に助かったよ。まさに九死に一生を得る体験だったね。」
窮すれば通ず(きゅうすればつうず)

- 意味・教訓
どうにもならないほど追い詰められた状況でも、必死に考えれば打開策が見つかることがある。
困難なときこそ諦めずに工夫し、乗り越えることが大切だという教え。 - 使用例
「ピンチだったけど、ギリギリのところでアイデアが浮かんで乗り切れたよ!窮すれば通ず、だね。」
窮鼠猫を噛む(きゅうそねこをかむ)

- 意味・教訓
弱い者でも、追い詰められると必死になって強い者に反撃することがある。
相手を追い詰めすぎると、思わぬ反撃を受けることがあるので、慎重に対応することが大切だという教え。 - 使用例
「普段は大人しい彼が、上司に強く反論していたよ。窮鼠猫を噛むってやつだね。」
漁夫の利(ぎょふのり)

- 意味・教訓
二者が争っている間に、第三者が何の苦労もなく利益を得ること。
無駄な争いを避けることの重要性や、状況を冷静に見極めてチャンスを掴むことの大切さを教える言葉。 - 使用例
「A社とB社が価格競争している間に、C社が新商品で市場を独占したね。まさに漁夫の利だよ。」
清水の舞台から飛び降りる(きよみずのぶたいからとびおりる)

- 意味・教訓
思い切って大きな決断をすること。
迷いや不安があっても、勇気を出して実行することが大切だという教え。 - 使用例
「ずっと悩んでいたけど、ついに転職を決意したよ。清水の舞台から飛び降りるつもりで挑戦するよ!」
木を見て森を見ず(きをみてもりをみず)

- 意味・教訓
物事の一部分だけを見て、全体を見失ってしまうこと。細かいことに気を取られすぎると、大事な本質を見落としてしまうという教訓。 - 使用例
「細かいミスばかり指摘して、全体の流れを見ていないよ。それじゃ木を見て森を見ずだよ。」
腐っても鯛(くさってもたい)

- 意味・教訓
優れたものは、たとえ多少の欠点があっても、その価値が完全に失われることはないということ。元々の質の高さは簡単には損なわれないという教訓。 - 使用例
「この古いブランドバッグ、少し傷んでいるけどやっぱり高級感があるね。腐っても鯛だよ。」
口は災いの元(くちはわざわいのもと)

- 意味・教訓
不用意な発言が原因で、思わぬトラブルや災難を招いてしまうこと。発言には注意し、慎重に言葉を選ぶべきだという教訓。 - 使用例
「何気なく言った一言で相手を怒らせてしまったよ…。本当に口は災いの元だね。」
苦しい時の神頼み(くるしいときのかみだのみ)

- 意味・教訓
普段は神や仏を信じていなくても、困った時や苦しい時だけ頼ろうとすること。日頃から努力や準備を怠らないことが大切だという教訓。 - 使用例
「試験前になって急に神社にお参りするなんて、苦しい時の神頼みだね。もっと早くから勉強しておけばよかったのに。」
口も八丁手も八丁(くちもはっちょうてもはっちょう)

- 意味・教訓
話が上手なだけでなく、実際の行動や技術も優れていること。口先だけではなく、実力も伴っている人を指す。 - 使用例
「彼はプレゼンが上手なだけじゃなく、実際に仕事もできるね。まさに口も八丁手も八丁だよ。」
食わず嫌い(くわずぎらい)

- 意味・教訓
実際に試したことがないのに、先入観や見た目だけで嫌だと思い込み、避けてしまうこと。何事も経験してみることが大切だという教訓。 - 使用例
「ずっと納豆は苦手だと思っていたけど、食べてみたら意外と美味しかったよ。完全に食わず嫌いだったな。」
君子危うきに近寄らず(くんしあやうきにちかよらず)

- 意味・教訓
賢い人は、危険なことやリスクのある状況には近づかないものだということ。慎重な判断が大切であるという教訓。 - 使用例
「その投資話、なんだか怪しいよ。君子危うきに近寄らずって言うし、無理に手を出さないほうがいいんじゃない?」
芸は身を助ける(げいはみをたすける)

- 意味・教訓
何か特技や技能を持っていると、いざという時に自分の助けになることがあるということ。どんな小さな技術でも、身につけておくことが大切だという教訓。 - 使用例
「海外で仕事を探すことになったけど、日本語を教えられるおかげでなんとか生活できてるよ。芸は身を助けるとはこのことだね。」
怪我の功名(けがのこうみょう)

- 意味・教訓
失敗や思わぬアクシデントが、結果的に良い方向に働くこと。何が幸いするかわからないという教訓。 - 使用例
「電車を乗り間違えたけど、そのおかげで昔の友達と偶然再会したよ。まさに怪我の功名だね。」
【スポンサーリンク】
犬猿の仲(けんえんのなか)

- 意味・教訓
非常に仲が悪く、互いに激しく対立している関係のたとえ。
もともとは犬と猿が相性が悪いとされていることに由来する。 - 使用例
「あの二人は昔から犬猿の仲だから、一緒に仕事をさせるのは難しいよ。」
喧嘩両成敗(けんかりょうせいばい)

- 意味・教訓
喧嘩や争いごとが起こったとき、どちらにも責任があるとして、双方を同じように罰すること。
また、一方だけを贔屓せず、公正な判断を下すべきだという教訓でもある。 - 使用例
「どっちが先に手を出したかは関係ないよ。喧嘩両成敗だから、両方とも罰を受けるべきだ。」
光陰矢の如し(こういんやのごとし)
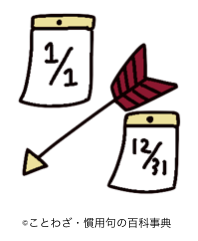
- 意味・教訓
月日が過ぎるのはとても早く、戻ることはないというたとえ。
時間を無駄にせず、大切に使うべきだという教訓を含む。 - 使用例
「気づけばもう一年が経ったのか。まさに光陰矢の如しだね。」
後悔先に立たず(こうかいさきにたたず)

- 意味・教訓
物事が終わった後で悔やんでも、取り返しがつかないというたとえ。
失敗しないように、事前に慎重に行動することが大切であるという教訓を含む。 - 使用例
「もっと早く準備しておけばよかった…でも後悔先に立たずだね。」
孝行のしたい時分に親は無し(こうこうのしたいじぶんにおやはなし)

- 意味・教訓
親が生きているうちに孝行しなければ、亡くなってから後悔しても遅いというたとえ。
親や大切な人への感謝や恩返しは、できるときにしておくべきだという教訓。 - 使用例
「もっと親孝行しておけばよかった…。孝行のしたい時分に親は無しとは、まさにこのことだね。」
郷に入っては郷に従え(ごうにいってはごうにしたがえ)

- 意味・教訓
新しい環境に入ったら、その土地や集団の習慣やルールに従うべきだという教え。自分のやり方に固執せず、周囲に適応することが大切である。 - 使用例
「海外に引っ越したなら、その国の文化を尊重することが大切だよ。郷に入っては郷に従えって言うだろ?」
弘法にも筆の誤り(こうぼうにもふでのあやまり)

- 意味・教訓
どんなに優れた人でも、時には失敗することがあるという教え。完璧な人はいないので、ミスをしたとしても落ち込まず、次に活かすことが大切である。 - 使用例
「君が計算ミスをしたのは仕方ないよ。あの天才教授ですら間違えることがあるんだから、弘法にも筆の誤りって言うだろ?」
弘法筆を選ばず(こうぼうふでをえらばず)

- 意味・教訓
本当に優れた人は、道具や環境に左右されることなく、素晴らしい結果を出すことができるという教え。技術や実力があれば、どんな状況でも対応できる。 - 使用例
「プロのカメラマンなら、高級なカメラがなくても素晴らしい写真を撮れるものさ。弘法筆を選ばずって言うだろ?」
紺屋の白袴(こうやのしろばかま)
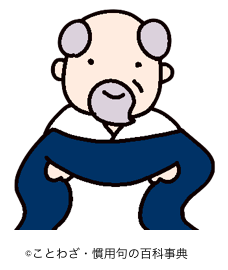
- 意味・教訓
他人のために忙しく働いている人ほど、自分のことには手が回らず、疎かになってしまうという教え。専門家でも自分のことには意外と無頓着なことがある。 - 使用例
「父は大工なのに、うちの家の修理は全然やらないんだよ。まさに紺屋の白袴ってやつだね。」
虎穴に入らずんば虎子を得ず(こけつにいらずんばこじをえず)

- 意味・教訓
大きな成功や成果を得るためには、危険や困難を恐れずに挑戦することが必要だという教え。リスクを取らなければ、大きな報酬は得られない。 - 使用例
「新しい事業に挑戦するのは不安だけど、成功したいなら思い切ってやるしかないよ。虎穴に入らずんば虎子を得ず、って言うだろ?」
転ばぬ先の杖(ころばぬさきのつえ)

- 意味・教訓
何事も事前にしっかり準備しておけば、失敗やトラブルを防ぐことができるという教え。備えあれば憂いなし。 - 使用例
「試験前にちゃんと復習しておけば、焦らずに済むよ。転ばぬ先の杖って言うし、早めに準備しよう!」
五十歩百歩(ごじっぽひゃっぽ)

- 意味・教訓
わずかな違いはあっても、本質的には大差がないことを示す教え。自分のことを棚に上げて他人を批判するのは意味がない。 - 使用例
「テストの点数で競ってるけど、10点も20点も大して変わらないよ。五十歩百歩なんだから、お互い切もっと頑張ろう。」
【スポンサーリンク】