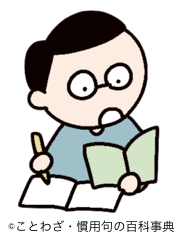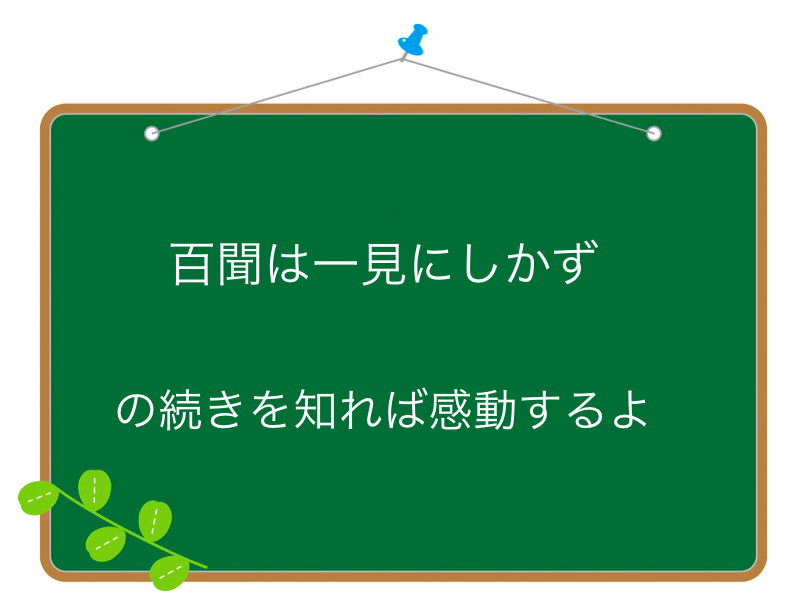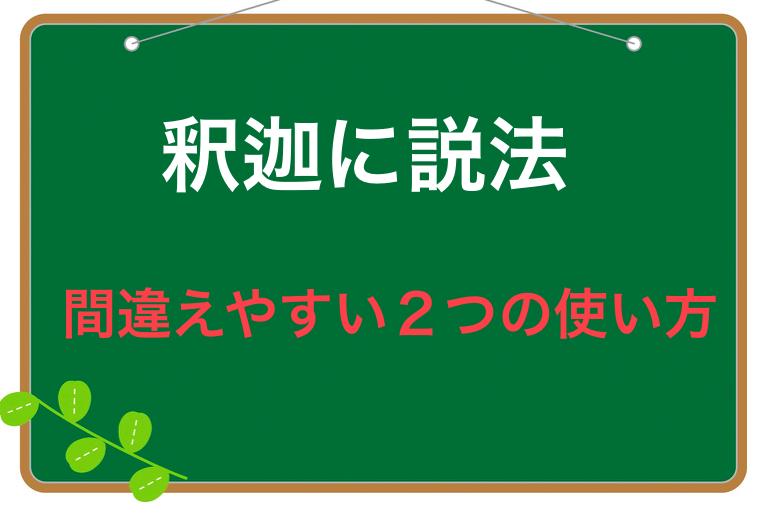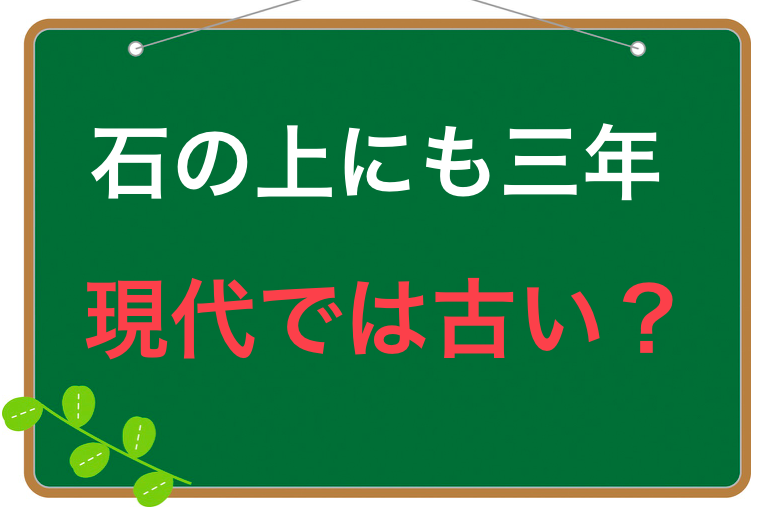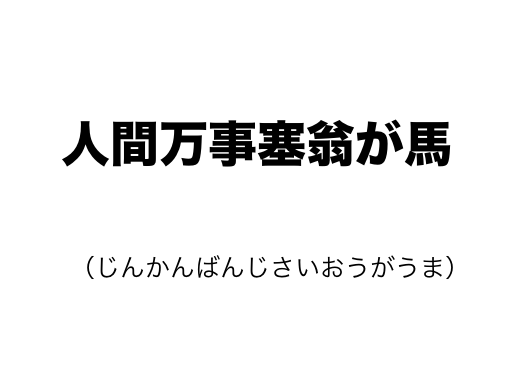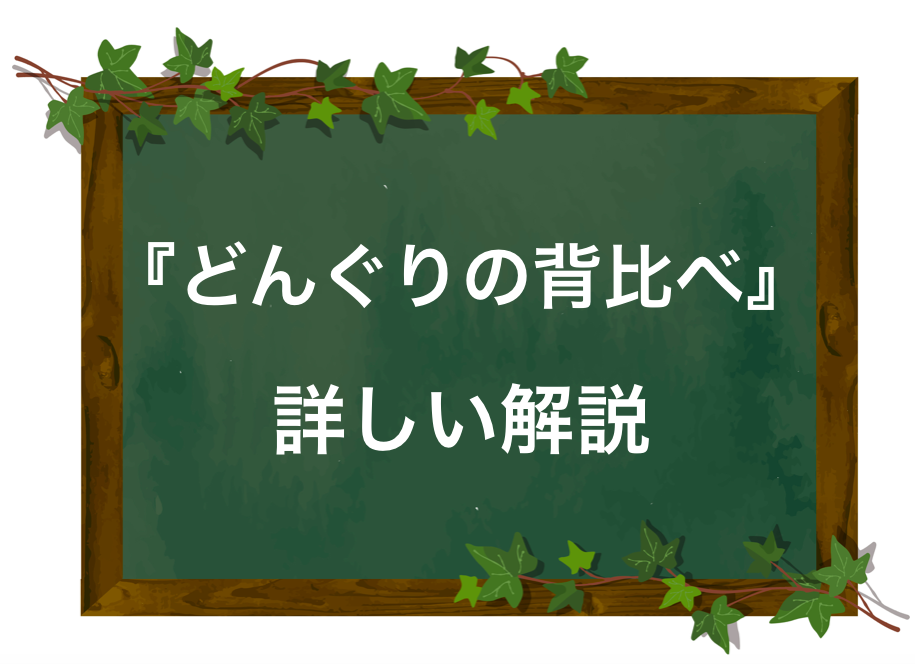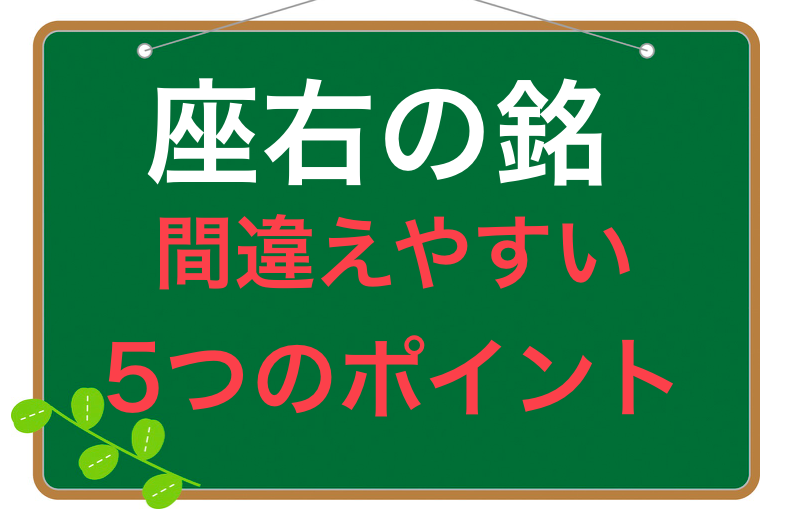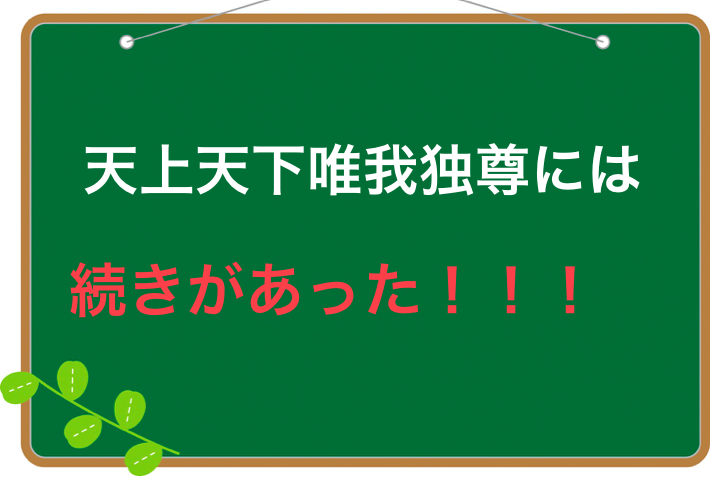ことわざ、慣用句、故事成語は、日本語や多くの言語で用いられる言葉の一部であり、それぞれに独自の特徴があります。
ことわざは、広く一般的に使われる人生の知恵や教訓を短い言葉で表現する固定された表現方法です。
一方慣用句は特定の文脈や状況で使用される固定表現で、その意味は単語からは想像がつかないものが多いです。
さらに故事成語は、長い歴史と伝統を持つ表現で、物語や伝説から生まれたもので、漢字で表されることが多く、その成り立ちや起源を知ることで深い意味を理解することができます。
この記事では、『ことわざ・慣用句・故事成語のそれぞれの違いと特徴』について詳しく見ていきましょう。
目次
「ことわざ」と「慣用句」と「故事成語」の違い
ことわざ、慣用句、故事成語は、日本語や多くの言語で用いられる言葉の一部であり、それぞれに独自の特徴があります。
ことわざとは、広く普及している民間伝承や経験則などを言葉に表したもので、一般に簡潔な表現で重要な教訓や価値観を伝えるものを指します。日本だけでなく、世界中にさまざまなことわざがあります。ことわざは、一言で説明できるような深い意味があり、簡潔かつ分かりやすい表現であることが特徴です。また、一つのことわざから多くの教訓を学ぶことができるため、語り継がれることでその国や文化の背景や人々の価値観を知ることができるとされています。例えば「石の上にも三年」といったものが挙げられます。
一方、慣用句は、一般的に固定された言葉の組み合わせで、それぞれの言葉の意味よりも、表現全体としての意味が重要とされる言葉のことを指します。慣用句は、ある特定の状況や習慣に応じて定着した表現であり、その背景を知っていないと、表現の意味が分からない場合があります。例えば、「空気を読む」という慣用句は、相手の気持ちや状況を感じ取り、それに応じた行動をすることを意味します。このように、慣用句は、それ自体に意味があるわけではなく、背景にある文脈が重要であるという特徴があります。
簡単に言うと、ことわざは単体で使う事が出来ますが、慣用句は前後の文章が必要になる表現が多いものになります。
例えば、「猿も木から落ちる」ということわざは単体で意味が通じますが、「舌の根の乾かぬうち」という慣用句は前後に文章がなければ単体では意味を成しません。
さらに、故事成語は、物語や逸話の中に登場する言葉や表現で、教訓や知恵を表すものを指します。例えば、「虎穴に入らずんば虎子を得ず」といったものが挙げられます。故事成語は、そのままでは意味が分からないことが多く、物語や逸話を知っていることが前提となります。一般的には、ことわざや慣用句と比べて、より文学的な印象を与えることが多いとされます。
以上のように、ことわざ、慣用句、故事成語にはそれぞれ特徴がありますが、いずれも独特な表現方法を持ち、生活や文化の中で重要な役割を果たしています。
次の項目からは、それぞれの特徴や詳細を例を含めてより詳しく解説していきます。
「慣用句」とは

私たちが毎日使っている言葉の中に、二つ以上のことば(単語)が組み合わさって、もとの言葉とは全く違った特別の意味に使われる、面白い言葉が沢山あります。
例えば、「首を長くする」はただ首を高く伸ばすだけではなく、遠くを見ながら「まだか、まだか。」と楽しみな事が待っている様子を表します。
「テストで100点とって鼻が高い」は自慢をすることを意味します。
「山登りをして足が棒になる」は疲れて足がきかなくなるを意味します。
きっと、みなさんもこのような言葉を使った事があるでしょうし、耳にしたことがあるでしょう。
このようなことばの業が使われている句を「慣用句」と言います。
「慣用句」の例
慣用句はとくに人間の体に関係した言葉を取り入れたものが沢山あります。
体の部分の言葉は人が毎日くらしていくとき、いつも使い慣れているもので、新しい言葉を生んでいくのに自然と使い込む事が多く、都合よく使えたのが理由と言われています。
慣用句は昔から今日まで長い間、多くの人々に使いこなされて私たちの日常の会話や文章にどんどん用いられ、私たちの言葉を使う生活を豊かにしているのです。
それでは、人間の体に関係した慣用句の例を少しだけあげてみましょう。
「頭」を使った慣用句

頭が高い
威張っていて、目上の人にも礼を欠いているようす。
頭を冷やす
高ぶった気持ちを落ち着かせる。冷静になる。
「眉」を使った慣用句

眉を開く
心の中にあった今までの心配事がなくなりほっとするという意味。心配事がなくなって、晴れやかな顔になる。
眉をひそめる
心配事や、怪訝であったり不愉快であったりして、眉のあたりにしわをよせて顔をしかめること。
「声」を使った慣用句

声を潜める
周囲の人に聞こえないように声を小さくする。
呼び声が高い
評判が高い。うわさされる。
「その他」の体を使った慣用句
上記以外にも、沢山の体を使った慣用句が存在します。
当サイトに収録している、体の部分が入っている慣用句を集めましたのでこちらの記事でご覧ください。
「ことわざ」とは
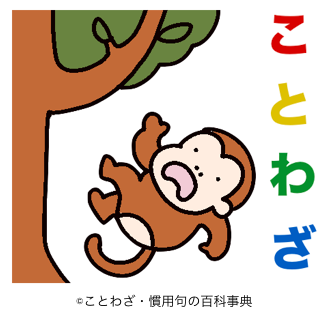
「河童の川流れ」「急いては事を仕損じる」「捕らぬ狸の皮算用」などのように、人々が生活していく上で、注意するように戒めた事柄や、笑いや例えで相手をやり込めるような事柄を、短い言葉でいいあらわしたものが「ことわざ」になります。
これらのように、二つ三つの言葉が繋がって、人間としての教えや戒めを説いたもの、また人間や世間の強みや弱みを皮肉めいて表したものを、特に「ことわざの業」を略して「ことわざ」と呼んでいます。
ちなみに、「ことわざ」は漢字で「諺」と書きます。
ことわざは、いつ、誰が作ったというものではなく、たくさんの人々の生活の中から、自然に生まれた言葉になります。
子供の時に、夏の暑さが厳しくて、「早くすずしくならないかなぁ」と思っている時に、大人の人が「『暑さ寒さも彼岸まで』というからもう少しの辛抱だよ」と言うのを聞いたことはありませんか?
夏の暑さは秋のお彼岸を過ぎるとおさまり、冬の寒さは春のお彼岸を過ぎるとやわらぐという意味の言葉です。
このような、気の利いた言い回しで、生活をしていく上に役立ついろいろな知恵を教えてくれるのがことわざになります。
「ことわざ」の例
それでは、少しことわざの例をあげてみましょう。
仕事や勉強のやり方を教えたことわざ
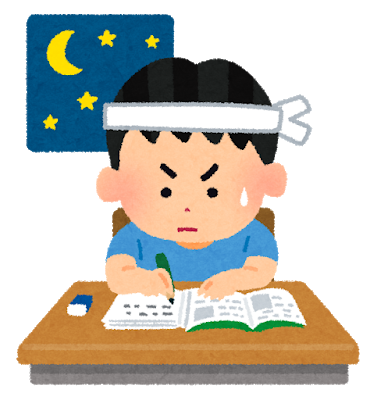
石の上にも三年(いしのうえにもさんねん)
冷たい石の上でも3年も座りつづけていれば暖まってくる。がまん強く辛抱すれば必ず成功することのたとえ。
故きを温ねて新しきを知る(ふるきをたずねてあたらしきをしる)
古いことを調べて、新しい知識や意義を再発見するという意味。
生活の経験から得た知識や深い知恵が込められているもの。

終わり良ければ全て良し(おわりよければすべてよし)
最初や途中がどうであれ、結局大切なのは結果であるということ。
待てば海路の日和あり(まてばかいろのひよりあり)
今は思うようにいかなくても、あせらずに待っていればチャンスはそのうちにやってくるということのたとえ。
誰もが持っている欠点や弱みを言い表したもの。

鵜の真似をする烏(うのまねをするからす)
自分の腕前を知らずに徒に人の真似をして失敗すること。
溺れる者は藁をも掴む(おぼれるものはわらをもつかむ)
とても苦しんだり、困ったりしたときや、切羽詰まった状況の時には、助かりたい一心でどんなに頼りないものにもすがりつき、救いを求めることのたとえ。
世の中を生きていくのに心得ておきたい色々な教え。

負けるが勝ち(まけるがかち)
時には、あえて争わないで相手に勝ちを譲ったほうが、結果的には自分に有利となって勝利に結びつくことがあるということ。
「ことわざ」の表現
ことわざには、色々な「表現の形」があります。
対句形式(ついくけいしき)
「頭でっかち尻つぼみ」ということわざは、「頭」「でっかち」と「尻」「つぼみ」という対(つい)になった表現、すなわち対句形式となっています。
言葉の調子
「頭でっかち尻つぼみ」には、「あ・た・ま・で・っ・か・ち」ん七つの音と「し・り・つ・ぼ・み」の五つの音という七五音の組み合わせも含まれています。
音の反復
「当たるも八卦当たらぬも八卦」では、「あたるもーあたらぬも」と「はっけーはっけ」という音が繰り返される「音の反復」があります。
列挙形式
「一富士二鷹三茄子」は、言葉を並べる「列挙形式」となっています。
数の提示
「一を聞いて十を知る」ということわざは、「一」と「十」という数量を表す「数の提示」があります。
一つのことわざが何種類かの「表現の形」を持つ場合もあります。
この「表現の形」に着目してことわざを見てみると、自分の表現にも役立てる事ができます。
「故事成語」とは

故事成語とは、昔の出来事や故事、または古典に登場する人物や事件に由来して作られた、一定の意味を持つ言葉や表現のことを指します。ことわざや慣用句と同様に、簡潔で力強い表現であり、教訓や人生の知恵を伝えることが多いです。
故事成語は、漢文や古典文学から派生したものが多いため、漢字が多用され、難解な場合があります。しかし、一度理解してしまえば、印象的で忘れがたい表現が多く、文章の中で効果的に使われます。
例えば、「一石二鳥」や「二兎追う者は一兎も得ず」などは、広く知られた故事成語であり、それぞれ「一つの行為で2つの利益を得ることができる」と「欲張って2つのことを同時に追い求めると、どちらも手に入らなくなる」という意味を表します。
また、「百聞は一見に如かず」や「塞翁が馬」などは、中国古典の故事に由来しています。前者は「何度も聞くよりも、一度見た方がわかりやすい」という意味で、後者は「善悪は予想できず、どんな出来事もすべては運命の流れに従っている」という教えを表しています。
故事成語は、日本語の表現において重要な役割を持っています。多くの故事成語が日本の文化や歴史に関わるものであり、その言葉によって、古代の風習や価値観を知ることができると同時に、現代においても有用な知恵や助言を与えてくれるものとなっています。
「故事成語」の例
故事成語の中には、「井の中の蛙大海を知らず」などのことわざや、「一挙両得」などの四字熟語、「圧巻」などの二字熟語なども含まれています。
こちらの記事で沢山の故事成語の例をご紹介していますのでご覧ください。
ことわざ・慣用句・故事成語の違いまとめ
- ことわざ・・・昔から伝えられてきた、人の生活の役に立つ知恵や教えを表す言葉。
- 慣用句・・・いくつかの言葉が組み合わせたり、もとの言葉の意味とはちがう意味をもつようになった言葉。
- 故事成語・・・昔の中国でおこったことがもとになってできた言葉。
ことわざや慣用句、故事成語は、長い時間、沢山の人々がどのように生きてきたかという歴史がつまっています。
そして過去の事だけではなく、これからの私たちはどのように生きていくのが良いか、手がかりとなる知恵が沢山詰まっています。
なるほどなるほどと楽しく読んでいくうちに、それらの知恵が自然と頭と心に入ってきます。
これが「ことばの業」の魅力です。