【判を貸すとも人請けするな】の意味と使い方や例文(類義語)
「判を貸すとも人請けするな」の意味(類義語) 【ことわざ】 判を貸すとも人請けするな 【読み方】 はんをかすともひとうけするな 【意味】 すべての現象は時間の経過とともに変化するが、真の姿は少しも変わることなく過去・現在...
 「は」で始まることわざ
「は」で始まることわざ「判を貸すとも人請けするな」の意味(類義語) 【ことわざ】 判を貸すとも人請けするな 【読み方】 はんをかすともひとうけするな 【意味】 すべての現象は時間の経過とともに変化するが、真の姿は少しも変わることなく過去・現在...
 「は」で始まることわざ
「は」で始まることわざ「万里一条の鉄」の意味(出典・語源由来) 【ことわざ】 万里一条の鉄 【読み方】 ばんりいちじょうのてつ 【意味】 すべての現象は時間の経過とともに変化するが、真の姿は少しも変わることなく過去・現在・未来にわたって一本の...
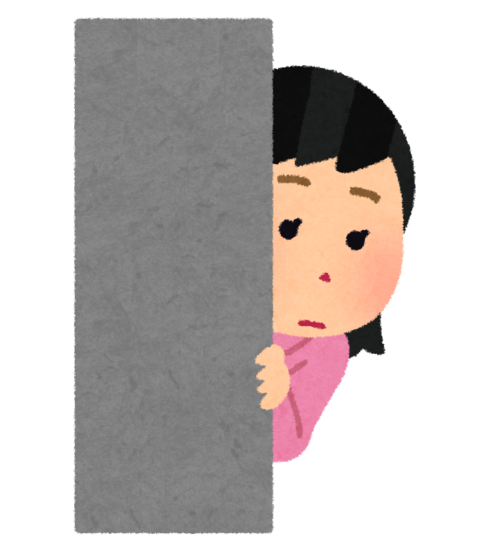 「は」で始まることわざ
「は」で始まることわざ「半面の識」の意味(出典・故事) 【ことわざ】 半面の識 【読み方】 はんめんのしき 【意味】 少しだけ会ったことのある人の顔をずっと覚えていること。ちょっとした知り合い。 【出典】 「後漢書ごかんじょ」 【故事】 中国...
 「は」で始まることわざ
「は」で始まることわざ「反哺の孝」の意味(出典・語源由来・類義語) 【ことわざ】 反哺の孝 【読み方】 はんぽのこう 【意味】 親からの恩に報いるような孝行。 【出典】 「本草綱目ほんぞうこうもく」 【語源由来】 カラスの子は成長後、親鳥の口...
 「は」で始まることわざ
「は」で始まることわざ「万卒は得易く一将は得難し」の意味(語源由来) 【ことわざ】 万卒は得易く一将は得難し 【読み方】 ばんそつはえやすくいっしょうはえがたし 【意味】 優秀な人材は少ないということ。 【語源由来】 多数の兵士を集めるのは簡...
 「は」で始まることわざ
「は」で始まることわざ「万人心を異にすれば則ち一人の用無し」の意味(出典) 【ことわざ】 万人心を異にすれば則ち一人の用無し 【読み方】 ばんにんこころをことにすればすなわちいちにんのようなし 【意味】 たくさんの人がいても心が一つにならなけ...
 「は」で始まることわざ
「は」で始まることわざ「万死を出でて一生に遇う」の意味(出典・類義語) 【ことわざ】 万死を出でて一生に遇う 【読み方】 ばんしをいでていっしょうにあう 【意味】 助かる可能性が少ない危ない状態から、どうにか命が助かること。 【出典】 「貞観...
 「は」で始まることわざ
「は」で始まることわざ「晩食以て肉に当て、安歩して以て車に当つ」の意味(出典・語源由来) 【ことわざ】 晩食以て肉に当て、安歩して以て車に当つ 【読み方】 ばんしょくもってにくにあて、あんぽしてもってくるまにあつ 【意味】 貧しくても清く正し...
 「は」で始まることわざ
「は」で始まることわざ「繁盛の地に草生えず」の意味(類義語) 【ことわざ】 繁盛の地に草生えず 【読み方】 はんじょうのちにくさはえず 【意味】 人通りが多くにぎわっている土地は、雑草が生える暇がない。 【類義語】 ・人通りに草生えず ・使っ...
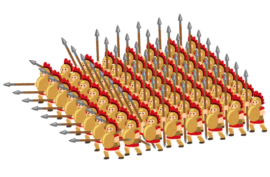 「は」で始まることわざ
「は」で始まることわざ「万乗の君」の意味(出典・語源由来) 【ことわざ】 万乗の君 【読み方】 ばんじょうのきみ 【意味】 天子。大きな国の君主。 【出典】 「孟子もうし」 【語源由来】 一万代の兵車を出すことができる意から。 「万乗の君」の...
 「は」で始まることわざ
「は」で始まることわざ「万死一生を顧みず」の意味(出典) 【ことわざ】 万死一生を顧みず 【読み方】 ばんしいっしょうをかえりみず 【意味】 生きのびることを考えたり、希望を持たないこと。 【出典】 「史記しき」 「万死一生を顧みず」の解説 ...
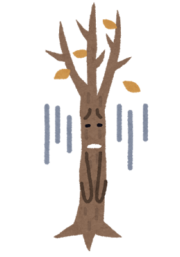 「は」で始まることわざ
「は」で始まることわざ「葉をかいて根を断つ」の意味(語源由来・類義語) 【ことわざ】 葉をかいて根を断つ 【読み方】 はをかいてねをたつ 【意味】 小さなことにこだわり、全てをだめにしてしまうことのたとえ。 【語源由来】 余分な枝葉を除こうと...
 「は」で始まることわざ
「は」で始まることわざ「春の雪と歯抜け狼は怖くない」の意味(類義語) 【ことわざ】 春の雪と歯抜け狼は怖くない 【読み方】 はるのゆきとはぬけおおかみはこわくない 【意味】 春の雪は降ってすぐにとけてなくなるし、歯の抜けた狼は噛みつかれること...
 「は」で始まることわざ
「は」で始まることわざ「春の日と継母はくれそうでくれない」の意味 【ことわざ】 春の日と継母はくれそうでくれない 【読み方】 はるのひとままはははくれそうでくれない 【意味】 春の日の長さを表すことば。 「春の日と継母はくれそうでくれない」の...
 「は」で始まることわざ
「は」で始まることわざ「春小雨夕立に秋日照り」の意味 【ことわざ】 春小雨夕立に秋日照り 【読み方】 はるこさめゆうだちにあきひでり 【意味】 春には小雨、夏は夕立、秋は日照りが続くと、その年は豊作になるということ。 「春小雨夕立に秋日照り」...
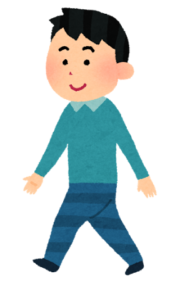 「は」で始まることわざ
「は」で始まることわざ「春の晩飯後三里」の意味 【ことわざ】 春の晩飯後三里 【読み方】 はるのばんめしあとさんり 【意味】 春は冬より日が長く、夕食の後でも三里歩けるほどだということ。 「春の晩飯後三里」の解説 「春の晩飯後三里」の使い方 ...
 「は」で始まることわざ
「は」で始まることわざ「春植えざれば秋実らず」の意味(類義語) 【ことわざ】 春植えざれば秋実らず 【読み方】 はるうえざればあきみのらず 【意味】 努力なしに良い結果を得られるはずがないということ。 【類義語】 ・蒔かぬ種は生えぬ 「春植え...
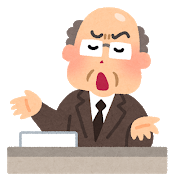 「は」で始まることわざ
「は」で始まることわざ「針を以て地を刺す」の意味(類義語) 【ことわざ】 針を以て地を刺す 【読み方】 はりをもってちをさす 【意味】 貧しい見識で高い見識に勝手な判断を下すこと。また、不可能なことやむだなことを計画すること。 【類義語】 ・...
 「は」で始まることわざ
「は」で始まることわざ「針を倉に積む」の意味(語源由来) 【ことわざ】 針を倉に積む 【読み方】 はりをくらにつむ 【意味】 長年にわたり、こつこつと小金をためこむこと。 【語源由来】 小さな針を倉に積んでもなかなかいっぱいにならないことから...
 「は」で始まることわざ
「は」で始まることわざ「針を棒に取りなす」の意味(類義語) 【ことわざ】 針を棒に取りなす 【読み方】 はりをぼうにとりなす 【意味】 針ほどの小さなことを、棒ほどの大きな事として大げさに言うこと。 【類義語】 ・針小棒大 ・針を棒 「針を棒...
 「は」で始まることわざ
「は」で始まることわざ「針ほどの穴から棒ほどの風がくる」の意味 【ことわざ】 針ほどの穴から棒ほどの風がくる 【読み方】 はりほどのあなからぼうほどのかぜがくる 【意味】 開放した窓からの風よりも、針ほどの隙間から吹き込む風のほうが寒く感じる...
 「は」で始まることわざ
「は」で始まることわざ「針は小さくても呑まれぬ」の意味 【ことわざ】 針は小さくても呑まれぬ 【読み方】 はりはちいさくてものまれぬ 【意味】 小さいからといっても針をのみこむことはできないことから。 「針は小さくても呑まれぬ」の解説 「針は...
 「は」で始まることわざ
「は」で始まることわざ「針とる者車をとる」の意味(語源由来) 【ことわざ】 針とる者車をとる 【読み方】 はりとるものくるまをとる 【意味】 小さな悪行だからと見のがすと、いつか大きな悪行をするようになる。 【語源由来】 針を盗むという小さな...
 「は」で始まることわざ
「は」で始まることわざ「針で掘って鍬で埋める」の意味(語源由来・類義語) 【ことわざ】 針で掘って鍬で埋める 【読み方】 はりでほってくわでうめる 【意味】 努力を続けて少しずつためてきたものを一気に失くしてしまうこと。 【語源由来】 針で少...
 「は」で始まることわざ
「は」で始まることわざ「張りつめた弓はいつか弛む」の意味 【ことわざ】 張りつめた弓はいつか弛む 【読み方】 はりつめたゆみはいつかゆるむ 【意味】 緊張はずっと続くものではない。常に気を張っているつもりでも、気が緩んで失敗することがあるとい...
 「は」で始まることわざ
「は」で始まることわざ「腹を剖きて珠を蔵む」の意味(出典・語源由来) 【ことわざ】 腹を剖きて珠を蔵む 【読み方】 はらをさきてたまをおさむ 【意味】 命よりも財貨を大切にすること。利益や欲望のために無茶をして、身を滅ぼすこと。 【出典】 「...
 「は」で始まることわざ
「は」で始まることわざ「腹は立て損、喧嘩は仕損」の意味(類義語) 【ことわざ】 腹は立て損、喧嘩は仕損 【読み方】 はらはたてぞん、けんかはしぞん 【意味】 腹を立てると自分が損をするだけだし、喧嘩は何の得にもならない。腹を立てず我慢すること...
 「は」で始まることわざ
「は」で始まることわざ「腹は借り物」の意味 【ことわざ】 腹は借り物 【読み方】 はらはかりもの 【意味】 妊娠する母親の腹は一時的な借り物で、生まれてくる子の身分は父親の身分で決まるということ。 「腹は借り物」の解説 「腹は借り物」の使い方...
 「は」で始まることわざ
「は」で始まることわざ「腹の立つように家倉建たぬ」の意味 【ことわざ】 腹の立つように家倉建たぬ 【読み方】 はらのたつようにいえくらたたぬ 【意味】 生きていると腹が立つことが多く腹を立てるのは容易だが、家や倉を建てるために金を稼ぐのは容易...
 「は」で始まることわざ
「は」で始まることわざ「腹の皮が張れば目の皮がたるむ」の意味 【ことわざ】 腹の皮が張れば目の皮がたるむ 【読み方】 はらのかわがはればめのかわがたるむ 【意味】 腹が満たされると眠くなるということ。また、人間は生活が豊かになると怠惰になると...
 「は」で始まることわざ
「は」で始まることわざ「薔薇に刺あり」の意味(類義語) 【ことわざ】 薔薇に刺あり 【読み方】 ばらにとげあり 【意味】 きれいな薔薇に棘があるように、美しいものは人に害を与える一面があるということ。 「薔薇に刺あり」の解説 「薔薇に刺あり」...
 「は」で始まることわざ
「は」で始まることわざ「腹立てるより義理立てよ」の意味 【ことわざ】 腹立てるより義理立てよ 【読み方】 はらたてるよりぎりたてよ 【意味】 腹が立つことがあっても、我慢して義理を立てた方が自分のためになるということ。 「腹立てるより義理立て...
 「は」で始まることわざ
「は」で始まることわざ「腹が立つなら親を思い出せ」の意味 【ことわざ】 腹が立つなら親を思い出せ 【読み方】 はらがたつならおやをおもいだせ 【意味】 腹が立ったら、問題を起こすと親が悲しむことになると思って我慢するようにということ。 「腹が...
 「は」で始まることわざ
「は」で始まることわざ「腹がすいてもひもじゅうない」の意味(出典・類義語) 【ことわざ】 腹がすいてもひもじゅうない 【読み方】 はらがすいてもひもじゅうない 【意味】 腹が減ってもひもじいと弱音を吐いたりしないということ。 【出典】 「浄瑠...
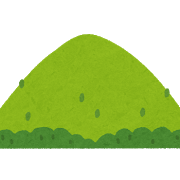 「は」で始まることわざ
「は」で始まることわざ「生ゆる山は山口から見ゆる」の意味(類義語) 【ことわざ】 生ゆる山は山口から見ゆる 【読み方】 はゆるやまはやまぐちからみゆる 【意味】 木の育ちがよい山は、山の入口に立つだけで分かる。 【類義語】 ・尊い寺は門から ...
 「は」で始まることわざ
「は」で始まることわざ「はやり目なら病み目でもよい」の意味(語源由来) 【ことわざ】 はやり目なら病み目でもよい 【読み方】 はやりめならやみめでもよい 【意味】 むやみやたらに流行を追いかける者の愚かさをいう言葉。 【語源由来】 流行してい...
 「は」で始まることわざ
「は」で始まることわざ「はやる芝居は外題から」の意味 【ことわざ】 はやる芝居は外題から 【読み方】 はやるしばいはげだいから 【意味】 はやっている芝居は、題名から人を魅了する。内容も大切だが、題名が大切ということ。 「はやる芝居は外題から...
 「は」で始まることわざ
「は」で始まることわざ「はやり事は六十日」の意味(類義語) 【ことわざ】 はやり事は六十日 【読み方】 はやりごとはろくじゅうにち 【意味】 流行は長く続かず、60日もすれば世の中から忘れ去られるということ。 【類義語】 ・はやり物は廃り物 ...
 「は」で始まることわざ
「は」で始まることわざ「早飯も芸のうち」の意味 【ことわざ】 早飯も芸のうち 【読み方】 はやめしもげいのうち 【意味】 早くご飯を食べることも芸の一つに数えて良いということ。 【類義語】 ・早飯早糞芸のうち ・早飯早糞早走り 「早飯も芸のう...
 「は」で始まることわざ
「は」で始まることわざ「早飯早糞早算用」の意味(類義語) 【ことわざ】 早飯早糞早算用 【読み方】 はやめしはやぐそはやざんよう 【意味】 早くご飯を食べ、早く用便をして、早く計算ができるということは、雇用される者の大事な技能だということ。 ...
 「は」で始まることわざ
「は」で始まることわざ「早寝早起き病知らず」の意味 【ことわざ】 早寝早起き病知らず 【読み方】 はやねはやおきやまいしらず 【意味】 早寝早起きの規則正しい生活を送れば、健康に恵まれ病気知らずになるということ。 「早寝早起き病知らず」の解説...
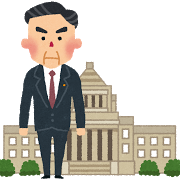 「は」で始まることわざ
「は」で始まることわざ「林深ければ則ち鳥棲み、水広ければ則ち魚游ぶ」の意味(出典・語源由来・類義語) 【ことわざ】 林深ければ則ち鳥棲み、水広ければ則ち魚游ぶ 【読み方】 はやしふかければすなわちとりすみ、みずひろければすなわちうおあそぶ 【...
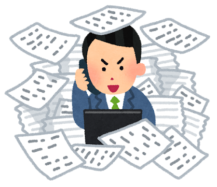 「は」で始まることわざ
「は」で始まることわざ「早くて悪し大事なし、遅くて悪し猶悪し」の意味 【ことわざ】 早くて悪し大事なし、遅くて悪し猶悪し 【読み方】 はやくてわるしだいじなし、おそくてわるしなおわるし 【意味】 仕事の出来が悪くても仕事が早ければしょうがない...
 「は」で始まることわざ
「は」で始まることわざ「早好きの早飽き」の意味(類義語・英語) 【ことわざ】 早好きの早飽き 【読み方】 はやすきのはやあき 【意味】 何かをすぐに好きになるものは、飽きるのも早いということ。 【類義語】 ・近惚れの早飽き 【英語】 Soon...
 「は」で始まることわざ
「は」で始まることわざ「早くて間に合わぬ鍛冶屋の向こう槌」の意味(語源由来) 【ことわざ】 早くて間に合わぬ鍛冶屋の向こう槌 【読み方】 はやくてまにあわぬかじやのむこうづち 【意味】 自分だけ早すぎることで、全体の調子を狂わせること。協力し...
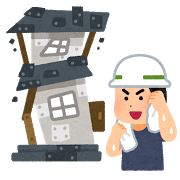 「は」で始まることわざ
「は」で始まることわざ「早きは宜しゅうて失あり、遅きは悪しゅうて失なし」の意味 【ことわざ】 早きは宜しゅうて失あり、遅きは悪しゅうて失なし 【読み方】 はやきはよろしゅうてしつあり、おそきはあしゅうてしつなし 【意味】 仕事が早いの褒められ...
 「は」で始まることわざ
「は」で始まることわざ「早合点の早忘れ」の意味 【ことわざ】 早合点の早忘れ 【読み方】 はやがてんのはやわすれ 【意味】 飲み込みが速い人は、忘れるのも早いので頼りにならないということ。 「早合点の早忘れ」の解説 「早合点の早忘れ」の使い方...
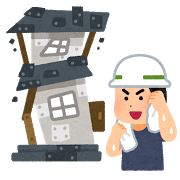 「は」で始まることわざ
「は」で始まることわざ「早かろう悪かろう」の意味(類義語・英語訳) 【ことわざ】 早かろう悪かろう 【読み方】 はやかろうわるかろう 【意味】 仕事がはやいと出来が悪くなりがちであるということ。 【類義語】 ・早い者に上手なし 【英語訳】 G...
 「は」で始まることわざ
「は」で始まることわざ「早起き三両倹約五両」の意味(類義語) 【ことわざ】 早起き三両倹約五両 【読み方】 はやおきさんりょうけんやくごりょう 【意味】 早起きと倹約は、両方とも大きな利益になるということ。 【類義語】 ・朝起き三両始末五両 ...
 「は」で始まることわざ
「は」で始まることわざ「早牛も淀、遅牛も淀」の意味(語源由来・類義語) 【ことわざ】 早牛も淀、遅牛も淀 【読み方】 はやうしもよど、おそうしもよど 【意味】 どうやっても行きつく所は同じなのだから、あわてる必要はないということ。 【語源由来...
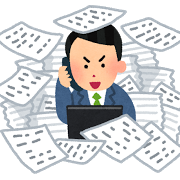 「は」で始まることわざ
「は」で始まることわざ「早い者に上手なし」の意味(類義語・英語訳) 【ことわざ】 早い者に上手なし 【読み方】 はやいものにじょうずなし 【意味】 仕事が早いものには、できあがりが雑になることがあるということ。 【類義語】 ・早かろう悪かろう...
 「は」で始まることわざ
「は」で始まることわざ「早いが勝ち」の意味 【ことわざ】 早いが勝ち 【読み方】 はやいがかち 【意味】 人より先にした者が利益を得るということ。 「早いが勝ち」の解説 「早いが勝ち」の使い方 「早いが勝ち」の例文 現代では、特許をとったもの...
 「は」で始まることわざ
「は」で始まることわざ「早い馬も千里、のろい牛も千里」の意味(語源由来・類義語) 【ことわざ】 早い馬も千里、のろい牛も千里 【読み方】 はやいうまもせんり、のろいうしもせんり 【意味】 どうやっても結局は同じところに達するのだから、あわてる...
 「は」で始まることわざ
「は」で始まることわざ「鱧も一期、海老も一期」の意味(語源由来・類義語) 【ことわざ】 鱧も一期、海老も一期 【読み方】 はももいちご、えびもいちご 【意味】 境遇の違いはあっても、人の一生は大体同じであるということ。 【語源由来】 エビを餌...
 「は」で始まることわざ
「は」で始まることわざ「浜の真砂」の意味(語源由来) 【ことわざ】 浜の真砂 【読み方】 はまのまさご 【意味】 数が多いこと。無数にあること。 【語源由来】 数が多くて数えきれないことから。 「浜の真砂」の解説 「浜の真砂」の使い方 「浜の...
 「は」で始まることわざ
「は」で始まることわざ「はまった後で井戸の蓋をする」の意味(語源由来・類義語) 【ことわざ】 はまった後で井戸の蓋をする 【読み方】 はまったあとでいどのふたをする 【意味】 事が起きてしまってから用心すること。 【語源由来】 井戸に誰かが落...
 「は」で始まることわざ
「は」で始まることわざ「蛤で海をかえる」の意味(語源由来・類義語) 【ことわざ】 蛤で海をかえる 【読み方】 はまぐりでうみをかえる 【意味】 とてもなしとげることができないこと、努力しようとも無駄なことのたとえ。 【語源由来】 蛤の貝殻で海...
 「は」で始まることわざ
「は」で始まることわざ「歯亡び舌存す」の意味(出典・語源由来・故事・類義語) 【ことわざ】 歯亡び舌存す 【読み方】 はほろびしたそんす 【意味】 剛強なものはかえって早く滅び、柔軟なものが後まで生き残るというたとえ。 【出典】 「説苑ぜいえ...
 「は」で始まることわざ
「は」で始まることわざ「母の折檻より隣の人の扱いが痛い」の意味(語源由来・類義語) 【ことわざ】 母の折檻より隣の人の扱いが痛い 【読み方】 ははのせっかんよりとなりのひとのあつかいがいたい 【意味】 親の子への愛情の深さをいう。子にとっては...
 「は」で始まることわざ
「は」で始まることわざ「祖母育ちは三百安い」の意味(類義語) 【ことわざ】 祖母育ちは三百安い 【読み方】 ばばそだちさんびゃくやすい 【意味】 おばあちゃんっ子は甘やかされ大切にされるから、他の子より頼りなく出来が悪くみえるということ。 【...
 「は」で始まることわざ
「は」で始まることわざ「母方より食い方」の意味 【ことわざ】 母方より食い方 【読み方】 ははかたよりくいかた 【意味】 親戚を心配する前に、自分の生活を成り立たせることを考える方が大事だということ。 「母方より食い方」の解説 「母方より食い...
 「は」で始まることわざ
「は」で始まることわざ「母ありて一子寒く母去りて三子寒し」の意味(出典・故事) 【ことわざ】 母ありて一子寒く母去りて三子寒し 【読み方】 ははありていっしさむくははさりてさんしさむし 【意味】 継母のせいで寒い思いをするのは継子一人だが、継...
 「は」で始まることわざ
「は」で始まることわざ「跳ねる馬は死んでも跳ねる」の意味(語源由来・類義語) 【ことわざ】 跳ねる馬は死んでも跳ねる 【読み方】 はねるうまはしんでもはねる 【意味】 悪い癖は死んでもなおらないということ。 【語源由来】 跳ねる癖のある馬は、...
 「は」で始まることわざ
「は」で始まることわざ「花を賞するに慎みて離披に至る勿れ」の意味(出典) 【ことわざ】 花を賞するに慎みて離披に至る勿れ 【読み方】 はなをしょうするにつつしみてりひにいたるなかれ 【意味】 花は満開になる前に見るのがよい。物事はピークに達す...
 「は」で始まることわざ
「は」で始まることわざ「鼻をかめと言えば血の出るほどかむ」の意味(語源由来) 【ことわざ】 鼻をかめと言えば血の出るほどかむ 【読み方】 はなをかめといえばちのでるほどかむ 【意味】 人に言われたことに反抗して、度を越したやり方であてつけがま...
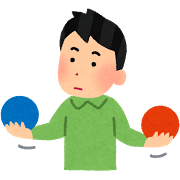 「は」で始まることわざ
「は」で始まることわざ「花も折らず実も取らず」の意味(類義語・対義語) 【ことわざ】 花も折らず実も取らず 【読み方】 はなもおらずみもとらず 【意味】 両方を手に入れようと欲張ると、結局一つも得られないことのたとえ。 【類義語】 ・二兎を追...
 「は」で始まることわざ
「は」で始まることわざ「鼻へ食うと長者になる」の意味 【ことわざ】 鼻へ食うと長者になる 【読み方】 はなへくうとちょうじゃになる 【意味】 油代を惜しんで明かりを灯さず、口と鼻を間違えるほどの暗闇の中で食事をするような倹約家ならば金持ちにな...
 「は」で始まることわざ
「は」で始まることわざ「花発いて風雨多し」の意味(出典・類義語) 【ことわざ】 花発いて風雨多し 【読み方】 はなひらいてふううおおし 【意味】 大事な時には邪魔が入りやすく思い通りにいかないということ。花が咲くころには風や雨になることが多い...
 「は」で始まることわざ
「は」で始まることわざ「花は山人は里」の意味 【ことわざ】 花は山人は里 【読み方】 はなはやまひとはさと 【意味】 物にはそれぞれふさわしい場所があるということ。桜の花は人がいない深山でこそ一番美しく眺めることができ、人間は人里に行っ てこ...
 「は」で始まることわざ
「は」で始まることわざ「花は半開、酒はほろ酔い」の意味(出典・語源由来) 【ことわざ】 花は半開、酒はほろ酔い 【読み方】 はなははんかい、さけはほろよい 【意味】 何事もほどほどがよく、完璧でない点に味わいを感じるということ。 【出典】 「...
 「は」で始まることわざ
「は」で始まることわざ「花は根に帰る、鳥は古巣に帰る」の意味(語源由来) 【ことわざ】 花は根に帰る、鳥は古巣に帰る 【読み方】 はなはねにかえる、とりはふるすにかえる 【意味】 花は木の根元に散って肥料になり、鳥は自分の巣に帰る。全ての物事...
 「は」で始まることわざ
「は」で始まることわざ「花は折りたし梢は高し」の意味(語源由来・類義語) 【ことわざ】 花は折りたし梢は高し 【読み方】 はなはおりたしこずえはたかし 【意味】 思い通りにならないこと。手に入れたいが、その方法がないこと。 【語源由来】 花の...
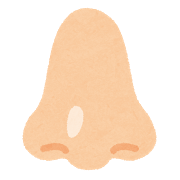 「は」で始まることわざ
「は」で始まることわざ「鼻の先の疣疣」の意味(類義語) 【ことわざ】 鼻の先の疣疣 【読み方】 はなのさきのいぼいぼ 【意味】 邪魔に思えるが、取ることもできないもののこと。 【類義語】 ・目の上の瘤 「鼻の先の疣疣」の解説 「鼻の先の疣疣」...
 「は」で始まることわざ
「は」で始まることわざ「花の下より鼻の下」の意味(語源由来・類義語) 【ことわざ】 花の下より鼻の下 【読み方】 はなのしたよりはなのした 【意味】 風流を楽しむより、生活を成り立たせることの方が大事だということ。 【語源由来】 桜の花の下で...
 「は」で始まることわざ
「は」で始まることわざ「花の傍らの深山木」の意味(語源由来) 【ことわざ】 花の傍らの深山木 【読み方】 花の傍らの深山木 【意味】 優れたもののそばにあって、見劣りするもののたとえ。 【語源由来】 美しく咲きほこる花のそばでは、深い山に生え...
 「は」で始まることわざ
「は」で始まることわざ「花盗人は風流のうち」の意味 【ことわざ】 花盗人は風流のうち 【読み方】 はなぬすびとはふうりゅうのうち 【意味】 美しい花を見てつい一枝折ってしまうのは風流心によるものだから、とがめるほどのことではないということ。 ...
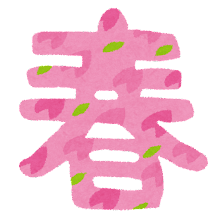 「は」で始まることわざ
「は」で始まることわざ「花に三春の約あり」の意味 【ことわざ】 花に三春の約あり 【読み方】 はなにさんしゅんのやくあり 【意味】 そう約束していたかのように、春になると必ず花が咲くということ。 「花に三春の約あり」の解説 「花に三春の約あり...
 「は」で始まることわざ
「は」で始まることわざ「花七日」の意味(語源由来) 【ことわざ】 花七日 【読み方】 はななぬか 【意味】 盛りの時期が短くはかないことのたとえ。 【語源由来】 桜の花の盛りは七日しかないということから。 「花七日」の解説 「花七日」の使い方...
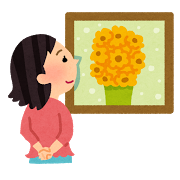 「は」で始まることわざ
「は」で始まることわざ「話を絵に描いたよう」の意味 【ことわざ】 話を絵に描いたよう 【読み方】 はなしをえにかいたよう 【意味】 美しい絵のように、話がうまくまとまり過ぎていて信用できないこと。 「話を絵に描いたよう」の解説 「話を絵に描い...
 「は」で始まることわざ
「は」で始まることわざ「洟垂れ小僧も次第送り」の意味 【ことわざ】 洟垂れ小僧も次第送り 【読み方】 はなたれこぞうもしだいおくり 【意味】 鼻水を垂らしているような幼い子供でも、順に成長して大人になるということ。 「洟垂れ小僧も次第送り」の...
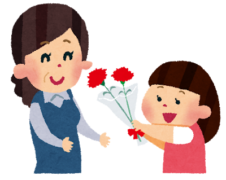 「は」で始まることわざ
「は」で始まることわざ「花好きの畑に花が集まる」の意味(語源由来・類義語) 【ことわざ】 花好きの畑に花が集まる 【読み方】 はなずきのはたけにはながあつまる 【意味】 花が好きな人の所に花が集まるように、自然と好きなものが集まってくること。...
 「は」で始まることわざ
「は」で始まることわざ「話半分」の意味(類義語・英語) 【ことわざ】 話半分 【読み方】 はなしはんぶん 【意味】 話の半分程度はうそや誇張であるから、半分ぐらい割り引いて聞くくらいがちょうどよいということ。 【類義語】 ・話半分嘘半分 ・話...
 「は」で始まることわざ
「は」で始まることわざ「話は立っても足腰立たぬ」の意味 【ことわざ】 話は立っても足腰立たぬ 【読み方】 はなしはたってもあしこしたたぬ 【意味】 話をしているうちに話題が下品なものになると、そろそろおしまいになるということ。 「話は立っても...
 「は」で始まることわざ
「は」で始まることわざ「話は下で果てる」の意味(類義語) 【ことわざ】 話は下で果てる 【読み方】 はなしはしもではてる 【意味】 話をしているうちに話題が下品なものになると、そろそろおしまいになるということ。 【類義語】 ・話が下へ回ると仕...
 「は」で始まることわざ
「は」で始まることわざ「話の名人は嘘の名人」の意味 【ことわざ】 話の名人は嘘の名人 【読み方】 はなしのめいじんはうそのめいじん 【意味】 人に話すのが上手な人は、嘘や誇張表現でおもしろおかしく語ることがあるため注意して話を聞かなければいけ...
 「は」で始まることわざ
「は」で始まることわざ「話の蓋は取らぬが秘密」の意味 【ことわざ】 話の蓋は取らぬが秘密 【読み方】 はなしのふたはとらぬがひみつ 【意味】 秘密は蓋をしたままだから秘密を保てるのであって、不注意に人に話すものではないということ。人に話してし...
 「は」で始まることわざ
「は」で始まることわざ「話では腹は張らぬ」の意味(語源由来・英語) 【ことわざ】 話では腹は張らぬ 【読み方】 はなしでははらははらぬ 【意味】 口先だけで行動が伴わなければ、利益は得られないということ。 【語源由来】 話に聞くだけで実際に食...
 「は」で始まることわざ
「は」で始まることわざ「話し上手の仕事下手」の意味(類義語) 【ことわざ】 話し上手の仕事下手 【読み方】 はなしじょうずのしごとべた 【意味】 口先だけ立派なことをいうも、実務となると役に立たない者をあざけっていう。 【類義語】 ・口叩きの...
 「は」で始まることわざ
「は」で始まることわざ「鳩の豆使い」の意味(語源由来・類義語) 【ことわざ】 鳩の豆使い 【読み方】 はとのまめつかい 【意味】 お使いの途中で寄り道して戻ってこないこと。 【語源由来】 鳩は好物の豆を見ると、食べることに夢中になって他のこと...
 「は」で始まることわざ
「は」で始まることわざ「話し上手の口下手」の意味 【ことわざ】 話し上手の口下手 【読み方】 はなしじょうずのくちべた 【意味】 話術はないが、聞き手が理解できるように話すことができる人のことをいう。 「話し上手の口下手」の解説 「話し上手の...
 「は」で始まることわざ
「は」で始まることわざ「鼻毛を読む」の意味(類義語) 【ことわざ】 鼻毛を読む 【読み方】 はなげをよむ 【意味】 女性が、自分にうつつをぬかす男性を見ぬいて、思うようにもてあそぶこと。愚弄すること。 【類義語】 ・鼻毛を数える ・尻毛を抜く...
 「は」で始まることわざ
「は」で始まることわざ「鼻毛を抜く」の意味(類義語) 【ことわざ】 鼻毛を抜く 【読み方】 はなげをぬく 【意味】 相手を手玉に取ったり、だましたり迷わせること。 【類義語】 ・鼻毛を読む 「鼻毛を抜く」の解説 「鼻毛を抜く」の使い方 「鼻毛...
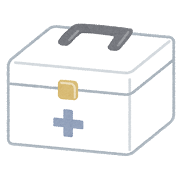 「は」で始まることわざ
「は」で始まることわざ「鼻糞丸めて万金丹」の意味 【ことわざ】 鼻糞丸めて万金丹 【読み方】 はなくそまるめてまんきんたん 【意味】 薬の原料は案外つまらないものが多いこと。また、薬効がないことのたとえ。子どもが鼻糞をほじり丸めたりしているの...
 「は」で始まることわざ
「は」で始まることわざ「端から和尚はない」の意味(類義語) 【ことわざ】 端から和尚はない 【読み方】 はなからおしょうはない 【意味】 物事には順番や段階があって、一足飛びには進めないということ。 【類義語】 ・沙弥から長者にはなれぬ 「端...
 「は」で始まることわざ
「は」で始まることわざ「花が見たくば吉野へござれ」の意味(語源由来) 【ことわざ】 花が見たくば吉野へござれ 【読み方】 はながみたくばよしのへござれ 【意味】 本場へ行き本物に触れることが、一番大事だということ。 【語源由来】 桜の花が見た...
 「は」で始まることわざ
「は」で始まることわざ「花多ければ実少なし」の意味(語源由来・類義語) 【ことわざ】 花多ければ実少なし 【読み方】 はなおおければみすくなし 【意味】 外見を飾る人は、誠実さに欠けるものだということ。 【語源由来】 花がたくさん咲く木には、...
 「は」で始まることわざ
「は」で始まることわざ「鳩を憎み豆を作らぬ」の意味(語源由来) 【ことわざ】 鳩を憎み豆を作らぬ 【読み方】 はとをにくみまめをつくらぬ 【意味】 些細なことにこだわって大切なことをしないために、自分や世間に損害を与えること。 【語源由来】 ...
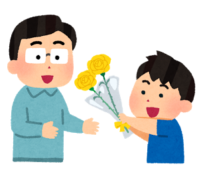 「は」で始まることわざ
「は」で始まることわざ「鳩に三枝の礼あり、烏に反哺の孝あり」の意味(語源由来・類義語) 【ことわざ】 鳩に三枝の礼あり、烏に反哺の孝あり 【読み方】 はとにさんしのれいあり、からすにはんぽのこうあり 【意味】 礼儀と孝行を大事にするべきだとい...
 「は」で始まることわざ
「は」で始まることわざ「髪を簡して櫛る」の意味(出典・語源由来・類義語) 【ことわざ】 髪を簡して櫛る 【読み方】 はつをかんしてくしけずる 【意味】 細かいことに過剰にこだわること。必要のないことを入念にすること。 【出典】 「荘子そうじ」...
 「は」で始まることわざ
「は」で始まることわざ「初雪は目の薬」の意味 【ことわざ】 初雪は目の薬 【読み方】 はつゆきはめのくすり 【意味】 真っ白で目に鮮やかな初雪をたたえていうことば。白く美しい初雪は、目の疲れや汚れを取ってくれるということ。 「初雪は目の薬」の...
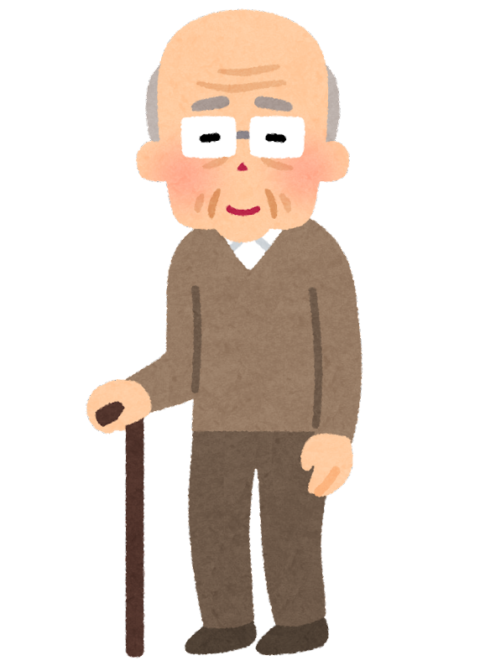 「は」で始まることわざ
「は」で始まることわざ「初物七十五日」の意味 【ことわざ】 初物七十五日 【読み方】 はつものしちじゅうごにち 【意味】 初物を珍重する俗説で、初物を食べると寿命が75日延びるとされる。 「初物七十五日」の解説 「初物七十五日」の使い方 「初...
 「は」で始まることわざ
「は」で始まることわざ「八歳の翁、百歳の童」の意味 【ことわざ】 八歳の翁、百歳の童 【読み方】 はっさいのおきな、ひゃくさいのわらんべ 【意味】 子どもであっても知恵も分別もある子もいれば、老人でも無知で分別がない愚かな大人もいる。人の賢さ...
 「は」で始まることわざ
「は」で始まることわざ「伐性の斧」の意味(出典・語源由来) 【ことわざ】 伐性の斧 【読み方】 ばっせいのおの 【意味】 人の身体や心に害を与えるもののこと。女性におぼれたり、身の程知らずの幸運に期待すること。 【出典】 「呂氏春秋りょししゅ...
 「は」で始まることわざ
「は」で始まることわざ「八卦裏返り」の意味(類義語) 【ことわざ】 八卦裏返り 【読み方】 はっけうらがえり 【意味】 占いは真逆に出ることが多く、悪い結果が出ても気にすることはないということ。 【類義語】 ・夢は逆夢 「八卦裏返り」の解説 ...
 「は」で始まることわざ
「は」で始まることわざ「白駒の隙を過ぐるが如し」の意味(出典・語源由来・類義語) 【ことわざ】 白駒の隙を過ぐるが如し 【読み方】 はっくのげきをすぐるがごとし 【意味】 月日の経つのがとてもはやいこと。 【出典】 「荘子そうじ」 【語源由来...
 「は」で始まることわざ
「は」で始まることわざ「八分は足らず十分はこぼれる」の意味(語源由来) 【ことわざ】 八分は足らず十分はこぼれる 【読み方】 はちぶはたらずじゅうぶんはこぼれる 【意味】 何事もほどほどで満足して、あまり欲張らない方が良いということ。 【語源...
 「は」で始まることわざ
「は」で始まることわざ「八分されても未だ二分残る」の意味(語源由来) 【ことわざ】 八分されても未だ二分残る 【読み方】 ばちはめのまえ 【意味】 仲間外れにされても負けないということ。 【語源由来】 八分にされても、まだ二分のこっているとい...
 「は」で始まることわざ
「は」で始まることわざ「罰は目の前」の意味(類義語) 【ことわざ】 罰は目の前 【読み方】 ばちはめのまえ 【意味】 悪い事をすると、すぐに罰が当たること。因果応報が早いこと。 【類義語】 ・天罰覿面てんばつてきめん 「罰は目の前」の解説 「...
 「は」で始まることわざ
「は」で始まることわざ「八十の三つ子」の意味(語源由来・英語) 【ことわざ】 八十の三つ子 【読み方】 はちじゅうのみつご 【意味】 年老いると、無邪気な子供のようになるということ。 【語源由来】 八十歳は三歳の幼児と同じという意から。 【英...
 「は」で始まることわざ
「は」で始まることわざ「八十の手習い」の意味(英語) 【ことわざ】 八十の手習い 【読み方】 はちじゅうのてならい 【意味】 年老いてから学問や習い事を始めること。晩学。 【英語】 Never too old to learn.(年を取り過ぎ...
 「は」で始まることわざ
「は」で始まることわざ「八細工七貧乏」の意味(類義語) 【ことわざ】 八細工七貧乏 【読み方】 はちざいくしちびんぼう 【意味】 なんでもできる器用な人が、一つの事に集中できずどれも中途半端で貧乏することが多いということ。また、そのような人。...
 「は」で始まることわざ
「は」で始まることわざ「働けば回る」の意味 【ことわざ】 働けば回る 【読み方】 はたらけばまわる 【意味】 働くほどに金回りが良くなるということ。 「働けば回る」の解説 「働けば回る」の使い方 「働けば回る」の例文 どうすれば儲かるか。考え...
 「は」で始まることわざ
「は」で始まることわざ「働かざる者食うべからず」の意味(出典・英語) 【ことわざ】 働かざる者食うべからず 【読み方】 はたらかざるものくうべからず 【意味】 働かない怠惰な人間は、食べることが許されないということ。 【出典】 「新約聖書」 ...
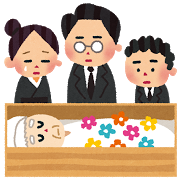 「は」で始まることわざ
「は」で始まることわざ「二十後家は立つが三十後家は立たぬ」の意味(類義語) 【ことわざ】 二十後家は立つが三十後家は立たぬ 【読み方】 はたちごけはたつがさんじゅうごけはたたぬ 【意味】 何事にも相応の準備が必要だということ。 【類義語】 ・...
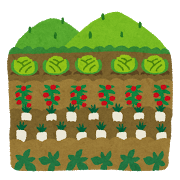 「は」で始まることわざ
「は」で始まることわざ「畑あっての芋種」の意味(語源由来) 【ことわざ】 畑あっての芋種 【読み方】 はたけあってのいもだね 【意味】 良い母親じゃないと良い子は生まれてこない。 【語源由来】 畑がなければ、よい芋種があっても芋は育たないこと...
 「は」で始まることわざ
「は」で始まることわざ「裸百貫」の意味 【ことわざ】 裸百貫 【読み方】 はだかひゃっかん 【意味】 財産が全く無くても、男は銭百貫文の価値があるということ。 「裸百貫」の解説 「裸百貫」の使い方 「裸百貫」の例文 財産と呼べるものは何もない...
 「は」で始まることわざ
「は」で始まることわざ「裸で道中はならぬ」の意味(語源由来) 【ことわざ】 裸で道中はならぬ 【読み方】 はだかでどうちゅうはならぬ 【意味】 何事にも相応の準備が必要だということ。 【語源由来】 一文無しでは旅をすることはできない意から。 ...
 「は」で始まることわざ
「は」で始まることわざ「裸馬の捨て鞭」の意味 【ことわざ】 裸馬の捨て鞭 【読み方】 はだかうまのすてむち 【意味】 すべてを失い、やけになって無茶苦茶なことをすること。 「裸馬の捨て鞭」の解説 「裸馬の捨て鞭」の使い方 「裸馬の捨て鞭」の例...
 「は」で始まることわざ
「は」で始まることわざ「肌に粟を生ず」の意味(語源由来) 【ことわざ】 肌に粟を生ず 【読み方】 はだえにあわをしょうず 【意味】 寒さや恐ろしさのために身震いするさま。鳥肌が立つ。 【語源由来】 皮膚が収縮し、肌に粟つぶのようなものが出るこ...
 「は」で始まることわざ
「は」で始まることわざ「鯊の鉤で、はたやは釣れぬ」の意味(語源由来・対義語) 【ことわざ】 鯊の鉤で、はたやは釣れぬ 【読み方】 はぜのはりで、はたやはつれぬ 【意味】 少しの利益では、人を動かすことはできないということ。 【語源由来】 ハゼ...
 「は」で始まることわざ
「は」で始まることわざ「蓮の台の半座を分かつ」の意味(語源由来・類義語) 【ことわざ】 蓮の台の半座を分かつ 【読み方】 はすのうてなのはんざをわかつ 【意味】 強いきずなで結ばれた仲のこと。 【語源由来】 死後も極楽浄土で、一枚の蓮華の台座...
 「は」で始まることわざ
「は」で始まることわざ「恥を知るは勇に近し」の意味(出典) 【ことわざ】 恥を知るは勇に近し 【読み方】 はじをしるはゆうにちかし 【意味】 自分の間違いを素直に認めることは、勇気が必要だ。名誉を重んじ恥を知る者は、勇気ある者といえる。 【出...
 「は」で始まることわざ
「は」で始まることわざ「恥を言わねば理が聞こえぬ」の意味 【ことわざ】 恥を言わねば理が聞こえぬ 【読み方】 はじをいわねばりがきこえぬ 【意味】 隠しておきたい恥もすべて打ち明けなければ、自分の事情をよく理解してもらえないということ。 「恥...
 「は」で始まることわざ
「は」で始まることわざ「走れば躓く」の意味(類義語・対義語) 【ことわざ】 走れば躓く 【読み方】 はしればつまずく 【意味】 急いでいる時こそ落ち着くべきだということ。急いで走ろうとすると気が急いてつまずくように、慌てると失敗することが多い...
 「は」で始まることわざ
「は」で始まることわざ「走り馬の草を食うよう」の意味 【ことわざ】 走り馬の草を食うよう 【読み方】 はしりうまのくさをくうよう 【意味】 円滑ではなくぎこちないこと。走る馬が立ち止まって草を食べ、再び走っては草を食べ、調子が一定でないこと。...
 「は」で始まることわざ
「は」で始まることわざ「柱には虫入るも鋤の柄には虫入らず」の意味(語源由来・類義語) 【ことわざ】 柱には虫入るも鋤の柄には虫入らず 【読み方】 はしらにはむしいるもすきのえにはむしいらず 【意味】 怠惰なものは心がたるみだめになるが、働き者...
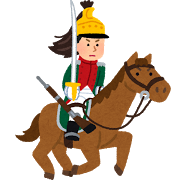 「は」で始まることわざ
「は」で始まることわざ「馬上に居て之を得」の意味(出典・故事) 【ことわざ】 馬上に居て之を得 【読み方】 ばじょうにいてこれをう 【意味】 馬に乗り戦って、武力で天下をとること。 【出典】 「史記しき」 【故事】 中国漢の高祖は、臣の陸賈り...
 「は」で始まることわざ
「は」で始まることわざ「箸より重いものを持たない」の意味(語源由来) 【ことわざ】 箸より重いものを持たない 【読み方】 はしよりおもいものをもたない 【意味】 裕福な家に生まれ育ち、働いたことがないということ。 【語源由来】 箸を持つ以上の...
 「は」で始まることわざ
「は」で始まることわざ「箸も持たぬ乞食」の意味(語源由来・類義語) 【ことわざ】 箸も持たぬ乞食 【読み方】 はしももたぬこじき 【意味】 何一つもっていないこと。 【語源由来】 箸一つ持っていない乞食の意から。 【類義語】 ・御器も持たぬ乞...
 「は」で始まることわざ
「は」で始まることわざ「始めを慎みて終わりを敬む」の意味(出典) 【ことわざ】 始めを慎みて終わりを敬む 【読み方】 はじめをつつしみておわりをつつしむ 【意味】 何をするにも、最初と最後を慎重に行うことが大事だということ。 【出典】 「春秋...
 「は」で始まることわざ
「は」で始まることわざ「始めを原ねて終わりに反る」の意味(出典) 【ことわざ】 始めを原ねて終わりに反る 【読み方】 はじめをたずねておわりにかえる 【意味】 最初にまでさかのぼって探究してから、終わりまで筋道を立ててきわめる。最初から終わり...
 「は」で始まることわざ
「は」で始まることわざ「始めを言わねば末が聞こえぬ」の意味(類義語) 【ことわざ】 始めを言わねば末が聞こえぬ 【読み方】 はじめをいわねばすえがきこえぬ 【意味】 はじめからきちんと説明しないと、なぜそういう結果になったのか理解できないとい...
 「は」で始まることわざ
「は」で始まることわざ「始めよし後悪し」の意味 【ことわざ】 始めよし後悪し 【読み方】 はじめよしのちわるし 【意味】 はじめが順調だとつい油断して、後で悪い結果を招くということ。はじめに力を出しすぎると、後々差し支えるということ。 「始め...
 「は」で始まることわざ
「は」で始まることわざ「始め半分」の意味(類義語・英語) 【ことわざ】 始め半分 【読み方】 はじめはんぶん 【意味】 何事も始めがうまくいけば、物事の半分は終わったようなものだから、慎重にとりかかれということ。また、あれこれ頭を悩ませるより...
 「は」で始まることわざ
「は」で始まることわざ「始めの囁き後のどよみ」の意味 【ことわざ】 始めの囁き後のどよみ 【読み方】 はじめのささやきあとのどよみ 【意味】 秘密は二、三人にに知られれば、いずれ世間に知られるということ。 「始めの囁き後のどよみ」の解説 「始...
 「は」で始まることわざ
「は」で始まることわざ「始めに二度なし」の意味(類義語) 【ことわざ】 始めに二度なし 【読み方】 はじめににどなし 【意味】 何事も始めが大事だが、一度きりでやり直しがきくものではないということ。 【類義語】 始めが大事 「始めに二度なし」...
 「は」で始まることわざ
「は」で始まることわざ「始めて俑を作る者は其れ後なからんか」の意味(出典・語源由来) 【ことわざ】 始めて俑を作る者は其れ後なからんか 【読み方】 はじめてようをつくるものはそれのちなからんか 【意味】 人道に反するような悪習を最初に作ったも...
 「は」で始まることわざ
「は」で始まることわざ「始めちょろちょろ中ぱっぱ、赤子泣くとも蓋取るな」の意味 【ことわざ】 始めちょろちょろ中ぱっぱ、赤子泣くとも蓋取るな 【読み方】 はじめちょろちょろなかぱっぱ、あかごなくともふたとるな 【意味】 かまどで御飯を上手に炊...
 「は」で始まることわざ
「は」で始まることわざ「始めきらめき奈良刀」の意味(語源由来) 【ことわざ】 始めきらめき奈良刀 【読み方】 はじめきらめきならがたな 【意味】 始めだけ立派に見えること。めっきがはげやすいこと。 【語源由来】 なまくらな奈良刀は、最初のうち...
 「は」で始まることわざ
「は」で始まることわざ「始めあるものは必ず終わりあり」の意味(出典) 【ことわざ】 始めあるものは必ず終わりあり 【読み方】 はじめあるものはかならずおわりあり 【意味】 どんなことにも始めと終わりがあるということ。生あるものには必ず死が訪れ...
 「は」で始まることわざ
「は」で始まることわざ「箸に目鼻をつけても男は男」の意味(類義語) 【ことわざ】 箸に目鼻をつけても男は男 【読み方】 はしにめはなをつけてもおとこはおとこ 【意味】 どんなに落ちぶれようとも、男性は男として尊敬されなければいけないということ...
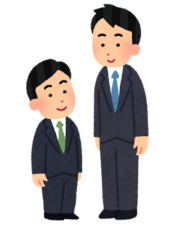 「は」で始まることわざ
「は」で始まることわざ「箸に虹梁」の意味(語源由来) 【ことわざ】 箸に虹梁 【読み方】 はしにこうりょう 【意味】 両者が大きくかけはなれていること。 【語源由来】 細く短い箸と太く長い虹梁では比較にならないほど差があることから。 「箸に虹...
 「は」で始まることわざ
「は」で始まることわざ「箸に当たり棒に当たる」の意味 【ことわざ】 箸に当たり棒に当たる 【読み方】 はしにあたりぼうにあたる 【意味】 怒りを無関係な者に八つ当たりすること。 「箸に当たり棒に当たる」の解説 「箸に当たり棒に当たる」の使い方...
 「は」で始まることわざ
「は」で始まることわざ「箸と主とは太いのへかかれ」の意味(類義語) 【ことわざ】 箸と主とは太いのへかかれ 【読み方】 はしとしゅうとはふといのへかかれ 【意味】 箸は太くて折れないものがいいように、仕える主人も頼れるしっかりした人がいい。 ...
 「は」で始まることわざ
「は」で始まることわざ「橋がなければ渡られぬ」の意味(類義語) 【ことわざ】 橋がなければ渡られぬ 【読み方】 はしがなければわたられぬ 【意味】 仲立ちがなければ物事がうまくいかないものだ。目的達成のためには、様々な手段・方法が必要だという...
 「は」で始まることわざ
「は」で始まることわざ「箸が転んでもおかしい年頃」の意味 【ことわざ】 箸が転んでもおかしい年頃 【読み方】 はしがころんでもおかしいとしごろ 【意味】 知ったかぶりをして話すこと。 「箸が転んでもおかしい年頃」の解説 「箸が転んでもおかしい...
 「は」で始まることわざ
「は」で始まることわざ「箱根知らずの江戸話」の意味(語源由来・類義語) 【ことわざ】 箱根知らずの江戸話 【読み方】 はこねしらずのえどばなし 【意味】 知ったかぶりをして話すこと。 【語源由来】 関西の人が箱根の山を越えたこともないのに、江...
 「は」で始まることわざ
「は」で始まることわざ「擌にかかれる鳥」の意味(語源由来) 【ことわざ】 擌にかかれる鳥 【読み方】 はごにかかれるとり 【意味】 逃げようとも逃げることができないこと。 【語源由来】 擌にかかった鳥は、もがこうとも逃れられないことから。 「...
 「は」で始まることわざ
「は」で始まることわざ「禿が三年目につかぬ」の意味(類義語) 【ことわざ】 禿が三年目につかぬ 【読み方】 はげがさんねんめにつかぬ 【意味】 好きな人の禿げた頭は、三年間気にならない。 【類義語】 ・痘痕あばたも靨えくぼ 「禿が三年目につか...
 「は」で始まることわざ
「は」で始まることわざ「白鷺は塵土の穢れを禁ぜず」の意味(語源由来) 【ことわざ】 白鷺は塵土の穢れを禁ぜず 【読み方】 はくろはじんどのけがれをきんぜず 【意味】 清廉潔白なものは、どんな環境に置かれても正しさをまげない。 【語源由来】 シ...
 「は」で始まることわざ
「は」で始まることわざ「歯車が嚙み合わない」の意味(語源由来) 【ことわざ】 歯車が嚙み合わない 【読み方】 はぐるまがかみあわない 【意味】 人の考えや動きがくいちがって、スムーズに事が運ばないこと。 【語源由来】 歯車の歯と歯がうまく合わ...
 「は」で始まることわざ
「は」で始まることわざ「伯楽の一顧」の意味(出典・故事) 【ことわざ】 伯楽の一顧 【読み方】 はくらくのいっこ 【意味】 鑑識眼のある者から才能を認められ、重用されること。世に埋もれていた才能を実力者に見出され、発揮すること。 【出典】 「...
 「は」で始まることわざ
「は」で始まることわざ「伯兪杖に泣く」の意味(出典・語源由来・故事) 【ことわざ】 伯兪杖に泣く 【読み方】 はくゆつえになく 【意味】 親孝行な子が、親を思う気持ちの厚いこと。 【出典】 説苑ぜいえん 【語源由来】 親が年老いたことに気付い...
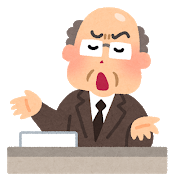 「は」で始まることわざ
「は」で始まることわざ「莫耶を鈍しと為し鉛刀を銛しと為す」の意味(出典・語源由来) 【ことわざ】 莫耶を鈍しと為し鉛刀を銛しと為す 【読み方】 ばくやをにぶしとなしえんとうをするどしとなす 【意味】 人の賢さや愚かさに関する世間の評判が当てに...
 「は」で始まることわざ
「は」で始まることわざ「白面の書生」の意味(出典) 【ことわざ】 白面の書生 【読み方】 はくめんのしょせい 【意味】 年若く経験不足の学者や学生のことをいう。また、読書人。 【出典】 「宋書そうじょ」 中国、宋の文帝が北魏を討とうとしたとき...
 「は」で始まることわざ
「は」で始まることわざ「白璧の微瑕」の意味(出典・語源由来・類義語) 【ことわざ】 白璧の微瑕 【読み方】 はくへきのびか 【意味】 完璧なものに少しの欠点があること。また、それがあって惜しまれること。 【出典】 蕭統しょうとう「陶淵明集序と...
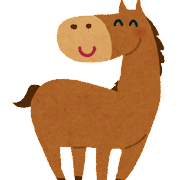 「は」で始まることわざ
「は」で始まることわざ「白馬は馬に非ず」の意味(出典・類義語) 【ことわざ】 白馬は馬に非ず 【読み方】 はくばはうまにあらず 【意味】 詭弁。こじつけ。 【出典】 「公孫竜子こうそんりゅうし」 【類義語】 ・堅白同異の弁 「白馬は馬に非ず」...
 「は」で始まることわざ
「は」で始まることわざ「白眉」の意味(出典・故事) 【ことわざ】 白眉 【読み方】 はくび 【意味】 多数あるものの中で、最もすぐれている人や物のこと。 【出典】 「三国志さんごくし」 【故事】 中国三国時代、蜀 (しょく) の馬氏の五人兄弟...
 「は」で始まることわざ
「は」で始まることわざ「白頭新の如し」の意味(出典・語源由来) 【ことわざ】 白頭新の如し 【読み方】 はくとうしんのごとし 【意味】 交際の深さは時間の長さではなく、相手の気持ちを知るかどうかだということ。 【出典】 「史記しき」 【語源由...
 「は」で始まることわざ
「は」で始まることわざ「白鳥の歌」の意味(語源由来) 【ことわざ】 白鳥の歌 【読み方】 はくちょうのうた 【意味】 ある人が最後に作った詩歌、曲、演奏をたたえていう。 【語源由来】 白鳥は死ぬ前に一度だけ美しい声で鳴くというヨーロッパの伝説...
 「は」で始まることわざ
「は」で始まることわざ「伯仲の間」の意味(出典・語源由来・類義語) 【ことわざ】 伯仲の間 【読み方】 はくちゅうのかん 【意味】 差がなく優劣がつけにくい。互角であること。 【出典】 「典論てんろん」 【語源由来】 昔の中国では、兄弟の上の...
 「は」で始まることわざ
「は」で始まることわざ「博奕は色より三分濃し」の意味(語源由来) 【ことわざ】 博奕は色より三分濃し 【読み方】 ばくちはいろよりさんぶこし 【意味】 ばくちの魅力にはあらがえず、やめることができない。 【語源由来】 ばくちは女遊びよりおもし...
 「は」で始まることわざ
「は」で始まることわざ「博打と相場は死ぬまで止まぬ」の意味 【ことわざ】 博打と相場は死ぬまで止まぬ 【読み方】 ばくちとそうばはしぬまでやまぬ 【意味】 賭け事も相場も、一度はまったら抜け出せなくなること。 「博打と相場は死ぬまで止まぬ」の...
 「は」で始まることわざ
「は」で始まることわざ「白刃前に交われば流矢を顧みず」の意味(出典・語源由来) 【ことわざ】 白刃前に交われば流矢を顧みず 【読み方】 はくじんまえにまじわればりゅうしをかえりみず 【意味】 大きな困難を前にしては、小さな困難を顧みる余裕のな...
 「は」で始まることわざ
「は」で始まることわざ「柏舟の操」の意味(出典・故事) 【ことわざ】 柏舟の操 【読み方】 はくしゅうのみさお 【意味】 未亡人が夫に操をたてること。 【出典】 「詩経しきょう」 【故事】 中国春秋時代、衛の太子共伯の妻が夫の死後も父母のすす...
 「は」で始まることわざ
「は」で始まることわざ「麦秀の嘆」の意味(出典・故事) 【ことわざ】 麦秀の嘆 【読み方】 ばくしゅうのたん 【意味】 生まれ育った国が滅びることを嘆くこと。 【出典】 「史記しき」 【故事】 中国古代、殷の紂王ちゅうおうのおじである箕子きし...
 「は」で始まることわざ
「は」で始まることわざ「白玉楼中の人となる」の意味(出典・語源由来・類義語) 【ことわざ】 白砂は泥中に在りて之と皆黒し 【読み方】 はくさはでいちゅうにありてこれとみなくろし 【意味】 悪い環境におかれると、良いものも悪くなること。 【出典...
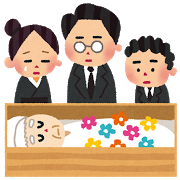 「は」で始まることわざ
「は」で始まることわざ「白玉楼中の人となる」の意味(出典・故事) 【ことわざ】 白玉楼中の人となる 【読み方】 はくぎょくろうちゅうのひととなる 【意味】 文人が亡くなること。 【出典】 「李商隠りしょういん–李長吉小伝りちょうき...
 「は」で始まることわざ
「は」で始まることわざ「伯牙、琴を破る」の意味(出典・故事・類義語) 【ことわざ】 伯牙、琴を破る 【読み方】 はくが、ことをやぶる 【意味】 理解者である親友を失った悲しみのこと。 【出典】 「呂氏春秋りょししゅんじゅう」 【故事】 中国春...
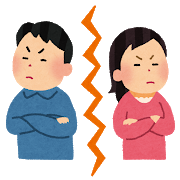 「は」で始まることわざ
「は」で始まることわざ「破鏡重ねて照らさず、落花枝に上り難し」の意味(出典・語源由来・類義語) 【ことわざ】 破鏡重ねて照らさず、落花枝に上り難し 【読み方】 はきょうかさねててらさず、らっかえだにのぼりがたし 【意味】 一旦損なわれたものは...
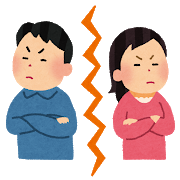 「は」で始まることわざ
「は」で始まることわざ「破鏡」の意味(出典・故事・類義語) 【ことわざ】 破鏡 【読み方】 はきょう 【意味】 離婚する。夫婦の別れ。 【出典】 「神異経しんいけい」 【故事】 やむをえず別居することになった夫婦が、鏡を二つに割って半分ずつ持...
 「は」で始まることわざ
「は」で始まることわざ「謀を以て謀を討つ」の意味 【ことわざ】 謀を以て謀を討つ 【読み方】 はかりごとをもってはかりごとをうつ 【意味】 敵の計略を逆手に取り裏をかくこと。 「謀を以て謀を討つ」の解説 「謀を以て謀を討つ」の使い方 「謀を以...
 「は」で始まることわざ
「は」で始まることわざ「籌を帷幄の中に運らし、勝ちを千里の外に決す」の意味(出典・故事) 【ことわざ】 籌を帷幄の中に運らし、勝ちを千里の外に決す 【読み方】 はかりごとをいあくのうちにめぐらし、かちをせんりのほかにけっす 【意味】 本陣にい...
 「は」で始まることわざ
「は」で始まることわざ「謀は密なるを貴ぶ」の意味(出典) 【ことわざ】 謀は密なるを貴ぶ 【読み方】 はかりごとはみつなるをたっとぶ 【意味】 事前準備をしっかりしてから始めれば、失敗しないということ。 【出典】 「三略さんりゃく」 「謀は密...
 「は」で始まることわざ
「は」で始まることわざ「謀定まりて後戦う」の意味(出典・語源由来) 【ことわざ】 謀定まりて後戦う 【読み方】 はかりごとさだまりてのちたたかう 【意味】 事前準備をしっかりしてから始めれば、失敗しないということ。 【出典】 「新唐書しんとう...
 「は」で始まることわざ
「は」で始まることわざ「測り難きは人心」の意味(出典) 【ことわざ】 測り難きは人心 【読み方】 はかりがたきはひとごころ 【意味】 人の心ほど推し量るのが難しいものはない。人の心は変わりやすく頼りにならないということ。 【出典】 「史記しき...
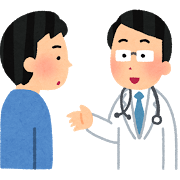 「は」で始まることわざ
「は」で始まることわざ「馬鹿は死ななきゃ治らない」の意味(類義語) 【ことわざ】 馬鹿は死ななきゃ治らない 【読み方】 ばかはしななきゃなおらない 【意味】 利口ぶったりしないのが真の利口者で、利口ぶるのが愚か者だということ。 【類義語】 ・...
 「は」で始まることわざ
「は」で始まることわざ「馬鹿の真似する利口者、利口の真似する馬鹿者」の意味(類義語) 【ことわざ】 馬鹿の真似する利口者、利口の真似する馬鹿者 【読み方】 ばかのまねするりこうもの、りこうのまねするばかもの 【意味】 利口ぶったりしないのが真...
 「は」で始まることわざ
「は」で始まることわざ「刃金が棟へ回る」の意味(語源由来・類義語) 【ことわざ】 刃金が棟へ回る 【読み方】 はがねがむねへまわる 【意味】 知恵や力量が衰えていくこと。 【語源由来】 刀の鋼がすり減って峰で切るようになり、切れ味が悪くなる意...
 「は」で始まることわざ
「は」で始まることわざ「墓に布団は着せられず」の意味(語源由来・類義語) 【ことわざ】 墓に布団は着せられず 【読み方】 はかにふとんはきせられず 【意味】 親が存命中に孝行をせよということ。 【語源由来】 寒いだろうと墓に蒲団を掛けても何に...
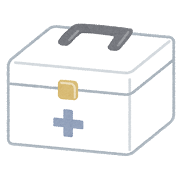 「は」で始まることわざ
「は」で始まることわざ「馬鹿に付ける薬はない」の意味(類義語・英語) 【ことわざ】 馬鹿に付ける薬はない 【読み方】 ばかにつけるくすりはない 【意味】 愚かな者をなおす薬はない。馬鹿に何をしても救いようがない。 【類義語】 ・下愚の性移るべ...
 「は」で始まることわざ
「は」で始まることわざ「馬鹿な子ほど可愛い」の意味(類義語) 【ことわざ】 馬鹿な子ほど可愛い 【読み方】 ばかなこほどかわいい 【意味】 親にとっては、賢い子より愚かな子のほうがふびんでかわいいということ。 【類義語】 ・純な子は可愛い ・...
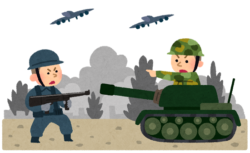 「は」で始まることわざ
「は」で始まることわざ「馬革を以て屍を裹む」の意味 【ことわざ】 馬革を以て屍を裹む 【読み方】 ばかくをもってしかばねをつつむ 【意味】 戦士が戦場で死ぬこと。また、戦場で死ぬことが戦士の本望だということ。 【出典】 「後漢書ごかんじょ」 ...
 「は」で始まることわざ
「は」で始まることわざ「馬鹿と煙は高いところへ上る」の意味 【ことわざ】 馬鹿と煙は高いところへ上る 【読み方】 ばかとけむりはたかいところへのぼる 【意味】 煙が上に上がるように、馬鹿はおだてにのりやすいということ。 「馬鹿と煙は高いところ...
 「は」で始まることわざ
「は」で始まることわざ「化かす化かすが化かされる」の意味(類義語) 【ことわざ】 化かす化かすが化かされる 【読み方】 ばかすばかすがばかされる 【意味】 人をだまそうとしたのに、だまそうとした人からだまされてしまうこと。 【類義語】 ・騙す...
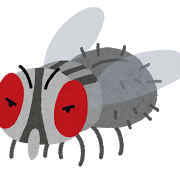 「は」で始まることわざ
「は」で始まることわざ「蠅が飛べば虻も飛ぶ」の意味(類義語) 【ことわざ】 蠅が飛べば虻も飛ぶ 【読み方】 はえがとべばあぶもとぶ 【意味】 似ている者同士は、お互いに真似をすること。むやみやたらに同調すること。 【類義語】 ・雁が立てば鳩も...
 「は」で始まることわざ
「は」で始まることわざ「枚を銜む」の意味 【ことわざ】 枚を銜む 【読み方】 ばいをふくむ 【意味】 声をたてずに息をこらすこと。 「枚を銜む」の解説 「枚を銜む」の使い方 「枚を銜む」の例文 母さんはばあちゃん(父さんの母さん)を街で見かけ...
 「は」で始まることわざ
「は」で始まることわざ「灰を吹いて眯する無からんと欲す」の意味(出典・語源由来) 【ことわざ】 灰を吹いて眯する無からんと欲す 【読み方】 はいをふいてべいするなからんとほっす 【意味】 無理な望みや自分勝手な望みのこと。 【出典】 「淮南子...
 「は」で始まることわざ
「は」で始まることわざ「肺腑を衝く」の意味 【ことわざ】 肺腑を衝く 【読み方】 はいふをつく 【意味】 人の心の奥底までひびくこと。深い感銘や衝撃を与えること。 「肺腑を衝く」の解説 「肺腑を衝く」の使い方 「肺腑を衝く」の例文 恩師の言葉...
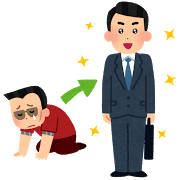 「は」で始まることわざ
「は」で始まることわざ「灰を飲み胃を洗う」の意味(出典・語源由来) 【ことわざ】 灰を飲み胃を洗う 【読み方】 はいをのみいをあらう 【意味】 改心して善人になること。 【出典】 「南史なんし」 【語源由来】 灰を飲んで汚れた胃の中を洗い清め...
 「は」で始まることわざ
「は」で始まることわざ「掃いて捨てるほど」の意味(類義語) 【ことわざ】 掃いて捨てるほど 【読み方】 はいてすてるほど 【意味】 とても多くてあり余るほどであるということ。多すぎて希少性がなく価値が感じられないこと。 【類義語】 ・浜の真砂...
 「は」で始まることわざ
「は」で始まることわざ「吐いた唾は呑めぬ」の意味(類義語・対義語) 【ことわざ】 吐いた唾は呑めぬ 【読み方】 はいたつばはのめぬ 【意味】 発言した後で、その発言を取り消すことはできないということ。 【類義語】 ・口から出れば世間 【対義語...
 「は」で始まることわざ
「は」で始まることわざ「杯杓に勝えず」の意味(出典) 【ことわざ】 杯杓に勝えず 【読み方】 はいしゃくにたえず 【意味】 酒を飲み過ぎて、それ以上飲めないということ。 【出典】 「史記しき」 「杯杓に勝えず」の解説 「杯杓に勝えず」の使い方...
 「は」で始まることわざ
「は」で始まることわざ「梅花は莟めるに香あり」の意味(語源由来・類義語) 【ことわざ】 梅花は莟めるに香あり 【読み方】 ばいかはつぼめるにかあり 【意味】 将来偉大になる人は、子供の時から人並みはずれたところがあるということ。 【語源由来】...
 「は」で始まることわざ
「は」で始まることわざ「奪い合う物は中から取る」の意味(類義語) 【ことわざ】 奪い合う物は中から取る 【読み方】 ばいあうものはなかからとる 【意味】 二人が奪い合っている内に、第三者が利益を横から奪っていってしまうこと。 【類義語】 ・争...
 「は」で始まることわざ
「は」で始まることわざ「春の雪と叔母の杖は怖くない」の意味(語源由来) 【ことわざ】 春の雪と叔母の杖は怖くない 【読み方】 はるのゆきとおばのつえはこわくない 【意味】 春の雪も叔母のお説教も恐れるに足りない。 【語源・由来】 叔母のお説教...
 「は」で始まることわざ
「は」で始まることわざ「春に三日の晴れ無し」の意味(語源由来) 【ことわざ】 春に三日の晴れ無し 【読み方】 はるにみっかのはれなし 【意味】 春の晴天は三日ともたない。春は雨が多いということ。 【語源・由来】 春は雨が多いことから。 「春に...
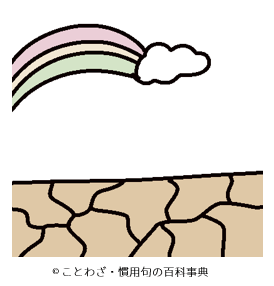 「は」で始まることわざ
「は」で始まることわざ「白虹張れば干天」の意味(語源由来) 【ことわざ】 白虹張れば干天 【読み方】 はっこうはればかんてん 【意味】 色が鮮明ではない虹を白虹といい、この虹が出ると晴れが長く続き干ばつになる。 【語源・由来】 白虹がでるとき...
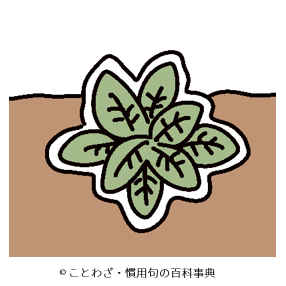 「は」で始まることわざ
「は」で始まることわざ「八十八夜の別れ霜」の意味(語源由来) 【ことわざ】 八十八夜の別れ霜 【読み方】 はちじゅうはちやのわかれじも 【意味】 八十八夜の頃に降りる霜は季節の最後に降りる霜で、これ以後は降りないとされる。 【語源・由来】 「...
 「は」で始まることわざ
「は」で始まることわざ「はこべの花が閉じると雨」の意味(語源由来・類義語) 【ことわざ】 はこべの花が閉じると雨 【読み方】 はこべのはながとじるとあめ 【意味】 はこべの花が閉じると雨が降ることが多い。 【語源・由来】 はこべの花は湿度が高...