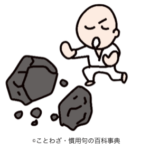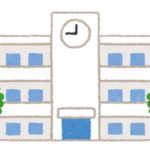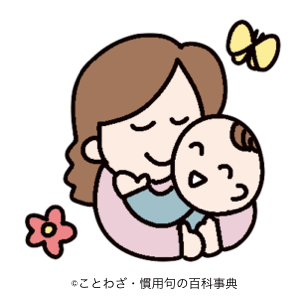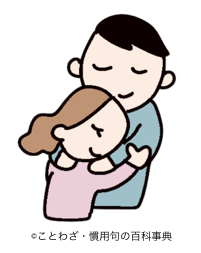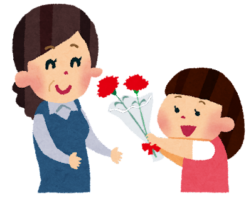目次
- 「あ」で始まる小学校で習う慣用句
- 「い」で始まる小学校で習う慣用句
- 「う」で始まる小学校で習う慣用句
- 「え」で始まる小学校で習う慣用句
- 「お」で始まる小学校で習う慣用句
- 「か」で始まる小学校で習う慣用句
- 「き」で始まる小学校で習う慣用句
- 「く」で始まる小学校で習う慣用句
- 「け」で始まる小学校で習う慣用句
- 「こ」で始まる小学校で習う慣用句
- 「さ」で始まる小学校で習う慣用句
- 「し」で始まる小学校で習う慣用句
- 「す」で始まる小学校で習う慣用句
- 「せ」で始まる小学校で習う慣用句
- 「そ」で始まる小学校で習う慣用句
- 「た」で始まる小学校で習う慣用句
- 「ち」で始まる小学校で習う慣用句
- 「つ」で始まる小学校で習う慣用句
- 「て」で始まる小学校で習う慣用句
- 「と」で始まる小学校で習う慣用句
- 「な」で始まる小学校で習う慣用句
- 「に」で始まる小学校で習う慣用句
- 「ぬ」で始まる小学校で習う慣用句
- 「ね」で始まる小学校で習う慣用句
- 「の」で始まる小学校で習う慣用句
- 「は」で始まる小学校で習う慣用句
- 「ひ」で始まる小学校で習う慣用句
- 「ふ」で始まる小学校で習う慣用句
- 「へ」で始まる小学校で習う慣用句
- 「ほ」で始まる小学校で習う慣用句
- 「ま」で始まる小学校で習う慣用句
- 「み」で始まる小学校で習う慣用句
- 「む」で始まる小学校で習う慣用句
- 「め」で始まる小学校で習う慣用句
- 「も」で始まる小学校で習う慣用句
- 「や」で始まる小学校で習う慣用句
- 「ゆ」で始まる小学校で習う慣用句
- 「よ」で始まる小学校で習う慣用句
- 「ら」で始まる小学校で習う慣用句
- 「り」で始まる小学校で習う慣用句
- 「れ」で始まる小学校で習う慣用句
- 「ろ」で始まる小学校で習う慣用句
- 「わ」で始まる小学校で習う慣用句
「あ」で始まる小学校で習う慣用句

愛想を尽かす
あきれて好意や親愛の情をなくす。見限る。
開いた口が塞がらない
相手の態度やようす、言った言葉を受けて、思っていたよりすごかった為、驚きどう反応していいか分からず、ことばも出ないようすなどのことです。
相槌を打つ
相手の話に同感の意思を伝えるために、うなずいたり調子を合わせたりすること。
合いの手を入れる
歌や踊りに合わせて手拍子を打ったり、掛け声をかけること。また、人との会話で、相手の話を促したり、うまく話題を展開したりするために、言葉を挟むこと。
阿吽の呼吸
「阿吽」とは吐く息と吸う息のことで、二人以上が一緒にある物事をする時のお互いの微妙な調子の合い具合。
青菜に塩
ものごとがうまくいかず、元気がなくなり、しょんぼりしている人の様子。
赤子の手を捻る
①実力がちがいすぎるので、かんたんに相手をまかすことができてしまう。
②抵抗する力がない者に暴力をふるう。
赤の他人
何の関係も縁もない人。
胡坐をかく
いい気になっていて努力、改善をしない。また、ずうずうしい態度をとるたとえ。
揚げ足を取る
言葉尻をとらえたり、言い間違いにつけこんだりして相手をやりこめること。
挙句の果て
物事の最後の結果、最後の最後ということ。
顎が干上がる
生計の手段を失って困る。生活できなくなる。
顎で使う
高慢な態度で人をつかうこと。
顎を出す
疲れてもう動けないような状態のことだが、手に負えなくなって困る状態のこともいう。
足が奪われる
事故やストライキなどで電車やバスが利用できなくなる。
足が地に着かない
緊張や興奮のため心が落ち着かない。考え方や行動が浮ついて、しっかりしていない。
足が付く
身元や足取りが分かること。
足が出る
はじめの予定よりも多くのお金がかかる。赤字になる。
足が棒になる
長い時間歩いたり、立っていたりして足が突っ張って棒のようになってしまう。ひどくつかれる。
足に任せる
特に目的を決めないで、気の向くままに歩く。また、足の力の続く限り歩く。
足の踏み場もない
歩くすき間もないくらいに、たくさんのものがちらかっている。
味も素っ気もない
潤いや面白味が全くない。つまらない。
足元から鳥が立つ
身近な所で思いがけないことが起こるたとえ。また、急に思いついたようにものごとを始めるようすにも使う。
足下(元)に火がつく
危険や都合の悪いことが迫ること。
足下(元)を見る
相手の弱点を見つけて、そこに付け込むたとえ。身近なことを見つめなおすときにも使う。売買や貸借の際の金銭も、こちらの事情を知られてしまうことで、相手のいいなりになってしまう。
足を洗う
汚れた足をきれいに洗うことから、悪いおこないや悪い仲間とのつながりをやめて、まじめに生活すること。
味を占める
一度経験した利益に味を覚えて、またそれを望む。
足をすくう
相手のすきに付け入って、失敗や敗北に導く。
足を運ぶ
出かけていくこと。
足を引っ張る
みんなで力を合わせてよい結果を出そうとしているとき、だれかがそれを妨げるような行いをすること。
足を向けて寝られない
人から受けた恩を常に忘れない気持ちを表す言葉。
頭が上がらない
相手に引け目を感じて、相手と同等の気持ちになれないこと。
頭が痛い
心配ごとがあって、頭が痛くなるほど思い悩むこと。
頭が固い
やわらかで自由な考え方できない。その場その場にあったやり方が出来ないという意味。
頭が切れる
頭の回転が早く、てきぱきと物事を処理する能力があるという意味。
頭が下がる
感心したり、尊敬したりする気持ちになるという意味。
頭を抱える
よい考えが浮かばず、どうしたらいいのかわからなくなってしまう。苦悩しているという意味。
頭を冷やす
高ぶった気持ちを落ち着かせる。冷静になる。
頭をもたげる
①押さえられていたり、隠れていたりした物事や気持ちが表に出て、世間に知られるようになる。
②力をつけてくる。他者を抑えて、その実力を表す。台頭する。
呆気に取られる
思いがけないことにあって、おどろきあきれ、ぼうっとしてしまう。
後味が悪い
物事が終わったあとに残る感じや気分がよくないこと。
後足で砂をかける
今までお世話になった方や恩がある方に、最後の方で裏切った上に、大変な迷惑や被害ををかけて去ることをたとえている。
後の祭り
物事が終わった後に後悔をしても手遅れであるということ。
後を引く
余波がいつまでも続いて、きまりがつかない。尾を引く。
いつまでも欲しい感じが残る。
危ない橋を渡る
危険だと分かっていて、あえて実行することをたとえている。
脂が乗る
仕事などの調子が出て、意欲的に取り組んでいる。
油を売る
むだ話をして、仕事を怠ける。
油を絞る
①あれこれと言葉で厳しく叱ったり責めたりする。
②できない問題や難問を出して力を厳しく試す。
甘い汁を吸う
自分は何もしないで他人の働きで利益を得る。
天の邪鬼
何事によらず人の意見に逆らった行動ばかりするひねくれ者。
合わせる顔がない
面目なくて、その人に会いに行けない。その人の前に出られない。
泡を食う
突然のことに驚き慌てる。
案の定
予想していたとおりに事が運ぶさま。
「い」で始まる小学校で習う慣用句

生き馬の目を抜く
息が合う
息が切れる
行き掛けの駄賃
息が詰まる
息が長い
息を凝らす
息を殺す
息をつく
息を呑む
息を弾ませる
息を吹き返す
石にかじりついても
痛くも痒くもない
痛くもない腹を探られる
痛し痒し
鼬ごっこ
板につく
至れり尽くせり
一か八か
一から十まで
一も二もなく
一巻の終わり
一国一城の主
一刻を争う
一糸乱れず
一矢報いる
一石を投じる
一線を画す
一杯食わされる
居ても立っても居られない
意表を突く
色を失う
色を付ける
引導を渡す
「う」で始まる小学校で習う慣用句

上には上がある
浮足立つ
雨後の筍
後ろ髪を引かれる
後ろ指を指される
嘘八百
うだつが上がらない
有頂天になる
現を抜かす
腕が上がる
腕が立つ
腕に覚えがある
腕に縒りを掛ける
打てば響く
腕を振るう
腕を磨く
独活の大木
鰻登り
鵜呑みにする
鵜の目鷹の目
馬が合う
海の物とも山の物ともつかない
有無を言わせず
裏目に出る
裏をかく
売り言葉買い言葉
瓜二つ
上の空
「え」で始まる小学校で習う慣用句

得手に帆を揚げる
絵に描いた餅
襟を正す
縁もゆかりもない
「お」で始まる小学校で習う慣用句

おうむ返し
大きな顔をする
大きな口をきく
大船に乗ったよう
大風呂敷を広げる
大目玉を食う
大目に見る
奥歯に物が挟まる
おくびにも出さない
遅れをとる
お茶を濁す
音に聞く
同じ穴の狢
鬼が笑う
鬼の首を取ったよう
お鉢が回る
思う壺
重荷を下ろす
親の脛をかじる
親の光は七光
折り紙付き
音頭を取る
恩に着せる
恩を仇で返す
「か」で始まる小学校で習う慣用句

飼い犬に手を噛まれる
灰燼に帰す
快刀乱麻を断つ
顔色をうかがう
顔が売れる
顔が利く
顔が立つ
顔がつぶれる
顔が広い
顔から火が出る
顔に泥を塗る
顔を売る
顔を出す
影が薄い
影になり日向になり
影も形もない
影を潜める
籠の鳥
風上にも置けない
笠に着る
風の便り
風の吹き回し
方(片)がつく
固唾を呑む
肩で息をする
型にはまる
肩の荷が下りる
片腹痛い
片棒を担ぐ
肩身が狭い
語るに落ちる
肩を怒らす
肩を落とす
方(片)を付ける
肩を並べる
肩を持つ
活を入れる
合点がいかない
角が立つ
金が物を言う
兜を脱ぐ
鎌を掛ける
蚊帳の外
烏の行水
借りてきた猫
枯れ木に花
閑古鳥が鳴く
眼中にない
癇に障る
堪忍袋の緒が切れる
看板に偽りなし
「き」で始まる小学校で習う慣用句

気が多い
気が置けない
気が重い
気が利く
気が気でない
機が熟す
気が進まない
気が立つ
気が小さい
気が散る
気が付く
気が強い
気が遠くなる
気が咎める
気がない
気が抜ける
気が早い
気が回る
気が短い
気が向く
気が滅入る
気が弱い
聞き耳を立てる
聞く耳を持たない
機嫌を取る
机上の空論
帰心矢の如し
機先を制する
狐につままれる
木で鼻を括る
軌道に乗る
気に入る
気に掛ける
気に食わない
気に病む
着の身着のまま
気は心
牙を剥く
きまりが悪い
木目が細かい
肝(胆)が据わる
肝(胆)が太い
肝(胆)に銘じる
肝(胆)をつぶす
肝(胆)を冷やす
脚光を浴びる
灸を据える
行間を読む
気を落とす
気を配る
気を取られる
気を取り直す
気を回す
気を揉む
気を許す
「く」で始まる小学校で習う慣用句

食うか食われるか
釘を刺す
臭いものに蓋をする
草の根を分けて捜(探)す
口が重い
口が堅い
口が軽い
口が滑る
口が減らない
口車に乗る
くちばしが黄色い
口火を切る
口も八丁手も八丁
口を利く
口を酸っぱくする
口をつぐむ
口を尖らせる
口を拭う
口を挟む
口を割る
苦肉の策
首が回らない
首になる
首を傾げる
首を切る
首を長くする
軍配が上がる
群を抜く
「け」で始まる小学校で習う慣用句

芸がない
怪我の功名
下駄を預ける
煙に巻く
けりを付ける
「こ」で始まる小学校で習う慣用句

甲乙付け難し
業を煮やす
心が通う
心が弾む
心を奪われる
心を鬼にする
腰が強い
腰が低い
腰を折る
腰を据える
言葉を濁す
胡麻をする
小耳に挟む
転んでもただでは起きない
「さ」で始まる小学校で習う慣用句

砂上の楼閣
匙を投げる
「し」で始まる小学校で習う慣用句

思案に暮れる
歯牙にも掛けない
敷居が高い
舌の根の乾かぬうち
十指に余る
尻尾を出す
しのぎを削る
しびれを切らす
白羽の矢が立つ
白を切る
尻馬に乗る
尻が重い
尻が軽い
尻に火がつく
白い目で見る
「す」で始まる小学校で習う慣用句

雀の涙
脛をかじる
隅に置けない
「せ」で始まる小学校で習う慣用句

背に腹は代えられない
世話を焼く
「そ」で始まる小学校で習う慣用句

俎上に載せる
「た」で始まる小学校で習う慣用句

対岸の火事
太鼓判を押す
大なり小なり
たがが緩む
高嶺(根)の花
高飛車に出る
高みの見物
宝の持ち腐れ
高を括る
竹を割ったよう
叩けばほこりが出る
太刀打ちできない
立つ瀬がない
手綱を締める
立て板に水
盾(楯)にとる
縦の物を横にもしない
棚に上げる
他人の空似
狸寝入り
種をまく
頼みの綱
駄目を押す
袂を分かつ
便りのないのは良い便り
「ち」で始まる小学校で習う慣用句

血が通う
血が騒ぐ
血眼になる
血も涙もない
茶々を入れる
長蛇の列
血湧き肉躍る
「つ」で始まる小学校で習う慣用句

月夜に提灯
付け焼き刃
つむじを曲げる
爪に火をともす
爪の垢ほど
爪の垢を煎じて飲む
面の皮が厚い
鶴の一声
「て」で始まる小学校で習う慣用句

手が空く
手が掛かる
手が込む
手が付けられない
手が出ない
手が届く
手が早い
手ぐすねを引く
手心を加える
梃子でも動かない
手塩にかける
手玉に取る
手に汗握る
手に余る
手に付かない
手に取るように
手の内を見せる
手の平(掌)を返す
手八丁口八丁
手も足も出ない
出る幕がない
手を上げる
手を入れる
手を打つ
手を変え品を変え
手を借りる
手を切る
手を下す
手を染める
手を出す
手を尽くす
手を握る
手を抜く
手を引く
手を広げる
手を回す
手を焼く
伝家の宝刀
天狗になる
天秤に掛ける
「と」で始まる小学校で習う慣用句

峠を越す
度肝を抜く
独壇場
毒にも薬にもならない
毒を食らわば皿まで
毒を以て毒を制す
年甲斐もなく
土壇場
とどのつまり
飛ぶ鳥を落とす勢い
途方に暮れる
虎の子
取り付く島もない
取るものも取りあえず
「な」で始まる小学校で習う慣用句

無い袖は振れない
長い目で見る
流れに棹さす
名は体を表す
涙に暮れる
涙を呑む
名もない
鳴り物入り
「に」で始まる小学校で習う慣用句

荷が重い
苦虫を噛み潰したよう
二足の草鞋を履く
二の足を踏む
二の舞を演じる
「ぬ」で始まる小学校で習う慣用句

糠喜び
濡れ衣を着せられる
「ね」で始まる小学校で習う慣用句

猫の手も借りたい
猫の額
猫も杓子も
猫を被る
寝た子を起こす
寝耳に水
根も葉もない
音を上げる
年貢の納め時
「の」で始まる小学校で習う慣用句

熨斗を付ける
喉から手が出る
乗りかかった船
「は」で始まる小学校で習う慣用句

歯が浮く
歯が立たない
箔が付く
白紙に戻す
拍車を掛ける
薄氷を踏む
箸にも棒にも掛からない
蜂の巣をつついたよう
八方塞がり
鼻息が荒い
話に花が咲く
鼻であしらう
鼻に掛ける
鼻に付く
鼻持ちならない
鼻を明かす
花を持たせる
歯に衣着せぬ
羽を伸ばす
幅を利かせる
羽目を外す
腹が黒い
腹に据えかねる
腹の虫が収まらない
腸が煮えくり返る
腹を決める
腹を割る
張り子の虎
反旗を翻す
「ひ」で始まる小学校で習う慣用句

膝を交える
額を集める
左うちわで暮らす
筆舌に尽くし難い
一泡吹かせる
一筋縄ではいかない
一旗揚げる
一肌脱ぐ
一人(独り)相撲を取る
火に油を注ぐ
非の打ち所がない
火の車
日の目を見る
火花を散らす
火蓋を切る
冷や飯を食う
氷山の一角
ピリオドを打つ
火を見るより明らか
ピンからキリまで
「ふ」で始まる小学校で習う慣用句

風雲急を告げる
風前の灯
袋の鼠
筆が立つ
腑に落ちない
「へ」で始まる小学校で習う慣用句

へそが茶を沸かす
へそを曲げる
屁の河童
弁慶の泣き所
片鱗を示す
「ほ」で始まる小学校で習う慣用句

判官びいき
棒に振る
頬が落ちる
墓穴を掘る
矛先を向ける
骨が折れる
骨身を惜しまず
骨身を削る
骨を埋める
骨を折る
洞が峠を決め込む
盆と正月が一緒に来たよう
「ま」で始まる小学校で習う慣用句

枚挙に暇がない
魔が差す
間が抜ける
間が悪い
巻き添えを食う
馬子にも衣装
末席を汚す
的を射る
俎板の鯉
眉をひそめる
真綿で首を絞める
「み」で始まる小学校で習う慣用句

見得を切る
見栄を張る
身が入る
右から左
右と言えば左
みこしを上げる
水と油
水に流す
水の滴るよう
水も漏らさぬ
水をあける
水を打ったよう
水を得た魚のよう
水を差す
味噌を付ける
道草を食う
身に余る
身に染みる
身に付ける
身につまされる
身の毛がよだつ
耳が痛い
耳が早い
耳慣れない
耳に入れる
耳にたこができる
耳に付く
耳に挟む
耳を疑う
耳を貸す
耳を傾ける
耳を澄ます
耳をそばだてる
耳を揃える
身も蓋もない
見る影もない
身を入れる
身を切られるよう
身を削る
身を立てる
「む」で始まる小学校で習う慣用句

虫がいい
虫が知らせる
虫が好かない
虫の息
虫の居所が悪い
虫も殺さない
胸が痛む
胸が一杯になる
胸が躍る
胸が騒ぐ
胸がすく
胸がつぶれる
胸が詰まる
胸が張り裂ける
胸に刻む
胸を打つ
胸を貸す
胸を借りる
胸をなで下ろす
胸を張る
無用の長物
「め」で始まる小学校で習う慣用句

明暗を分ける
目が利く
目が眩む
目が肥える
目が覚める
目頭が熱くなる
目が高い
目が出る
芽が出る
目が届く
目がない
眼鏡にかなう
目が回る
目から鱗が落ちる
目から鼻へ抜ける
目から火が出る
目くじらを立てる
目白押し
目処が付く
目と鼻の先
目に余る
目に入れても痛くない
目に浮かぶ
目に留まる
目にも留まらぬ
目の色を変える
目の敵にする
目の毒
目の前が真っ暗になる
目星を付ける
目も当てられない
目もくれない
目を疑う
目を掛ける
目を配る
目を凝らす
目を皿のようにする
目を白黒させる
目を付ける
目をつぶる
目を通す
目を盗む
目を離す
目を光らす
目を細める
目を丸くする
目を回す
目を見張る
面目を施す
「も」で始まる小学校で習う慣用句

元の鞘に納まる
元も子もない
物心が付く
物にする
物になる
物の数
物の見事に
物は相談
諸刃の剣
門前払い
「や」で始まる小学校で習う慣用句

矢面に立つ
役者が一枚上
焼け石に水
野次を飛ばす
痩せても枯れても
柳に風
野に下る
矢の催促
藪から棒
山が当たる
山が見える
山を掛ける
矢も楯もたまらず
槍玉に挙げる
「ゆ」で始まる小学校で習う慣用句

有終の美を飾る
勇断を下す
油断も隙もない
指折り数える
指をくわえる
弓折れ矢尽きる
湯水のように使う
弓を引く
夢のまた夢
夢枕に立つ
「よ」で始まる小学校で習う慣用句

用が足りる
洋の東西を問わず
要領がいい
欲に目が眩む
横車を押す
横の物を縦にもしない
横槍を入れる
四つに組む
余念がない
呼び水になる
弱音を吐く
世を挙げて
夜を徹する
世をはばかる
「ら」で始まる小学校で習う慣用句

烙印を押される
埒が明かない
「り」で始まる小学校で習う慣用句

溜飲が下がる
竜虎相搏つ
両手に花
両天秤にかける
「れ」で始まる小学校で習う慣用句
例によって例のごとし
レッテルを貼る
「ろ」で始まる小学校で習う慣用句
老骨に鞭打つ
路頭に迷う
呂律が回らない
論をまたない
「わ」で始まる小学校で習う慣用句

我が意を得る
若気の至り
我が道を行く
脇目も振らず
渡りに船
藁にもすがる
割に合う
割を食う
我に返る
我を忘れる
輪を掛ける