「聞くは一時の恥聞かぬは一生の恥」の意味と使い方や例文!語源由来・類語・対義語・英語表現・注意点
「聞くは一時の恥聞かぬは一生の恥」とは 読み方・意味 ことわざ:聞くは一時の恥聞かぬは一生の恥 読み方:きくはいっときのはじきかぬはいっしょうのはじ 意味:その場で知らないことを聞くのは恥ずかしいけれど、聞かないままだと...
 「き」で始まることわざ
「き」で始まることわざ「聞くは一時の恥聞かぬは一生の恥」とは 読み方・意味 ことわざ:聞くは一時の恥聞かぬは一生の恥 読み方:きくはいっときのはじきかぬはいっしょうのはじ 意味:その場で知らないことを聞くのは恥ずかしいけれど、聞かないままだと...
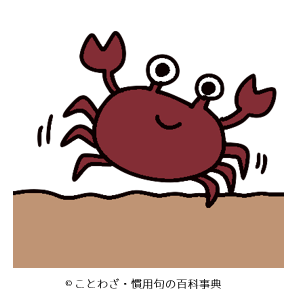 「か」で始まることわざ
「か」で始まることわざ「蟹の横這い」の意味(類義語・対義語・英語訳) 【ことわざ】 蟹の横這い 【読み方】 かにのよこばい 【意味】 他者からすれば効率の悪いやり方でも、当人からしたら最も効率の良いやり方であること。また、物事がうまく進まない...
 「か」で始まることわざ
「か」で始まることわざ「稼ぐに追いつく貧乏なし」の意味(語源由来・類義語・対義語・英語訳) 【ことわざ】 稼ぐに追いつく貧乏なし 【読み方】 かせぐにおいつくびんぼうなし 【意味】 真面目にこつこつと仕事をし稼いでいれば、貧乏になることはない...
 「か」で始まることわざ
「か」で始まることわざ「嵩に懸かる」の意味(語源由来・英語訳) 【ことわざ】 嵩に懸かる 【読み方】 かさにかかる 【意味】 己よりも地位や力が劣る者に威圧的な態度をとる。また、有利な立場に乗じて相手を攻めることを意味している。 【語源・由来...
 「か」で始まることわざ
「か」で始まることわざ「陰になり日向になり」の意味(類義語・英語訳) 【ことわざ】 陰になり日向になり 【読み方】 かげになりひなたになり 【意味】 ある時は陰という裏側から支え、またある時は日向という表側で人を支えることを意味している。 【...
 「か」で始まることわざ
「か」で始まることわざ「学問に近道なし」の意味(故事・類義語) 【ことわざ】 学問に近道なし 【読み方】 がくもんにちかみちなし 【意味】 学問を修めるためには、一つ一つの基礎を積み重ねて学んでこそ初めて習得するものであり、裏技は存在しないと...
 「か」で始まることわざ
「か」で始まることわざ「灰燼に帰す」の意味(出典・類義語・英語訳) 【ことわざ】 灰燼に帰す 【読み方】 かいじんにきす 【意味】 何もかもが跡形もなく全て燃え尽きてしまうことを意味する。 【出典】 『史記』「烏有此事也」 【類義語】 ・烏有...
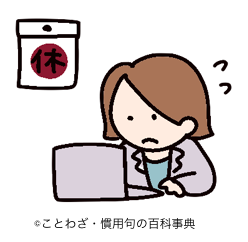 「な」で始まることわざ
「な」で始まることわざ【ことわざ】 怠け者の節句働き 【読み方】 なまけもののせっくばたらき 【意味】 ふだん怠けている人は、ほかの人が休みの日に、かえって働かなくてはならないということ。ふだん働かない人を小ばかにしたことば。 【語源・由来】...
 「な」で始まることわざ
「な」で始まることわざ「名は体を表す」の意味(語源由来・類義語・英語訳) 【ことわざ】 名は体を表す 【読み方】 なはたいをあらわす 【意味】 名前というものは、その人本人の性格や、その物の実体など本質を表しているということ。 【語源・由来】...
 「な」で始まることわざ
「な」で始まることわざ「為せば成る、為さねば成らぬ何事も」の意味(語源由来・類義語) 【ことわざ】 為せば成る、為さねば成らぬ何事も 【読み方】 なせばなる、なさねばならぬなにごとも 【意味】 自分ではできないと思っていても、その気になればで...
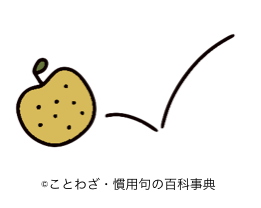 「な」で始まることわざ
「な」で始まることわざ「梨の礫」の意味(語源由来・類義語・英語訳) 【ことわざ】 梨の礫 【読み方】 なしのつぶて 【意味】 電話をしても、手紙を出しても一向に返事がないこと。まったく連絡がないこと。 【語源由来】 “礫”とは、投げつけた小石...
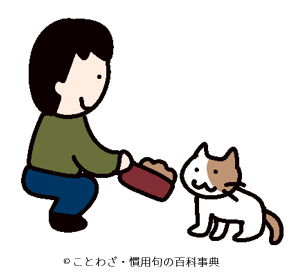 「な」で始まることわざ
「な」で始まることわざ「情けが仇」の意味(類義語・対義語・英語訳) 【ことわざ】 情けが仇 【読み方】 なさけがあだ 【意味】 他人に対し、少なからずの情けや好意を持ってしまったことが逆に良くない結果を招くという意味。 【類義語】 ・恩が仇 ...
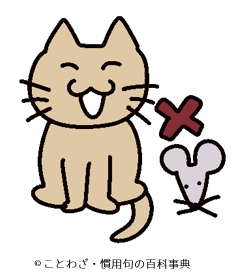 「な」で始まることわざ
「な」で始まることわざ「鳴く猫は鼠を捕らぬ」の意味(語源由来・類義語・対義語・英語訳) 【ことわざ】 鳴く猫は鼠を捕らぬ 【読み方】 なくねこはねずみをとらぬ 【意味】 よく喋るものはかえって実行しないことのたとえ。 【語源・由来】 よく鳴い...
 「な」で始まることわざ
「な」で始まることわざ「無くて七癖有って四十八癖」の意味(語源由来・類義語・英語訳) 【ことわざ】 無くて七癖有って四十八癖 【読み方】 なくてななくせあってしじゅうはっくせ 【意味】 人はだれでも多かれ少かれ何らかの癖を持っているものだとい...
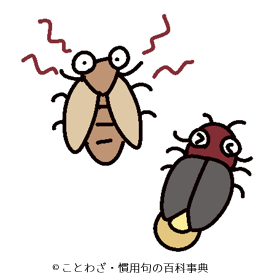 「な」で始まることわざ
「な」で始まることわざ「鳴く蝉よりも鳴かぬ蛍が身を焦がす」の意味(語源由来・類義語・英語訳) 【ことわざ】 鳴く蝉よりも鳴かぬ蛍が身を焦がす 【読み方】 なくせみよりもなかぬほたるがみをこがす 【意味】 自分の思っていることを全て口に出す者よ...
 「な」で始まることわざ
「な」で始まることわざ「泣く子は育つ」の意味(語源由来・類義語・英語訳) 【ことわざ】 泣く子は育つ 【読み方】 なくこはそだつ 【意味】 生まれたばかりの赤ちゃんが、力の限り声を張り上げて泣くことは元気の証であるため、健康で健やかに育つとい...
 「な」で始まることわざ
「な」で始まることわざ【ことわざ】 泣く子と地頭には勝てぬ 【読み方】 なくことじとうにはかてぬ 【意味】 自己中心的でわがままな者や自分よりも身分が上の者、権力者には逆立ちしても勝てることはできないので、無茶なことを言われようとも逆らうこと...
 「な」で始まることわざ
「な」で始まることわざ【ことわざ】 流れに棹さす 【読み方】 ながれにさおさす 【意味】 自分に好都合なことが度々重なり、上手く物事が進むという意味。 【語源・由来】 川の流れに乗って進んでいる舟に、竿をさすことでさらに進むことから転じてきて...
 「な」で始まることわざ
「な」で始まることわざ【ことわざ】 長い物には巻かれろ 【読み方】 ながいものにはまかれろ 【意味】 自分よりも権力が上である者や、大勢が賛成することには逆らわず、おとなしく従っておいたほうが物事がうまく進むということ。 【語源・由来】 元と...
 「な」で始まることわざ
「な」で始まることわざ「泣いて馬謖を斬る」の意味(出典・故事・類義語・英語訳) 【ことわざ】 泣いて馬謖を斬る 【読み方】 ないてばしょくをきる 【意味】 ルールを守るためには、たとえ肉親や親しい人であろうと己の情を捨て、切り捨てないといけな...
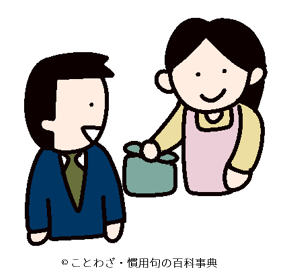 「な」で始まることわざ
「な」で始まることわざ「内助の功」の意味(語源由来・類義語・英語訳) 【ことわざ】 内助の功 【読み方】 ないじょのこう 【意味】 表舞台ではなく裏方で人を支えることをいう。また、夫を陰ながら支え、出世させたりする妻を指す。 【語源・由来】 ...
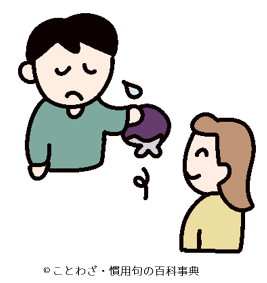 「な」で始まることわざ
「な」で始まることわざ「無いが意見の総じまい」の意味(類義語・対義語・英語訳) 【ことわざ】 無いが意見の総じまい 【読み方】 ないがいけんのそうじまい 【意味】 放浪や道楽など無駄にお金を使う人にいくら忠告や説教をしようと無駄であるが、持ち...
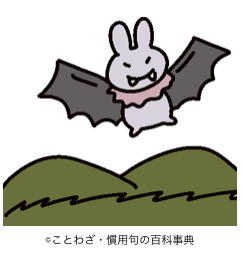 「と」で始まることわざ
「と」で始まることわざ「鳥なき里の蝙蝠」の意味(語源由来・類義語・英語訳) 【ことわざ】 鳥なき里の蝙蝠 【読み方】 とりなきさとのこうもり 【意味】 本当にその分野の優れた人がいないところでは、少し詳しいだけであたかもその分野の専門家のよう...
 「と」で始まることわざ
「と」で始まることわざ「取り付く島もない」の意味(語源由来・類義語・英語訳) 【ことわざ】 取り付く島もない 【読み方】 とりつくしまもない 【意味】 頼ろうとしても、冷たくあしらわれたりして頼るに頼れない状態を意味する。 【語源・由来】 航...
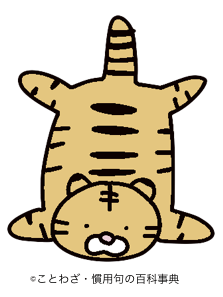 「と」で始まることわざ
「と」で始まることわざ「虎は死して皮を留め人は死して名を残す」の意味(語源由来・類義語) 【ことわざ】 虎は死して皮を留め人は死して名を残す 【読み方】 とらはししてかわをとどめひとはししてなをのこす 【意味】 虎は死んでもあの美しい毛皮が残...
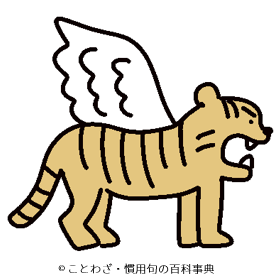 「と」で始まることわざ
「と」で始まることわざ「虎に翼」の意味(語源由来・類義語・英語訳) 【ことわざ】 虎に翼 【読み方】 とらにつばさ 【意味】 ただでさえ強い者に、さらなる力が加わることを意味している。 【語源・由来】 中国の王朝・唐の歴史家・令狐徳棻(れいこ...
 「と」で始まることわざ
「と」で始まることわざ【ことわざ】 飛ぶ鳥を落とす勢い 【読み方】 とぶとりをおとすいきよい 【意味】 勢いが非常に盛んなようす。権力・威力などが血気盛んであることを意味する。 【語源・由来】 飛んでいる鳥を落とすほどに、不可能なことを可能に...
 「と」で始まることわざ
「と」で始まることわざ「図南の翼」の意味(出典・類義語・英語訳) 【ことわざ】 図南の翼 【読み方】 となんのつばさ 【意味】 壮大な計画や目標を立て、それらを成し遂げようとすることをいう。 【出典】 中国の戦国時代の思想家であり、道教の始祖...
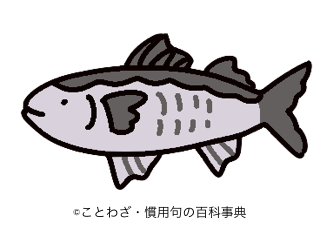 「と」で始まることわざ
「と」で始まることわざ「とどのつまり」の意味(語源由来・類義語・英語訳) 【ことわざ】 とどのつまり 【意味】 最終的にたどり着つくところを意味する。 【語源・由来】 とどのつまりの“とど”とは、魚のボラを指しており、ボラが成長する過程でハク...
 「と」で始まることわざ
「と」で始まることわざ「塗炭の苦しみ」の意味(出典・類義語・英語訳) 【ことわざ】 塗炭の苦しみ 【読み方】 とたんのくるしみ 【意味】 酷く、耐え難い苦しみや苦痛を味わうことを意味する。 【出典】 『書経』、「有夏 昏徳にして 民塗炭に墜つ...
 「と」で始まることわざ
「と」で始まることわざ「屠所の羊」の意味(語源由来・類義語・英語訳) 【ことわざ】 屠所の羊 【読み方】 としょのひつじ 【意味】 少しずつ死期が迫っていること。死や不幸な出来事に直面し、生気を失うことを意味している。 【語源・由来】 屠所の...
 「と」で始まることわざ
「と」で始まることわざ「年には勝てない」の意味(語源由来・類義語・英語訳) 【ことわざ】 年には勝てない 【読み方】 としにはかてない 【意味】 気持ちは若くとも、年のとった体はいうことを聞いてくれないということ。 【語源・由来】 若い頃は少...
 「と」で始まることわざ
「と」で始まることわざ「毒を以て毒を制す」の意味(語源由来・類義語・対義語・英語訳) 【ことわざ】 毒を以て毒を制す 【読み方】 どくをもってどくをせいす 【意味】 この場合の毒とは、悪やそれらに関わるものを指し、悪事には悪事を、悪人には悪人...
 「と」で始まることわざ
「と」で始まることわざ「毒を食らわば皿まで」の意味(語源由来・類義語・対義語・英語訳) 【ことわざ】 毒を食らわば皿まで 【読み方】 どくをくらわばさらまで 【意味】 一度悪事に手を出したのならばどこで終わっても悪事は悪事のため、それならばい...
 「と」で始まることわざ
「と」で始まることわざ「毒にも薬にもならない」の意味(語源由来・類義語・英語訳) 【ことわざ】 毒にも薬にもならない 【読み方】 どくにもくすりにもならない 【意味】 何の役にも立たなく、居ても居なくても、あっても無くてもどうでもよいというこ...
 「と」で始まることわざ
「と」で始まることわざ「十で神童十五で才子二十過ぎれば只の人」の意味(語源由来・類義語・対義語・英語訳) 【ことわざ】 十で神童十五で才子二十過ぎれば只の人 【読み方】 とおでしんどうじゅうごでさいしはたちすぎればただのひと 【意味】 いくら...
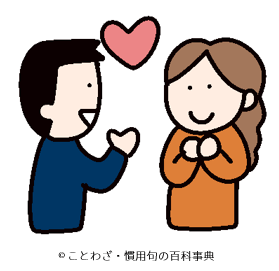 「と」で始まることわざ
「と」で始まることわざ「遠くて近きは男女の仲」の意味(語源由来・類義語・対義語・英語訳) 【ことわざ】 遠くて近きは男女の仲 【読み方】 とおくてちかきはだんじょのなか 【意味】 男性と女性は精神的に離れた関係だと思われているが、思っているほ...
 「か」で始まることわざ
「か」で始まることわざ【ことわざ】 勝てば官軍、負ければ賊軍 【読み方】 かてばかんぐん、まければぞくぐん 【意味】 勝った方はすべて正しいとされ、負けた方はすべて悪いとされるたとえ。短く、「勝てば官軍」として使われることが多い。 【語源・由...
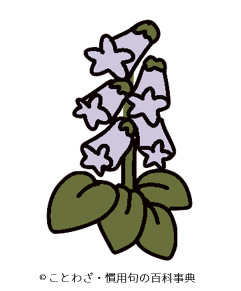 「き」で始まることわざ
「き」で始まることわざ「桐一葉」の意味(語源由来・類義語・英語訳) 【ことわざ】 桐一葉 【読み方】 きりひとは 【意味】 桐一葉とは、あらゆるものの衰退の兆しを表す言葉である。また、一つの事から様々な視点で物事をとらえる時にも用いる。 【語...
 「か」で始まることわざ
「か」で始まることわざ【ことわざ】 勝って兜の緒を締めよ 【読み方】 かってかぶとのおをしめよ 【意味】 物事において成功や決着がついたからといって気を緩ゆるめてしまいそうになるが、緩めるのではなくさらに気を引き締しめないといけないと言う意味...
 「か」で始まることわざ
「か」で始まることわざ「渇して井を穿つ」の意味(語源由来・類義語・対義語・英語訳) 【ことわざ】 渇して井を穿つ 【読み方】 かっしていをうがつ 【意味】 前もって準備をしなくて、必要な時に必要なものを準備するのでは到底間に合わないという意味...
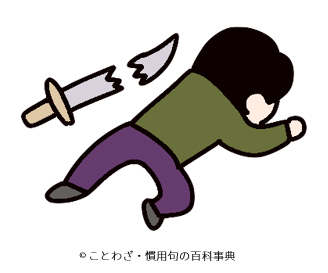 「か」で始まることわざ
「か」で始まることわざ「刀折れ矢尽きる」の意味(語源由来・出典・類義語・英語訳) 【ことわざ】 刀折れ矢尽きる 【読み方】 かたなおれやつきる 【意味】 何かと戦ったり、挑戦したりする手段や方法が無くなることをいう。 【語源由来】 『後漢書』...
 「か」で始まることわざ
「か」で始まることわざ【ことわざ】 風邪は万病の元 【読み方】 かぜはまんびょうのもと 【意味】 風邪はあらゆる病気の元であるということ。 【語源・由来】 こじれた風邪はさまざまな合併症を引き起こすことからいう。また、たかが風邪くらいと侮って...
 「か」で始まることわざ
「か」で始まることわざ「苛政は虎よりも猛し」の意味(故事・類義語) 【ことわざ】 苛政は虎よりも猛し 【読み方】 かせいはとらよりもたけし 【意味】 民衆を苦しめる政治は、性質が荒く乱暴な虎よりも恐ろしいという意味。 【故事】 元々は『礼記ら...
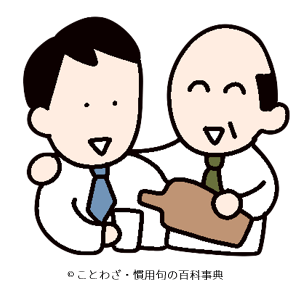 「か」で始まることわざ
「か」で始まることわざ「駆けつけ三杯」の意味(語源由来・類義語・英語訳) 【ことわざ】 駆けつけ三杯 【読み方】 かけつけさんばい 【意味】 他人の杯を受ける者には三杯飲ませる意から転じて、酒席などで遅れてきた客に続けざまに酒を三杯飲ませるこ...
 「か」で始まることわざ
「か」で始まることわざ「駆け馬に鞭」の意味(語源由来・類義語・対義語・英語訳) 【ことわざ】 駆け馬に鞭 【読み方】 かけうまにむち 【意味】 現時点で力がある者、勢いがある者にさらに力を与えること。 【語源・由来】 普通に走っているだけでも...
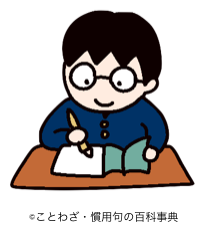 「か」で始まることわざ
「か」で始まることわざ【ことわざ】 学問に王道なし 【読み方】 がくもんにおうどうなし 【意味】 学問には安易に習得できるような方法はない。 【語源・由来】 紀元前3000年ごろのギリシアの数学者エウクレイデスから幾何学を学んでいたエジプト王...
 「か」で始まることわざ
「か」で始まることわざ「蝸牛角上の争い」の意味(語源由来・出典・類義語・英語訳) 【ことわざ】 蝸牛角上の争い 【読み方】 かぎゅうかくじょうのあらそい 【意味】 小さなことで争ったり、喧嘩をしたりすること。また、家や学校などといった狭い世界...
 「か」で始まることわざ
「か」で始まることわざ【ことわざ】 怪力乱神を語らず 【読み方】 かいりょくらんしんをかたらず 【意味】 世間一般常識から逸脱した、怪奇現象や死後の世界、超能力といった言葉では説明できないようなものは、人には自ずから語らないものであるというこ...
 「か」で始まることわざ
「か」で始まることわざ「会稽の恥」の意味(故事・類義語) 【ことわざ】 会稽の恥 【読み方】 かいけいのはじ 【意味】 戦いや勝負ごとに負け、恥や屈辱を受けること。また、己の名誉に対する侮辱を受けること。 【故事】 中国の故事であり、会稽の恥...
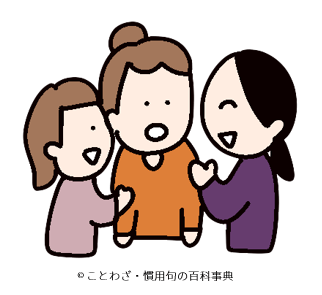 「お」で始まることわざ
「お」で始まることわざ「女三人寄れば姦しい」の意味(語源由来・類義語・英語訳) 【ことわざ】 女三人寄れば姦しい 【読み方】 おんなさんにんよればかしましい 【意味】 女性という人々は時におしゃべり好きなため、そんな人たちが3人も集まると五月...
 「お」で始まることわざ
「お」で始まることわざ「女心と秋の空」の意味(語源由来・類義語・対義語) 【ことわざ】 女心と秋の空 【読み方】 おんなごころとあきのそら 【意味】 年齢関係なく、女性の感情は秋の天気のようにコロコロと移ろいやすく、気まぐれだということ。 【...
 「お」で始まることわざ
「お」で始まることわざ「尾を振る犬は叩かれず」の意味(語源由来・類義語・対義語・英語訳) 【ことわざ】 尾を振る犬は叩かれず 【読み方】 おをふるいぬはたたかれず 【意味】 親愛の意を表しておけば攻撃されないということ。 【語源・由来】 飼い...
 「お」で始まることわざ
「お」で始まることわざ【ことわざ】 終わり良ければ全て良し 【読み方】 おわりよければすべてよし 【意味】 最初や途中がどうであれ、結局大切なのは結果であるということ。 【語源・由来】 イングランド(イギリス)の詩人であり、劇作家として16世...
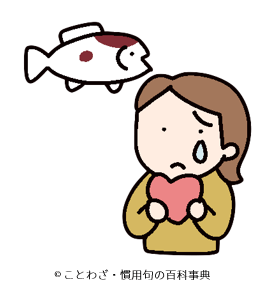 「お」で始まることわざ
「お」で始まることわざ「及ばぬ鯉の滝登り」の意味(語源由来・類義語・英語訳) 【ことわざ】 及ばぬ鯉の滝登り 【読み方】 およばぬこいのたきのぼり 【意味】 いくら頑張っても、目的を達成することは不可能であるということ。また、決して叶うことは...
 「お」で始まることわざ
「お」で始まることわざ「泳ぎ上手は川で死ぬ」の意味(語源由来・類義語・対義語・英語訳) 【ことわざ】 泳ぎ上手は川で死ぬ 【読み方】 およぎじょうずはかわでしぬ 【意味】 己の能力や才能に驕(おご)りを持つあまり、得意分野で失敗してしまうこと...
 「お」で始まることわざ
「お」で始まることわざ「親馬鹿子馬鹿」の意味(語源由来・類義語・英語訳) 【ことわざ】 親馬鹿子馬鹿 【読み方】 おやばかこばか 【意味】 自分の子どもを愛し可愛がるあまり客観的に子どもを見ることができず、子どもの愚かさ加減に気づかない。また...
 「あ」で始まることわざ
「あ」で始まることわざ「慌てる乞食は貰いが少ない」の意味(語源由来・類義語・対義語・英語訳) 【ことわざ】 慌てる乞食は貰いが少ない 【読み方】 あわてるこじきはもらいがすくない 【意味】 焦ったり、目先の利益だけを求め事を進めると、かえって...
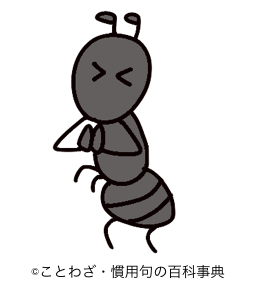 「あ」で始まることわざ
「あ」で始まることわざ「蟻の思いも天に届く」の意味(語源由来・類義語・英語訳) 【ことわざ】 蟻の思いも天に届く 【読み方】 ありのおもいもてんにとどく 【意味】 力の弱い者でも一心に念じれば望みが達せられることのたとえ。 【語源・由来】 蟻...
 「あ」で始まることわざ
「あ」で始まることわざ「嵐の前の静けさ」の意味(語源由来・類義語・英語) 【ことわざ】 嵐の前の静けさ 【読み方】 あらしのまえのしずけさ 【意味】 何か不吉なことや事件が起こる前の、何とも言えない不気味な静けさをたとえている。 【語源・由来...
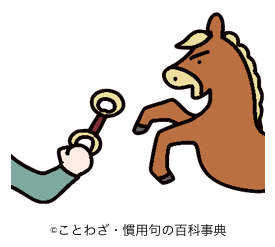 「あ」で始まることわざ
「あ」で始まることわざ「荒馬の轡は前から」の意味(語源由来・類義語・英語訳) 【ことわざ】 荒馬の轡は前から 【読み方】 あらうまのくつわはまえから 【意味】 難解な問題に対面した時は、難しく考えずに堂々と正面からぶつかる気持ちで向かえばよい...
 「あ」で始まることわざ
「あ」で始まることわざ「過ちては改むるに憚ること勿れ」の意味(語源由来・出典・類義語・英語訳) 【ことわざ】 過ちては改むるに憚ること勿れ 【読み方】 あやまちてはあらたむるにはばかることなかれ 【意味】 過ちを置かした時は、他人の目や己のプ...
 「あ」で始まることわざ
「あ」で始まることわざ「雨降って地固まる」とは 読み方・意味 ことわざ:雨降って地固まる 読み方:あめふってじかたまる 意味:悪いことや困難な状況が起きたあとに、かえってものごとがよい方向に進み、結果的にものごとがしっかりと安定すること。 &...
 「あ」で始まることわざ
「あ」で始まることわざ「飴と鞭」の意味(語源由来・類義語・英語訳) 【ことわざ】 飴と鞭 【読み方】 あめとむち 【意味】 褒めるところはしっかりと褒めたり、甘やかすときはとことん甘やかすが、過ちを犯したりした場合は厳しく罰するということ。 ...
 「あ」で始まることわざ
「あ」で始まることわざ「雨夜の月」の意味(語源由来・類義語・英語訳) 【ことわざ】 雨夜の月 【読み方】 あまよのつき 【意味】 現実には存在するが、それを目で見ることができないことをたとえている。また、想像するだけで実現しないこと、めったに...
 「あ」で始まることわざ
「あ」で始まることわざ「雨垂れ石を穿つ」の意味(出典・故事・類義語) 【ことわざ】 雨垂れ石を穿つ 【読み方】 あまだれいしをうがつ 【意味】 どんなに微力だろうとそれを諦めず継続していけば、いつの日にか努力が実るということ。 【出典】 『漢...
 「あ」で始まることわざ
「あ」で始まることわざ【ことわざ】 虻蜂取らず 【読み方】 あぶはちとらず 【意味】 二つを同時に手に入れようとすると、両方とも手に入らない。また、二つのことを一度にしようとしても、どちらもできなくなる。 【語源・由来】 虻と蜂を餌にする蜘蛛...
 「あ」で始まることわざ
「あ」で始まることわざ【ことわざ】 危ない橋を渡る 【読み方】 あぶないはしをわたる 【意味】 危険だと分かっていて、あえて実行することをたとえている。 【語源・由来】 今にも腐り落ちそうな吊り橋を、危険だと知りながらあえて渡ることから転じて...
 「あ」で始まることわざ
「あ」で始まることわざ【ことわざ】 痘痕も靨 【読み方】 あばたもえくぼ 【意味】 好きになるとどんな欠点でも長所に見えるということのたとえ。 【語源・由来】 恋する者の目には、相手のあばたでもえくぼのように見えるということから。 【類義語】...
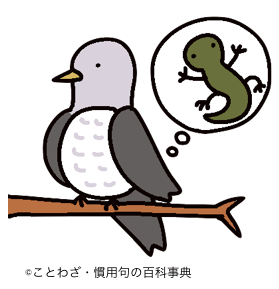 「あ」で始まることわざ
「あ」で始まることわざ「あの声で蜥蜴食らうか時鳥」の意味(語源由来・類義語・対義語・英語訳) 【ことわざ】 あの声で蜥蜴食らうか時鳥 【読み方】 あのこえでとかげくらうかほととぎす 【意味】 人や物事は必ずしも外見だけが全てではなく、外見と中...
 「あ」で始まることわざ
「あ」で始まることわざ【ことわざ】 穴があったら入りたい 【読み方】 あながあったらはいりたい 【意味】 非常に恥ずかしく、身を隠したい様のこと。 【出典】 中国の前漢時代の政治思想家および文章家でもある、賈誼かぎの『新書』からきている。そこ...
 「あ」で始まることわざ
「あ」で始まることわざ【ことわざ】 後は野となれ山となれ 【読み方】 あとはのとなれやまとなれ 【意味】 今がどうにかなれば、後はどうにでもなれということ。 【語源・由来】 自分が立ち去ったあとは、野になろうが山になろうが構わないということか...
 「あ」で始まることわざ
「あ」で始まることわざ「後の祭り」とは 読み方・意味 ことわざ:後の祭り 読み方:あとのまつり 意味:なにかをしたり言ったりするのが遅すぎて、手遅れになった状態のこと 「後の祭り」は、「手遅れ」や「タイミングを逃してもはや意味が...
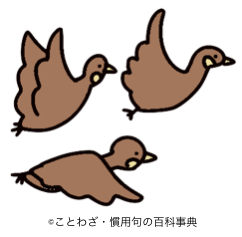 「あ」で始まることわざ
「あ」で始まることわざ「後の雁が先になる」の意味(語源由来・類義語・英語) 【ことわざ】 後の雁が先になる 【読み方】 あとのかりがさきになる 【意味】 油断すれば後から来るものに追い越される。 【語源・由来】 雁は列をなして飛行するが、後尾...
 「あ」で始まることわざ
「あ」で始まることわざ【ことわざ】 後足で砂をかける 【読み方】 あとあしですなをかける 【意味】 今までお世話になった方や恩がある方に、最後の方で裏切った上に、大変な迷惑や被害ををかけて去ることをたとえている。 【語源・由来】 犬や馬といっ...
 「あ」で始まることわざ
「あ」で始まることわざ「羹に懲りて膾を吹く」の意味(故事・出典・類義語・対義語) 【ことわざ】 羹に懲りて膾を吹く 【読み方】 あつものにこりてなますをふく 【意味】 たった一度の失敗に懲りて、必要以上に注意深くなることを表している。 【故事...
 「あ」で始まることわざ
「あ」で始まることわざ【ことわざ】 暑さ寒さも彼岸まで 【読み方】 あつささむさもひがんまで 【意味】 彼岸を過ぎれば、暑さや寒さは落ち着き、過ごしやすい日々になるということ。 【語源・由来】 彼岸にあたる春分の日と秋分の日は、昼と夜の長さが...
 「き」で始まることわざ
「き」で始まることわざ【ことわざ】 聞いて極楽見て地獄 【読み方】 きいてごくらくみてじごく 【意味】 人の話で聞いた内容と、実際に見た差がはげしいこと。 【語源・由来】 江戸時代に、農村の娘に綺麗な着物とおいしいご飯が食べられる極楽な場所が...
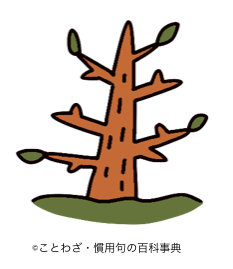 「か」で始まることわざ
「か」で始まることわざ【ことわざ】 枯れ木も山の賑わい 【読み方】 かれきもやまのにぎわい 【意味】 役に立たないようなものでも、ないよりはましだということ。 【語源・由来】 たとえ枯れた木でも、何もない山よりは、にぎやかでよいということから...
 「か」で始まることわざ
「か」で始まることわざ「痒い所に手が届く」の意味(語源由来・類義語・対義語) 【ことわざ】 痒い所に手が届く 【読み方】 かゆいところにてがとどく 【意味】 相手の望むことを察し、細かいところまで気配りや配慮がなされている様をいう。 【語源・...
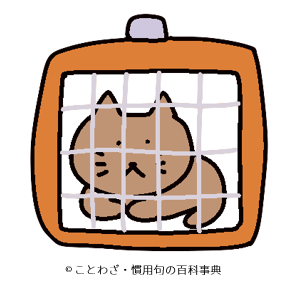 「か」で始まることわざ
「か」で始まることわざ「借りてきた猫」の意味(語源由来・類義語・対義語・英語訳) 【ことわざ】 借りてきた猫 【読み方】 かりてきたねこ 【意味】 普段の姿とは打って変わり、非常におとなしい様を指している。 【語源・由来】 ねずみが家に住み着...
 「か」で始まることわざ
「か」で始まることわざ【ことわざ】 鴨が葱を背負って来る 【読み方】 かもがねぎをせおってくる 【意味】 自分に好都合な出来事、また願っても無い好機が訪れることをいう。 【語源・由来】 鴨が葱を背負って来るとは、鴨鍋を作ろうとしていた時に、ま...
 「か」で始まることわざ
「か」で始まることわざ【ことわざ】 烏の行水 【読み方】 からすのぎょうずい 【意味】 よく洗わないで、風呂からさっさと出てきてしまうようすのたとえ。 【語源・由来】 カラスが水浴びをするとき、数分で羽とくちばしを洗い整える姿からきている。 ...
 「か」で始まることわざ
「か」で始まることわざ「亀の甲より年の功」とは 読み方・意味 ことわざ:亀の甲より年の功 読み方:かめのこうよりとしのこう 意味:年長者の人生経験や知恵は、非常に価値があるということ。 「亀の甲より年の功」ということわざは、年長...
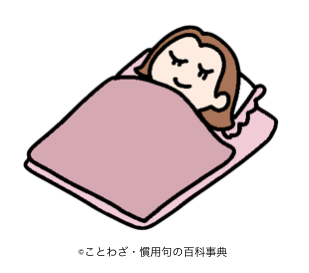 「か」で始まることわざ
「か」で始まることわざ【ことわざ】 果報は寝て待て 【読み方】 かほうはねてまて 【意味】 幸福というものは人の力ではどうすることもできないから、やるべきことをやったら、自然に身を任せ気長に待つことが良いということ。 【語源・由来】 仏教の「...
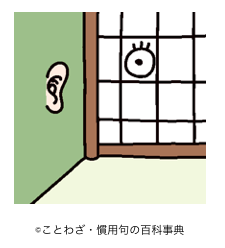 「か」で始まることわざ
「か」で始まることわざ「壁に耳あり障子に目あり」とは 読み方・意味 ことわざ:壁に耳あり障子に目あり 読み方:かべにみみありしょうじにめあり 意味:秘密はもれやすいということ。 「壁に耳あり障子に目あり」とは、秘密にしたいことで...
 「か」で始まることわざ
「か」で始まることわざ【ことわざ】 金は天下の回り物 【読み方】 かねはてんかのまわりもの 【意味】 今、お金がない人でもいつか手に入れることができるし、お金持ちでも失うこともあるということ。 【語源・由来】 お金は一つのところにとどまるもの...
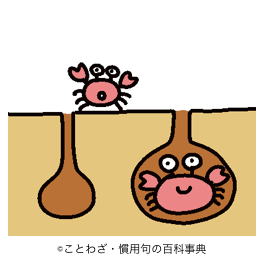 「か」で始まることわざ
「か」で始まることわざ「蟹は甲羅に似せて穴を掘る」の意味(類義語・語源由来・英語訳) 【ことわざ】 蟹は甲羅に似せて穴を掘る 【読み方】 かにはこうらににせてあなをほる 【意味】 人は自分の身の丈に合った、考えや行動をとることが一番良いという...
 「か」で始まることわざ
「か」で始まることわざ「渇しても盗泉の水を飲まず」の意味(語源由来・類義語・対義語・英語訳) 【ことわざ】 渇しても盗泉の水を飲まず 【読み方】 かっしてもとうせんのみずをのまず 【意味】 どんなに辛く苦しいことがあっても、決して悪いことはし...
 「か」で始まることわざ
「か」で始まることわざ【ことわざ】 火中の栗を拾う 【読み方】 かちゅうのくりをひろう 【意味】 自分ではなく他人の利益のために、そそのかされ危険をおかし、酷い目にあうことのたとえ。 【由来】 火中の栗を拾うの語源になったといわれているのが、...
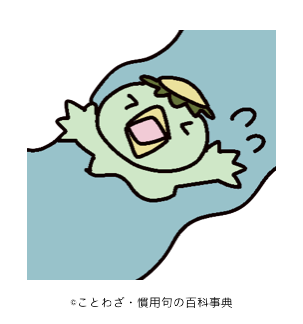 「か」で始まることわざ
「か」で始まることわざ【ことわざ】 河童の川流れ 【読み方】 かっぱのかわながれ 【意味】 どんなにその道の達人や名人であっても、時には失敗する、というたとえ。 【語源・由来】 日本の伝説上の動物・妖怪である河童は、川や沼に住み泳ぎを得意とす...
 「か」で始まることわざ
「か」で始まることわざ「風穴を開ける」の意味(語源由来・対義語・英語訳) 【ことわざ】 風穴を開ける 【読み方】 かざあなをあける 【意味】 悪習といった古い習慣により柔軟性に乏しく凝り固まった価値観をもつ組織や物事などに、新鮮な風(新たな価...
 「か」で始まることわざ
「か」で始まることわざ【ことわざ】 蛙の面に水 【読み方】 かえるのつらにみず 【意味】 どんな酷い目にあっても、顔色を変えることなく、平気なこと。または無神経なこと。図太いことのたとえとして使われる。 【語源・由来】 両生類である蛙は、生態...
 「か」で始まることわざ
「か」で始まることわざ「蛙の子は蛙」とは 読み方・意味 ことわざ:蛙の子は蛙 読み方:かえるのこはかえる 意味:子どもが成長すると結局は親に似てくる、または親と同じような道を歩むということ。 「蛙の子は蛙」とは、子どもは成長する...
 「か」で始まることわざ
「か」で始まることわざ「快刀乱麻を断つ」の意味(類義語・語源由来・英語訳) 【ことわざ】 快刀乱麻を断つ 【読み方】 かいとうらんまをたつ 【意味】 鋭い刀で、乱れた麻糸を断ち切ること。難しい物事を鮮やかに解決することのたとえ。 【語源・由来...
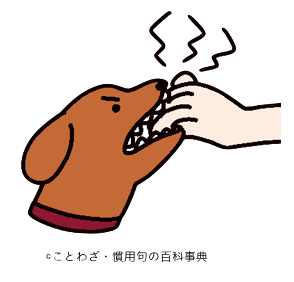 「か」で始まることわざ
「か」で始まることわざ【ことわざ】 飼い犬に手を噛まれる 【読み方】 かいいぬにてをかまれる 【意味】 世話をしていた者や信用していた者に、裏切られたり害を加えられたりすること。 【語源・由来】 可愛がって面倒をみていた飼い犬に手をかまれたこ...