一まとまりの決まった言いまわしを持つ慣用句は、わたしたちの日常の生活の中で数多く用いられています。
慣用句の種類はたくさんあり、おぼえるのが大変ですが、それぞれの意味を知ると面白い発見があります。
この記事では、沢山ある慣用句の中でも、厳選して有名な慣用句を100個にしぼり意味付きで掲載しました。
また、それぞれの慣用句の上の⭐️印は知っておきたい慣用句の重要度を表しています。
絶対知っておこう よく使われるから知っておこう 一応、知っておこうあなたが知っている慣用句はいくつありますか?
有名なことわざは、【ことわざ100選】有名なことわざ意味付きをご覧ください。
当サイトに収録してある全ての慣用句は、慣用句一覧検索をご覧ください。
当サイトの目次・逆引きは、逆引き検索一覧をご覧ください。
目次
「あ行」の慣用句意味付き
相づちを打つ(あいづちをうつ)

【意味】
人の話を聞きながら、うなずいたり、「はい」「いいえ」などと調子を合わせたりすること。


ただ黙って聞いてるだけやと、相手は「あれ、聞いてるんか?」って不安になるかもしれへんから、ちゃんと相づちを打って、話を聞いてるんやってことを伝えるのは大切やな。
揚げ足をとる(あげあしをとる)

【意味】
人の言いまちがいや言葉の一部分だけをとらえて、困らせる。


ちょっとしたミスも許さへん、そんな意地悪なやり方を表してるわけやな。これは、あんまり良い態度とは言えへんな。
あごを出す

【意味】
へとへとに、疲れること。体の疲労だけでなく、大きな仕事や問題を抱え、自分の力ではどうすることもできず、困り果てた場合にも使う。


足も動かへんほどにクタクタで、あごだけが前に出てる…それって、もうほんまに何もできへん状態やな。
朝飯前(あさめしまえ)

【意味】
朝食前(ちょうしょくまえ)のわずかな時間でもできるほど、簡単でたやすいこと。

朝食を取る前の短い時間でもできるようなこと、つまり何の問題もなくやれることを表現しているんだ。

たとえば、「この仕事、朝飯前や!」って言うて、これは「これくらいの仕事は楽勝や!」って意味になるんやな。
足が出る
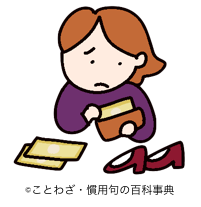
【意味】
①用意していたより多く、お金を使ってしまうこと。
②隠しごとが現れる。ぼろがでる。

一つ目は、出費が予算や収入を超えてしまう、つまり赤字になることを指すよ。
二つ目は、隠していたことが明らかになる、つまり秘密がばれてしまうことを言うんだ。

一つ目は、ようは計画してた金額を越えてしまって、もう足が出ちゃう、つまり赤字になっちゃう状態やな。
二つ目は、ぼろというか、秘密というか、そんなんが出てきちゃう、バレちゃうってことやな。
足を引っぱる

【意味】
人の成功をじゃますること。大勢で何かする時、一人だけうまくできず、みんなに迷惑をかけてしまう場合にも使う。


うーん、これは良くない行為やな。成功する人を応援する方がええわな。
味もそっけもない

【意味】
味わいがなく、おもしろみに欠ける。

例えば、感動も興奮もない説明や話といった具体的な場面で使われることが多いんだ。

例えば、説明があんまりにも乾燥してて、聞いてるこっちがハッとすることもない、ドキッとすることもない、そんなつまらん感じやな。もうちょっとワクワクする要素が欲しいところやな。
足が棒になる(あしがぼうになる)

【意味】
歩きすぎや、立ちっぱなしで、足がひどく疲れること。


この感じ、ショッピングに付き合った後とかによくあるわな。
頭が上がらない

【意味】
相手に対して借りや弱みがあって、対等につきあえない。


例えば、借金があるとか、何か大きな恩を受けてるとかやな。頭を上げて堂々と振る舞うことができない、そんな状態を指すんやな。
後の祭り

【意味】
間に合わず、手おくれになってしまうこと。ちょうどよい機会を逃してしまい、後悔している時にも使う。


祭りが終わってから、それに参加しようとしたら、もう遅いんやな。どんなに悔やんでも、取り返すことができへん、そんな状況を表してるんやな。
油を売る

【意味】
もともとは、雑談でむだに時間をつぶす、の意味。現在は主に、「寄り道をする」という意味で使う。


仕事をちゃんとやらずに、ダラダラと時間を使ってしまう、そんな行動を指してるんやな。
息を殺す

【意味】
どんな小さな音もたてないよう、息をするのにも気をつかい、じっとしていること。


たとえば、隠れてるときにバレへんように、息の音さえ立てへんようにするんや。ほんまに静かにしとる状態を指してるんやな。
息をのむ
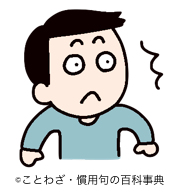
【意味】
一瞬息が止まるほど驚く。


えらい美しい景色を見たときや、驚きの出来事があったときに、思わず息を止めてしまうって状態を言うんやな。
いたちごっこ
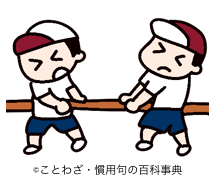
【意味】
お互いに同じことをくりかえし、物事が前に進んでいかないこと。


まるで地べたを走り回るいたちみたいに、ぐるぐると同じことを繰り返しても、結局何も解決せんってことやな。これは、「くり返し無駄な行動をするより、新しいアプローチを考えるべき」って教えてくれる言葉やな。
いもを洗うよう

【意味】
人が大勢いて、こみあっている様子。

イメージとしては、里芋を桶に入れて棒でかき混ぜて洗うような光景なんだよ。

なるほどな、なんかそう言われてみると、よく見る光景やわ。電車のラッシュ時とか、お祭りの混雑時とかによくある光景やな。それを「いもを洗うよう」と言うんやな。
後ろ髪を引かれる

【意味】
後に残してきたものが気がかりで、頭の後ろの髪の毛を引っ張られるように、先へ進むことができないこと。

つまり、何かに未練が残っていて、思い切り前へ進むことができない状態を言うんだ。

それが「後ろ髪を引かれる」ってことや。これは心の引っ張られる感じを表した言葉やな。
腕が鳴る(うでがなる)

【意味】
自分の技術や能力を発揮したくて、じっとしていられないこと。「腕」とは「腕前」の意味。

たとえば、対戦前などに自分の能力を試したくて待ちきれない、そんな感じだね。

もう待ちきれへん、さっさとやらせてくれって感じやな。そんな時に使うのが「腕が鳴る」って表現なんやな。これは、自分の力を試すのが待ちきれないっていう気持ちを表してるんやな。
馬が合う

【意味】
お互いに気持ちがぴったり合い、相性がいいこと。

たとえば、ある人と特に相性が良くて、いつも一緒に行動したくなるような時に使われるんだ。

なんか、あの人とはホンマに馬が合うわって言うて、一緒にいろんなことをやりたくなるんやな。これは、自分と相性のいい人を見つけたときに使う表現やな。
上の空(うわのそら)

【意味】
ほかのことに気をとられて、集中できない様子。

また、心が浮ついて落ち着かないさまも指すんだ。

人の話を聞いてても、実は頭の中は他のことでいっぱいっていう状態やな。
大目玉を食う

【意味】
ひどくしかられること。「大目玉を食らう」ともいう。だれかをしかる時は、「大目玉を食わす」「大目玉を食らわす」と使う。

怒って目を見開いて叱る、という意味からきているんだ。

なんか悪さしたら、親に大目玉を食わされるでっていうんやな。これは、ものすごく叱られることを表してるわけやな。
親のすねをかじる

【意味】
子供がひとり立ちできる年齢になっても自立せず、親に養ってもらうこと。

つまり、まだ自立できず、親からの援助を必要としている状況を言うんだ。

これは、まだ一人前になれへん自分を反省するときや、親に感謝するときに使う言葉やな。
「か行」の慣用句意味付き
顔から火が出る

【意味】
ひどく恥ずかしい思いをして、顔が真っ赤になる。

つまり、大きな失敗をしたときや、周りの人々に恥ずかしい行動を見られたときなどに使うんだ。

「顔から火が出る」って、本当に火が出るわけちゃうけど、それくらい恥ずかしいんやな。これは、自分の失敗やミスを反省する時に使う言葉やで。
顔が広い

【意味】
交際範囲が広く、知り合いが多い。

つまり、多くの人々と良好な関係を持ち、多方面につながりがある人を指すんだ。

たとえば、政界に顔が広いって言うと、政治家や関連の人たちと知り合いが多い、ってことになるわけや。これは、人脈の大切さを教えてくれる言葉やな。
固唾を吞む(かたずをのむ)

【意味】
成り行きを心配しながら、じっと見守ること。ほかにどうすることもできず、ただ唾をのみこんで見つめることからきた言葉。

つまり、何か大切なことの結果を静かに待つ、その間ずっと心配で心が落ち着かない状態を指すんだ。

みんながシーンとして、息をのんで結果を待つ、そんな場面で使う言葉やな。これは、重要な瞬間の緊張感を表してるんやで。
肩の荷がおりる

【意味】
肩を背負った重い荷物をおろしたように、責任や負担がなくなり、ほっとすること。「肩の荷をおろす」とも使う。

つまり、困難な仕事や問題が終わった時に、その重圧から開放されることを指しているんだ。

もうそれについて気を使わなあかんことがなくなって、ほっと一息つけるってわけや。これは、解放感を表してる言葉やな。
肩身がせまい

【意味】
恥ずかしい思いをして、まわりに対し、ひけ目を感じる。

つまり、何らかの理由で自分の立場や行動が他人に比べて見劣りすると感じることを指しているんだ。

これは、自己評価が低くて、落ち込んでる気持ちを表してるんやな。
兜を脱ぐ(かぶとをぬぐ)

【意味】
相手に降参(こうさん)し、もうかなわないと示すこと。昔の戦で、敵に降参する時、かぶとをぬいで戦う意志がないことを示したことからきた言葉。

現代では、相手の力量を認めて自分が負けを認める、つまり降参することを表しているんだよ。

現代では、自分が負けを認めるときや相手のすごさを認めるときに使う表現なんやな。
気が置けない

【意味】
あれこれ気を使わずに、つきあえること。「気の置けない」ともいう。

つまり、心から自然体で接することができる関係を表しているんだ。

気を使わず、心から打ち解けて話すことができるような関係のことを指すんやな。自分を偽らずに、素のままでいられる友達とかに使う言葉やな。
気が気でない

【意味】
ひどく心配で落ち着かない。

頭の中で何かがぐるぐると回って、普通に過ごすことが難しい状態を示しているんだ。

何か気になることがあって、心がおらんなった状態のことを指してるんやな。普段の気持ちとは違って、心配事でいっぱいやってことを表してるんやで。
気に病む(きにやむ)

【意味】
心配で、いろいろ思い悩むこと。特に心配する必要がないのに、あれこれ考えすぎる場合に使う。


何かがうまく行かなかったときや、気になることがあるときに、それをずっと心に引っかかってる状態を言うんやな。それはちょうど病気になるくらい、気にしてしまう状況を表してるんやで。
肝をつぶす

【意味】
ひどく驚くこと。「肝」とは、心とか度胸という意味。


肝は度胸や気力の象徴やから、それがつぶれるほど驚くっていうんは、相当驚いたりショックを受けたってことやな。
釘をさす

【意味】
相手が、まちがいをおこしたり、約束を破ったりしないよう、前もって注意しておく。

つまり、確実に約束を守るように、念を押す行為を表現しているんだ。

うっかり約束を破ったり、うやむやにすることができへんように、一度ちゃんと確認しておくことの大切さを教えてくれてるんやな。
草の根を分けて探す(くさのねをわけてさがす)

【意味】
探し残しのないよう、見えないところまで、すべてさがす。


草の一本一本を分けて見るくらい、くまなく探すんやな。それは、何も見逃さず、徹底的に調べることの大切さを教えてくれてるわけやな。
口が軽い

【意味】
言ってはいけないこと、秘密にすべきことを、簡単にぺらぺらしゃべってしまうこと。


おしゃべりで、ついつい秘密や内緒話まで口に出しちゃうんやな。これは、口をつぐむことの大切さを教えてくれてるんやで。
口がすっぱくなる

【意味】
同じことを何度も何度も、くりかえしいう様子。説教や小言、注意などの場合に用いる。

つまり、あまりにも多く言い続けて、もう言うのが嫌になるほど、という意味だよ。

嫌になるほど繰り返して話すんやな。これは、「ちゃんとわかってもらうために、何度も言うことの大切さ」を教えてくれてるわけやな。
口車に乗る

【意味】
うまく言いくるめられ、だまされること。おだてられて、何かさせられる、という意味にも使う。

つまり、相手の言葉に引き込まれて、見えないところで利用されてしまうという意味だ。

相手の言葉にすっかり乗せられて、気づいたらいいように使われてた、みたいな。これは、「言葉にだまされへんように、しっかりと自分で考えることの大切さ」を教えてくれるんやな。
くちばしを入れる

【意味】
人のすることに、わきからあれこれ口出しする。「くちばしをはさむ」ともいう。

つまり、他人の事情に無理に介入したり、口を出すという意味だ。

他人のことに、ちょっかい出して意見を言ったりするんやな。これは、「自分の関係ないことには口出ししないことの大切さ」を教えてくれてるわけやな。
口火を切る(くちびをきる)

【意味】
みんなの先頭に立ち、真っ先に始める。話し始める、の意味でも使う。

自分が率先して行動することで、周囲もそれに続く、という意味があるんだ。

他の人が迷ってるときに、自分がスタートを切ることで、みんなもついてくる動きができるってことやな。これは「リーダーシップを取ること」を教えてくれる言葉やで。
首を長くする

【意味】
楽しみにしていることが早く実現しないかと、待ちこがれる。


すごく楽しみにしてて、早くその時が来てほしいと思う心情を表してるんやな。これは、「大切なことを楽しみに待つこと」を教えてくれる言葉やな。
くものこを散らす

【意味】
大勢の人が、四方八方に、ぱっと逃げていく様子。

まるで蜘蛛の子が袋から出て四方八方に散ってしまうような様子をイメージしているんだ。

まるで蜘蛛の子が袋から飛び出て、あっちこっちに逃げていくような光景やな。一緒にいたはずのみんなが、いざというときにはすぐに四方八方に逃げ出すってことを教えてくれてるんやな。
煙に巻く(けむにまく)

【意味】
相手がよく知らないようなことを一方的に話して、とまどわせる。


まるで煙で視界を遮るように、相手が何が何だかわからなくなるってわけや。これは、「うまい話には裏があるかもしれない」って教えてくれる言葉やな。
心をくだく

【意味】
いろいろと気を配ったり、心配したりする。

特に、何か大切な事柄について深く思い悩むことを指すんだ。

これは、「自分の大事なことに対して真剣に取り組む」を教えてくれる言葉なんやで。
ごまをする

【意味】
自分の利益のために、人のきげんをとる。


これは、人間関係の難しさや複雑さを教えてくれる言葉やな。でも、あんまりごますぎると逆に怪しまれるから、バランスが大事やで。
「さ行」の慣用句意味付き
さじを投げる

【意味】
物事がよくなる見込みがないと、あきらめてしまう。

一般的には、問題を解決する見込みがないと判断して、あきらめる、もしくは手を引くことを指すんだ。

これは、ときにはあきらめる勇気も必要やってことを教えてくれる言葉やで。
さばを読む

【意味】
自分の都合のいいように、数や量を実際より多く言ったり、少なく言ったりする。

今では、実際よりも多く見せたり、少なく見せたりして事実を曲げる行為を指すようになったんだ。

これは、事実を曲げて都合よく見せることの危険性を教えてくれる言葉やな。でも、ウソはバレた時に信用を失うから、正直に行こうな。
舌つづみを打つ

【意味】
物を、おいしそうに食べる様子。「舌つづみを鳴らす」ともいう。美味しいものを食べる時、自然と舌で音を立てることからきた言葉。

一つ目は、何かがとても美味しいと感じた時に、舌を鳴らすことを指すんだ。二つ目は、不満や不快な感情を表すために舌打ちをすることを指すんだ。

二つ目は「何やこりゃ、ちょっと気に入らへん!」って感じで舌打ちすることやな。同じ「舌つづみを打つ」でも、状況や感情によって全く違う意味になるんやな。これは、言葉のニュアンスによって意味が変わることを教えてくれる言葉やな。
舌を巻く

【意味】
言葉が出ないほど感心すること。舌を巻いて縮めると、声がでなくなることからきた言葉。


誰かの上手さや、思わぬことが起こったときに、「うわっ、これはびっくりやで!」っていう感じで使うんやな。これは、驚きや感嘆の表現を教えてくれる言葉やな。
しっぽを出す

【意味】
かくしていたことを人に知られてしまうこと。悪いことを知られた場合の言葉で、よいことの時には使わない。


それと同じで、隠してたことや、ごまかしてたことがバレて、あっ、バレてもうた!っていう状態を表す言葉なんやな。
しのぎをけずる

【意味】
激しく争う。


例えば、選挙の激戦区とか、そんな感じで使えるわけや。
雀の涙(すずめのなみだ)

【意味】
雀の流す涙ほど、ほんのわずかなこと。

雀の涙ほどの小ささから、この言葉は生まれたんだ。

つまり、ごくわずかなもの、ちょっとしかないものを表すんやな。退職金が「雀の涙」って言われたら、たいした額やないってことやな。
図に乗る

【意味】
自分の望み通り、あるいは思い通りになったのをいいことに、調子に乗ってつけあがる。


ちょっとほめられたら、すぐにつけあがってしまう、そんな感じの意味やな。これは、自分の立場を忘れずに、謙虚さを忘れへんように注意しようってことを教えてくれるんやで。
「た行」の慣用句意味付き
太鼓判を押す(たいこばんをおす)

【意味】
絶対にまちがいないと、うけあう。

まるで太鼓のように大きな印を押すことから来ているんだ。

プロが大きな判子を押して、「この腕前は絶対に良い!」って言うてるようなもんやな。これは、その人やものが本当に信頼できるということを強く表してるわけやな。
立て板に水
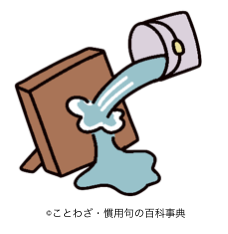
【意味】
言葉がつかえず、すらすら話す様子。

まるで立てた板に水が滑り落ちていくように、スムーズに話が進む様子を描いているんだ。

立てた板に水がスーっと流れ落ちるように、話がスラスラと出てくる状態を言うんやな。これは、お話上手な人を表す言葉なんやで。
棚に上げる

【意味】
自分に都合の悪いことには、ふれないでおく。


要するに、都合の悪いことは見ないふり、聞かないふりすることを表してるんやな。
血も涙もない

【意味】
少しも思いやりの心がない。

感情や共感の欠如を示す言葉だよ。

例えば、「血も涙もない借金の取り立て」って言うときは、どんなに困ってても無情に借金を返せって迫るような状況を言うんやろな。
手塩にかける

【意味】
自分の手で世話をして大切に育てる。

つまり、愛情を注ぎながら、手間ひまをかけて丁寧に育てることを言うんだ。

自分で世話をして、その成長を見守るっていうのは、大変やけど、それだけに達成感もあるんやろな。これは、自分の手で物事を育て上げる大切さを教えてくれる言葉やね。
手の裏を返す

【意味】
態度が突然、がらりと変わる様子。「手の平を返す」「たなごころを返す」ともいう。

まるで手の裏を返すように、突然行動や態度が変わることを表現しているよ。

一瞬でふりむいたり、言葉遣いが変わったりすることを言うんやろな。人間、変わるのは早いから気をつけなアカンな。
手に余る

【意味】
自分の力では、どうにもならないこと。

手の内に入らない、つまり自分の手の内に収まらないほど難しい事象や問題に対して使われるんだ。

手に余るほど難しい問題や、自分の能力を超えた事を言うんやな。つまり、自分一人ではどうにもならへん事態や問題に直面したときに使う言葉やで。
手を焼く

【意味】
てこずる。もてあます。

つまり、それが難しくて、どう対応したらいいのか困ってしまう状況を言うんだ。

いつもうまくいくわけやないから、この表現はリアルやね。
峠を越す(とうげをこす)

【意味】
いちばん盛りの時期を過ぎて、衰え始める。

つまり、大変だったことが終わって、やっと楽になる瞬間のことを言うんだ。

それはつまり、どんなに困難な時期でも、それを乗り越えれば楽になるということを教えてくれる言葉やね。
途方に暮れる

【意味】
どうしてよいのかわからず、困り果てる。

つまり、手段や解決法が見つからず、困り果ててしまうことを言うんだ。

思いつく手立てを全部試してもダメで、もうどうしようもない状態のことを言うんやな。完全に迷子状態やんな、これは。
「な行」の慣用句意味付き
長い目で見る

【意味】
現在の状態だけで判断せず、将来を期待して見守る。

つまり、すぐの結果に囚われずに、もっと遠くを見て物事を考えることが大切だと教えてくれる言葉なんだ。

今ピンチでも、将来的にはチャンスに変わるかもしれへんから、いつも長い目で物事を見ることが大切やってことやな。
梨のつぶて
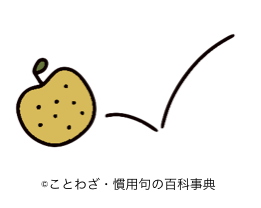
【意味】
いくら連絡しても、さっぱり返事がない様子。

ここでの「梨」は「無し」を掛けた言葉遊びで、「返事が無し」という意味になるんだ。

んで、「梨」は実は、「無し」って意味なんやで。返事が無し、つまり返事がない、ってことを遊んで言うたわけやな。それはちょっと悲しいけど、面白い表現やね。
涙をのむ

【意味】
くやしいことやつらいことをじっと我慢する。


つまり、内心は涙でいっぱいでも、それを飲み込んで我慢する、という感じか。なんとなく胸が痛むわな。
二の足を踏む(にのあしをふむ)

【意味】
思いきれず、ためらう。


一歩目は進んでも、二歩目が踏み出せずに足踏みしてしまう感じやな。勇気が出ずに躊躇してしまう様子を表してるわけや。
二の句がつげない
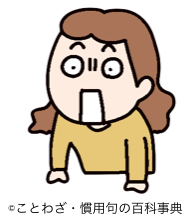
【意味】
驚きあきれて、何か言おうにも次の言葉が出てこない。


あまりのことにビックリして、次に何を言うべきかわからんくなる状況を表してるんやな。こりゃ、びっくりさせられた時の気持ちがようわかる表現やな。
猫の手も借りたい

【意味】
忙しくて人手が足りず、手伝いがほしいこと。


猫の手でも借りて、何とかこなしたいくらい忙しい状況を言うんやな。わかりやすいな、これは。
根も葉もない

【意味】
何の根拠もないことのたとえ。


つまり、なんの証拠もなく、ただの噂話やウソを指すんやな。これは、信憑性を確かめなあかん、と教えてくれる言葉やな。
のどから手が出る

【意味】
ほしくてたまらない様子。


のどからまで手が出そうなくらい、どうしてもほしいと思う気持ちを言うんやな。これは、ものすごい欲求を表してるわけやな。
「は行」の慣用句意味付き
歯が立たない

【意味】
相手が強くて、かなわない。

1つ目は物事が非常に困難で、解決できない、つまり「固くて噛むことができない」状況を表す。2つ目は相手の能力や実力が自分を遥かに上回っており、とても対抗できない、つまり「相手が自分の技量をはるかに超えていて、とても取り組めない」状況を指すんだ。

固すぎて歯が立たない、あるいは相手が強すぎて歯が立たない、どっちも厳しい状況を言うんやな。これは、自分の力を知る、または自己認識の大切さを教えてくれる表現やな。
鼻をあかす

【意味】
人を出し抜いて、びっくりさせる。あっと言わせる。


つまり、他人よりも優れた行動や結果を出して、一目置かせるってこと。それは、努力が認められ、評価されることの大切さを教えてくれる表現やな。
鼻が高い

【意味】
得意で、誇らしげな様子。


これは、自分の成功や達成感を表現する良い言葉やな。
鼻にかける

【意味】
自慢する。


自分の長所や成功を見せびらかすことを言うんやな。でもほんまにすごい人は、自慢せんでもみんなに認められるんやで。
腹が黒い

【意味】
心の中で、何かたくらんでいる様子。


表面はにっこり笑ってても、中身は全然違うんや。こういう人には気をつけんとあかんな。見た目だけで人を判断せん方がええんやで。
火の消えたよう

【意味】
急に活気がなくなって、さびしくなる様子。


これは、元気というのは自分だけじゃなく、周りの人にも影響するってことを教えてくれる言葉やな。
不意をつく

【意味】
相手が思いもかけない時に、当然何かする。逆に突然何かされる場合は「不意をつかれる」という。


でも、これはちょっとしたイタズラから、大事な戦略まで、色んな場面で使える表現やな。
袋のねずみ

【意味】
追いつめられ、逃げ場を失った様子。


鼠が袋の中に入ったら、出ることができへんもんな。どうにもならん状況に陥った時のたとえやな。困った時には、この言葉が思い出されるわな。
へそを曲げる

【意味】
きげんをそこねて、すねた態度をとる。


人間関係がこじれて、こんな状況になったら、大変やな。誰かが「へそ曲げてる」って時は、ちょっと機嫌を直してやるのも大切やな。
ほおが落ちる

【意味】
とてもおいしいことのたとえ。

とても驚くほど美味しいことを強調するために使われるんだ。

つまり、「これは美味しすぎて、ほっぺたが落ちそうや!」っていうのが、この表現の元々の意味やな。これは、何かすごく美味しいものを食べた時に使ってみたいな。
骨が折れる
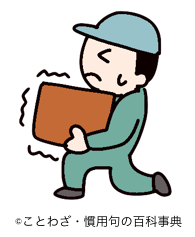
【意味】
とても苦労する。


骨を本当に折るのは痛いし大変やもんな、そのイメージで使われてるんやな。これは、何か大変なことに取り組む時によく使われる表現なんやで。
「ま行」の慣用句意味付き
まくらを高くする

【意味】
安心して眠ること。安心する、という意味にも使う。

この表現は、心配事がなくて、思いっきりリラックスできる状態を描いているんだ。

あんまり気にすることなく、ゆったりとした心地で生活できる状態を表してるんやな。なんかええな、これは。
眉をひそめる

【意味】
心配ごとや不愉快なことのせいで、顔をしかめる。


顔つきからも、どことなく気に入らないことがあるんやなって感じが伝わってくるんやな。
水に流す

【意味】
過去のもめごとを、なかったことにする。


水に流して、全部流れていったかのように、それらを全てなかったことにするってことや。過去のことは過去のこととして、もう気にせん、それを示すんやな。
水の泡になる

【意味】
努力したことが、すべて無駄になってしまうことのたとえ。

例えば、「今までの練習が水の泡になった」のように、すべての努力が報われず、結果が出ない状況を描いているんだよ。

たとえば、いっぱい練習したのに、試合で全く結果が出せなかったら、それは全部水の泡、全部ムダになっちゃったってことやな。
水を打ったよう

【意味】
大勢の人が口をきかず、しずまりかえる様子。

つまり、その場が急に静かになる状況を表す言葉なんだよ。

いきなりみんながシーンとなって、何も音がしなくなるような感じやで。まるで、水面に何も投げ入れへんときのようにピタリと静まり返るんやな。
耳にたこができる

【意味】
同じことを何度も何度も、いやになるくらい聞かされる。

たこは、漢字で「胼胝」と書き、皮膚が厚くなって角質化することを示しているんだよ。

たこができるほど、っていうからには、もう本当に聞き飽きて、はっきり言ってウザいぐらい聞かされたってことやな。ほんまに耳にたこができるんちゃうかと思うほど、同じ話を聞かされたって感じやな。
耳が痛い

【意味】
自分の失敗や欠点をつかれて、聞いているのがつらいこと。


他人から直球で弱点突かれると、耳がちょっと痛い感じになるしな。これは、「自分の問題点を直視する大切さ」を教えてくれてる言葉やな。
耳が早い

【意味】
うわさや情報をすばやく聞きつけること。

つまり、新しい情報や話題に敏感で、いち早くそれをキャッチする能力を持っているということだよ。

あっという間に情報をつかむ人は、周りから見ても「耳が早い」って思われるんやろな。これは、「情報収集力の重要さ」を教えてくれる言葉やで。
虫の居所が悪い

【意味】
きげんが悪く、ささいなことでも怒り出す状態。

つまり、ちょっとしたことでイライラする、という感じだね。

ちょっとしたことでも気に障るくらい、機嫌が悪いんやな。これは、心の整理が必要な時や、休息が必要な時を示す言葉やな。
虫がいい

【意味】
自分の都合ばかり考えて、人のことを考えない、自分勝手な様子。「虫がよすぎる」という形で使うことも多い。

自分中心で他人を無視する、そんな意味が含まれているね。

他人のことを顧みず、自分だけが楽をしようとする状態やな。これは、自己中心的な行動はダメだっていう、注意喚起の言葉やな。
胸を張る

【意味】
自信に満ちて得意げな様子。

つまり、自分の能力や成果に自信を持ち、誇りに思う状態を表しているんだ。

自分のできることや達成したことを誇りに思って、得意げにする状態やな。これは、自信を持つことの大切さを教えてくれる言葉やで。
目が肥える
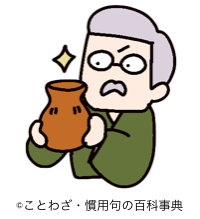
【意味】
いいものを見慣れて、いいものと、そうでないものを見分ける力がつく。
目に余る

【意味】
①やることがひどすぎて、だまって見ていられない。
②数が多くて一目で見渡せないほどである。

一つ目は、何かが度を超えてひどい状態で、黙って見ていられないほどのことを指すよ。
二つ目の意味は、何かがとてもたくさんあって、一度に全てを見渡すことができない状態を指しているんだ。

二つ目は「めちゃくちゃたくさんあって、一目で全部見ることができへん」ってことやな。どっちも「目に余る」って言うんやな、なるほどな。
目を三角にする
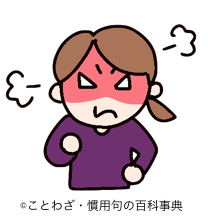
【意味】
はげしく怒る様子。


目が三角形みたいに尖って見えるくらい、はげしく怒っているというわけや。この言葉は、「人の怒りや威嚇」を伝えるんやで。
目を白黒させる

【意味】
驚き、あわてること。ひどく苦しくて目玉を動かす場合にも使う。


なるほど、これは「驚きや混乱」の状況を表してるんやな。
「や行」の慣用句意味付き
やぶから棒

【意味】
突然何かをすることのたとえ。


要するに「唐突に」って意味やね。
山をかける

【意味】
万に一つの幸運をねらい、当てずっぽうに何かすること。試験の時、問題に出そうなところを予想しそこだけ勉強する、という意味に使われることが多い。

試験においては、特定の問題だけに集中して勉強するという状況を表すのに使われることが多いんだよ。

でも、これはちょっとリスキーやな。それが当たればラッキーだけど、外れたら一発で詰むやん。全範囲を勉強することの大切さを思い出させてくれる言葉やな。
指をくわえる

【意味】
①どうにかしたいと思いながらも手が出せず、ただ、そばで見ている。うらやましがる。
②きまり悪そうにする。恥ずかしそうにする。

一つ目は、何かを羨ましく思いながら、それに手を出すことができない状況を指すよ。
二つ目は、きまり悪さや恥ずかしさを感じている様子を表現しているんだ。

欲しいものが手に入らないときの切なさや、人前で恥ずかしがるときの気まずさを表現するんや。これは、人間の感情の細かな描写を表す言葉やで。
「わ行」の慣用句意味付き
わらにもすがる

【意味】
追いつめられて、どうしようもなくなった時、頼りにならないものまで頼りにすること。


まあ、つまりは、絶体絶命の時には何でもいいから助けてくれ、って思うんやな。これは、人間が困った時の必死さを表してるんやで。
輪をかける

【意味】
物事の程度が、いっそう大きくなること。実際より大げさに言う、といった意味にも使う。


つまり、すごいことがさらにすごくなる、もしくは悪いことがさらに悪くなるってわけや。これは、いつも以上に強調したいときに使う表現やな。












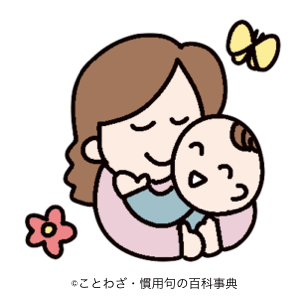
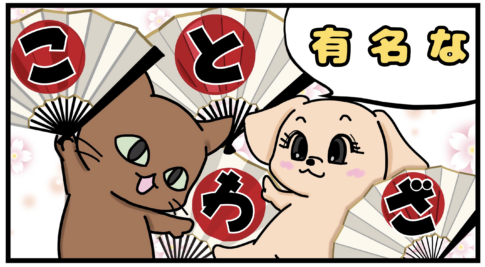





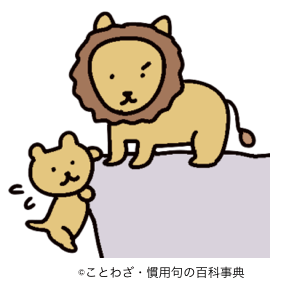






相手の話を理解しているし、興味を持っていることを示す一種の礼儀とも言えるね。