【琴線に触れる】の意味と使い方や例文
「琴線に触れる」の意味 【慣用句】 琴線に触れる 【読み方】 きんせんにふれる 【意味】 あることに共鳴し深く感動する。 「琴線に触れる」の解説 「琴線に触れる」の使い方 「琴線に触れる」の例文 音楽を作り、それを鑑賞す...
 「き」で始まる慣用句
「き」で始まる慣用句「琴線に触れる」の意味 【慣用句】 琴線に触れる 【読み方】 きんせんにふれる 【意味】 あることに共鳴し深く感動する。 「琴線に触れる」の解説 「琴線に触れる」の使い方 「琴線に触れる」の例文 音楽を作り、それを鑑賞す...
 「き」で始まる慣用句
「き」で始まる慣用句「気を悪くする」の意味(対義語) 【慣用句】 気を悪くする 【読み方】 きをわるくする 【意味】 きげんを悪くする。いやな気持ちになる。 【対義語】 気を良くする 「気を悪くする」の解説 「気を悪くする」の使い方 「気を...
 「き」で始まる慣用句
「き」で始まる慣用句「気を楽にする」の意味 【慣用句】 気を楽にする 【読み方】 きをらくにする 【意味】 気持ちをゆったりさせる。気楽にする。 「気を楽にする」の解説 「気を楽にする」の使い方 「気を楽にする」の例文 彼女の失敗をみんなが...
 「き」で始まる慣用句
「き」で始まる慣用句「気を良くする」の意味(対義語) 【慣用句】 気を良くする 【読み方】 きをよくする 【意味】 うれしくなる。いい気分になる。 【対義語】 気を悪くする 「気を良くする」の解説 「気を良くする」の使い方 「気を良くする」...
 「き」で始まる慣用句
「き」で始まる慣用句「気を持たせる」の意味 【慣用句】 気を持たせる 【読み方】 きをもたせる 【意味】 いかにももっともらしいことを言ったりして、相手に期待や希望を持たせる。 「気を持たせる」の解説 「気を持たせる」の使い方 「気を持たせ...
 「き」で始まる慣用句
「き」で始まる慣用句「機を見るに敏」の意味(出典) 【慣用句】 機を見るに敏 【読み方】 きをみるにびん 【意味】 好都合な状況や時期をすばやくつかんで的確に行動するさま。 【出典】 「論語」 「機を見るに敏」の解説 「機を見るに敏」の使い...
 「き」で始まる慣用句
「き」で始まる慣用句「気を引く」の意味 【慣用句】 気を引く 【読み方】 きをひく 【意味】 自分のほうに、関心を向けさせるようにする。 「気を引く」の解説 「気を引く」の使い方 「気を引く」の例文 彼は、彼女の気を引こうと盛んに話しかけて...
 「き」で始まる慣用句
「き」で始まる慣用句「気を張る」の意味 【慣用句】 気を張る 【読み方】 きをはる 【意味】 気持ちを引き締める。緊張させる。 「気を張る」の解説 「気を張る」の使い方 「気を張る」の例文 涙をこぼさないでいるためには、ずいぶん気を張らなけ...
 「き」で始まる慣用句
「き」で始まる慣用句「気を遣う」の意味 【慣用句】 気を遣う 【読み方】 きをつかう 【意味】 周りの人に細かいところまで心をはたらかせる。 「気を遣う」の解説 「気を遣う」の使い方 「気を遣う」の例文 彼女はお嬢様育ちだから、頭のいい人で...
 「き」で始まる慣用句
「き」で始まる慣用句「気を静める」の意味 【慣用句】 気を静める 【読み方】 きをしずめる 【意味】 興奮を落ち着かせ冷静さを取り戻すこと。 「気を静める」の解説 「気を静める」の使い方 「気を静める」の例文 いったいその話は、どこまでが真...
 「き」で始まる慣用句
「き」で始まる慣用句「気を利かせる」の意味 【慣用句】 気を利かせる 【読み方】 きをきかせる 【意味】 相手の気持ちや考え、その場の状況に配慮して行動する。「気を利かす」ともいう。 「気を利かせる」の解説 「気を利かせる」の使い方 「気を...
 「き」で始まる慣用句
「き」で始まる慣用句「気を入れる」の意味 【慣用句】 気を入れる 【読み方】 きをいれる 【意味】 本気になって集中して取り組む。 「気を入れる」の解説 「気を入れる」の使い方 「気を入れる」の例文 先生が一生懸命話をしていたが、生徒はだれ...
 「き」で始まる慣用句
「き」で始まる慣用句【慣用句】 機を逸する 【読み方】 きをいっする 【意味】 よい機会を取り逃がす。 【類義語】 ・機を失する 「機を逸する」の使い方 「機を逸する」の例文 思い立ったが吉日というように、いたずらに時を移しては、機を逸する...
 「き」で始まる慣用句
「き」で始まる慣用句「虚勢を張る」の意味 【慣用句】 虚勢を張る 【読み方】 きょせいをはる 【意味】 実力もないのに、あるように見せかけて、威張る。 「虚勢を張る」の解説 「虚勢を張る」の使い方 「虚勢を張る」の例文 父は自分の兄弟に対し...
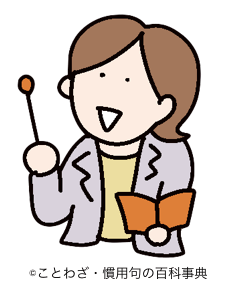 「き」で始まる慣用句
「き」で始まる慣用句「教鞭を執る」の意味 【慣用句】 教鞭を執る 【読み方】 きょうべんをとる 【意味】 教師になって生徒を教える。教職につく。 「教鞭を執る」の解説 「教鞭を執る」の使い方 「教鞭を執る」の例文 先生は90歳になったが、今...
 「き」で始まる慣用句
「き」で始まる慣用句「灸を据える」の意味(語源由来) 【慣用句】 灸を据える 【読み方】 きゅうをすえる 【意味】 灸で、病気を治そうとする意味で、厳しく注意をして行動を改めさせようとすること。 【語源由来】 「灸」は漢方療法の一つ。皮膚の...
 「き」で始まる慣用句
「き」で始まる慣用句「旧交を温める」の意味 【慣用句】 旧交を温める 【読み方】 きゅうこうをあたためる 【意味】 途絶えていた昔からの交際を再び始める。 「旧交を温める」の解説 「旧交を温める」の使い方 「旧交を温める」の例文 その温泉で...
 「き」で始まる慣用句
「き」で始まる慣用句「杞憂」の意味とは(出典・故事) 【故事成語】 杞憂 【読み方】 きゆう 【意味】 心配しなくてもよいことを、むやみに心配すること。取り越し苦労。「憂」は心配する意味。 【出典】 「列子」 【故事】 昔、中国の杞(き)の...
 「き」で始まる慣用句
「き」で始まる慣用句「気もそぞろ」の意味 【慣用句】 気もそぞろ 【読み方】 きもそぞろ 【意味】 違うことに気持ちが向いていて、集中できないようす。「そぞろ」は、なんとなくそわそわして落ち着かない様子。 「気もそぞろ」の解説 「気もそぞろ...
 「き」で始まる慣用句
「き」で始まる慣用句「肝が潰れる」の意味(類義語) 【慣用句】 肝が潰れる 【読み方】 きもがつぶれる 【意味】 非常に驚く。「肝」は、ここでは心・気力の意味。 【類義語】 ・肝を潰す(きもをつぶす) 「肝が潰れる」の解説 「肝が潰れる」の...
 「き」で始まる慣用句
「き」で始まる慣用句「木目が細かい」の意味 【慣用句】 木目が細かい 【読み方】 きめがこまかい 【意味】 ①肌や物の表面がすべすべした手ざわりである。 ②心づかいや注意が細かいところまで行き届いている。 「木目が細かい」の解説 「木目が細...
 「き」で始まる慣用句
「き」で始まる慣用句「気脈を通じる」の意味 【慣用句】 気脈を通じる 【読み方】 きみゃくをつうじる 【意味】 何かの目的のために、ひそかに連絡をとってお互いの気持ちや考えを通じ合わせる。「気脈」は血液の通う筋道で、ここでは気持ちのつながり...
 「き」で始まる慣用句
「き」で始まる慣用句「踵を接する」の意味(語源由来) 【慣用句】 踵を接する 【読み方】 きびすをせっする 【意味】 ①人が切れ目なく続く。 ②ものごとが次々と起こる。 【語源由来】 「踵」はかかと。前後の人の踵が接するほど、人が引き続いて...
 「き」で始まる慣用句
「き」で始まる慣用句「牙を剥く」の意味(語源由来) 【慣用句】 牙を剥く 【読み方】 きばをむく 【意味】 敵意を露骨にあらわす。また、危害を加えようとする。 【語源由来】 動物が牙をむき出しにする意味から。 「牙を剥く」の解説 「牙を剥く...
 「き」で始まる慣用句
「き」で始まる慣用句「牙を研ぐ」の意味(語源由来・類義語) 【慣用句】 牙を研ぐ 【読み方】 きばをとぐ 【意味】 相手をやっつけてやろうと、周到に準備をして待ち構えること。 【語源由来】 動物が獲物をねらって牙を磨くことから。 【類義語】...
 「き」で始まる慣用句
「き」で始まる慣用句「気のせい」の意味 【慣用句】 気のせい 【読み方】 きのせい 【意味】 はっきりした理油はないが、なんとなくそう思える。 「気のせい」の解説 「気のせい」の使い方 「気のせい」の例文 彼女が僕のことをちらちら見るので、...
 「き」で始まる慣用句
「き」で始まる慣用句「気にする」の意味 【慣用句】 気にする 【読み方】 きにする 【意味】 気がかりと思う。心配する。 「気にする」の解説 「気にする」の使い方 「気にする」の例文 最近、心の調子がおかしくて、それまで気にしていなかったこ...
 「き」で始まる慣用句
「き」で始まる慣用句「機に乗じる」の意味(類義語) 【慣用句】 機に乗じる 【読み方】 きにじょうじる 【意味】 その場の状況をうまくとらえて、それに応じて適切に行動する。 【類義語】 機に乗ずる 「機に乗じる」の解説 「機に乗じる」の使い...
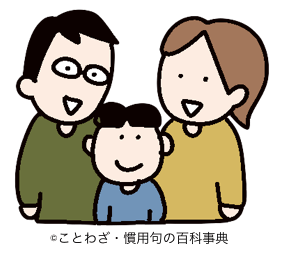 「き」で始まる慣用句
「き」で始まる慣用句「切っても切れない」の意味 【慣用句】 切っても切れない 【読み方】 きってもきれない 【意味】 切ろうとしても切ることができない、強いつながりがある。 「切っても切れない」の解説 「切っても切れない」の使い方 「切って...
 「き」で始まる慣用句
「き」で始まる慣用句「喜寿」の意味(語源由来) 【慣用句】 喜寿 【読み方】 きじゅ 【意味】 数え年の七七歳。また、その祝い。喜の祝い。喜の字の祝い。 【語源由来】 「喜」の字の草体「㐂」が「七十七」と分解できるところから。 「喜寿」の解...
 「き」で始まる慣用句
「き」で始まる慣用句「気骨がある」の意味 【慣用句】 気骨がある 【読み方】 きこつがある 【意味】 自分の信念を貫き通す強い意志を持つ。 「気骨がある」の解説 「気骨がある」の使い方 「気骨がある」の例文 今回の人選に際して、生真面目で気...
 「き」で始まる慣用句
「き」で始まる慣用句「機嫌を取る」の意味(類義語) 【慣用句】 機嫌を取る 【読み方】 きげんをとる 【意味】 人の気分を慰めやわらげるようにする。人の気に入るような言動をする。 【類義語】 御機嫌を取る 「機嫌を取る」の解説 「機嫌を取る...
 「き」で始まる慣用句
「き」で始まる慣用句「聞く耳を持たない」の意味 【慣用句】 聞く耳を持たない 【読み方】 きくみみをもたない 【意味】 相手の話を聞こうとする気持ちがない。 「聞く耳を持たない」の解説 「聞く耳を持たない」の使い方 「聞く耳を持たない」の例...
 「き」で始まる慣用句
「き」で始まる慣用句「鬼気迫る」の意味 【慣用句】 鬼気迫る 【読み方】 ききせまる 【意味】 非常に恐ろしい気配が身に迫ってくるように感じられる。「鬼気」は、この世のものとは思われない恐ろしい気配。 「鬼気迫る」の解説 「鬼気迫る」の使い...
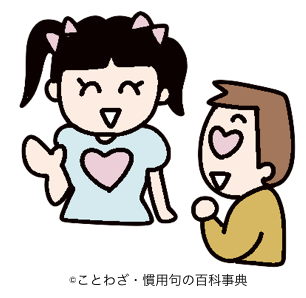 「き」で始まる慣用句
「き」で始まる慣用句「聞きしに勝る」の意味 【慣用句】 聞きしに勝る 【読み方】 ききしにまさる 【意味】 うわさに聞いていた以上である。 「聞きしに勝る」の解説 「聞きしに勝る」の使い方 「聞きしに勝る」の例文 彼の全財産を投入したコレク...
 「き」で始まる慣用句
「き」で始まる慣用句「気が若い」の意味 【慣用句】 気が若い 【読み方】 きがわかい 【意味】 年の割に気持ちが元気で若々しい。 「気が若い」の解説 「気が若い」の使い方 「気が若い」の例文 彼女は45歳だが、気が若いので、大学生のアルバイ...
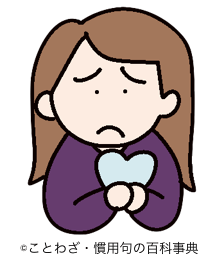 「き」で始まる慣用句
「き」で始まる慣用句「気が弱い」の意味(対義語) 【慣用句】 気が弱い 【読み方】 きがよわい 【意味】 自信が持てずに、他人に気兼ねしたり、思いどおりに行動できなかったりする。 【対義語】 気が強い 「気が弱い」の解説 「気が弱い」の使い...
 「き」で始まる慣用句
「き」で始まる慣用句「気が滅入る」の意味 【慣用句】 気が滅入る 【読み方】 きがめいる 【意味】 嫌なことや失敗したことで気持ちが沈んで、ゆううつになる。 「気が滅入る」の解説 「気が滅入る」の使い方 「気が滅入る」の例文 このまま家にい...
 「き」で始まる慣用句
「き」で始まる慣用句「気が向く」の意味 【慣用句】 気が向く 【読み方】 きがむく 【意味】 しようとする気になる。乗り気になる。 「気が向く」の解説 「気が向く」の使い方 「気が向く」の例文 彼は、とても旅行が好きなので、気が向くと雨だろ...
 「き」で始まる慣用句
「き」で始まる慣用句「気が回る」の意味 【慣用句】 気が回る 【読み方】 きがまわる 【意味】 細かな所まで注意が行き届く。 「気が回る」の解説 「気が回る」の使い方 「気が回る」の例文 彼が、過労で死んだということをきかされて、私は、彼が...
 「き」で始まる慣用句
「き」で始まる慣用句「気が張る」の意味 【慣用句】 気が張る 【読み方】 きがはる 【意味】 緊張して、気持ちが引き締まる。 「気が張る」の解説 「気が張る」の使い方 「気が張る」の例文 昨日から気が張っていたせいで、意識しなかったのだけれ...
 「き」で始まる慣用句
「き」で始まる慣用句「気が早い」の意味 【慣用句】 気が早い 【読み方】 きがはやい 【意味】 せっかちである。 「気が早い」の解説 「気が早い」の使い方 「気が早い」の例文 娘が生まれた瞬間に、夫は、出産の喜びと同時に、もう、娘が嫁に行く...
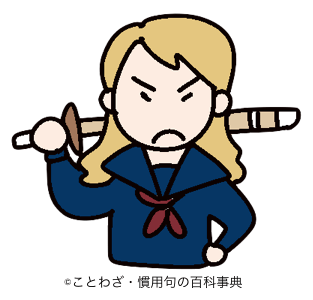 「き」で始まる慣用句
「き」で始まる慣用句「気が強い」の意味(対義語) 【慣用句】 気が強い 【読み方】 きがつよい 【意味】 気性が激しく容易に屈しない性格である。勝ち気である。 【対義語】 気が弱い 「気が強い」の解説 「気が強い」の使い方 「気が強い」の例...
 「き」で始まる慣用句
「き」で始まる慣用句「気が立つ」の意味 【慣用句】 気が立つ 【読み方】 きがたつ 【意味】 いらいらする。興奮する。 「気が立つ」の解説 「気が立つ」の使い方 「気が立つ」の例文 近所で大規模な工事が始まり、その騒音のせいで、祖母は気が立...
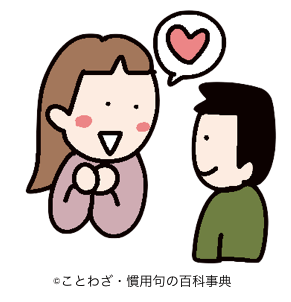 「き」で始まる慣用句
「き」で始まる慣用句「気がある」の意味(対義語) 【慣用句】 気がある 【読み方】 きがある 【意味】 ①関心がある ②恋い慕う気持ちが向いている。 【対義語】 気が無い 「気がある」の解説 「気がある」の使い方 「気がある」の例文 彼は、...
 「き」で始まる慣用句
「き」で始まる慣用句「気合を入れる」の意味(類義語) 【慣用句】 気合を入れる 【読み方】 きあいをいれる 【意味】 ①気持ちを引き締める。 ②叱りつけて、やる気を起こさせる。「気合い」は、意気込み。かけ声。 【類義語】 ・ねじを巻く ・発...
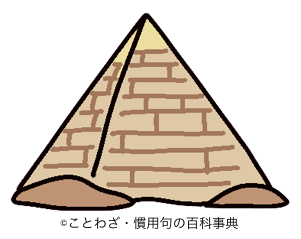 「き」で始まる慣用句
「き」で始まる慣用句「金字塔」の意味 【慣用句】 金字塔 【読み方】 きんじとう 【意味】 ①「金」の字の形の塔。ピラミッドをいう。 ②後世に永く残る立派な業績。偉大な作品や事業。 「金字塔」の解説 「金字塔」の使い方 「金字塔」の例文 オ...
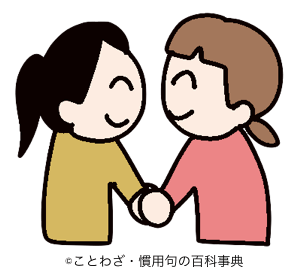 「き」で始まる慣用句
「き」で始まる慣用句「気を許す」の意味 【慣用句】 気を許す 【読み方】 きをゆるす 【意味】 相手を信用して警戒心や緊張を解く。油断する。 「気を許す」の解説 「気を許す」の使い方 「気を許す」の例文 気を許していた友人に裏切られ、ショッ...
 「き」で始まる慣用句
「き」で始まる慣用句「気を揉む」の意味 【慣用句】 気を揉む 【読み方】 きをもむ 【意味】 あれこれと心配すること。 「気を揉む」の解説 「気を揉む」の使い方 「気を揉む」の例文 彼は、健太くんの名付け親なのだから、健太くんが今どうしてい...
 「き」で始まる慣用句
「き」で始まる慣用句「気を回す」の意味 【慣用句】 気を回す 【読み方】 きをまわす 【意味】 あれこれと余計なことまで心配したり想像したりする。 「気を回す」の解説 「気を回す」の使い方 「気を回す」の例文 息子の帰宅が遅いと、つい気を回...
 「き」で始まる慣用句
「き」で始まる慣用句「気を吐く」の意味 【慣用句】 気を吐く 【読み方】 きをはく 【意味】 意気込みを示す。威勢のよいことを示す。 「気を吐く」の解説 「気を吐く」の使い方 「気を吐く」の例文 店長は、自分が本社に戻るために業績を上げよう...
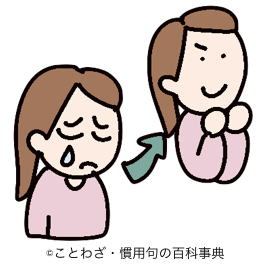 「き」で始まる慣用句
「き」で始まる慣用句「気を取り直す」の意味 【慣用句】 気を取り直す 【読み方】 きをとりなおす 【意味】 気落ちした状態から、思い直して元気を出す。 「気を取り直す」の解説 「気を取り直す」の使い方 「気を取り直す」の例文 台風の直撃で、...
 「き」で始まる慣用句
「き」で始まる慣用句「気を取られる」の意味 【慣用句】 気を取られる 【読み方】 きをとられる 【意味】 ほかのことに注意を奪われる。 「気を取られる」の解説 「気を取られる」の使い方 「気を取られる」の例文 彼女は、何か他のことに気を取ら...
 「き」で始まる慣用句
「き」で始まる慣用句「気を落とす」の意味 【慣用句】 気を落とす 【読み方】 きをおとす 【意味】 がっかりする。失望する。 「気を落とす」の解説 「気を落とす」の使い方 「気を落とす」の例文 彼は、大学受験に失敗してしまい、気を落としてい...
 「き」で始まる慣用句
「き」で始まる慣用句「気を失う」の意味 【慣用句】 気を失う 【読み方】 きをうしなう 【意味】 意識を失う。気絶する。 意欲を失う。気落ちする。 「気を失う」の解説 「気を失う」の使い方 「気を失う」の例文 その事件の現場は人の多い場所だ...
 「き」で始まる慣用句
「き」で始まる慣用句「虚を衝く」の意味 【慣用句】 虚を衝く 【読み方】 きょをつく 【意味】 相手の弱点や無防備につけ込んで攻撃する。 「虚を衝く」の解説 「虚を衝く」の使い方 「虚を衝く」の例文 彼とエレベーターで談笑していたが、到着し...
 「き」で始まる慣用句
「き」で始まる慣用句「興に乗る」の意味 【慣用句】 興に乗る 【読み方】 きょうにのる 【意味】 おもしろさを感じて何かをする。興に乗ずる。 「興に乗る」の解説 「興に乗る」の使い方 「興に乗る」の例文 音楽を聞くと、彼女は興に乗って、どこ...
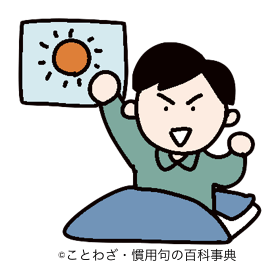 「き」で始まる慣用句
「き」で始まる慣用句「今日という今日」の意味 【慣用句】 今日という今日 【読み方】 きょうというきょう 【意味】 今日こそ。 「今日という今日」の解説 「今日という今日」の使い方 「今日という今日」の例文 今日という今日、話を一歩先へ進め...
 「き」で始まる慣用句
「き」で始まる慣用句「牛耳る」の意味(語源由来) 【慣用句】 牛耳る 【読み方】 ぎゅうじる 【意味】 指導者となって、思うままに支配する。 【語源由来】 古代中国では、諸侯が同盟を結ぶときには、その中心人物である盟主が牛の耳を裂き、各々が...
 「き」で始まる慣用句
「き」で始まる慣用句「肝を冷やす」の意味 【慣用句】 肝を冷やす 【読み方】 きもをひやす 【意味】 危険を感じてぞっとする。ひやっとする。 「肝を冷やす」の解説 「肝を冷やす」の使い方 「肝を冷やす」の例文 静かに戸を押すと、音をたてて、...
 「き」で始まる慣用句
「き」で始まる慣用句「肝を潰す」の意味 【慣用句】 肝を潰す 【読み方】 きもをつぶす 【意味】 突然のことで、非常にびっくりすること。たいそう驚くこと。 「肝を潰す」の解説 「肝を潰す」の使い方 「肝を潰す」の例文 手紙を見た父は、ぺたり...
 「き」で始まる慣用句
「き」で始まる慣用句「肝が太い」の意味 【慣用句】 肝が太い 【読み方】 きもがふとい 【意味】 何事にも動じない。大胆である。 「肝が太い」の解説 「肝が太い」の使い方 「肝が太い」の例文 彼は新人だけれども肝が太い上に、アイディアが他の...
 「き」で始まる慣用句
「き」で始まる慣用句「肝が小さい」の意味 【慣用句】 肝が小さい 【読み方】 きもがちいさい 【意味】 度量が小さい。度胸がない。 「肝が小さい」の解説 「肝が小さい」の使い方 「肝が小さい」の例文 彼は、父の跡を継いで社長になるのは自分以...
 「き」で始まる慣用句
「き」で始まる慣用句「肝が据わる」の意味 【慣用句】 肝が据わる 【読み方】 きもがすわる 【意味】 度胸があって、めったなことでは驚かない。 「肝が据わる」の解説 「肝が据わる」の使い方 「肝が据わる」の例文 彼は幾多の修羅場をくぐってき...
 「き」で始まる慣用句
「き」で始まる慣用句「肝が大きい」の意味 【慣用句】 肝が大きい 【読み方】 きもがおおきい 【意味】 何事にも驚いたり物おじしたりしない。 「肝が大きい」の解説 「肝が大きい」の使い方 「肝が大きい」の例文 あの人は、私と同い年なのに、こ...
 「き」で始まる慣用句
「き」で始まる慣用句「きまりが悪い」の意味(語源由来) 【慣用句】きまりが悪い 【読み方】 きまりがわるい 【意味】 他に対して面目が立たない。恥ずかしい。 きちんと整っていない。しまりがつかない。 【語源由来】 「決まり」とは、動詞「決ま...
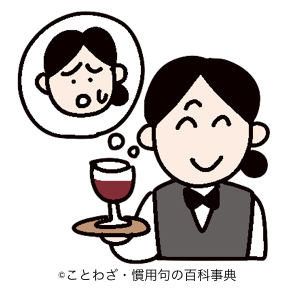 「き」で始まる慣用句
「き」で始まる慣用句「気骨が折れる」の意味(語源由来) 【慣用句】 気骨が折れる 【読み方】 きぼねがおれる 【意味】 いろいろと神経を使って、気疲れする。 【語源由来】 「気骨(きぼね)」が心づかい。気苦労という意味であることから。 「気...
 「き」で始まる慣用句
「き」で始まる慣用句「踵を返す」の意味(語源由来) 【慣用句】 踵を返す 【読み方】 きびすをかえす 【意味】 引き返す。後戻りする。 【語源由来】 「踵」はかかとのこと。「くびす」ともいう。かかとを来た方向に向けることから。 「踵を返す」...
 「き」で始まる慣用句
「き」で始まる慣用句「着の身着のまま」の意味 【慣用句】 着の身着のまま 【読み方】 きのみきのまま 【意味】 着ているもののほかは何も持っていないこと。 「着の身着のまま」の解説 「着の身着のまま」の使い方 「着の身着のまま」の例文 防寒...
 「き」で始まる慣用句
「き」で始まる慣用句「気に病む」の意味 【慣用句】 気に病む 【読み方】 きにやむ 【意味】 悪い方に考えて思い悩む。 「気に病む」の解説 「気に病む」の使い方 「気に病む」の例文 彼は急に理由もなく体重が減ったので、何か病気なのではないか...
 「き」で始まる慣用句
「き」で始まる慣用句「気に障る」の意味 【慣用句】 気に障る 【読み方】 きにさわる 【意味】 不愉快になる。気分を害する。 「気に障る」の解説 「気に障る」の使い方 「気に障る」の例文 人の意見にとりあえず反対しようとする彼の態度は気に障...
 「き」で始まる慣用句
「き」で始まる慣用句「気に食わない」の意味 【慣用句】 気に食わない 【読み方】 きにくわない 【意味】 自分の気持ちに合わないので、不満に思う。気に入らない。 「気に食わない」の解説 「気に食わない」の使い方 「気に食わない」の例文 男性...
 「き」で始まる慣用句
「き」で始まる慣用句「気に掛ける」の意味 【慣用句】 気に掛ける 【読み方】 きにかける 【意味】 心にとめて考える。心配する。 「気に掛ける」の解説 「気に掛ける」の使い方 「気に掛ける」の例文 誰もがこの会社は安泰だと、この時点ではそう...
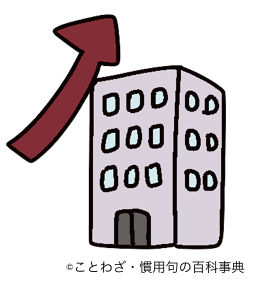 「き」で始まる慣用句
「き」で始まる慣用句「軌道に乗る」の意味(語源由来) 【慣用句】 軌道に乗る 【読み方】 きどうにのる 【意味】 計画どおりに物事が順調に進む。 【語源由来】 「軌道」は汽車、電車の線路、レール。 「軌道に乗る」の解説 「軌道に乗る」の使い...
 「き」で始まる慣用句
「き」で始まる慣用句「気で気を病む」の意味 【慣用句】 気で気を病む 【読み方】 きできをやむ 【意味】 必要のない心配をして、自分で自分を苦しめる。 「気で気を病む」の解説 「気で気を病む」の使い方 「気で気を病む」の例文 彼は、家の外は...
 「き」で始まる慣用句
「き」で始まる慣用句「聞き耳を立てる」の意味 【慣用句】 聞き耳を立てる 【読み方】 ききみみをたてる 【意味】 注意して聞き取ろうとすること。 「聞き耳を立てる」の解説 「聞き耳を立てる」の使い方 「聞き耳を立てる」の例文 彼女に言葉を発...
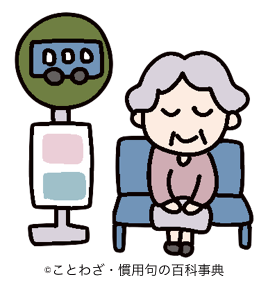 「き」で始まる慣用句
「き」で始まる慣用句「気が長い」の意味(対義語) 【慣用句】 気が長い 【読み方】 きがながい 【意味】 ゆったりしていてあせらないこと。おっとりしてがまん強く、心が広い性格の人もさす。 【対義語】 ・気が短い 「気が長い」の解説 「気が長...
 「き」で始まる慣用句
「き」で始まる慣用句「気がない」の意味(語源由来) 【慣用句】 気がない 【読み方】 きがない 【意味】 関心や興味がなく、その気にならないこと。 【語源由来】 その気がないという意味から。 「気がない」の解説 「気がない」の使い方 「気が...
 「き」で始まる慣用句
「き」で始まる慣用句「気が咎める」の意味(語源由来) 【慣用句】 気が咎める 【読み方】 きがとがめる 【意味】 罪の意識を感じる。後ろめたい。やましさを感じる。 【語源由来】 「咎める」があやまちや罪を取り立てて、非難する。なじる。という...
 「き」で始まる慣用句
「き」で始まる慣用句「気が遠くなる」の意味(語源由来) 【慣用句】 気が遠くなる 【読み方】 きがとおくなる 【意味】 物事の規模がはなはだしく大きいようす。 【語源由来】 意識が薄れてぼうっとなるような感じだの意味から。 「気が遠くなる」...
 「き」で始まる慣用句
「き」で始まる慣用句「気が付く」の意味 【慣用句】 気が付く 【読み方】 きがつく 【意味】 ①そのことに注意がむく。考え付く。 ②気を失っていた人が、意識を取り戻す。また、眠っていた人が目を覚ます。 ③細かなところまで、注意が行き届く。 ...
 「き」で始まる慣用句
「き」で始まる慣用句「気が急く」の意味(語源由来) 【慣用句】 気が急く 【読み方】 きがせく 【意味】 心があせって落ち着かない。 【語源由来】 急ごうと気持ちがあせることから。 「気が急く」の解説 「気が急く」の使い方 「気が急く」の例...
 「き」で始まる慣用句
「き」で始まる慣用句「気が済む」の意味(語源由来) 【慣用句】 気が済む 【読み方】 きがすむ 【意味】 気持ちが収まる。気がかりなことがなくなり落ち着く。 【語源由来】 気になっていたことが終わることから。 「気が済む」の解説 「気が済む...
 「き」で始まる慣用句
「き」で始まる慣用句「気が進まない」の意味(語源由来) 【慣用句】 気が進まない 【読み方】 きがすすまない 【意味】 そのことをしようという意欲がわかない。 【語源由来】 自ら進んで物事をしようと思わないことから。 「気が進まない」の解説...
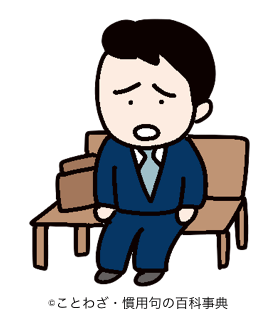 「き」で始まる慣用句
「き」で始まる慣用句「気が重い」の意味 【慣用句】 気が重い 【読み方】 きがおもい 【意味】 よくない結果が予想されたり、負担に感じることがあって、気持ちが沈むこと。 「気が重い」の解説 「気が重い」の使い方 「気が重い」の例文 明日も気...
 「き」で始まる慣用句
「き」で始まる慣用句「気落ちする」の意味(語源由来) 【慣用句】 気落ちする 【読み方】 きおちする 【意味】 がっかりして力を落とすこと。落胆。 【語源由来】 気持ちが沈み、力を落とすことから。 「気落ちする」の解説 「気落ちする」の使い...
 「き」で始まる慣用句
「き」で始まる慣用句「気炎を揚げる」の意味(語源由来・類義語) 【慣用句】 気炎を揚げる 【読み方】 きえんをあげる 【意味】 炎のように盛んな意気を示し、威勢のよい言葉を吐くこと。 【語源由来】 燃え上がるように盛り上がること。またその意...
 「き」で始まる慣用句
「き」で始まる慣用句「黄色い声」の意味 【慣用句】 黄色い声 【読み方】 きいろいこえ 【意味】 女性や子供のかん高い声。きいきい声。 「黄色い声」の解説 「黄色い声」の使い方 「黄色い声」の例文 アイドルがテレビ局から出てくると、出口で待...
 「き」で始まる慣用句
「き」で始まる慣用句「脚光を浴びる」の意味(語源由来) 【慣用句】 脚光を浴びる 【読み方】 きゃっこうをあびる 【意味】 舞台に立つこと。注目される存在になること。 【語源由来】 「脚光」は、舞台の床の前方に据えて、俳優を足元から照らす照...
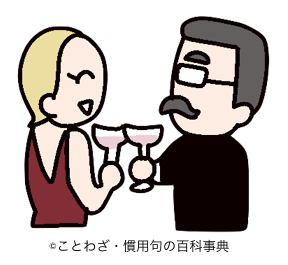 「き」で始まる慣用句
「き」で始まる慣用句「綺羅星の如く」の意味(語源由来・類義語) 【慣用句】 綺羅星の如く 【読み方】 きら、ほしのごとく 【意味】 地位の高い人や立派な人が多く並ぶ様子のたとえ。 【語源由来】 「綺羅」には美しい衣服という意味があり、転じて...
 「き」で始まる慣用句
「き」で始まる慣用句「牛耳を執る」の意味(故事) 【慣用句】 牛耳を執る 【読み方】 ぎゅうじをとる 【意味】 ある団体や組織などの主導権を握る。 【故事】 「左伝哀公十七年」にある故事から。諸侯が同盟を結ぶ儀式で、盟主が牛の耳を割いて血を...
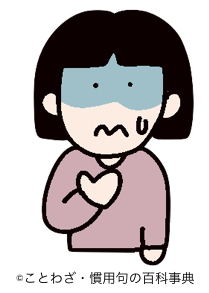 「き」で始まる慣用句
「き」で始まる慣用句「気を呑まれる」の意味 【慣用句】 気を呑まれる 【読み方】 きをのまれる 【意味】 心理的に圧倒されること。 「気を呑まれる」の解説 「気を呑まれる」の使い方 「気を呑まれる」の例文 リングに立った瞬間、相手の強烈なオ...
 「き」で始まる慣用句
「き」で始まる慣用句「気を配る」の意味 【慣用句】 気を配る 【読み方】 きをくばる 【意味】 周囲の人々や状況に注意をして、手落ちがないようにあれこれと心を使うこと。 「気を配る」の解説 「気を配る」の使い方 「気を配る」の例文 初対面の...
 「き」で始まる慣用句
「き」で始まる慣用句「気に掛かる」の意味 【慣用句】 気に掛かる 【読み方】 きにかかる 【意味】 心配事や疑問などがひっかかって離れないこと。 「気に掛かる」の解説 「気に掛かる」の使い方 「気に掛かる」の例文 明日は先日受診した健康診断...
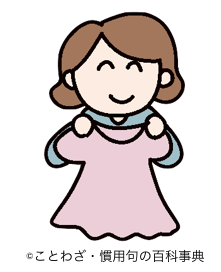 「き」で始まる慣用句
「き」で始まる慣用句「気に入る」の意味 【慣用句】 気に入る 【読み方】 きにいる 【意味】 好みに合うこと。 「気に入る」の解説 「気に入る」の使い方 「気に入る」の例文 この店で気に入った物があれば、遠慮せずに何でも買ってかまわないよ。...
 「き」で始まる慣用句
「き」で始まる慣用句「気が揉める」の意味(類義語) 【慣用句】 気が揉める 【読み方】 きがもめる 【意味】 あることをするのにためらいを感じること。 【類義語】 やきもきする 「気が揉める」の解説 「気が揉める」の使い方 「気が揉める」の...
 「き」で始まる慣用句
「き」で始まる慣用句「気が引ける」の意味 【慣用句】 気が引ける 【読み方】 きがひける 【意味】 気おくれしたり引け目をかんじること。 「気が引ける」の解説 「気が引ける」の使い方 「気が引ける」の例文 周りの人たちの顔を見るとみんな優秀...
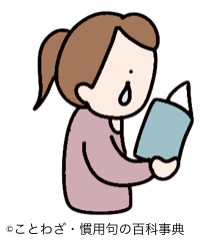 「き」で始まる慣用句
「き」で始まる慣用句「行間を読む」の意味 【慣用句】 行間を読む 【読み方】 ぎょうかんをよむ 【意味】 文字面に表れていない、筆者の真意などをくみとる。 「行間を読む」の解説 「行間を読む」の使い方 「行間を読む」の例文 行間を読むのに必...
 「き」で始まる慣用句
「き」で始まる慣用句「気が短い」の意味(類義語) 【慣用句】 気が短い 【読み方】 きがみじかい 【意味】 すぐいらいらしたり怒ったりすること。 【類義語】 短気である 「気が短い」の解説 「気が短い」の使い方 「気が短い」の例文 あの人は...
 「き」で始まる慣用句
「き」で始まる慣用句「気が抜ける」の意味(類義語) 【慣用句】 気が抜ける 【読み方】 きがぬける 【意味】 物事が中断したり緊張をなくすようなことが起きたりして、張り合いがなくなること。 【類義語】 拍子抜けする 「気が抜ける」の解説 「...
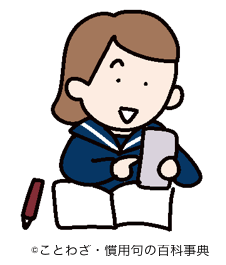 「き」で始まる慣用句
「き」で始まる慣用句「気が散る」の意味 【慣用句】 気が散る 【読み方】 きがちる 【意味】 一つのことに気持ちが集中できないこと。 「気が散る」の解説 「気が散る」の使い方 「気が散る」の例文 外の景色があまりにも綺麗なものだから、それ...
 「き」で始まる慣用句
「き」で始まる慣用句「気が気でない」の意味 【慣用句】 気が気でない 【読み方】 きがきでない 【意味】 悪い事態を予測して非常に気がかりになって落ち着かないこと。 「気が気でない」の解説 「気が気でない」の使い方 「気が気でない」の例文 ...
 「き」で始まる慣用句
「き」で始まる慣用句「気が利く」の意味 【慣用句】 気が利く 【読み方】 きがきく 【意味】 細かなところまで注意や配慮が行き届き、臨機応変な対応ができること。 「気が利く」の解説 「気が利く」の使い方 「気が利く」の例文 彼は気が利くので...
 「き」で始まる慣用句
「き」で始まる慣用句「気が多い」の意味 【慣用句】 気が多い 【読み方】 きがおおい 【意味】 心が定まらず、関心や興味がいろいろに変わること。 「気が多い」の解説 「気が多い」の使い方 「気が多い」の例文 彼は気が多い人なので、一つのこと...
 「き」で始まる慣用句
「き」で始まる慣用句「機が熟す」の意味 【慣用句】 機が熟す 【読み方】 きがじゅくす 【意味】 ものごとをするのにちょうどよい時期になること。 「機が熟す」の解説 「機が熟す」の使い方 「機が熟す」の例文 作品の構想はすっかり出来上がって...
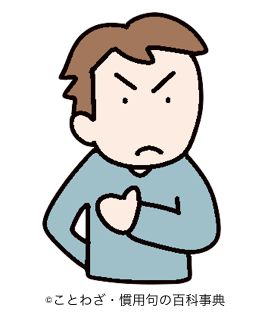 「き」で始まる慣用句
「き」で始まる慣用句「肝に銘じる」の意味(類義語) 【慣用句】 肝に銘じる 【読み方】 きもにめいじる 【意味】 心に深く刻みつけて忘れないようにする。 【類義語】 骨に刻む 「肝に銘じる」の解説 「肝に銘じる」の使い方 「肝に銘じる」の例...
 「き」で始まる慣用句
「き」で始まる慣用句「狐につままれる」の意味(語源由来) 【慣用句】 狐につままれる 【読み方】 きつねにつままれる 【意味】 意外なことが突然起こって、わけがわからず、ぼんやりする様子のたとえ。 【語源由来】 狐に化かされた時のように呆然...