【鬼も十八番茶も出花】の意味と使い方や例文(語源由来・類義語・英語訳)
「鬼も十八番茶も出花」の意味(語源由来・類義語・英語) 【ことわざ】 鬼も十八番茶も出花 【読み方】 おにもじゅうはちばんちゃもでばな 【意味】 どんなものにも、その魅力がいちばん発揮される時期があるということ。女性は誰...
 「お」で始まることわざ
「お」で始まることわざ「鬼も十八番茶も出花」の意味(語源由来・類義語・英語) 【ことわざ】 鬼も十八番茶も出花 【読み方】 おにもじゅうはちばんちゃもでばな 【意味】 どんなものにも、その魅力がいちばん発揮される時期があるということ。女性は誰...
 「お」で始まることわざ
「お」で始まることわざ「鬼の空念仏」の意味(語源由来・類義語・英語) 【ことわざ】 鬼の空念仏 【読み方】 おにのそらねんぶつ 【意味】 無慈悲な者が心にもなく殊勝なようすをすることのたとえ。鬼の念仏。 【語源・由来】 無慈悲で残酷な鬼が、心...
 「お」で始まることわざ
「お」で始まることわざ「鬼の首を取ったよう」の意味(語源由来・英語) 【ことわざ】 鬼の首を取ったよう 【読み方】 おにのくびをとったよう 【意味】 大変な功名・手柄を立てたかのように得意になるさま。 【語源・由来】 鬼の首を討ち取ったわけで...
 「お」で始まることわざ
「お」で始まることわざ【ことわざ】 鬼の霍乱 【読み方】 おにのかくらん 【意味】 ふだんきわめて健康な人が珍しく病気になることのたとえ 【語源・由来】 「霍乱(かくらん)」は、日射病のこと。また、夏に起こりやすいとされる、吐き気や下痢を伴う...
 「お」で始まることわざ
「お」で始まることわざ「鬼が出るか蛇が出るか」の意味(語源由来・類義語・英語訳) 【ことわざ】 鬼が出るか蛇が出るか 【読み方】 おにがでるかじゃがでるか 【意味】 どんなに恐ろしいことが待っているのか、わからないというたとえ。 また、将来ど...
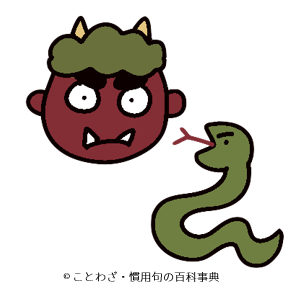 「お」で始まることわざ
「お」で始まることわざ「鬼が住むか蛇が住むか」の意味(語源由来・英語訳) 【ことわざ】 鬼が住むか蛇が住むか 【読み方】 おにがすむかじゃがすむか 【意味】 世の中には、どのような恐ろしい考えの人が住んでいるのかわからないというたとえ。 また...
 「お」で始まることわざ
「お」で始まることわざ「同じ釜の飯を食う」の意味(類義語・英語訳) 【ことわざ】 同じ釜の飯を食う 【読み方】 おなじかまのめしをくう 【意味】 他人ではあるが、一緒に生活して苦楽をともにした親しい仲間のこと。 【類義語】 一つ釜の飯を食う(...
 「お」で始まることわざ
「お」で始まることわざ「男やもめに蛆がわき、女やもめに花が咲く」の意味(語源由来・類義語・英語) 【ことわざ】 男やもめに蛆がわき、女やもめに花が咲く 【読み方】 おとこやもめにうじがわき、おんなやもめにはながさく 【意味】 男性は妻を亡くす...
 「お」で始まることわざ
「お」で始まることわざ「男は敷居を跨げば七人の敵あり」の意味(語源由来・類義語・英語訳) 【ことわざ】 男は敷居を跨げば七人の敵あり 【読み方】 おとこはしきいをまたげばしちにんのてきあり 【意味】 男性は社会に出れば多くの敵に出会うというた...
 「お」で始まることわざ
「お」で始まることわざ「男心と秋の空」の意味(語源由来・類義語・英語) 【ことわざ】 男心と秋の空 【読み方】 おとこごころとあきのそら 【意味】 秋の天候が変わりやすいように、男性の愛情も変わりやすいというたとえ。 【語源・由来】 秋の空模...
 「お」で始まることわざ
「お」で始まることわざ【ことわざ】 小田原評定 【読み方】 おだわらひょうじょう 【意味】 長引いてなかなか決定しない相談。 【語源・由来】 豊臣秀吉が小田原城を攻囲した時、小田原城内で北条氏直の腹心等の和戦の評定が長引いて決定しなかったこと...
 「お」で始まることわざ
「お」で始まることわざ「恐れ入谷の鬼子母神」の意味(語源由来) 【ことわざ】 恐れ入谷の鬼子母神 【読み方】 おそれいりやのきしもじん 【意味】 「恐れ入りました」をしゃれていったことば。 【語源・由来】 「鬼子母神(きしもじん・きしぼじん)...
 「お」で始まることわざ
「お」で始まることわざ「教うるは学ぶの半ば」の意味(出典・類義語・英語) 【ことわざ】 教うるは学ぶの半ば 【読み方】 おしうるはまなぶのなかば 【意味】 人にものを教えるということは、半分は自分で勉強することにもなるというたとえ。 【出典】...
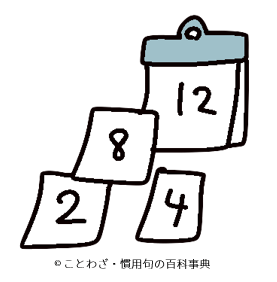 「お」で始まることわざ
「お」で始まることわざ「送る月日に関守なし」の意味(語源由来・類義語・英語訳) 【ことわざ】 送る月日に関守なし 【読み方】 おくるつきひにせきもりなし 【意味】 年月が過ぎるのは早いというたとえ。 【語源・由来】 「関守(せきもり)」とは、...
 「お」で始まることわざ
「お」で始まることわざ「奥歯に物が挟まる」の意味(語源由来・類義語・対義語・英語訳) 【ことわざ】 奥歯に物が挟まる 【読み方】 おくばにものがはさまる 【意味】 物事をはっきり言わず、何か隠すような言い方をする。 【語源・由来】 奥歯に物が...
 「お」で始まることわざ
「お」で始まることわざ「奥歯に衣着せる」の意味(語源由来・類義語・英語) 【ことわざ】 奥歯に衣着せる 【読み方】 おくばにきぬきせる 【意味】 物事をはっきり言わず、どこか思わせぶりに言う。 【語源・由来】 奥歯に衣をかぶせると、発音が不明...
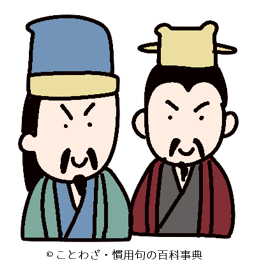 「う」で始まることわざ
「う」で始まることわざ「魚と水」の意味(語源由来・出典・類義語・対義語・英語訳) 【ことわざ】 魚と水 【読み方】 うおとみず 【意味】 とても親密な関係のことのたとえ。また、夫婦の仲がむつまじいこと。 【語源・由来】 水と魚が切り離せないよ...
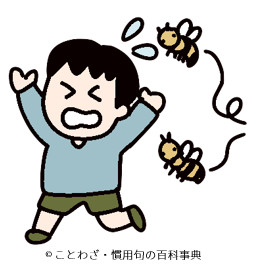 「う」で始まることわざ
「う」で始まることわざ「上を下へ」の意味(語源由来・類義語・英語訳) 【ことわざ】 上を下へ 【読み方】 うえをしたへ 【意味】 入り乱れて、とても慌てふためいているようす。 【語源・由来】 上にあるべきものを下にし、下にあるべきものを上にす...
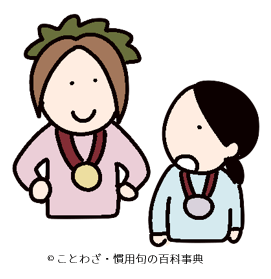 「う」で始まることわざ
「う」で始まることわざ「上には上がある」の意味(語源由来・類義語) 【ことわざ】 上には上がある 【読み方】 うえにはうえがある 【意味】 最高にすぐれていると思っても、さらにすぐれたものがある。うぬぼれや欲望を戒める言葉。 【語源・由来】 ...
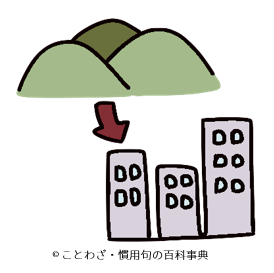 「う」で始まることわざ
「う」で始まることわざ「有為転変は世の習い」の意味(出典・類義語・英語訳) 【ことわざ】 有為転変は世の習い 【読み方】 ういてんぺんはよのならい 【意味】 この世の現象、ものごとすべては、すべてとどまることなく移り変わっていくというたとえ。...
 「い」で始まることわざ
「い」で始まることわざ「陰徳あれば必ず陽報あり」の意味(語源由来・出典・類義語・対義語・英語訳) 【ことわざ】 陰徳あれば必ず陽報あり 【読み方】 いんとくあればかならずようほうあり 【意味】 人目につかなくても善行を積んだ人には、よい報いが...
 「い」で始まることわざ
「い」で始まることわざ「殷鑑遠からず」の意味(出典・類義語・英語訳) 【ことわざ】 殷鑑遠からず 【読み方】 いんかんとおからず 【意味】 失敗の先例は、遠くに求めなくてもすぐ目の前にある。 【出典】 「詩経・大雅・蕩」から。殷王朝は前代の夏...
 「い」で始まることわざ
「い」で始まることわざ「引導を渡す」の意味(語源由来・英語訳) 【ことわざ】 引導を渡す 【読み方】 いんどうをわたす 【意味】 相手に仕方がないことだとあきらめさせること。 死者を葬る際に経文や法語を唱えること。 死を免れられないことや、最...
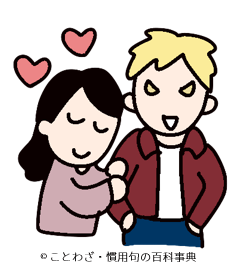 「い」で始まることわざ
「い」で始まることわざ「色は思案の外」の意味(語源由来・類義語・英語訳) 【ことわざ】 色は思案の外 【読み方】 いろはしあんのほか 【意味】 恋愛というものは人の理性を失わせることがあるというたとえ。 常識では予測や判断ができないことが多い...
 「い」で始まることわざ
「い」で始まることわざ「色の白いは七難隠す」の意味(語源由来・類義語・英語訳) 【ことわざ】 色の白いは七難隠す 【読み方】 いろのしろいはしちなんかくす 【意味】 色が白ければ、顔かたちに多少欠点があっても、隠すことができるというたとえ。 ...
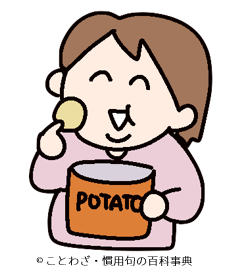 「い」で始まることわざ
「い」で始まることわざ「色気より食い気」の意味(語源由来・類義語・英語訳) 【ことわざ】 色気より食い気 【読み方】 いろけよりくいけ 【意味】 色欲より食欲を先にする。転じて、外見よりも中身を重んずるということ。 【語源・由来】 食欲が満た...
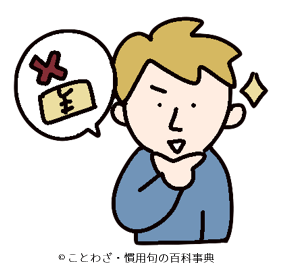 「い」で始まることわざ
「い」で始まることわざ「色男金と力はなかりけり」の意味(語源由来) 【ことわざ】 色男金と力はなかりけり 【読み方】 いろおとこかねとちからはなかりけり 【意味】 女に好かれるような美男子には、とかく金と腕力がない意。 【語源・由来】 美男子...
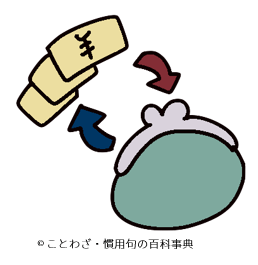 「い」で始まることわざ
「い」で始まることわざ「入るを量りて出ずるを為す」の意味(出典・類義語・英語訳) 【ことわざ】 入るを量りて出ずるを為す 【読み方】 いるをはかりていずるをなす 【意味】 収入額をきちんと把握して、それに見合う支出をしなさいというたとえ。 【...
 「い」で始まることわざ
「い」で始まることわざ「命の洗濯」の意味(語源由来・類義語・英語訳) 【ことわざ】 命の洗濯 【読み方】 いのちのせんたく 【意味】 日頃の苦労から解放されて楽しむことのたとえ。 【語源・由来】 命の垢を洗い流して、寿命をのばそうということが...
 「い」で始まることわざ
「い」で始まることわざ「命長ければ恥多し」の意味(出典・類義語・対義語・英語訳) 【ことわざ】 命長ければ恥多し 【読み方】 いのちながければはじおおし 【意味】 長生きをすると、それだけ恥をさらす機会が多くなるというたとえ。 【出典】 「荘...
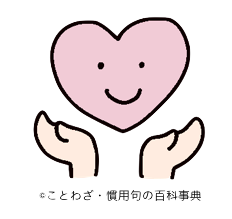 「い」で始まることわざ
「い」で始まることわざ「命あっての物種」とは 読み方・意味 ことわざ:命あっての物種 読み方:いのちあってのものだね 意味:なにごとも生きているからこそできるのである。生命にかかわる危険はなんとしても回避し、命を大切にしなさいという教え。 &...
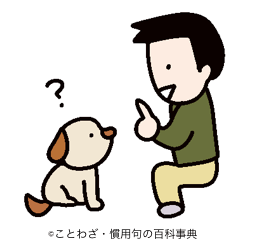 「い」で始まることわざ
「い」で始まることわざ「犬に論語」の意味(語源由来・類義語・英語) 【ことわざ】 犬に論語 【読み方】 いぬにろんご 【意味】 道理を聞かせても、なんの益もないこと。 【語源・由来】 犬にありがたい教えを聞かせても、なにもわからないことから。...
 「い」で始まることわざ
「い」で始まることわざ「犬と猿」の意味(語源由来・類義語・英語訳) 【ことわざ】 犬と猿 【読み方】 いぬとさる 【意味】 とても仲が悪いこと。 【語源・由来】 犬と猿は仲が悪いということが由来。 【類義語】 ・猫と犬(ねこといぬ) ・水と油...
 「い」で始まることわざ
「い」で始まることわざ「愛しき子には旅をさせよ」の意味(語源由来・類義語・英語訳) 【ことわざ】 愛しき子には旅をさせよ 【読み方】 いとしきこにはたびをさせよ 【意味】 子供がかわいいとつい甘やかしたくなるが、本当にかわいいと思うならば苦労...
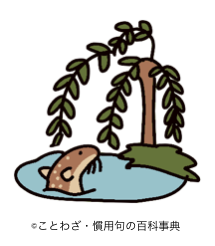 「い」で始まることわざ
「い」で始まることわざ「いつも柳の下に泥鰌は居らぬ」の意味(語源由来・類義語・対義語・英語訳) 【ことわざ】 いつも柳の下に泥鰌は居らぬ 【読み方】 いつもやなぎのしたにどじょうはおらぬ 【意味】 一度成功したからといって、同じやり方で、いつ...
 「い」で始まることわざ
「い」で始まることわざ「いつも月夜に米の飯」の意味(語源由来・類義語・英語訳) 【ことわざ】 いつも月夜に米の飯 【読み方】 いつもつきよにこめのめし 【意味】 毎日月がきれいな夜で、米の飯が続けばこの世は天国のように良いというたとえ。 また...
 「い」で始まることわざ
「い」で始まることわざ【ことわざ】 いつまでもあると思うな親と金 【読み方】 いつまでもあるとおもうなおやとかね 【意味】 親が生きているうちに一人前になって、孝行をし、お金はあるうちに倹約をしておかないとかならず困るときがくる、という教え。...
 「い」で始まることわざ
「い」で始まることわざ「一匹の馬が狂えば千匹の馬も狂う」の意味(語源由来・類義語・英語) 【ことわざ】 一匹の馬が狂えば千匹の馬も狂う 【読み方】 いっぴきのうまがくるえばせんびきのうまもくるう 【意味】 一人の行動が、他の大勢の行動を駆り立...
 「い」で始まることわざ
「い」で始まることわざ「一杯は人酒を飲む、二杯は酒酒を飲む、三杯は酒人を飲む」の意味(語源由来・類義語・英語) 【ことわざ】 一杯は人酒を飲む、二杯は酒酒を飲む、三杯は酒人を飲む 【読み方】 いっぱいはひとさけをのむ、にはいはさけさけをのむ、...
 「い」で始まることわざ
「い」で始まることわざ「一敗地に塗れる」の意味(出典・類義語・英語訳) 【ことわざ】 一敗地に塗れる 【読み方】 いっぱいちにまみれる 【意味】 二度と立ち上がれないほど大敗してしまう。 【出典】 「史記・高祖本紀」 ...
 「い」で始まることわざ
「い」で始まることわざ「一頭地を抜く」の意味(出典) 【ことわざ】 一頭地を抜く 【読み方】 いっとうちをぬく 【意味】 人より頭ひとつ分抜きんでていることのたとえ。 また、多くの人々よりも優れているということ。 【出典】 「宋史・蘇軾伝(そ...
 「い」で始まることわざ
「い」で始まることわざ「一銭を笑う者は一銭に泣く」の意味(語源由来・類義語・英語) 【ことわざ】 一銭を笑う者は一銭に泣く 【読み方】 いっせんをわらうものはいっせんになく 【意味】 どんなにわずかな金額でも、お金は大事にしなければいけないと...
 「い」で始まることわざ
「い」で始まることわざ「一寸の光陰軽んずべからず」の意味(語源由来・類義語・英語) 【ことわざ】 一寸の光陰軽んずべからず 【読み方】 いっすんのこういんかろんずべからず 【意味】 わずかな時間でもむだに過ごしてはいけない。 【語源・由来】 ...
 「い」で始まることわざ
「い」で始まることわざ「一将功成りて万骨枯る」の意味(出典・故事・類義語・英語) 【ことわざ】 一将功成りて万骨枯る 【読み方】 いっしょうこうなりてばんこつかる 【意味】 一人の将軍の輝かしい功名の陰には、幾万の兵が屍を戦場にさらした結果で...
 「い」で始まることわざ
「い」で始まることわざ「一挙手一投足」の意味(出典・類義語・英語) 【ことわざ】 一挙手一投足 【読み方】 いっきょしゅいっとうそく 【意味】 わずかな労力。少しの努力。細かないちいちの動作。一挙一動。 【出典】 韓愈かんゆ「応科目時与人書」...
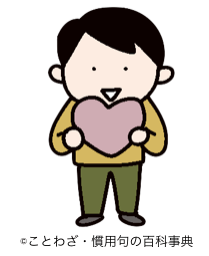 「あ」で始まることわざ
「あ」で始まることわざ「朝に道を聞かば、夕べに死すとも可なり」の意味(出典・類義語・英語訳) 【ことわざ】 朝に道を聞かば、夕べに死すとも可なり 【読み方】 あしたにみちをきかば、ゆうべにしすともかなり 【意味】 人として大切な道徳を聞いて悟...
 「あ」で始まる慣用句
「あ」で始まる慣用句「足下を見る」の意味(語源由来・類義語・英語訳) 【慣用句】 足下を見る 【読み方】 あしもとをみる 【意味】 相手の弱みにつけこむこと。 【語源由来】 駕籠かごかき(今のタクシー運転手)などが、旅行者の足の疲れ具合を見...
 「あ」で始まることわざ
「あ」で始まることわざ「足下から鳥が立つ」の意味(語源由来・類義語・英語) 【ことわざ】 足下から鳥が立つ 【読み方】 あしもとからとりがたつ 【意味】 ①身近な所で意外なことが起こる。 ②急に思いたってあわただしく物事を始める。 【語源・由...
 「あ」で始まることわざ
「あ」で始まることわざ「朝には富児の門を扣き、暮には肥馬の塵に随う」の意味(語源由来・英語訳) 【ことわざ】 朝には富児の門を扣き、暮には肥馬の塵に随う 【読み方】 あしたにはふじのもんをたたき、ゆうべにはひばのちりにしたがう 【意味】 常に...
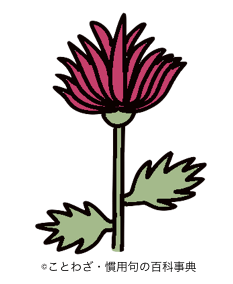 「あ」で始まることわざ
「あ」で始まることわざ「薊の花も一盛り」の意味(語源由来・類義語・英語) 【ことわざ】 薊の花も一盛り 【読み方】 あざみのはなもひとさかり 【意味】 醜い女性でも、年頃になれば、魅力が出るものであるということ。 【語源・由来】 見た目にあま...
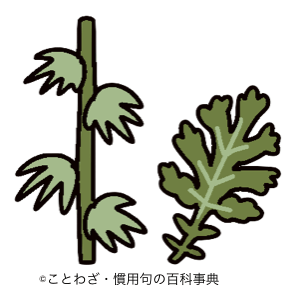 「あ」で始まることわざ
「あ」で始まることわざ「麻の中の蓬」の意味(語源由来・出典・類義語・対義語・英語訳) 【ことわざ】 麻の中の蓬 【読み方】 あさのなかのよもぎ 【意味】 善良な人と交われば、その感化を受けて善人になる。 【語源・由来】 曲がりやすい蓬も、まっ...
 「あ」で始まることわざ
「あ」で始まることわざ「浅瀬に仇波」の意味(語源由来・類義語・対義語・英語) 【ことわざ】 浅瀬に仇波 【読み方】 あさせにあだなみ 【意味】 思慮の浅い者ほどよくしゃべり、あれこれとうるさく騒ぎ立てるということ。 【語源・由来】 川の浅瀬に...
 「あ」で始まることわざ
「あ」で始まることわざ「朝顔の花一時」の意味(語源由来・類義語・英語訳) 【ことわざ】 朝顔の花一時 【読み方】 あさがおのはなひととき 【意味】 物事の盛りの時期がきわめて短く、はかないことのたとえ。 【語源・由来】 朝顔の花が朝咲いて、昼...
 「あ」で始まることわざ
「あ」で始まることわざ「浅い川も深く渡れ」の意味(語源由来・類義語・対義語・英語) 【ことわざ】 浅い川も深く渡れ 【読み方】 あさいかわもふかくわたれ 【意味】 物事の大きさや相手の強さに関わらず、何事も慎重に取り組むべきだというたとえ。 ...
 「あ」で始まることわざ
「あ」で始まることわざ「阿漕が浦に引く網」の意味(語源由来・英語訳) 【ことわざ】 阿漕が浦に引く網 【読み方】 あこぎがうらにひくあみ 【意味】 隠し事もたび重なると広く知られるということ。 【語源・由来】 古今和歌六帖の歌から。阿漕が浦は...
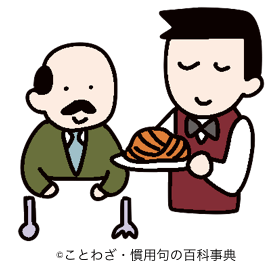 「あ」で始まることわざ
「あ」で始まることわざ「上げ膳据え膳」の意味(語源由来・英語訳) 【ことわざ】 上げ膳据え膳 【読み方】 あげぜんすえぜん 【意味】 全て人にやってもらい、自分ではなにもしないことのたとえ。 また、非常に優遇すること。 【語源・由来】 食膳(...
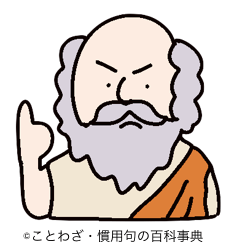 「あ」で始まることわざ
「あ」で始まることわざ「悪法もまた法なり」の意味(語源由来・英語訳) 【ことわざ】 悪法もまた法なり 【読み方】 あくほうもまたほうなり 【意味】 悪法であっても、法である限り守るべきだということ 【語源・由来】 古代ギリシャの哲学者ソクラテ...
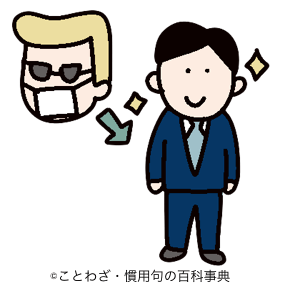 「あ」で始まることわざ
「あ」で始まることわざ「悪に強ければ善にも強し」の意味(語源由来・類義語・対義語・英語) 【ことわざ】 悪に強ければ善にも強し 【読み方】 あくにつよければぜんにもつよし 【意味】 大悪人がいったん改心すると、非常な善人となるものだ。 【語源...
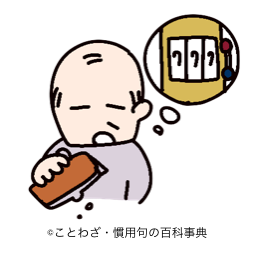 「あ」で始まることわざ
「あ」で始まることわざ【ことわざ】 悪銭身につかず 【読み方】 あくせんみにつかず 【意味】 悪いことをして手にいれたお金は、無駄に使ってしまい残らないというたとえ。 【類義語】 ・あぶく銭は身に付かず 【対義語】 ・正直の儲けは身につく 「...
 「あ」で始まることわざ
「あ」で始まることわざ「悪女の深情け」の意味(語源由来・英語訳) 【ことわざ】 悪女の深情け 【読み方】 あくじょのふかなさけ 【意味】 醜い女のほうが美人に比べて情が深いということ。転じて、男女の間に限らず、ありがた迷惑であるという意にも用...
 「あ」で始まることわざ
「あ」で始まることわざ「悪妻は百年の不作」の意味(語源由来・類義語・英語訳) 【ことわざ】 悪妻は百年の不作 【読み方】 あくさいはひゃくねんのふさく 【意味】 悪い妻を持つと、その悪影響は自分の一生だけでなく、子供や孫の代まで続くということ...
 「あ」で始まることわざ
「あ」で始まることわざ「諦めは心の養生」の意味(語源由来・英語) 【ことわざ】 諦めは心の養生 【読み方】 あきらめはこころのようじょう 【意味】 あきらめることは精神衛生上よいということ。 【語源・由来】 失敗や不運をいつまでも悔やまず、あ...
 「あ」で始まることわざ
「あ」で始まることわざ「秋の鹿は笛に寄る」の意味(語源由来・類義語・英語訳) 【ことわざ】 秋の鹿は笛に寄る 【読み方】 あきのしかはふえによる 【意味】 人が恋に身を滅ぼしたり、危険な状態に自ら身を投じることのたとえ。 【語源・由来】 秋の...
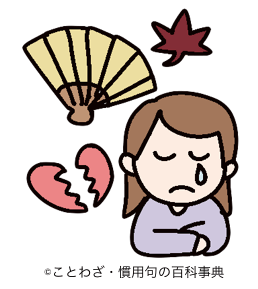 「あ」で始まることわざ
「あ」で始まることわざ「秋の扇」の意味(出典・故事・類義語・英語) 【ことわざ】 秋の扇 【読み方】 あきのおうぎ 【意味】 男の愛情を失った女のたとえ。 【出典】 文選もんぜん 【故事】 漢の宮女、班婕妤 (はんしょうよ) が君寵を失った自...
 「あ」で始まることわざ
「あ」で始まることわざ【ことわざ】 秋茄子は嫁に食わすな 【読み方】 あきなすはよめにくわすな 【意味】 秋にできるなすは美味しいから嫁には食べさせるなという、姑しゅうとめから嫁への意地悪なことば。または、茄子なすは体を冷やすので嫁には食べさ...
 「あ」で始まることわざ
「あ」で始まることわざ「商いは牛の涎」の意味(語源由来・類義語・英語) 【ことわざ】 商いは牛の涎 【読み方】 あきないはうしのよだれ 【意味】 商売は辛抱強く気長にコツコツと続けることが大切だというたとえ。 【語源・由来】 牛の涎は、長く細...
 「あ」で始まることわざ
「あ」で始まることわざ「空き樽は音が高い」の意味(語源由来・類義語・対義語・英語) 【ことわざ】 空き樽は音が高い 【読み方】 あきだるはおとがたかい 【意味】 浅はかで中身のない人ほど、良く知りもしないのに得意そうによくしゃべるということ。...
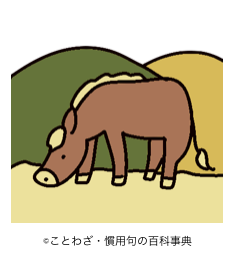 「あ」で始まることわざ
「あ」で始まることわざ「秋高く馬肥ゆ」の意味(語源由来・類義語・英語訳) 【ことわざ】 秋高く馬肥ゆ 【読み方】 あきたかくうまこゆ 【意味】 空が澄みわたって、高く晴れ上がった秋の日のたとえ。気温も高すぎず低すぎず過ごしやすく、食べ物の収穫...
 「あ」で始まることわざ
「あ」で始まることわざ【ことわざ】 仰いで天に愧じず 【読み方】 あおいでてんにはじず 【意味】 自分自身の行いにも心にも、なにもやましいことがないというたとえ。 やましいことがなにもなければ、天を見ても神に対しても恥ずべきことはないというこ...
 「あ」で始まることわざ
「あ」で始まることわざ【ことわざ】 敢えて後れたるに非ず、馬進まざればなり 【読み方】 あえておくれたるにあらず、うますすまざればなり 【意味】 自分の手柄を自慢したり誇らずに、へりくだることのたとえ。 【由来】 昔、中国の魯という国に、大夫...
 「あ」で始まることわざ
「あ」で始まることわざ【ことわざ】 相手のない喧嘩はできぬ 【読み方】 あいてのないけんかはできぬ 【意味】 喧嘩をしかけられても相手になるなという戒め。 【由来】 相手がいなければけんかはできないことから。 【類義】 ・相手なければ訴訟なし...
 「あ」で始まることわざ
「あ」で始まることわざ【ことわざ】 相手変われど主変わらず 【読み方】 あいてかわれどぬしかわらず 【意味】 相手は次々変わっているにも関わらず、相手をする側はなにも変わらないというたとえ。 【由来】 状況は変化しているのに、本人は変わらずに...
 「あ」で始まることわざ
「あ」で始まることわざ【ことわざ】 開いた口へ牡丹餅 【読み方】 あいたくちへぼたもち 【意味】 口を開けたところに牡丹餅が落ちてくるように思いがけない幸運がめぐってくること。努力をしていないにも関わらず、幸運に恵まれることのたとえ。 【類義...
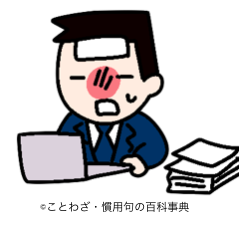 「よ」で始まることわざ
「よ」で始まることわざ「弱り目に祟り目」の意味(語源由来・類義語・英語訳) 【ことわざ】 弱り目に祟り目 【読み方】 よわりめにたたりめ 【意味】 困っているときに、さらに困ったことが重なっておきること。 【語源由来】 困っているときに、さら...
 「よ」で始まることわざ
「よ」で始まることわざ「寄らば大樹の陰」の意味(語源由来・類義語・英語訳) 【ことわざ】 寄らば大樹の陰 【読み方】 よらばたいじゅのかげ 【意味】 頼るならば、権力のあるものに頼ったほうがよいというたとえ。 大きくて力のあるものに頼るほうが...
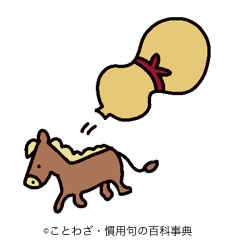 「ひ」で始まることわざ
「ひ」で始まることわざ【ことわざ】 瓢箪から駒が出る 【読み方】 ひょうたんからこまがでる 【意味】 思いがけないようなことがおこること。また、冗談のつもりだったことが、現実に起こること。 【語源・由来】 「駒」とは、馬のこと。瓢箪の狭い口か...
 「ひ」で始まることわざ
「ひ」で始まることわざ【ことわざ】 百聞は一見に如かず 【読み方】 ひゃくぶんはいっけんにしかず 【意味】 物事は、耳で何度も聞くより、一度実際に自分の目で見るほうがたしかだということ。 【故事】 中国の「漢書かんじょ趙充国伝ちょうじゅうこく...
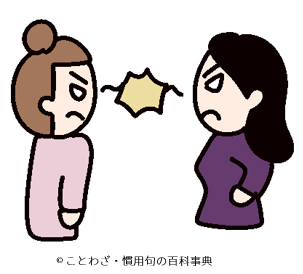 「ひ」で始まることわざ
「ひ」で始まることわざ「火蓋を切る」の意味(語源由来・類義語・英語訳) 【ことわざ】 火蓋を切る 【読み方】 ひぶたをきる 【意味】 競争や戦いを始めることのたとえ。 自分が始める場合だけでなく、相手によって始められる場合にも使う。 【語源・...
 「ひ」で始まることわざ
「ひ」で始まることわざ【ことわざ】 火の無い所に煙は立たぬ 【読み方】 ひのないところにけむりはたたぬ 【意味】 原因のない所に噂は立たないというたとえ。 【語源・由来】 煙が立つところには、必ず火があるということから。 【類義語】 ・ない名...
 「ひ」で始まることわざ
「ひ」で始まることわざ「火に油を注ぐ」の意味(語源由来・類義語) 【ことわざ】 火に油を注ぐ 【読み方】 ひにあぶらをそそぐ 【意味】 勢いの盛んなものがさらに勢いづくことのたとえ。 【語源由来】 燃えている火に油を注ぐと、さらに燃えることが...
 「ひ」で始まることわざ
「ひ」で始まることわざ「人を見て法を説け」の意味(語源由来・類義語・英語訳) 【ことわざ】 人を見て法を説け 【読み方】 ひとをみてほうをとけ 【意味】 相手の性格や性質をよく見極めて、ふさわしい方法で言い聞かせる必要があるというたとえ。 【...
 「ひ」で始まることわざ
「ひ」で始まることわざ「人を見たら泥棒と思え」の意味(語源由来・類義語・対義語・英語訳) 【ことわざ】 人を見たら泥棒と思え 【読み方】 ひとをみたらどろぼうとおもえ 【意味】 他人は信用できないものなので、人は軽々しく信用しないで疑ってかか...
 「ひ」で始まることわざ
「ひ」で始まることわざ「人は見かけによらぬもの」の意味(語源由来・類義語) 【ことわざ】 人は見かけによらぬもの 【読み方】 ひとはみかけによらぬもの 【意味】 人の本当の性格や能力は、見た目の印象や外見では判断できないことのたとえ。 外見と...
 「ひ」で始まることわざ
「ひ」で始まることわざ「人はパンのみにて生くるものに非ず」の意味(語源由来・英語訳) 【ことわざ】 人はパンのみにて生くるものに非ず 【読み方】 ひとはぱんのみにていくるものにあらず 【意味】 人は物質的な満足を得るだけではなく、精神的な支え...
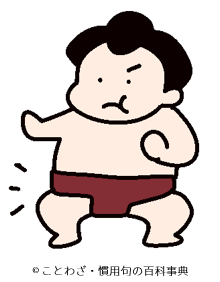 「ひ」で始まることわざ
「ひ」で始まることわざ「人の褌で相撲を取る」の意味(語源由来・類義語・英語訳) 【ことわざ】 人の褌で相撲を取る 【読み方】 ひとのふんどしですもうをとる 【意味】 他人のものを使って、自分の利益を得ることのたとえ。 【語源・由来】 褌は、お...
 「ひ」で始まることわざ
「ひ」で始まることわざ【ことわざ】 人の振り見て我が振り直せ 【読み方】 ひとのふりみてわがふりなおせ 【意味】 他人の行いの善し悪しを見て参考にすることで、自分の行いを見直し欠点を改めるように心がけると良いというたとえ。 【語源・由来】 自...
 「ひ」で始まることわざ
「ひ」で始まることわざ「人の口に戸は立てられぬ」の意味(語源由来・類義語・英語訳) 【ことわざ】 人の口に戸は立てられぬ 【読み方】 ひとのくちにとはたてられぬ 【意味】 世間の噂は防ぎきれない。 【語源由来】 家の戸と違い、人の口に戸を立て...
 「ひ」で始まることわざ
「ひ」で始まることわざ【ことわざ】 人の噂も七十五日 【読み方】 ひとのうわさもしちじゅうごにち 【意味】 人の噂は長く続くものではなく、七十五日もすれば忘れられてしまうものだということ。 【語源・由来】 噂を立てられても、人は飽きっぽいもの...
 「ひ」で始まることわざ
「ひ」で始まることわざ「人を謗るは鴨の味」の意味(語源由来・類義語・英語訳) 【ことわざ】 人を謗るは鴨の味 【読み方】 ひとをそしるはかものあじ 【意味】 他人の欠点を見つけて、あれこれ言って貶すことは気分の良いものだというたとえ。 【語源...
 「ひ」で始まることわざ
「ひ」で始まることわざ「ひだるい時にまずい物なし」の意味(語源由来・類義語・英語訳) 【ことわざ】 ひだるい時にまずい物なし 【読み方】 ひだるいときにまずいものなし 【意味】 空腹の時には、まずいと思う食べ物はなく、なんでもおいしく食べられ...
 「ひ」で始まることわざ
「ひ」で始まることわざ「肘鉄砲を食わせる」の意味(語源由来・英語訳) 【ことわざ】 肘鉄砲を食わせる 【読み方】 ひじでっぽうをくわせる 【意味】 誘った相手から拒絶されることのたとえ。 【語源・由来】 相手にひじでどんとつつかれて、押しのけ...
 「ひ」で始まることわざ
「ひ」で始まることわざ「引かれ者の小唄」の意味(語源由来・類義語・英語訳) 【ことわざ】 引かれ者の小唄 【読み方】 ひかれもののこうた 【意味】 負けたり、失敗したにも関わらず、負け惜しみや強がりをいうことのたとえ。 追い詰められて、どうに...
 「ひ」で始まることわざ
「ひ」で始まることわざ「贔屓の引き倒し」の意味(語源由来・類義語・英語訳) 【ことわざ】 贔屓の引き倒し 【読み方】 ひいきのひきたおし 【意味】 贔屓にしすぎたことで、その人を不利にしてしまうことのたとえ。 【語源・由来】 気に入っている人...
 「は」で始まることわざ
「は」で始まることわざ「針の穴から天を覗く」の意味(語源由来・類義語・英語訳) 【ことわざ】 針の穴から天を覗く 【読み方】 はりのあなからてんをのぞく 【意味】 少しの知識しかないにも関わらず、大きな問題を解決しようとすることのたとえ。 【...
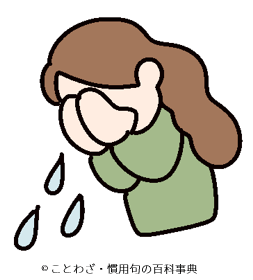 「は」で始まることわざ
「は」で始まることわざ「腸がちぎれる」の意味(語源由来・類義語・英語訳) 【ことわざ】 腸がちぎれる 【読み方】 はらわたがちぎれる 【意味】 耐えきれない、耐えがたい悲しみのたとえ。 【語源・由来】 昔、中国で猿の子供を捕らえて舟に乗せたと...
 「は」で始まることわざ
「は」で始まることわざ「腹八分目に医者いらず」の意味(語源由来・類義語・英語訳) 【ことわざ】 腹八分目に医者いらず 【読み方】 はらはちぶめにいしゃいらず 【意味】 満腹になるまで食べないで、八分目にしておくことで健康でい続けることができる...
 「は」で始まることわざ
「は」で始まることわざ「腹の虫が治まらない」の意味(語源由来・類義語・英語訳) 【ことわざ】 腹の虫が治まらない 【読み方】 はらのむしがおさまらない 【意味】 怒りが抑えきれないことのたとえ。 腹が立って、しゃくにさわり我慢できないこと。 ...
 「は」で始まることわざ
「は」で始まることわざ「流行り物は廃り物」の意味(語源由来・類義語・英語訳) 【ことわざ】 流行物は廃り物 【読み方】 はやりものはすたりもの 【意味】 流行というものは、一時的なことですぐに廃れてしまうということのたとえ。 流行といっても、...
 「は」で始まることわざ
「は」で始まることわざ【ことわざ】 花より団子 【読み方】 はなよりだんご 【意味】 花見などという風流なことよりも、食べるほうが大事というたとえ。外観よりも実質を、虚栄より実益を重んじること。また、風流を解さないことのたとえにも用いる。 【...
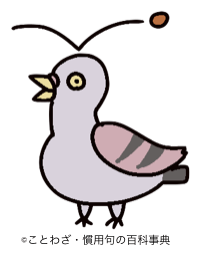 「は」で始まることわざ
「は」で始まることわざ「鳩が豆鉄砲を食ったよう」の意味(語源由来・類義語・英語訳) 【ことわざ】 鳩が豆鉄砲を食ったよう 【読み方】 はとがまめでっぽうをくったよう 【意味】 突然の出来事に驚いて、あっけにとられてきょとんとしている様子のたと...
 「は」で始まることわざ
「は」で始まることわざ「這っても黒豆」の意味(語源由来・類義語・英語訳) 【ことわざ】 這っても黒豆 【読み方】 はってもくろまめ 【意味】 自分が間違っていることが、はっきりとわかっていても、間違っていないと言い張って譲らないことのたとえ。...
 「は」で始まることわざ
「は」で始まることわざ「裸で物を落とす例なし」の意味(語源由来・類義語・英語訳) 【ことわざ】 裸で物を落とす例なし 【読み方】 はだかでものをおとすためしなし 【意味】 なにも持っていなければ、損をする恐れがなく、気楽であるというたとえ。 ...
 「は」で始まることわざ
「は」で始まることわざ「始めよければ終わりよし」の意味(語源由来・類義語・対義語・英語訳) 【ことわざ】 始めよければ終わりよし 【読み方】 はじめよければおわりよし 【意味】 物事は始めがうまくいけば、全て順調に進み、最後に良い結果を得るこ...
 「は」で始まることわざ
「は」で始まることわざ「馬脚を現す」の意味(語源由来・類義語・英語訳) 【ことわざ】 馬脚を現す 【読み方】 ばきゃくをあらわす 【意味】 包み隠していたことがあらわれる。化けの皮が剥がれる。ぼろを出す。 【語源・由来】 元曲(陳州糶米、第三...
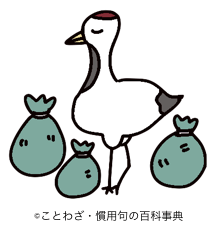 「は」で始まることわざ
「は」で始まることわざ「掃き溜めに鶴」の意味(語源由来・類義語・英語訳) 【ことわざ】 掃き溜めに鶴 【読み方】 はきだめにつる 【意味】 その場に似合わないような美しい人や優れた人がいるたとえ。 【語源・由来】 むさくるしいごみ捨て場に、鶴...
 「は」で始まることわざ
「は」で始まることわざ「馬鹿の一つ覚え」の意味(語源由来・類義語・英語訳) 【ことわざ】 馬鹿の一つ覚え 【読み方】 ばかのひとつおぼえ 【意味】 習い覚えたひとつのことばかりをいう人を嘲っていうことのたとえ。 また、それしかないようにくり返...
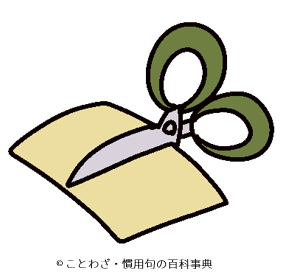 「は」で始まることわざ
「は」で始まることわざ「馬鹿と鋏は使いよう」の意味(語源由来・類義語・英語訳) 【ことわざ】 馬鹿と鋏は使いよう 【読み方】 ばかとはさみはつかいよう 【意味】 愚かな人でも、使い方によっては役に立つというたとえ。 また、人には能力に応じた使...
 「は」で始まることわざ
「は」で始まることわざ「馬鹿があればこそ利口が引き立つ」の意味(語源由来・類義語・英語訳) 【ことわざ】 馬鹿があればこそ利口が引き立つ 【読み方】 ばかがあればこそりこうがひきたつ 【意味】 世の中は、利口な人や愚かな人など、様々な人がいて...
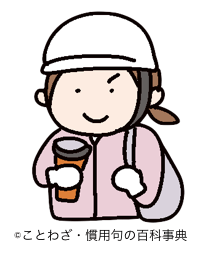 「そ」で始まることわざ
「そ」で始まることわざ「備えあれば憂いなし」の意味(語源由来・出典・類義語・対義語) 【ことわざ】 備えあれば憂いなし 【読み方】 そなえあればうれいなし 【意味】 平生から事に備えて準備をしておけば、何の心配もなくなるということ。 【語源・...
 「そ」で始まることわざ
「そ」で始まることわざ【ことわざ】 袖振り合うも多生の縁 【読み方】 そでふりあうもたしょうのえん 【意味】 人とのちょっとしたかかわりも、決して偶然ではなく、深い縁があってのことだから、人には親切にしなさいという教え。 【語源・由来】 すれ...
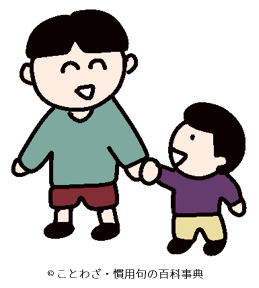 「そ」で始まることわざ
「そ」で始まることわざ「総領の甚六」の意味(語源由来・英語訳) 【ことわざ】 総領の甚六 【読み方】 そうりょうのじんろく 【意味】 長男や長女は、大事に育てられたので、弟妹よりもお人好しでおろかだ。 【語源・由来】 「江戸いろはかるた」のひ...
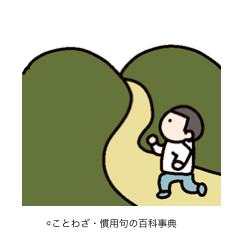 「せ」で始まることわざ
「せ」で始まることわざ「千里の道も一歩より起こる」の意味(出典・類義語) 【ことわざ】 千里の道も一歩より起こる 【読み方】 せんりのみちもいっぽよりおこる 【意味】 どんなに大きな仕事も、まずは手近なことの実行から始まるというたとえ。なにご...
 「せ」で始まることわざ
「せ」で始まることわざ【ことわざ】 前門の虎後門の狼 【読み方】 ぜんもんのとらこうもんのおおかみ 【意味】 困ったことや、災難から逃れることができたと思ったら、また困ったことや災難にあうというたとえ。 【語源・由来】 中国の「評史(ひょうし...
 「せ」で始まることわざ
「せ」で始まることわざ【ことわざ】 善は急げ 【読み方】 ぜんはいそげ 【意味】 よいことを思いついたら、すぐにやろうということ。 【類義語】 ・思い立ったが吉日きちじつ ・先んずれば人を制す ・先手必勝 【対義語】 ・急がば回れ ・急いては...
 「せ」で始まることわざ
「せ」で始まることわざ「船頭多くして船山に上る」とは 読み方・意味 ことわざ:船頭多くして船山に上る 読み方:せんどうおおくしてふねやまにのぼる 意味:指図する人が多すぎると混乱して、ものごとがうまく進まず、とんでもない結果になりかねないとい...
 「せ」で始まることわざ
「せ」で始まることわざ「背に腹は代えられぬ」とは 読み方・意味 ことわざ:背に腹は代えられぬ 読み方:せにはらはかえられぬ 意味:切迫した状況では大切なものを守るために、どうしてもなにかを犠牲にしなければならない。 「背に腹は代...
 「せ」で始まることわざ
「せ」で始まることわざ【ことわざ】 急いては事を仕損じる 【読み方】 せいてはことをしそんじる 【意味】 何事もあわててやると失敗することが多いので、落ち着いて行動しようということ。 【類義語】 ・急がば回れ ・急ぐことはゆるりとせよ ・走れ...
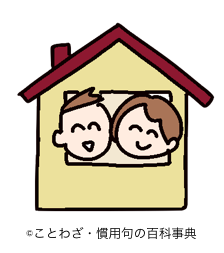 「す」で始まることわざ
「す」で始まることわざ【ことわざ】 住めば都 【読み方】 すめばみやこ 【意味】 心の持ちようで、どんなに不便な土地でも都のように快適に思えることのたとえ。長く住むと、どんなところでも良く思えてくることのたとえ。 【類義語】 ・地獄も住処すみ...
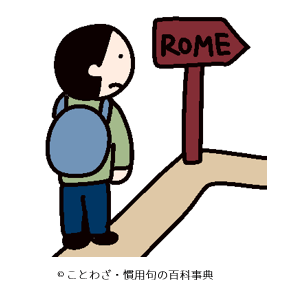 「す」で始まることわざ
「す」で始まることわざ「全ての道はローマに通ず」の意味(語源由来・類義語・英語) 【ことわざ】 全ての道はローマに通ず 【読み方】 すべてのみちはろーまにつうず 【意味】 多くのものが、中心に向かって集中しているということ。 あらゆることは、...
 「す」で始まることわざ
「す」で始まることわざ「捨てる神あれば拾う神あり」の意味(語源由来・類義語) 【ことわざ】 捨てる神あれば拾う神あり 【読み方】 すてるかみあればひろうかみあり 【意味】 一方で見捨てる人がいるかと思うと、他方で救ってくれる人がいる。世間は広...
 「す」で始まることわざ
「す」で始まることわざ「過ぎたるは猶及ばざるが如し」とは 読み方・意味 ことわざ:過ぎたるは猶及ばざるが如し 読み方:すぎたるはなおおよばざるがごとし 意味:何事もやりすぎるのは、足りないのと同じくらいよくないということ。 「過...
 「す」で始まることわざ
「す」で始まることわざ「雀百まで踊り忘れず」とは 読み方・意味 ことわざ:雀百まで踊り忘れず 読み方:すずめひゃくまでおどりわすれず 意味:雀が死ぬまで飛び跳ねる癖が抜けないように、幼いころに身につけた習慣は、年を取っても変わらないことのたと...
 「す」で始まることわざ
「す」で始まることわざ「好きこそ物の上手なれ」とは 読み方・意味 ことわざ:好きこそ物の上手なれ 読み方:すきこそもののじょうずなれ 意味:なにかを好きで熱心に取り組むと、自然とそのことが上達するということ。 「好きこそ物の上手...
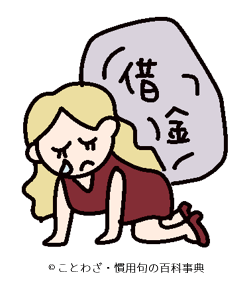 「す」で始まることわざ
「す」で始まることわざ「粋が身を食う」の意味(語源由来・類義語・対義語・英語訳) 【ことわざ】 粋が身を食う 【読み方】 すいがみをくう 【意味】 花柳界や芸人社会の事情に通じて粋がることは、遂にはその道に溺れて身を滅ぼすことになる。 【語源...
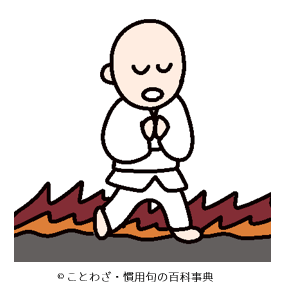 「し」で始まることわざ
「し」で始まることわざ「心頭を滅却すれば火もまた涼し」の意味(語源由来・類義語・英語訳) 【ことわざ】 心頭を滅却すれば火もまた涼し 【読み方】 しんとうをめっきゃくすればひもまたすずし 【意味】 心から雑念(ざつねん)を払い無念無想(むねん...
 「し」で始まることわざ
「し」で始まることわざ「吝ん坊の柿の種」の意味(語源由来・類義語・英語訳) 【ことわざ】 吝ん坊の柿の種 【読み方】 しわんぼうのかきのたね 【意味】 けちな人は、どんなつまらないものや、くだらないものでも執着(しゅうちゃく)して惜しがって手...
 「し」で始まることわざ
「し」で始まることわざ「知らぬが仏」とは 読み方・意味 ことわざ:知らぬが仏 読み方:しらぬがほとけ 意味:不愉快な事実を知らないうちは、仏のようにおだやかな気持ちでいられるということ。 「知らぬが仏(しらぬがほとけ)」とは、「...
 「し」で始まることわざ
「し」で始まることわざ【ことわざ】 初心忘るべからず 【読み方】 しょしんわするべからず 【意味】 物事を始めたばかりの頃の、真剣で謙虚な気持ちを忘れるなというたとえ。何事も最初に始めた頃の気持ちを忘れずに、すなおな気持ちで取り組むべきだとい...
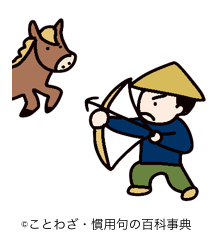 「し」で始まることわざ
「し」で始まることわざ【ことわざ】 将を射んと欲すれば先ず馬を射よ 【読み方】 しょうをいんとほっすればまずうまをいよ 【意味】 大きな目標を達成するためには、周辺のものから手にいれることが先決だというたとえ。相手を説得するためには、相手が信...
 「し」で始まることわざ
「し」で始まることわざ【ことわざ】 上手の手から水が漏れる 【読み方】 じょうずのてからみずがもれる 【意味】 名人でも、失敗をすることがあるということ。 【語源・由来】 「上手」とは、そのことに巧みな人という意味に由来。 江戸時代に、囲碁・...
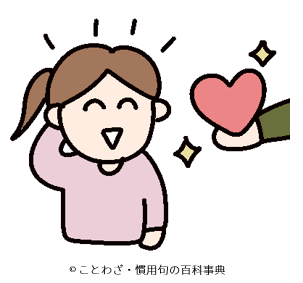 「し」で始まることわざ
「し」で始まることわざ「正直は一生の宝」の意味(語源由来・類義語・対義語・英語訳) 【ことわざ】 正直は一生の宝 【読み方】 しょうじきはいっしょうのたから 【意味】 正直だということは、一生を通して守らなければならないような、大切なものであ...
 「し」で始まることわざ
「し」で始まることわざ【ことわざ】 朱に交われば赤くなる 【読み方】 しゅにまじわればあかくなる 【意味】 人は環境に支配されやすいので、付き合う友達によって良くも悪くもなるということ。 【出典】 中国晋代の「太子少傅箴たいししょうふしん」に...
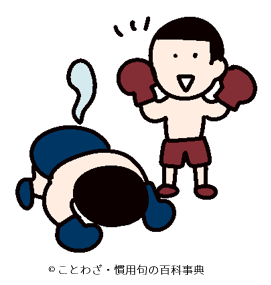 「し」で始まることわざ
「し」で始まることわざ「柔能く剛を制す」の意味(語源由来・出典・類義語・対義語・英語訳) 【ことわざ】 柔能く剛を制す 【読み方】 じゅうよくごうをせいす 【意味】 柔軟なものが、そのしなやかさでかたいものの矛先をそらし、結局は勝つことになる...
 「し」で始まることわざ
「し」で始まることわざ「蛇の道は蛇」の意味(語源由来・類義語・英語訳) 【ことわざ】 蛇の道は蛇 【読み方】 じゃのみちはへび 【意味】 同類のことは、同類がよく知っている。 その道の人間がその社会のことに、よく通じているというたとえ。 【語...
 「し」で始まることわざ
「し」で始まることわざ「釈迦に説法」とは 読み方・意味 ことわざ:釈迦に説法 読み方:しゃかにせっぽう 意味:仏教の開祖である釈迦に仏教を説くように、未熟な者がその道の専門家に向かって一人前の口を聞くことのたとえ。 「釈迦に説法...
 「し」で始まることわざ
「し」で始まることわざ「自慢は知恵の行き止まり」の意味(語源由来・類義語・英語訳) 【ことわざ】 自慢は知恵の行き止まり 【読み方】 じまんはちえのいきどまり 【意味】 自慢をするようになってしまうと、もはや進歩も向上もしなくなってしまうとい...
 「し」で始まることわざ
「し」で始まることわざ【ことわざ】 失敗は成功の基 【読み方】 しっぱいはせいこうのもと 【意味】 失敗することで、その原因を考えて反省し改善することで、同じ失敗をくり返さないように心がければ、次の成功をもたらす原動力になるということ。 【語...
 「し」で始まることわざ
「し」で始まることわざ「親しき仲にも礼儀あり」とは 読み方・意味 ことわざ:親しき仲にも礼儀あり 読み方:したしきなかにもれいぎあり 意味:親しい間柄であっても、最低限の礼儀は守らなくてはならないということ。 「親しき仲にも礼儀...
 「し」で始まることわざ
「し」で始まることわざ「地震雷火事親父」とは 読み方・意味 ことわざ:地震雷火事親父 読み方:じしんかみなりかじおやじ 意味:世の中でこわいもの、どうにもかなわない恐ろしいものを並べたもの。 「地震雷火事親父」とは? この言葉は...
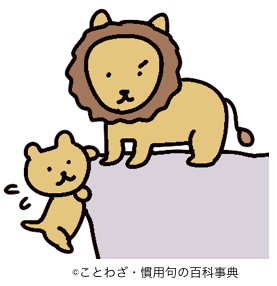 「し」で始まることわざ
「し」で始まることわざ「獅子の子落とし」の意味(出典・語源由来・類義語・英語訳) 【ことわざ】 獅子の子落とし 【読み方】 ししのこおとし 【意味】 自分の子供にわざと苦しいことをさせて、その能力を試し鍛え、立派な人間に育てようとすることのた...
 「し」で始まることわざ
「し」で始まることわざ【ことわざ】 地獄の沙汰も金次第 【読み方】 じごくのさたもかねしだい 【意味】 この世のことはすべて、お金さえあれば解決できるという意味。 【語源・由来】 この世の裁きよりも厳しいとされる、地獄の裁きでさえも、お金を出...
 「し」で始まることわざ
「し」で始まることわざ「地獄で仏に会ったよう」の意味(語源由来・類義語・英語訳) 【ことわざ】 地獄で仏に会ったよう 【読み方】 じごくでほとけにあったよう 【意味】 ひどく困っているときや、危ないときに、思いがけない助けに会って喜ぶことのた...
 「し」で始まることわざ
「し」で始まることわざ「鹿の角を蜂が刺す」の意味(語源由来・類義語・英語訳) 【ことわざ】 鹿の角を蜂が刺す 【読み方】 しかのつのをはちがさす 【意味】 なんにも感じないことのたとえ。 痛くもかゆくもないというたとえ。 手ごたえがないことの...
 「さ」で始まることわざ
「さ」で始まることわざ「三遍回って煙草にしょ」の意味(語源由来・類義語・英語訳) 【ことわざ】 三遍回って煙草にしょ 【読み方】 さんべんまわってたばこにしょ 【意味】 休むことを急いであと回しにしないで、念には念を入れて落ち度のないように気...
 「さ」で始まることわざ
「さ」で始まることわざ「三人寄れば文殊の知恵」とは 読み方・意味 ことわざ:三人寄れば文殊の知恵 読み方:さんにんよればもんじゅのちえ 意味:凡人でも3人集まれば、驚くような知恵や解決策が見つかることがある。 「三人寄れば文殊の...
 「さ」で始まることわざ
「さ」で始まることわざ【ことわざ】 山椒は小粒でもぴりりと辛い 【読み方】 さんしょうはこつぶでもぴりりとからい 【意味】 からだは小さいけれど、意志が強く、鋭い気性や優れた才能があり、非常に優秀で侮ることのできない人のたとえ。 【語源・由来...
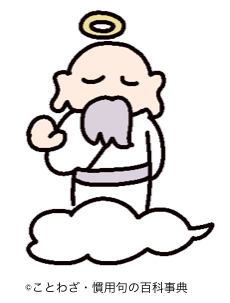 「さ」で始まることわざ
「さ」で始まることわざ【ことわざ】 触らぬ神に祟りなし 【読み方】 さわらぬかみにたたりなし 【意味】 よけいな物事に関係しなければ、わざわざ禍を招くこともないということ。 【語源・由来】 神と関係さえしなければ、祟りをこうむるはずもないとい...
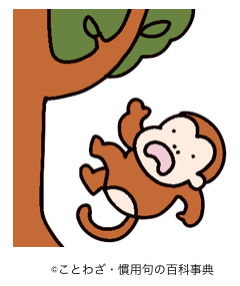 「さ」で始まることわざ
「さ」で始まることわざ「猿も木から落ちる」とは 読み方・意味 ことわざ:猿も木から落ちる 読み方:さるもきからおちる 意味:どんなにすぐれた名人でも、ときには失敗することもあるというたとえ。 「猿も木から落ちる」は、「どんな名人...
 「さ」で始まることわざ
「さ」で始まることわざ「猿の尻笑い」の意味(語源由来・類義語・英文) 【ことわざ】 猿の尻笑い 【読み方】 さるのしりわらい 【意味】 自分の欠点を省みず他人を笑うこと。 【語源・由来】 猿が自分の赤い尻に気付かないことから。 【類義語】 ・...
 「さ」で始まることわざ
「さ」で始まることわざ「匙を投げる」の意味(語源由来・類義語・英語訳) 【ことわざ】 匙を投げる 【読み方】 さじをなげる 【意味】 もうだめだと思って、見切りをつけて手を引くこと。医者が病人の治療をあきらめるほと、病状が悪化して、手の施しよ...
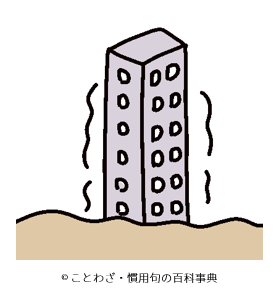 「さ」で始まることわざ
「さ」で始まることわざ「砂上の楼閣」の意味(語源由来・類義語・英語訳) 【ことわざ】 砂上の楼閣 【読み方】 さじょうのろうかく 【意味】 高層(こうそう)の立派な建物が砂の上に建てられているが、砂の上は柔らかく基礎が不安定で、長い間建物を維...
 「さ」で始まることわざ
「さ」で始まることわざ「先んずれば人を制す」の意味(出典・故事・類義語・対義語・英語訳) 【ことわざ】 先んずれば人を制す 【読み方】 さきんずればひとをせいす 【意味】 他人より先に事を行えば、有利な立場に立つことができるということ。 【出...