【石に齧りついても】の意味と使い方や例文(慣用句)
「石に齧りついても」の意味(語源由来) 【慣用句】 石に齧りついても 【読み方】 いしにかじりついても 【意味】 どんなに苦しくてもがまんして。 【語源由来】 目的達成のためには、石に齧りつくようないかなる苦難にも立ち向...
 「い」で始まる慣用句
「い」で始まる慣用句「石に齧りついても」の意味(語源由来) 【慣用句】 石に齧りついても 【読み方】 いしにかじりついても 【意味】 どんなに苦しくてもがまんして。 【語源由来】 目的達成のためには、石に齧りつくようないかなる苦難にも立ち向...
 「い」で始まることわざ
「い」で始まることわざ「石が浮かんで木の葉が沈む」の意味(語源由来・類義語) 【ことわざ】 石が浮かんで木の葉が沈む 【読み方】 いしがうかんでこのはがしずむ 【意味】 重い石が水に浮かんで、軽い木の葉が水に沈むように、物事のありさまが逆にな...
 「い」で始まる慣用句
「い」で始まる慣用句「息を吹き返す」の意味(語源由来) 【慣用句】 息を吹き返す 【読み方】 いきをふきかえす 【意味】 駄目だと思っていたものが、また勢いづくこと。 【語源由来】 生き返るという意味から。 「息を吹き返す」の解説 「息を吹...
 「い」で始まる慣用句
「い」で始まる慣用句「息を引き取る」の意味(語源由来) 【慣用句】 息を引き取る 【読み方】 いきをひきとる 【意味】 息が絶える。死ぬこと。 【語源由来】 仏教で、残された者たちが、亡くなった人の息を引き継ぐこと、命をつなぐという意味から...
 「い」で始まる慣用句
「い」で始まる慣用句「息を弾ませる」の意味 【慣用句】 息を弾ませる 【読み方】 いきをはずませる 【意味】 運動したり興奮したりして、激しい息づかいをする。 「息を弾ませる」の解説 「息を弾ませる」の使い方 「息を弾ませる」の例文 苦し気...
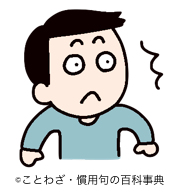 「い」で始まる慣用句
「い」で始まる慣用句「息を呑む」の意味とは?(類義語) 【慣用句】 息を呑む 【読み方】 いきをのむ 【意味】 呼吸を忘れるほどに驚いたり感動したりするさま。 【類義語】 ・我を忘れる ・声をのむ ・言葉を失う 「息を呑む」の語源由来 【語...
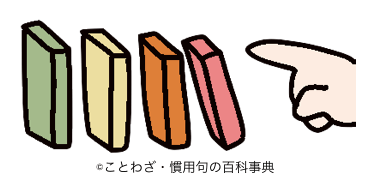 「い」で始まる慣用句
「い」で始まる慣用句「息を凝らす」の意味(類義語) 【慣用句】 息を凝らす 【読み方】 いきをこらす 【意味】 呼吸を静かにして、そのことに集中する。 【類義語】 ・息を殺す 「息を凝らす」の解説 「息を凝らす」の使い方 「息を凝らす」の例...
 「い」で始まる慣用句
「い」で始まる慣用句「息の根を止める」の意味(語源由来・類義語) 【慣用句】 息の根を止める 【読み方】 いきのねをとめる 【意味】 確実に殺す。立ち直れないほど相手を打ち負かす。 【語源由来】 呼吸ができないようにして殺す意から。 【類義...
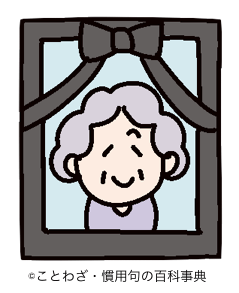 「い」で始まる慣用句
「い」で始まる慣用句「息が絶える」の意味 【慣用句】 息が絶える 【読み方】 いきがたえる 【意味】 呼吸がとまって死ぬこと。 「息が絶える」の解説 「息が絶える」の使い方 「息が絶える」の例文 もがいて苦しんでいる子供の様子を見て、すぐに...
 「い」で始まる慣用句
「い」で始まる慣用句「息が切れる」の意味 【慣用句】 息が切れる 【読み方】 いきがきれる 【意味】 息切れがする。あえぐ。 物事を続けることが苦しくなり、中途でやめる。 息が止まる。死ぬ。 「息が切れる」の解説 「息が切れる」の使い方 「...
 「い」で始まる慣用句
「い」で始まる慣用句「息が合う」の意味(類義語) 【慣用句】 息が合う 【読み方】 いきがあう 【意味】 ともに事をする二人以上の間で、気持ちや調子がぴったり合うこと。 【類義語】 ・馬が合う ・波長が合う 「息が合う」の解説 「息が合う」...
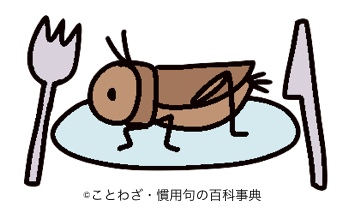 「い」で始まる慣用句
「い」で始まる慣用句「いかもの食い」の意味(語源由来) 【慣用句】 いかもの食い 【読み方】 いかものぐい 【意味】 一般に通常食べないものを食べることをいう。ただし災害遭難などのためにやむをえず餓死を免れるために口にするものは例外である。...
 「い」で始まる慣用句
「い」で始まる慣用句「家をたたむ」の意味 【慣用句】 家をたたむ 【読み方】 いえをたたむ 【意味】 その場所で続けてきた生活をやめてしまう。片付けて、よそへ移る。引き払う。 「家をたたむ」の解説 「家をたたむ」の使い方 「家をたたむ」の例...
 「い」で始まることわざ
「い」で始まることわざ「言いたいことは明日言え」の意味(語源由来・類義語・英語訳) 【ことわざ】 言いたいことは明日言え 【読み方】 いいたいことはあすいえ 【意味】 言いたいことがあったら、すぐ口に出さずに、一晩じっくり考えてから口にした方...
 「あ」で始まる慣用句
「あ」で始まる慣用句「案の定」の意味(語源由来) 【慣用句】 案の定 【読み方】 あんのじょう 【意味】 予想していたとおりに事が運ぶさま。 【語源由来】 案の定の「案」は、「考え」や「予想」、「計画」などを意味し、「定」は「確か」や「真実...
 「あ」で始まる慣用句
「あ」で始まる慣用句「合わせる顔がない」の意味 【慣用句】 合わせる顔がない 【読み方】 あわせるかおがない 【意味】 面目なくて、その人に会いに行けない。その人の前に出られない。 「合わせる顔がない」の解説 「合わせる顔がない」の使い方 ...
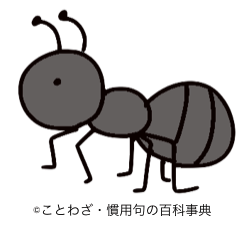 「あ」で始まる慣用句
「あ」で始まる慣用句「蟻の歩み」の意味 【慣用句】 蟻の歩み 【読み方】 ありのあゆみ 【意味】 休んだり怠けたりせず、少しずつでも絶えず進んでいくことの例え。 「蟻の歩み」の解説 「蟻の歩み」の使い方 「蟻の歩み」の例文 才能のある彼に比...
 「あ」で始まる慣用句
「あ」で始まる慣用句「ありがた迷惑」の意味(語源由来) 【慣用句】 ありがた迷惑 【読み方】 ありがためいわく 【意味】 人の親切や好意が、それを受ける人にとっては、かえって迷惑となること。また、そのさま。 【語源由来】 相手が親切心で行っ...
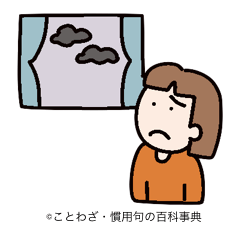 「あ」で始まることわざ
「あ」で始まることわざ「雨の降る日は天気が悪い」の意味(語源由来・類義語・英語訳) 【ことわざ】 雨の降る日は天気が悪い 【読み方】 あめのふるひはてんきがわるい 【意味】 あたりまえのこと、わかりきったことのたとえ。 【語源・由来】 「雨の...
 「あ」で始まる慣用句
「あ」で始まる慣用句「網の目を潜る」の意味(語源由来) 【慣用句】 網の目を潜る 【読み方】 あみのめをくぐる 【意味】 捜査網や法律に引っかからないようにする。 【語源由来】 「網の目」は、細かく張り巡らされているもののたとえであることか...
 「あ」で始まる慣用句
「あ」で始まる慣用句「天の邪鬼」の意味(語源由来) 【慣用句】 天の邪鬼 【読み方】 あまのじゃく 【意味】 何事によらず人の意見に逆らった行動ばかりするひねくれ者。 【語源由来】 「古事記」「日本書紀」に出てくる、「天探女(あまのさぐめ)...
 「あ」で始まる慣用句
「あ」で始まる慣用句「脂が乗る」の意味(語源由来) 【慣用句】 脂が乗る 【読み方】 あぶらがのる 【意味】 仕事などの調子が出て、意欲的に取り組んでいる。 【語源由来】 魚などの脂肪が増して味がよくなる意味から。 「脂が乗る」の解説 「脂...
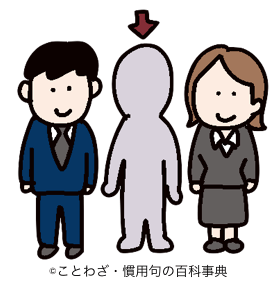 「あ」で始まる慣用句
「あ」で始まる慣用句「穴があく」の意味 【慣用句】 穴があく 【読み方】 あながあく 【意味】 欠員が生じたり予定が取り消しになったりするさま。 「穴があく」の解説 「穴があく」の使い方 「穴があく」の例文 急に、彼女から映画に行けないとい...
 「あ」で始まる慣用句
「あ」で始まる慣用句「後を引く」の意味 【慣用句】 後を引く 【読み方】 あとをひく 【意味】 余波がいつまでも続いて、きまりがつかない。尾を引く。 いつまでも欲しい感じが残る。 「後を引く」の解説 「後を引く」の使い方 「後を引く」の例文...
 「あ」で始まる慣用句
「あ」で始まる慣用句「後味が悪い」の意味(語源由来) 【慣用句】 後味が悪い 【読み方】 あとあじがわるい 【意味】 物事が終わったあとに残る感じや気分がよくないこと。 【語源由来】 「後味」が食べたあと、口の中に残る感じという意味であるこ...
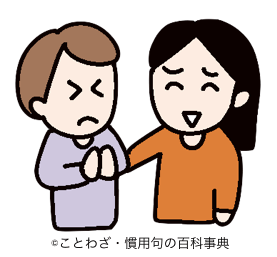 「お」で始まることわざ
「お」で始まることわざ「仇を恩にして報ずる」の意味(類義語) 【ことわざ】 仇を恩にして報ずる 【読み方】 あだをおんにしてほうじる 【意味】 非道な仕打ちを受けてもその相手に恨みを残さず、逆に情けを掛けることを言う。 【類義語】 ・仇を情け...
 「あ」で始まる慣用句
「あ」で始まる慣用句「遊び呆ける」の意味 【慣用句】 遊び呆ける 【読み方】 あそびほうける 【意味】 遊びに熱中し、他のことをかえりみない。 「遊び呆ける」の解説 「遊び呆ける」の使い方 「遊び呆ける」の例文 若いくせに金まわりが良くて、...
 「あ」で始まる慣用句
「あ」で始まる慣用句「足元にも及ばない」の意味(類義語) 【慣用句】 足元にも及ばない 【読み方】 あしもとにもおよばない 【意味】 相手が優れていて比べようもない。 【類義語】 ・足下へも寄り付けない 「足元にも及ばない」の解説 「足元に...
 「あ」で始まる慣用句
「あ」で始まる慣用句「足に任せる」の意味 【慣用句】 足に任せる 【読み方】 あしにまかせる 【意味】 特に目的を決めないで、気の向くままに歩く。また、足の力の続く限り歩く。 「足に任せる」の解説 「足に任せる」の使い方 「足に任せる」の例...
 「あ」で始まる慣用句
「あ」で始まる慣用句「足が鈍る」の意味 【慣用句】 足が鈍る 【読み方】 あしがにぶる 【意味】 歩く力や走る力が低下する。 「足が鈍る」の解説 「足が鈍る」の使い方 「足が鈍る」の例文 骨折して、長期入院していたので、治って退院するとき、...
 「あ」で始まる慣用句
「あ」で始まる慣用句「足が付く」の意味 【慣用句】 足が付く 【読み方】 あしがつく 【意味】 身元や足取りが分かること。 「足が付く」の解説 「足が付く」の使い方 「足が付く」の例文 捜査が難航していて暗礁に乗り上げるかと思われていた事件...
 「あ」で始まる慣用句
「あ」で始まる慣用句「顎が干上がる」の意味(語源由来・類義語) 【慣用句】 顎が干上がる 【読み方】 あごがひあがる 【意味】 生計の手段を失って困る。生活できなくなる。 【語源由来】 食べるものがなくて口の中が渇くことから。 【類義語】 ...
 「あ」で始まる慣用句
「あ」で始まる慣用句「あくせくする」の意味(語源由来) 【慣用句】 あくせくする 【読み方】 あくせくする 【意味】 細かいことを気にして、落ち着かないさま。目先のことにとらわれて、気持ちがせかせかするさま。 【語源由来】 「あくせく」の語...
 「あ」で始まることわざ
「あ」で始まることわざ「秋の夕焼け鎌を研げ」の意味(語源由来・出典・類義語) 【ことわざ】 秋の夕焼け鎌を研げ 【読み方】 あきのゆうやけかまをとげ 【意味】 夕焼けになった翌日は晴れるので、鎌を研いで草刈りや稲刈りに備えよということ。 【語...
 「い」で始まる慣用句
「い」で始まる慣用句「一から十まで」の意味(類義語) 【慣用句】 一から十まで 【読み方】 いちからじゅうまで 【意味】 始めから終わりまで、すべて 【類義語】 何から何まで 「一から十まで」の解説 「一から十まで」の使い方 「一から十まで...
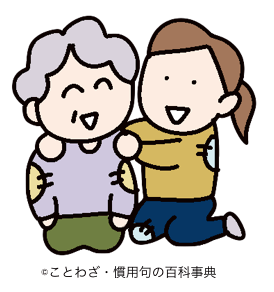 「い」で始まることわざ
「い」で始まることわざ「家貧しくして孝子顕る」の意味(語源由来・類義語) 【ことわざ】 家貧しくして孝子顕る 【読み方】 いえまずしくしてこうしあらわる 【意味】 貧しい家の子どもは親を助けて働かなくてはならないので、その親孝行ぶりが目立って...
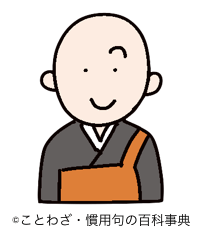 「あ」で始まる慣用句
「あ」で始まる慣用句「頭を丸める」の意味(語源由来) 【慣用句】 頭を丸める 【読み方】 あたまをまるめる 【意味】 僧侶になること。髪をそること。 【語源由来】 髪を剃ってつるつるになることから。 「頭を丸める」の解説 「頭を丸める」の使...
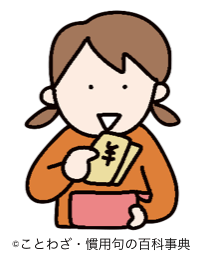 「あ」で始まる慣用句
「あ」で始まる慣用句「頭を撥ねる」の意味(類義語) 【慣用句】 頭を撥ねる 【読み方】 あたまをはねる 【意味】 他人の利益の一部をかすめ取る。 【類義語】 ・上前を撥ねる ・ピンをはねる ・ピンはねをする 「頭を撥ねる」の解説 「頭を撥ね...
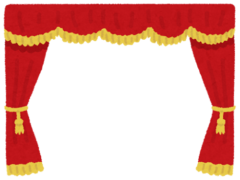 「ま」で始まる慣用句
「ま」で始まる慣用句【慣用句】 幕を開ける 【読み方】 まくをあける 【意味】 物事が始まる。 【語源・由来】 幕が開いて芝居が始まるという意味から。 【類義語】 幕が開く 「幕を開ける」の使い方 「幕を開ける」の例文 舞台ではちょうど「大...
 「ふ」で始まる慣用句
「ふ」で始まる慣用句【慣用句】 筆をおく 【読み方】 ふでをおく 【意味】 書き終える。書くのをやめること。擱筆する。 「筆をおく」の使い方 「筆をおく」の例文 作家人生の集大成となるであろう心血を注いできた大作も、ようやく筆をおく段階にな...
 「ふ」で始まる慣用句
「ふ」で始まる慣用句【慣用句】 蓋を開ける 【読み方】 ふたをあける 【意味】 物事を実際に始める。劇場などで興行を始める。 【語源・由来】 箱の中のものは蓋が閉まっていては中が見られないことを、予測できない未来に例えて言われる。 「蓋を開...
 「ひ」で始まる慣用句
「ひ」で始まる慣用句【慣用句】 一旗揚げる 【読み方】 ひとはたあげる 【意味】 事業を始めて身を起こす。成功を目指して新事業を起こす。 【語源・由来】 「一旗」とは、一本の旗のこと。昔、武士は手柄を立てるべく、家紋などのついた旗を掲げ、戦...
 「は」で始まることわざ
「は」で始まることわざ【ことわざ】 針の筵 【読み方】 はりのむしろ 【意味】 まるで針を植えた筵に座らされているように、いたたまれない気持ちをいうことば。不面目なことをしでかして自責の念に駆られながら人の前にいる状態の時などに使う。 【語源...
 「き」で始まる慣用句
「き」で始まる慣用句「脚光を浴びる」の意味(語源由来) 【慣用句】 脚光を浴びる 【読み方】 きゃっこうをあびる 【意味】 舞台に立つこと。注目される存在になること。 【語源由来】 「脚光」は、舞台の床の前方に据えて、俳優を足元から照らす照...
 「か」で始まる慣用句
「か」で始まる慣用句「鎌を掛ける」の意味(語源由来) 【慣用句】 鎌を掛ける 【読み方】 かまをかける 【意味】 知りたいことを相手に自然にしゃべらせるように、それとなく言いかけて誘導すること。 【語源由来】 鎌で引っ掛けて、相手を引き寄せ...
 「か」で始まる慣用句
「か」で始まる慣用句「舵を取る」の意味(語源由来) 【慣用句】 舵を取る 【読み方】 かじをとる 【意味】 物事がうまく進行するように誘導すること。 【語源由来】 舵を操作して船を進める意味から。 「舵を取る」の解説 「 「舵を取る」の使い...
 「た」で始まる慣用句
「た」で始まる慣用句「棚に上げる」の意味とは? 【慣用句】 棚に上げる 【読み方】 たなにあげる 【意味】 不都合なことには触れないで、そのままにしておく。 「棚に上げる」の語源由来 【語源由来】 棚に上げてしまっておくという意味から。 「...
 「あ」で始まる慣用句
「あ」で始まる慣用句「甘い汁を吸う」の意味(語源由来・類義語) 【慣用句】 甘い汁を吸う 【読み方】 あまいしるをすう 【意味】 自分は何もしないで他人の働きで利益を得る。 【語源由来】 「甘い汁」が転じて「利益」という意味。 【類義語】 ...
 「あ」で始まる慣用句
「あ」で始まる慣用句「味も素っ気もない」の意味とは? 【慣用句】 味も素っ気もない 【読み方】 あじもそっけもない 【意味】 潤いや面白味が全くない。つまらない。 「味も素っ気もない」の語源由来 【語源由来】 「素っ気」は相手への思いやり、...
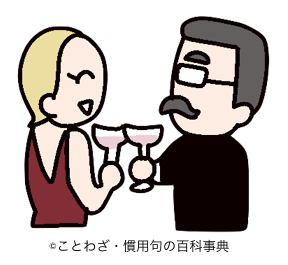 「き」で始まる慣用句
「き」で始まる慣用句「綺羅星の如く」の意味(語源由来・類義語) 【慣用句】 綺羅星の如く 【読み方】 きら、ほしのごとく 【意味】 地位の高い人や立派な人が多く並ぶ様子のたとえ。 【語源由来】 「綺羅」には美しい衣服という意味があり、転じて...
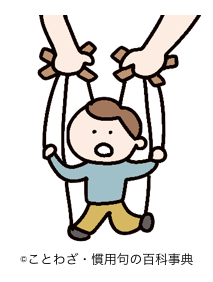 「い」で始まる慣用句
「い」で始まる慣用句「糸を引く」の意味(語源由来) 【慣用句】 糸を引く 【読み方】 いとをひく 【意味】 ①操り人形を、糸を引いて動かすことから、裏で指図して人を操る。 ②影響などが長く続いて絶えない。 ③ねばついて糸を張ったような状態に...
 「ね」で始まる慣用句
「ね」で始まる慣用句【慣用句】 根掘り葉掘り 【読み方】 ねほりはほり 【意味】 根を完全に掘り起こすように、何から何まで、事こまかく、しつこく問いただすこと。 「葉掘り」には意味はなく、「根掘り」に語呂を合わせただけ。 【由来】 根を掘り...
 「ね」で始まる慣用句
「ね」で始まる慣用句【慣用句】 猫撫で声 【読み方】 ねこなでごえ 【意味】 猫が人になでられたときに発するような、きげんを取るためのやさしくこびる声。 「猫撫で声」の使い方 「猫撫で声」の例文 さっきは猫撫で声を出したと思った刑事が、今度...
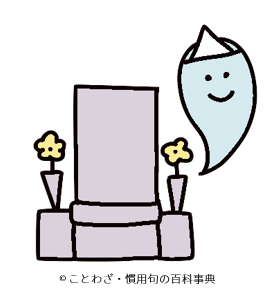 「く」で始まることわざ
「く」で始まることわざ「草葉の陰で喜ぶ」の意味(語源由来・英語訳) 【ことわざ】 草葉の陰で喜ぶ 【読み方】 くさばのかげでよろこぶ 【意味】 墓の下またはあの世で、亡くなった人が喜んでいるという事。 【語源・由来】 「草葉の陰」は草の葉の下...
 「く」で始まる慣用句
「く」で始まる慣用句「暗がりから牛」の意味 【慣用句】 暗がりから牛 【読み方】 くらがりからうし 【意味】 暗い所に黒い牛がいても形がはっきりしない。そこから、物事がはっきりせず、区別のつきにくいことのたとえ。また、ぐずぐずしていて、はき...
 「き」で始まる慣用句
「き」で始まる慣用句「牛耳を執る」の意味(故事) 【慣用句】 牛耳を執る 【読み方】 ぎゅうじをとる 【意味】 ある団体や組織などの主導権を握る。 【故事】 「左伝哀公十七年」にある故事から。諸侯が同盟を結ぶ儀式で、盟主が牛の耳を割いて血を...
 「ほ」で始まることわざ
「ほ」で始まることわざ【ことわざ】 吠える犬は噛み付かぬ 【読み方】 ほえるいぬはかみつかぬ 【意味】 噛み付く勇気のない犬ほど吠えることから、威勢のいい者に限って実力がないこと。 「吠える犬は噛み付かぬ」の使い方 「吠える犬は噛み付かぬ」の...
 「け」で始まることわざ
「け」で始まることわざ【ことわざ】 犬猿の仲 【読み方】 けんえんのなか 【意味】 とても仲が悪いこと。 【語源・由来】 犬と猿は、仲が悪いといわれていることから。 【類義語】 ・犬と猿 「犬猿の仲」の使い方 「犬猿の仲」の例文 事情を詳しく...
 「い」で始まることわざ
「い」で始まることわざ「犬は人に付き猫は家に付く」の意味(語源由来・類義語・英語訳) 【ことわざ】 犬は人に付き猫は家に付く 【読み方】 いぬはひとにつきねこはいえにつく 【意味】 犬は家人になつき、引っ越しにもついて行くが、猫は人よりも家の...
 「や」で始まる慣用句
「や」で始まる慣用句【慣用句】 野次馬 【読み方】 やじうま 【意味】 自分に関係のないことに、興味本位で騒ぎ立て、見物すること。また、人のしりについて騒ぎ回ること。また、その人々。 父馬。老いた牡馬。また、気性の強い馬。 「野次馬」の使い...
 「と」で始まる慣用句
「と」で始まる慣用句【慣用句】 何処の馬の骨 【読み方】 どこのうまのほね 【意味】 身元の確かでない者をののしっていう言葉。 「何処の馬の骨」の使い方 「何処の馬の骨」の例文 彼は、自分の娘に手を出そうとしていた何処の馬の骨かもわからない...
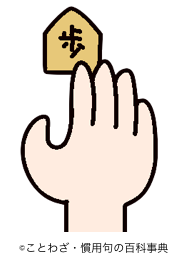 「こ」で始まる慣用句
「こ」で始まる慣用句【慣用句】 駒を進める 【読み方】 こまをすすめる 【意味】 次の段階へ進み出る。 「駒を進める」の使い方 「駒を進める」の例文 今回のことで経営再建の立役者ともなれば、将来は頭取まで上り詰めることも夢ではないかもしれな...
 「へ」で始まる慣用句
「へ」で始まる慣用句【慣用句】 屁の河童 【読み方】 へのかっぱ 【意味】 簡単、容易にできること。「河童の屁」が逆さになったことば。 【語源由来】 河童の屁は水中でするため勢いがないことからという説、「木っ端の火」(簡単に火がつくが、すぐ...
 「て」で始まる慣用句
「て」で始まる慣用句【慣用句】 天狗になる 【読み方】 てんぐになる 【意味】 いい気になって自慢する。得意になる。うぬぼれる。 【語源由来】 「天狗」は、赤い顔をして鼻が高く、翼をもった怪物。そこで、自慢して鼻を高くするようすを天狗にたと...
 「し」で始まる慣用句
「し」で始まる慣用句【慣用句】 鯱張る 【読み方】 しゃちほこばる 【意味】 しゃちほこのように、緊張して体をこわばらせる。「鯱」は想像上の動物で、頭は虎に似て体は魚。尾は跳ね上げた形の作り物にして、城などの屋根の両端に飾ったりする。緊張す...
 「こ」で始まることわざ
「こ」で始まることわざ「虎口を逃れて竜穴に入る」の意味(語源由来・類義語・英語訳) 【ことわざ】 虎口を逃れて竜穴に入る 【読み方】 ここうをのがれてりゅうけつにはいる 【意味】 災難が続いて起こる例え。 【語源・由来】 虎に食われそうな場面...
 「か」で始まることわざ
「か」で始まることわざ「河童に水練」の意味(語源由来・類義語・英語訳) 【ことわざ】 河童に水練 【読み方】 かっぱにすいれん 【意味】 泳ぎの達者な河童に泳ぎ方を教えるということから、ある分野に精通している人に対してその分野について教えよう...
 「む」で始まる慣用句
「む」で始まる慣用句【慣用句】 虫も殺さない 【読み方】 むしもころさない 【意味】 小さな虫も殺せないほど、優しくておとなしい。 「虫も殺さない」の使い方 「虫も殺さない」の例文 彼女は、虫も殺さないような顔をしているが、陰ではずいぶん悪...
 「む」で始まる慣用句
「む」で始まる慣用句【慣用句】 虫の息 【読み方】 むしのいき 【意味】 弱り果てて、今にも絶えそうな呼吸。また、その状態。 「虫の息」の使い方 「虫の息」の例文 雪崩から救出された彼は、運び出された時には既に虫の息であり、すぐに亡くなった...
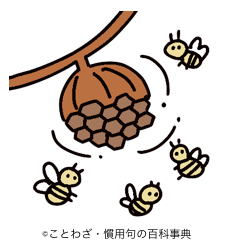 「は」で始まる慣用句
「は」で始まる慣用句【慣用句】 蜂の巣をつついたよう 【読み方】 はちのすをつついたよう 【意味】 蜂の巣をつつくと蜂の群れがいっせいに飛び立ち、飛び回る。そこから、大勢の人がいっせいに騒ぎ出して手がつけられない状態のたとえ。 「蜂の巣をつ...
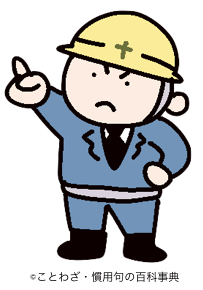 「あ」で始まることわざ
「あ」で始まることわざ「蟻の這い出る隙もない」の意味(語源由来) 【ことわざ】 蟻の這い出る隙もない 【読み方】 ありのはいでるすきもない 【意味】 少しの隙もなく、警戒が厳重なようす。 【語源由来】 小さなありでも逃げ出すことができないほど...
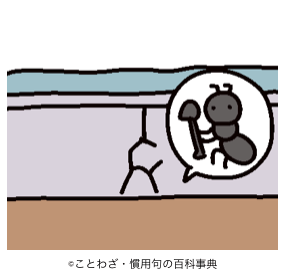 「あ」で始まることわざ
「あ」で始まることわざ「蟻の穴から堤も崩れる」の意味(語源由来・類義語・英語) 【ことわざ】 蟻の穴から堤も崩れる 【読み方】 ありのあなからつつみもくずれる 【意味】 わずかな油断や手違いで重大な物事が駄目になること。 【語源由来】 頑丈に...
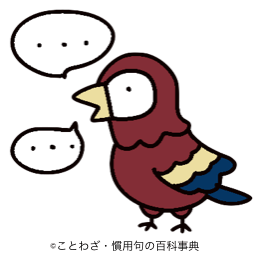 「お」で始まる慣用句
「お」で始まる慣用句「鸚鵡返し」の意味(語源由来) 【慣用句】 鸚鵡返し 【読み方】 おうむがえし 【意味】 ほかの人が言ったことを、そのまま言い返すこと。 【語源由来】 鳥のオウムが、人間の言うことをまねすることから。もとは、人のつくった...
 「ひ」で始まる慣用句
「ひ」で始まる慣用句【慣用句】 一つ穴の狢 【読み方】 ひとつあなのむじな 【意味】 同じ仲間、あるいは同類の意味で、多くの場合、同じような悪事、あるいは感心できないことをする人間を同一視していう。 「貉」は穴熊や狸の別称。 「一つ穴の狢」...
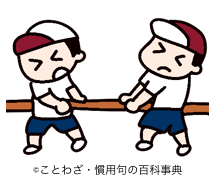 「い」で始まる慣用句
「い」で始まる慣用句「鼬ごっこ」の意味とは? 【慣用句】 鼬ごっこ 【読み方】 いたちごっこ 【意味】 二人が手の甲を交互につねり、その手を重ねてゆく遊び。 両方がたがいに同じことを繰り返して決着がつかないこと。 「鼬ごっこ」の語源由来 【...
 「さ」で始まる慣用句
「さ」で始まる慣用句【慣用句】 猿真似 【読み方】 さるまね 【意味】 何の考えもなく他人の真似をすること。 「猿真似」の使い方 「猿真似」の例文 カラオケ大会で賞を取ったと思ったら、調子に乗って、今度は派手な着物を着込んで歌手の猿真似をす...
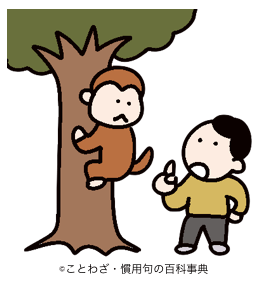 「さ」で始まる慣用句
「さ」で始まる慣用句「猿に木登り」の意味 【慣用句】 猿に木登り 【読み方】 さるにきのぼり 【意味】 教える必要のない者に教えるというむだなこと。 「猿に木登り」の解説 「猿に木登り」の使い方 「猿に木登り」の例文 あの子にピアノを教える...
 「さ」で始まる慣用句
「さ」で始まる慣用句「猿知恵」の意味 【慣用句】 猿知恵 【読み方】 さるぢえ 【意味】 気がきいているようで、実はあさはかな知恵。こざかしい知恵。 「猿知恵」の解説 「猿知恵」の使い方 「猿知恵」の例文 君らが何を企んでいるのか知らないが...
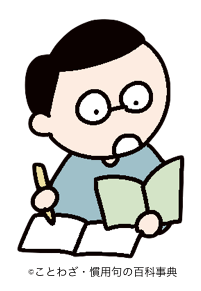 「と」で始まる慣用句
「と」で始まる慣用句「虎の巻」の意味 【慣用句】 虎の巻 【読み方】 とらのまき 【意味】 兵法の秘伝を記した書。講義などの種本。教科書の内容を解説した安易な学習書。手軽な参考書。あんちょこ。とらかんともいう。 「虎の巻」の解説 「虎の巻」...
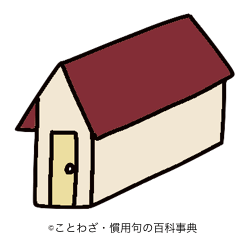 「う」で始まる慣用句
「う」で始まる慣用句「鰻の寝床」の意味 【慣用句】 鰻の寝床 【読み方】 うなぎのねどこ 【意味】 うなぎの寝床は体に合った細長いものだということから、入口が狭くて奥行きの深い建物や場所のたとえ。裏長屋や細長く狭い窮屈な場所にもいう。 「鰻...
 「け」で始まる慣用句
「け」で始まる慣用句「犬馬の労」の意味(類義語) 【慣用句】 犬馬の労 【読み方】 けんばのろう 【意味】 人のために、犬や馬のように私心なく、ひたすら尽くして働くこと。へりくだって言うことば。 【類義語】 ・汗馬の労 ・薪水の労 「犬馬の...
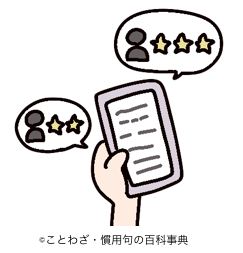 「け」で始まる慣用句
「け」で始まる慣用句【慣用句】 下馬評 【読み方】 げばひょう 【意味】 城門などの下馬する場所で、主人を待っている供の者が将軍などの批判をしたことから、世間での評判をいう。 「下馬評」の使い方 「下馬評」の例文 決勝戦においては下馬評では...
 「と」で始まる慣用句
「と」で始まる慣用句「虎の子」の意味 【慣用句】 虎の子 【読み方】 とらのこ 【意味】 大事にして手離さないもの。 「虎の子」の解説 「虎の子」の使い方 「虎の子」の例文 入院している間に虎の子のバラを枯らしてしまって、病気になったことよ...
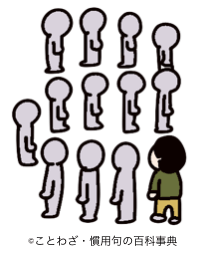 「ち」で始まる慣用句
「ち」で始まる慣用句【慣用句】 長蛇の列 【読み方】 ちょうだのれつ 【意味】 蛇のように長々と続く行列。 「長蛇の列」の使い方 「長蛇の列」の例文 通常は、レストランの出入り口は開放されているが、混雑時などには入口専用口と出口専用口に分け...
 「ね」で始まる慣用句
「ね」で始まる慣用句【慣用句】 猫の子一匹いない 【読み方】 ねこのこいっぴきいない 【意味】 全く人影のないようす。 【語源由来】 子猫の一匹でもいればまだいいものの、それすらいないということ。 【類義語】 ・鼠に引かれそう ・人っ子一人...
 「や」で始まる慣用句
「や」で始まる慣用句「山を掛ける」の意味とは?(類義語) 【ことわざ】 山を掛ける 【読み方】 やまをかける 【意味】 万一の幸運を当てにして、物事を行うこと。こうなるだろうと予想して用意すること。 【類義語】 山を張る 「山を掛ける」の語...
 「や」で始まる慣用句
「や」で始まる慣用句【慣用句】 山が見える 【読み方】 やまがみえる 【意味】 困難を乗り切って、先の見通しが付く。 「山が見える」の使い方 「山が見える」の例文 与野党の話し合いがつき、法案策定もようやく山が見えてきた。 海底部分の掘削が...
 「や」で始まる慣用句
「や」で始まる慣用句【慣用句】 野に下る 【読み方】 やにくだる 【意味】 公職を辞めて民間人になること。 「野に下る」の使い方 「野に下る」の例文 四十歳のときに、どうしても珈琲屋になりたくて野に下ったが、予想通りに周りからは、せっかく安...
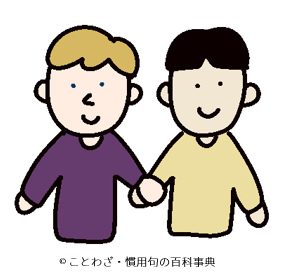 「よ」で始まることわざ
「よ」で始まることわざ【ことわざ】 洋の東西を問わず 【読み方】 ようのとうざいをとわず 【意味】 東洋と西洋との別なく世界共通。世界中。 【英語訳】 in all parts of the world in all countries an...
 「に」で始まることわざ
「に」で始まることわざ「西も東もわからない」の意味(語源由来・類義語・英語訳) 【ことわざ】 西も東もわからない 【読み方】 にしもひがしもわからない 【意味】 西の方角がどちらか、どちらが東の方角かわからないという意味。初めての土地に来た時...
 「あ」で始まることわざ
「あ」で始まることわざ「朝日が西から出る」の意味(語源由来・類義語・英語) 【ことわざ】 朝日が西から出る 【読み方】 あさひがにしからでる 【意味】 とうていあり得ないことのたとえ。 【語源・由来】 太陽が、西から昇ることは絶対あり得ないこ...
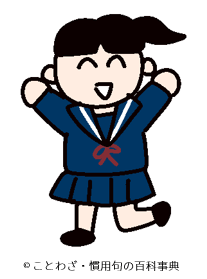 「し」で始まることわざ
「し」で始まることわざ「春秋に富む」の意味(出典・英語訳) 【ことわざ】 春秋に富む 【読み方】 しゅんじゅうにとむ 【意味】 歳月を豊富に持っているということで、年が若く、将来があることをいう。 【出典】 「史記」 【英語訳】 to be ...
 「か」で始まることわざ
「か」で始まることわざ【ことわざ】 門松は冥土の旅の一里塚 【読み方】 かどまつはめいどのたびのいちりづか 【意味】 めでたい門松も、それを立てるたびに年を重ねるから、次第に死に近づく標示ともみられるということ。 【語源・由来】 一休の狂歌で...
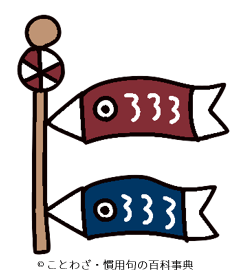 「え」で始まることわざ
「え」で始まることわざ「江戸っ子は五月の鯉の吹き流し」の意味(語源由来・類義語・英語訳) 【ことわざ】 江戸っ子は五月の鯉の吹き流し 【読み方】 えどっこはさつきのこいのふきながし 【意味】 鯉のぼりは空洞なので、口から勢いよく入った風が全部...
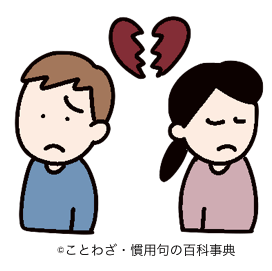 「あ」で始まる慣用句
「あ」で始まる慣用句「秋風が立つ」の意味(類義語) 【慣用句】 秋風が立つ 【読み方】 あきかぜがたつ 【意味】 男女の愛がさめるという意味。 【類義語】 ・秋風が吹く 「秋風が立つ」の解説 「秋風が立つ」の使い方 「秋風が立つ」の例文 早...
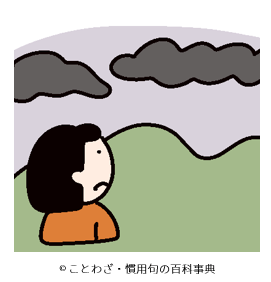 「ふ」で始まることわざ
「ふ」で始まることわざ「風雲急を告げる」の意味(英語訳) 【ことわざ】 風雲急を告げる 【読み方】 ふううんきゅうをつげる 【意味】 何か大事が起こりそうな不穏な気配がすることなどを表す表現。「風雲」は世の流れ・情勢などを意味する語。 【英語...
 「け」で始まることわざ
「け」で始まることわざ「蛍雪の功」の意味(出典・故事・類義語・英語訳) 【ことわざ】 蛍雪の功 【読み方】 けいせつのこう 【意味】 苦労して学問に励むことで、結果を出すこと。 【出典】 「晋書」 【故事】 「晋書」より。貧しくて灯火用の油が...
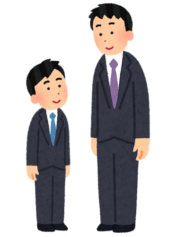 「く」で始まる慣用句
「く」で始まる慣用句【慣用句】 雲を衝く 【読み方】 くもをつく 【意味】 非常に背が高いことのたとえ。 「雲を衝く」の使い方 「雲を衝く」の例文 土地は起伏が多く、山は概して険しく高くて、遠くに薄く見える山のなかには雲を衝くほど高い山もあ...
 「く」で始まる慣用句
「く」で始まる慣用句「雲を霞と」の意味 【慣用句】 雲を霞と 【読み方】 くもをかすみと 【意味】 一目散に走って行方をくらますさま。 「雲を霞と」の解説 「雲を霞と」の使い方 「雲を霞と」の例文 最初の勢いはどこへやら、五人揃って無頼漢共...
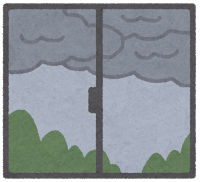 「く」で始まる慣用句
「く」で始まる慣用句【慣用句】 雲行きが怪しい 【読み方】 くもゆきがあやしい 【意味】 天候が悪くなりそうだということ。または、物事のなりゆきや情勢が悪い方へ向かいそうだということ。 「雲行きが怪しい」の使い方 「雲行きが怪しい」の例文 ...
 「か」で始まる慣用句
「か」で始まる慣用句「風の吹き回し」の意味 【慣用句】 風の吹き回し 【読み方】 かぜのふきまわし 【意味】 その時々の模様しだいで一定しないことにいう。その時々の加減。 「風の吹き回し」の解説 「風の吹き回し」の使い方 「風の吹き回し」の...
 「か」で始まる慣用句
「か」で始まる慣用句「風上に置けない」の意味 【慣用句】 風上に置けない 【読み方】 かざかみにおけない 【意味】 風上に悪臭を発するものがあると風下では非常に臭いことから、卑劣な人間をののしっていうことば。 「風上に置けない」の解説 「風...
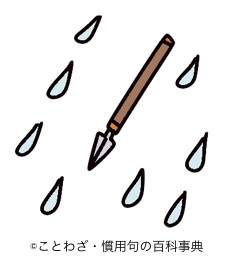 「あ」で始まることわざ
「あ」で始まることわざ「雨が降ろうが槍が降ろうが」の意味(類義語・英語訳) 【ことわざ】 雨が降ろうが槍が降ろうが 【読み方】 あめがふろうがやりがふろうが 【意味】 どんな障害や困難があろうとも、必ずやりとげようという堅い意思を表すことば。...
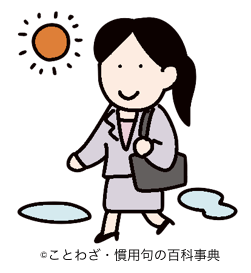 「あ」で始まることわざ
「あ」で始まることわざ「朝雨に傘要らず」の意味(語源由来・類義語・英語) 【ことわざ】 朝雨に傘要らず 【読み方】 あさあめにかさいらず 【意味】 朝のうちに降り出した雨はすぐに上がるので、出掛ける際に傘を持って行く必要がないということ。 【...
 「あ」で始まる慣用句
「あ」で始まる慣用句「青田買い」の意味(語源由来) 【慣用句】 青田買い 【読み方】 あおたがい 【意味】 稲の収穫前に、その田の収穫量を見越して先買いすること。企業が人材確保のため、卒業予定の学生の採用を早くから内定すること。卒業前の学生...
 「あ」で始まる慣用句
「あ」で始まる慣用句「青筋を立てる」の意味 【慣用句】 青筋を立てる 【読み方】 あおすじをたてる 【意味】 顔面に静脈が浮き出るほど、ひどく怒ったり、興奮したりする。 「青筋を立てる」の解説 「青筋を立てる」の使い方 「青筋を立てる」の例...
 「あ」で始まる慣用句
「あ」で始まる慣用句「合いの手を入れる」の意味 【慣用句】 合いの手を入れる 【読み方】 あいのてをいれる 【意味】 歌や踊りに合わせて手拍子を打ったり、掛け声をかけること。また、人との会話で、相手の話を促したり、うまく話題を展開したりする...
 「あ」で始まる慣用句
「あ」で始まる慣用句「愛想を尽かす」の意味 【慣用句】 愛想を尽かす 【読み方】 あいそをつかす 【意味】 あきれて好意や親愛の情をなくす。見限る。 「愛想を尽かす」の解説 「愛想を尽かす」の使い方 「愛想を尽かす」の例文 このお見合いが破...
 「は」で始まることわざ
「は」で始まることわざ「箸にも棒にも掛からない」の意味(類義語・英語訳) 【ことわざ】 箸にも棒にも掛からない 【読み方】 はしにもぼうにもかからない 【意味】 あまりにもひどすぎてどうにもできないこと。細い箸にも、太い棒にも、ひっかからない...
 「ふ」で始まる慣用句
「ふ」で始まる慣用句「不意を突く」の意味とは?(類義語) 【慣用句】 不意を突く 【読み方】 ふいをつく 【意味】 相手に対して出し抜けに予期しないことを行うこと。 【類義語】 不意を討つ 「不意を突く」の語源由来・解説 「不意を突く」の使...
 「ひ」で始まる慣用句
「ひ」で始まる慣用句【慣用句】 人を食う 【読み方】 ひとをくう 【意味】 人を人とも思わない態度をとる。馬鹿にすること。 「人を食う」の使い方 「人を食う」の例文 誠意をこめて話をしたのに、人を食ったような答えしか返ってこなかった。 彼の...
 「は」で始まる慣用句
「は」で始まる慣用句【慣用句】 ばつが悪い 【読み方】 ばつがわるい 【意味】 きまりが悪い。ぐあいが悪い。 「ばつが悪い」の使い方 「ばつが悪い」の例文 友人のうわさ話をしていたら、後ろにその友人がいたのでばつが悪い思いをした。 熱を出し...
 「ね」で始まる慣用句
「ね」で始まる慣用句【慣用句】 熱が冷める 【読み方】 ねつがさめる 【意味】 熱中していた状態から、もとに戻る。 「熱が冷める」の使い方 「熱が冷める」の例文 あまりに計画に熱中し過ぎて、 計画している間にだんだん熱が冷めてきて、旅行に行...
 「ね」で始まる慣用句
「ね」で始まる慣用句【慣用句】 念を押す 【読み方】 ねんをおす 【意味】 重ねて注意する。また、注意して確かめる。 「念を押す」の使い方 「念を押す」の例文 刑事さんに、「本当に、何も見なかったんですね?」と念を押して聞かれたが、本当に何...
 「そ」で始まる慣用句
「そ」で始まる慣用句【慣用句】 そつが無い 【読み方】 そつがない 【意味】 手落ちがない。手抜かりがない。むだがない。 「そつが無い」の使い方 「そつが無い」の例文 グループに一人、そつが無い人がいると、何事においても便利なものである。 ...
 「せ」で始まる慣用句
「せ」で始まる慣用句【慣用句】 世話を焼く 【読み方】 せわをやく 【意味】 他人の世話をする。進んで他人の面倒をみる。 「世話を焼く」の使い方 「世話を焼く」の例文 近所の結婚していない若い女性に世話を焼いて、結婚相手を見つけることが長年...
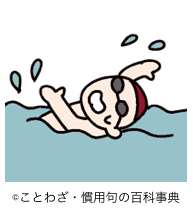 「よ」で始まることわざ
「よ」で始まることわざ「善く泳ぐ者は溺る」の意味(語源由来・出典・類義語・英語訳) 【ことわざ】 善く泳ぐ者は溺る 【読み方】 よくおよぐものはおぼる 【意味】 人は自分の得意とすることでは、かえって失敗しやすいという意味。 「游」は「泳」と...
 「ゆ」で始まることわざ
「ゆ」で始まることわざ「雄弁は銀沈黙は金」の意味(語源由来・類義語・英語訳) 【ことわざ】 雄弁は銀沈黙は金 【読み方】 ゆうべんはぎんちんもくはきん 【意味】 巧みな弁舌は素晴らしいが、それを銀ほどの値打ちとすれば、沈黙を守っているのはそれ...
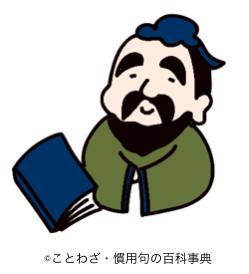 「ふ」で始まることわざ
「ふ」で始まることわざ「故きを温ねて新しきを知る」の意味(出典・類義語・英語訳) 【ことわざ】 故きを温ねて新しきを知る 【読み方】 ふるきをたずねてあたらしきをしる 【意味】 古いことを調べて、新しい知識や意義を再発見するという意味。 【出...
 「は」で始まることわざ
「は」で始まることわざ「話上手の聞き下手」の意味(対義語) 【ことわざ】 話上手の聞き下手 【読み方】 はなしじょうずのききべた 【意味】 話すことが上手な人は、人との会話においても自分の話に夢中になってしまい、とかく相手の話を聞かないし、聞...
 「に」で始まることわざ
「に」で始まることわざ【ことわざ】 日光を見ずして結構と言うな 【読み方】 にっこうをみずしてけっこうというな 【意味】 日光にある東照宮という建物の美しさを、ほめて言ったことば。 【語源・由来】 「にっこう」と「けっこう」のかけ言葉で、あの...
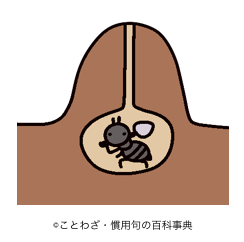 「せ」で始まることわざ
「せ」で始まることわざ【ことわざ】 千里の堤も蟻の穴から 【読み方】 せんりのつつみもありのあなから 【意味】 ささいなことでも油断すると、大きな災いを招くことがあるというたとえ。 【語源・由来】 蟻が堤防に作ったほんの小さな穴であっても、放...
 「か」で始まることわざ
「か」で始まることわざ「可愛い子には旅をさせよ」とは 読み方・意味 ことわざ:可愛い子には旅をさせよ 読み方:かわいいこにはたびをさせよ 意味:愛する子どもを甘やかすのではなく、あえて厳しい環境に送り出し、他人の中で困難を経験させることで、成...
 「か」で始まることわざ
「か」で始まることわざ【ことわざ】 鰹節を猫に預ける 【読み方】 かつおぶしをねこにあずける 【意味】 猫のそばに大好物の鰹節をおけばいつ食べられるかわからない。そこから、すこしも油断できないたとえ。また、過ちが起こりやすいことのたとえ。 【...
 「う」で始まることわざ
「う」で始まることわざ【ことわざ】 歌は世につれ世は歌につれ 【読み方】 うたはよにつれよはうたにつれ 【意味】 どんな歌が流行するかは世相の変化に伴って変わっていくが、一方、世相のほうも流行する歌に影響される。このように歌と世の中はおたがい...
 「い」で始まることわざ
「い」で始まることわざ「急がば回れ」ということわざは、昔から多くの場面で使われてきました。急いでいるときほど、遠回りに見えても安全で確実な道を選ぶことが、結果的に成功への近道になるという教えです。 しかし、「急がば回れ」という言葉の本当の意味...
 「い」で始まることわざ
「い」で始まることわざ「石の上にも三年」とは 読み方・意味 ことわざ:石の上にも三年 読み方:いしのうえにもさんねん 意味:つらくてもがまんして努力を続ければ、やがて報われるということ。 「石の上にも三年」とは、たとえ辛い状況で...
 「い」で始まることわざ
「い」で始まることわざ【ことわざ】 いざ鎌倉 【読み方】 いざかまくら 【意味】 さぁ、大変なことが起こった、いますぐかけつけねばならぬという意味。 【出典】 謡曲「鉢木」より。鎌倉幕府の執権職を辞した北条時頼が諸国を視察中、大雪の夜に佐野源...
 「あ」で始まることわざ
「あ」で始まることわざ【ことわざ】 揚げ足を取る 【読み方】 あげあしをとる 【意味】 相手の言葉のおかしなところや、言い間違いを、わざと取り上げて、からかったり悪口をいったりすること。 【語源・由来】 相撲で相手が足を揚あげたとき、その足を...
 「あ」で始まる慣用句
「あ」で始まる慣用句「足が地に着かない」の意味 【慣用句】 足が地に着かない 【読み方】 あしがちにつかない 【意味】 緊張や興奮のため心が落ち着かない。考え方や行動が浮ついて、しっかりしていない。 「足が地に着かない」の解説 「足が地に着...
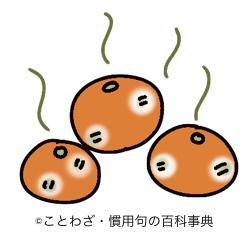 「あ」で始まる慣用句
「あ」で始まる慣用句「足が早い」の意味 【慣用句】 足が早い 【読み方】 あしがはやい 【意味】 食べ物などが腐りやすい。 売れ行きが早い 「足が早い」の解説 「足が早い」の使い方 「足が早い」の例文 だんだん気温が高くなっていて、お刺身の...
 「く」で始まる慣用句
「く」で始まる慣用句【慣用句】 口が減らない 【読み方】 くちがへらない 【意味】 口が達者である。勝手なことを次から次へと言う。 「口が減らない」の使い方 「口が減らない」の例文 明らかに自分のミスなのに、謝らないし言い訳ばかりで、本当に...
 「あ」で始まる慣用句
「あ」で始まる慣用句「顎を撫でる」の意味 【慣用句】 顎を撫でる 【読み方】 あごをなでる 【意味】 満足をしたときの仕草。得意になっている様子。 「顎を撫でる」の解説 「顎を撫でる」の使い方 「顎を撫でる」の例文 彼は、顎を撫でながら、将...
 「は」で始まることわざ
「は」で始まることわざ「杯中の蛇影」の意味(出典・故事・類義語・英語訳) 【ことわざ】 杯中の蛇影 【読み方】 はいちゅうのだえい 【意味】 疑心を起こせば、何でもないことにも神経を悩ますことのたとえ。 【出典】 「晋書・楽広伝」 【故事】 ...
 「は」で始まることわざ
「は」で始まることわざ「背水の陣」の意味(出典・故事・類義語・英語訳) 【ことわざ】 背水の陣 【読み方】 はいすいのじん 【意味】 背後に川などがあると後退できないので、軍勢は必死に戦う。同じようにあとがないという必死の覚悟で、物事に取り組...
 「は」で始まることわざ
「は」で始まることわざ「敗軍の将は兵を語らず」の意味(出典・故事・類義語・英語訳) 【ことわざ】 敗軍の将は兵を語らず 【読み方】 はいぐんのしょうはへいをかたらず 【意味】 戦争に敗れた将軍はその戦いについてあれこれ言うべきでないし、兵法の...
 「の」で始まることわざ
「の」で始まることわざ「上り一日下り一時」の意味(語源由来) 【ことわざ】 上り一日下り一時 【読み方】 のぼりいちにちくだりいっとき 【意味】 一日かけてようやく上り着くようなところも、下りはあっという間であるという意味。物事を作り上げるた...
 「の」で始まることわざ
「の」で始まることわざ「軒を貸して母屋を取られる」の意味(語源由来・類義語・英語訳) 【ことわざ】 軒を貸して母屋を取られる 【読み方】 のきをかしておもやをとられる 【意味】 軒先だけと思って貸したのに中心部の建物まで占拠されるということで...
 「の」で始まることわざ
「の」で始まることわざ「嚢中の錐」の意味(語源由来・出典・類義語・英語訳) 【ことわざ】 嚢中の錐 【読み方】 のうちゅうのきり 【意味】 優れた人物は目立つということ。 【語源・由来】 嚢(袋)の中に錐きり(先がとがっていて、穴をあける道具...
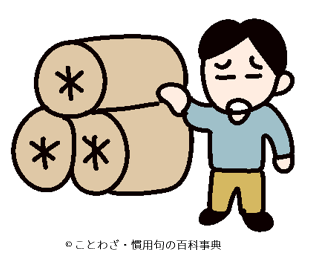 「ね」で始まることわざ
「ね」で始まることわざ「年貢の納め時」の意味(語源由来・英語訳) 【ことわざ】 年貢の納め時 【読み方】 ねんぐのおさめどき 【意味】 「年貢」は昔、田畑などに課せられていた租税のこと。悪事を働いていた者が捕まって、刑に服する時期のこと。また...
 「ね」で始まることわざ
「ね」で始まることわざ「寝た子を起こす」の意味(語源由来・類義語・英語訳) 【ことわざ】 寝た子を起こす 【読み方】 ねたこをおこす 【意味】 治まっている物事に無用の手出しをして、再びやっかいな問題を引き起こすこと。 【語源・由来】 ようや...
 「ね」で始まることわざ
「ね」で始まることわざ「猫も杓子も」の意味(語源由来・英語訳) 【ことわざ】 猫も杓子も 【読み方】 ねこもしゃくしも 【意味】 なにもかも。だれもかれも。 【語源・由来】 一休禅師の「生まれては死ぬるなりけりおしなべて釈迦も達磨も猫も杓子も...
 「ね」で始まることわざ
「ね」で始まることわざ「猫の目」の意味(語源由来・類義語・英語訳) 【ことわざ】 猫の目 【読み方】 ねこのめ 【意味】 物事がよく変わること。物事の移り変わりが激しいことのたとえ。 【語源・由来】 猫の目は、明るさによって丸くなったり細くな...
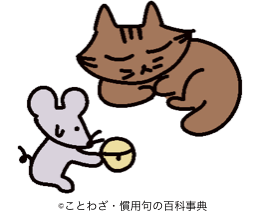 「ね」で始まることわざ
「ね」で始まることわざ「猫の首に鈴を付ける」の意味(語源由来・類義語・英語訳) 【ことわざ】 猫の首に鈴を付ける 【読み方】 ねこのくびにすずをつける 【意味】 よいアイデアでも、実行する人がいないような難しいこと。 【語源・由来】 「イソッ...
 「ね」で始まることわざ
「ね」で始まることわざ「猫に木天蓼」の意味(語源由来・類義語) 【ことわざ】 猫に木天蓼 【読み方】 ねこにまたたび 【意味】 猫は木天蓼が最高の好物であることから、大好物、または効果があることのたとえ。「木天蓼」はマタタビ科のつる性植物。「...
 「ぬ」で始まることわざ
「ぬ」で始まることわざ【ことわざ】 濡れぬ先の傘 【読み方】 ぬれぬさきのかさ 【意味】 失敗しないように、前もって用意をしておくことが大事だということ。 【語源・由来】 雨が降って濡れる前に、傘を用意しておくという意味から。 【類義語】 ・...
 「ぬ」で始まることわざ
「ぬ」で始まることわざ「濡れぬ先こそ露をも厭え」の意味(語源由来・類義語・英語訳) 【ことわざ】 濡れぬ先こそ露をも厭え 【読み方】 ぬれぬさきこそつゆをもいとえ 【意味】 濡れないうちは露に濡れるのさえ嫌なものだが、いったん濡れてしまうと...
 「ぬ」で始まることわざ
「ぬ」で始まることわざ「濡れ衣を着せる」の意味(英語訳) 【ことわざ】 濡れ衣を着せる 【読み方】 ぬれぎぬをきせる 【意味】 「濡れ衣」とは濡れた衣服のことで、「無実の罪」の比喩表現。無実の罪を負わされること。また、根も葉もないうわさ、とく...
 「ぬ」で始まることわざ
「ぬ」で始まることわざ「盗人を捕らえて見れば我が子なり」の意味(語源由来・英語訳) 【ことわざ】 盗人を捕らえて見れば我が子なり 【読み方】 ぬすびとをとらえてみればわがこなり 「盗人」は「ぬすっと」とも読む。 【意味】 盗人を捕らえたら意外...
 「ぬ」で始まることわざ
「ぬ」で始まることわざ「盗人にも三分の理」の意味(語源由来・類義語・英語訳) 【ことわざ】 盗人にも三分の理 「盗人」は「ぬすっと」とも読む。 【読み方】 ぬすびとにもさんぶのり 【意味】 盗人が盗みを働くにもそれなりの理屈があるということ。...
 「ぬ」で始まることわざ
「ぬ」で始まることわざ「盗人に追い銭」の意味(語源由来・類義語・英語訳) 【ことわざ】 盗人に追い銭 【読み方】 ぬすびとにおいせん 「盗人」は「ぬすっと」とも読む。 【意味】 「追い銭」とは、支払った上に、さらに払う余分な金。盗人に物を盗ま...
 「ぬ」で始まることわざ
「ぬ」で始まることわざ「盗人猛猛しい」の意味(語源由来・英語訳) 【ことわざ】 盗人猛猛しい 【読み方】 ぬすびとたけだけしい 【意味】 盗みや悪事を働いておきながら、ずぶとく平然としているさま。また、盗みや悪事を見咎められて居直ったり、逆に...
 「に」で始まることわざ
「に」で始まることわざ「忍の一字は衆妙の門」の意味(語源由来・類義語・英語訳) 【ことわざ】 忍の一字は衆妙の門 【読み方】 にんのいちじはしゅうみょうのもん 【意味】 忍耐はあらゆる道理に到達する入口であり、物事を成功させる基となるものだと...
 「に」で始まることわざ
「に」で始まることわざ「人間万事塞翁が馬」の意味(出典・故事・類義語) 【ことわざ】 人間万事塞翁が馬 【読み方】 にんげんばんじさいおうがうま 【意味】 人間の運命や幸不幸は予測できないということのたとえ。 【出典】 「准南子えなんじ」人間...
 「わ」で始まることわざ
「わ」で始まることわざ「和を以て貴しとなす」の意味(語源由来・出典・英語訳) 【ことわざ】 和を以て貴しとなす 【読み方】 わをもってとうとしとなす 【意味】 人々が仲良く、和合して事を行うのが最も尊いという意味。 【語源由来】 聖徳太子が制...
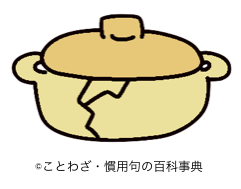 「わ」で始まることわざ
「わ」で始まることわざ「割れ鍋に綴じ蓋」の意味(語源由来・類義語・英語訳) 【ことわざ】 割れ鍋に綴じ蓋 【読み方】 われなべにとじぶた 【意味】 割れた鍋でもそれに似合う修繕した蓋があるという意味で、どんな人にもふさわしい配偶者が見つかると...
 「わ」で始まることわざ
「わ」で始まることわざ【ことわざ】 我思う、故に我在り 【読み方】 われおもう、ゆえにわれあり 【意味】 確実な知識を得るためには、いっさいの知識を疑う必要がある。外部・内部の感覚や数字上の真理も疑う。そして、最後に残るものは思索している自分...
 「わ」で始まることわざ
「わ」で始まることわざ「和して同ぜず」の意味とは?(出典・類義語・対義語・英語訳) 【ことわざ】 和して同ぜず 【読み方】 わしてどうぜず 【意味】 人と争わず仲良くするが、自分の意見はしっかり守っていてむやみに人に同調したりしないという意味...
 「わ」で始まることわざ
「わ」で始まることわざ【ことわざ】 我が物と思えば軽し笠の雪 【読み方】 わがものとおもえばかろしかさのゆき 【意味】 頭にかぶった笠に積もる雪も、自分の物だと思えば軽く感じる。苦しいことも自分の利益になると思えばそれほど気にならないという意...
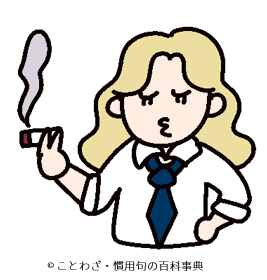 「わ」で始まることわざ
「わ」で始まることわざ【ことわざ】 若気の至り 【読み方】 わかげのいたり 【意味】 若さに任せて無分別な行動をしてしまうこと。また、その結果。「至り」は、物事の成り行きや結果の意味として使う。 【語源・由来】 若い人は経験も浅く、人間として...
 「ろ」で始まることわざ
「ろ」で始まることわざ【ことわざ】 ロバが旅に出たところで馬になって帰ってくるわけではない 【読み方】 ろばがたびにでたところでうまになってかえってくるわけではない 【意味】 知識のない者や愚かな者が旅に出ても、出発前と同じままで本質は変わら...
 「ろ」で始まることわざ
「ろ」で始まることわざ【ことわざ】 盧生の夢 【読み方】 ろせいのゆめ 【意味】 人間の一生が短く、栄枯盛衰のはかないことのたとえ。 【語源・由来】 「李泌」の「枕中記」より。中国、唐の盧生という青年が都で一旗あげようと田舎から邯鄲という都市...
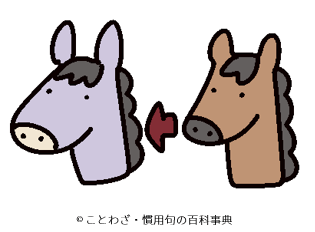 「ろ」で始まることわざ
「ろ」で始まることわざ【ことわざ】 驢事未だ去らざるに馬事到来す 【読み方】 ろじいまださらざるにばじとうらいす 【意味】 「驢」はロバの意味。一つのことが終わる前に、次のことがやってきたの意。 【語源・由来】 ロバに関することが終わらないう...
 「ろ」で始まることわざ
「ろ」で始まることわざ【ことわざ】 廬山の真面目 【読み方】 ろざんのしんめんもく 【意味】 「廬山」は、国江西省九江市南部にある山のこと。「真面目」とは、本当の姿という意味。廬山には多くの峰がそびえており、見る方向によって形が変わり、その全...
 「ろ」で始まることわざ
「ろ」で始まることわざ【ことわざ】 魯魚の誤り 【読み方】 ろぎょのあやまり 【意味】 魯の字と魚の字は形が似ていて誤りやすいが、そのように似た字を見誤ることのたとえ。 【語源・由来】 魯と魚は字の形がよく似ており、間違えやすいことから。 【...
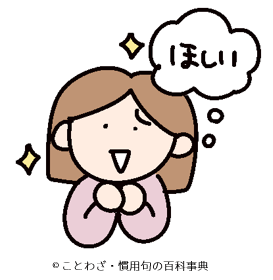 「ろ」で始まることわざ
「ろ」で始まることわざ【ことわざ】 隴を得て蜀を望む 【読み方】 ろうをえてしょくをのぞむ 【意味】 一つの望みを達すると、さらに次の望みがわいてくる。人間の欲望に限りがないこと。 【語源・由来】 中国の三国時代、魏の曹操が隴の地を得た時、部...
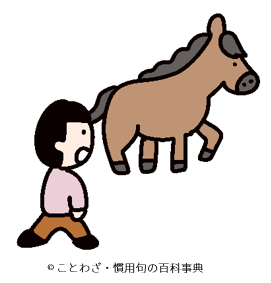 「ろ」で始まることわざ
「ろ」で始まることわざ【ことわざ】 老馬の智 【読み方】 ろうばのち 【意味】 経験を積んで、物事に練達した知恵。また、老馬にも教えを乞うほどの謙虚さが必要であるということ。 【語源・由来】 中国、春秋時代、斉の管仲が、遠征の帰途に雪の山中で...
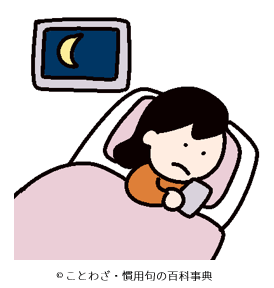 「よ」で始まることわざ
「よ」で始まることわざ【ことわざ】 宵っ張りの朝寝坊 【読み方】 よいっぱりのあさねぼう 【意味】 夜遅くまで起きていること。またその習慣のある人。よふかし。 【類義語】 ・朝寝坊の宵っ張り(あさねぼうのよいっぱり) 【英語訳】 stay u...
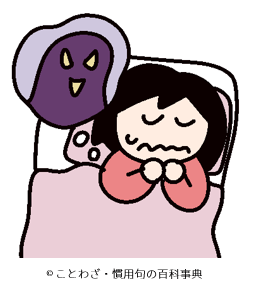 「ゆ」で始まることわざ
「ゆ」で始まることわざ【ことわざ】 夢は逆夢 【読み方】 ゆめはさかゆめ 【意味】 実際に起こることとは逆のことが夢に現れるものだという意味。悪い夢を見た時の気休めに使うことば。 【類義語】 ・八卦裏返り ・夢は嘘 ・夢は逆実 【対義語】 ・...
 「ゆ」で始まることわざ
「ゆ」で始まることわざ【ことわざ】 雪は豊年の瑞 【読み方】 ゆきはほうねんのしるし 【意味】 「瑞」とは、前兆・前ぶれの意味。大雪が降ったということは、米や麦などの収穫が多い豊作を迎える前兆だという意味。 【語源・由来】 「万葉集・三九二五...
 「ゆ」で始まることわざ
「ゆ」で始まることわざ【ことわざ】 雪と墨 【読み方】 ゆきとすみ 【意味】 物事の正反対なこと。また甚だしく相違のあることのたとえ。 【語源・由来】 真っ白な雪と真っ黒な墨が正反対であることから。 【類義語】 ・雲泥の差 ・雲泥万里 ・烏と...
 「ゆ」で始まることわざ
「ゆ」で始まることわざ【ことわざ】 行き大名の帰り乞食 【読み方】 ゆきだいみょうのかえりこじき 【意味】 旅行などで、行きには大名のように豪勢に金を使い、帰りは金がなくなって乞食のようにみじめになること。無計画に金を使って動きがとれなくなる...
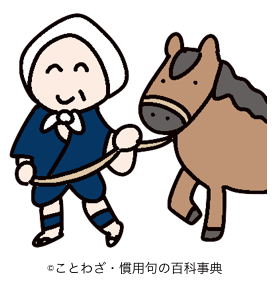 「ゆ」で始まることわざ
「ゆ」で始まることわざ「行き掛けの駄賃」の意味(語源由来・類義語・英語訳) 【ことわざ】 行き掛けの駄賃 【読み方】 ゆきがけのだちん 【意味】 ある仕事をするついでに他の仕事をして、利益を得ること。 【語源・由来】 馬子(馬をひいて人や荷物...
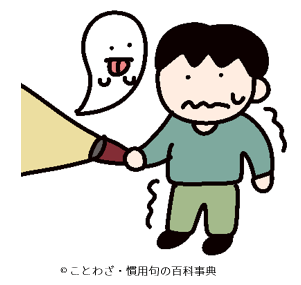 「ゆ」で始まることわざ
「ゆ」で始まることわざ【ことわざ】 幽霊の正体見たり枯れ尾花 【読み方】 ゆうれいのしょうたいみたりかれおばな 【意味】 幽霊が出るのではないかとびくびくしていると、枯れたススキの穂のようなつまらないものでも幽霊に見えたりするという意味。怖い...
 「ゆ」で始まることわざ
「ゆ」で始まることわざ【ことわざ】 幽明境を異にする 【読み方】 ゆうめいさかいをことにする 【意味】 「幽」は暗い冥土、「明」は明るい現世のこと。「境」はある部分の場所、範囲。死別すること。 【語源・由来】 あの世とこの世の境界を越えた者と...
 「ゆ」で始まることわざ
「ゆ」で始まることわざ【ことわざ】 勇将の下に弱卒無し 【読み方】 ゆうしょうのもとにじゃくそつなし 【意味】 「弱卒」とは、弱い兵士。頼りにならない部下の意味。大将が強くて勇ましければ、従う兵士もまた自然と勇敢だということ。指揮する者が優れ...
 「ゆ」で始まることわざ
「ゆ」で始まることわざ「有終の美を飾る」の意味とは?(出典・類義語・英語訳) 【ことわざ】 有終の美を飾る 【読み方】 ゆうしゅうのびをかざる 【意味】 最後まで物事をやり遂げて、しかも立派に締めくくること。 【出典】 『詩経』 【類義語】 ...
 「や」で始まることわざ
「や」で始まることわざ【ことわざ】 槍玉に挙げる 【読み方】 やりだまにあげる 【意味】 攻撃、非難の対象として責めること。「槍玉」とは、長い槍を小さな手玉のように自在にあやつることをいう。 【英語訳】 to make an example ...
 「や」で始まることわざ
「や」で始まることわざ【ことわざ】 闇夜に鉄砲 【読み方】 やみよにてっぽう 【意味】 目標の見えない暗闇で鉄砲を撃つことから、当てずっぽうにやるたとえ。さらに、向こう見ずにやることのたとえ。 【語源・由来】 「上方いろはかるた」「尾張いろは...
 「や」で始まることわざ
「や」で始まることわざ【ことわざ】 山の芋鰻になる 【読み方】 やまのいもうなぎになる 【意味】 山の芋が鰻になるように、あるものが別なものに変化することのたとえ。意外な出世をすることのたとえ。 【語源・由来】 山の芋が鰻になるようなあり得な...
 「や」で始まることわざ
「や」で始まることわざ「病膏肓に入る」の意味とは?(出典・英語訳) 【ことわざ】 病膏肓に入る 【読み方】 やまいこうこうにいる 【意味】 不治の病にかかること。転じて、ある物事に熱中してどうしようもなくなること。 【出典】 「春秋左氏伝・成...
 「や」で始まることわざ
「や」で始まることわざ【ことわざ】 藪蛇 【読み方】 やぶへび 【意味】 余計な手出しをしてかえって災いを招くたとえ。 【語源・由来】 わざわざ藪をつついて蛇を追い出し、その蛇に噛まれるということから。 【類義語】 ・草を打って蛇を驚かす ・...
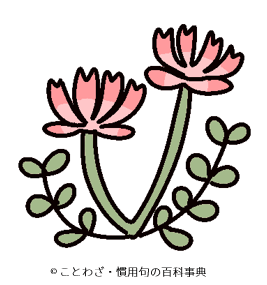 「や」で始まることわざ
「や」で始まることわざ【ことわざ】 やはり野に置け蓮華草 【読み方】 やはりのにおけれんげそう 【意味】 蓮華草のような野の花は野に咲いてこそ美しいのであって、家の中に飾っても似合わないという意味。分相応なことをしていれば間違いないという事。...
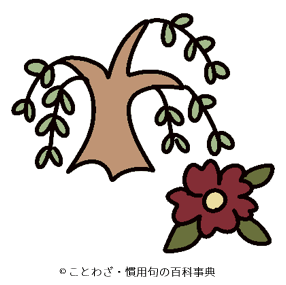 「や」で始まることわざ
「や」で始まることわざ【ことわざ】 柳は緑花は紅 【読み方】 やなぎはみどりはなはくれない 【意味】 美しい春景色の形容だが、それ以外に緑の柳や紅い花は当然のことであり、そこに人工ではない自然の真の姿があるといった意味を込めて使う。また、物事...
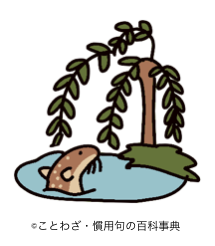 「や」で始まることわざ
「や」で始まることわざ「柳の下の泥鰌」の意味 【ことわざ】 柳の下の泥鰌 【読み方】 やなぎのしたのどじょう 【意味】 一度うまいことがあって味をしめても、同じようなことは何度も起こらないという意味。 【語源由来】 一度柳の下でたまたま泥鰌を...
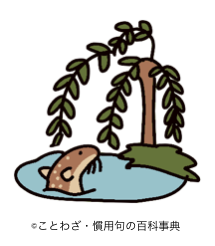 「や」で始まることわざ
「や」で始まることわざ「柳の下にいつも泥鰌はいない」の意味(類義語・対義語・英語訳) 【ことわざ】 柳の下にいつも泥鰌はいない 【読み方】 やなぎのしたにいつもどじょうはいない 【意味】 一度柳の下でたまたま泥鰌をとったからといって、同じ柳の...
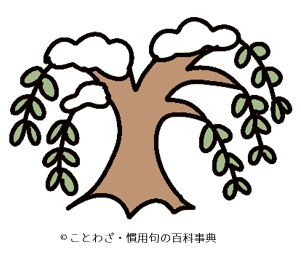 「や」で始まることわざ
「や」で始まることわざ【ことわざ】 柳に雪折れなし 【読み方】 やなぎにゆきおれなし 【意味】 柳の枝はよくしなうので、雪が積もっても振り落としてしまって折れない。そこから、柔軟なものは堅固なものより適応性があって困難に耐えるというたとえ。 ...
 「や」で始まることわざ
「や」で始まることわざ「痩せの大食い」の意味(英語訳) 【ことわざ】 痩せの大食い 【読み方】 やせのおおぐい 【意味】 やせているのに大食いの人のこと。また、やせている人のほうが思いのほか大食いの場合が多いということ。 【英語訳】 thin...
 「や」で始まることわざ
「や」で始まることわざ【ことわざ】 痩せ馬の声嚇し 【読み方】 やせうまのこえおどし 【意味】 痩せて弱々しい馬が、体に似合わず大きい声で人を脅すことから、口先だけは威勢がよいが、実力がないことの例え。 【語源・由来】 ー 【類義語】 ・痩せ...
 「や」で始まることわざ
「や」で始まることわざ【ことわざ】 痩せ馬に鞭 【読み方】 やせうまにむち 【意味】 弱いものにさらに打撃を与えることをいう。痛々しいさま。 【語源・由来】 痩せて力の弱い馬に、鞭を打ってひどい仕打ちをするさまから。 【類義語】 痩せ馬に針立...
 「や」で始まることわざ
「や」で始まることわざ【ことわざ】 安かろう悪かろう 【読み方】 やすかろうわるかろう 【意味】 値段が安ければそれだけ質が落ちるであろうという意味。安い物によい物はない。 【類義語】 ・銭は銭だけ ・安い高いは品による ・安い物は高い物 ・...
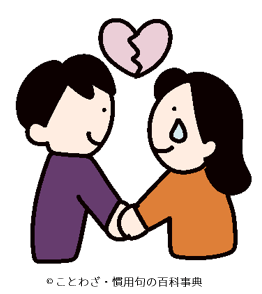 「や」で始まることわざ
「や」で始まることわざ【ことわざ】 焼け木杭に火がつく 【読み方】 やけぼっくいにひがつく 【意味】 一度縁が切れていた関係が、元に戻ることをいう。多くは、男女の関係に用いる。「焼け木杭」とは燃えさしの切り株や焼けた杭のこと。「木杭(ぼっくい...
 「や」で始まることわざ
「や」で始まることわざ【ことわざ】 焼け野の雉夜の鶴 【読み方】 やけののきぎすよるのつる 「きぎす」はキジの古名。 【意味】 親が子を思う切ない心のたとえ。 【語源・由来】 雉は自分の巣がある野が焼けだすと、身の危険をかえりみずに子を救うた...
 「や」で始まることわざ
「や」で始まることわざ【ことわざ】 焼きが回る 【読み方】 やきがまわる 【意味】 年をとるなどして、頭の回転や腕前などが衰えること。 【語源・由来】 刃物に焼き入れをするときに、火が回りすぎて焼きが強すぎると、かえって切れ味が悪くなることか...
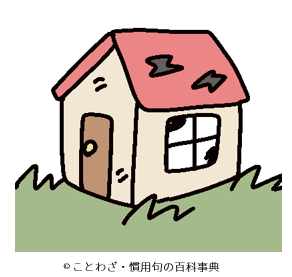 「も」で始まることわざ
「も」で始まることわざ【ことわざ】 門前雀羅を張る 【読み方】 もんぜんじゃくらをはる 【意味】 「雀羅」は雀などを捕らえる網。訪ねてくる人がなく、門の前に雀が群がり遊んでいて、網を張って捕らえられそうなほどだということ。訪ねてくる客もなく、...
 「も」で始まることわざ
「も」で始まることわざ【ことわざ】 門前市を成す 【読み方】 もんぜんいちをなす 【意味】 あたかも門の前に市場ができたかのように、人や車馬が集まってくること。名声などを慕って訪問する人が多い様子。 【語源・由来】 中国の前漢の時代の鄭崇が、...
 「も」で始まることわざ
「も」で始まることわざ【ことわざ】 諸刃の剣 【意味】 両側に刃のついた剣は敵を切ろうとして振り上げると、自分自身が怪我をすることがある。そこから、相手を傷つけると同時に自分も傷つく恐れのあるたとえ。また、一方では役立つが、一方では危険な事物...
 「も」で始まることわざ
「も」で始まることわざ【ことわざ】 物には時節 【読み方】 ものにはじせつ 【意味】 何事にも時機というものがあり、時機を外せば思うようには成功しないということ。状況判断が大切との戒めでもある。 【類義語】 ・好機逸すべからず ・事は時節 ・...
 「も」で始まることわざ
「も」で始まることわざ【ことわざ】 求めよ、さらば与えられん 【読み方】 もとめよ、さらばあたえられん 【意味】 ひたすら神に祈り求めれば、神は正しい信仰心を与えてくださるだろうという意味。転じて、積極的に努力すればよい結果が得られるというこ...
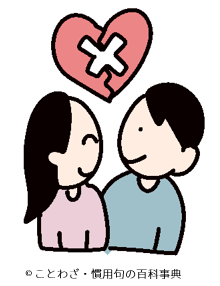 「も」で始まることわざ
「も」で始まることわざ【ことわざ】 元の鞘に収まる 【読み方】 もとのさやにおさまる 【意味】 けんかや仲たがいしていた者が、前の親しい間柄に戻る。多くは、男女の関係で用いられる。 【語源・由来】 「鞘」とは、刀や剣などの刀身の部分をおさめて...