【朝曇りは晴れ、夕曇りは雨】の意味と使い方や例文(語源由来)
「朝曇りは晴れ、夕曇りは雨」の意味(語源由来) 【ことわざ】 朝曇りは晴れ、夕曇りは雨 【読み方】 あさくもりははれ、ゆうぐもりはあめ 【意味】 朝曇っていると、その後は晴れ、夕方曇っていると、翌日は雨が降る。 【語源・...
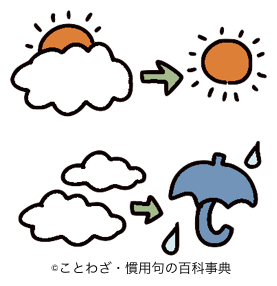 「あ」で始まることわざ
「あ」で始まることわざ「朝曇りは晴れ、夕曇りは雨」の意味(語源由来) 【ことわざ】 朝曇りは晴れ、夕曇りは雨 【読み方】 あさくもりははれ、ゆうぐもりはあめ 【意味】 朝曇っていると、その後は晴れ、夕方曇っていると、翌日は雨が降る。 【語源・...
 「あ」で始まることわざ
「あ」で始まることわざ「朝ぎりは日中晴れ」の意味(語源由来) 【ことわざ】 朝ぎりは日中晴れ 【読み方】 あさぎりはにっちゅうはれ 【意味】 その日一日晴天ということ。 【語源・由来】 夜、風が弱くよく晴れると、朝にかけて地面が冷え霧が生じる...
 「あ」で始まることわざ
「あ」で始まることわざ「朝露が降りると晴れ」の意味(語源由来・類義語) 【ことわざ】 朝露が降りると晴れ 【読み方】 あさつゆがおりるとはれ 【意味】 朝露は晴天のしるしであること。 【語源・由来】 高気圧圏内で良く晴れて風のない夜に放射冷却...
 「あ」で始まることわざ
「あ」で始まることわざ「朝雨博奕裸の基」の意味(語源由来・類義語) 【ことわざ】 朝雨博奕裸の基 【読み方】 あさあめばくちはだかのもと 【意味】 朝の雨が降っていてもしばらくすればやみ、着物を脱ぎたいほどの天気になる。 【語源・由来】 着物...
 「あ」で始まることわざ
「あ」で始まることわざ「朝雨は女の腕まくり」の意味(語源由来・類義語) 【ことわざ】 朝雨は女の腕まくり 【読み方】 あさあめはおんなのうでまくり 【意味】 朝の雨がすぐにやむように、女が腕まくりをして強がるのも恐れることはないということ。 ...
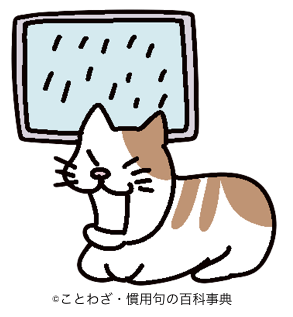 「あ」で始まることわざ
「あ」で始まることわざ「秋の雨が降れば猫の顔が三尺になる」の意味(語源由来・類義語) 【ことわざ】 秋の雨が降れば猫の顔が三尺になる 【読み方】 あきのあめがふればねこのかおがさんじゃくになる 【意味】 秋は晴れた日より雨の日の方があたたかい...
 「あ」で始まることわざ
「あ」で始まることわざ「朝虹はその日の洪水」の意味(語源由来) 【ことわざ】 朝虹はその日の洪水 【読み方】 あさにじはそのひのこうずい 【意味】 朝に虹がかかると、その日は大雨になる。 【語源・由来】 日本は、西から天気が崩れることが多い。...
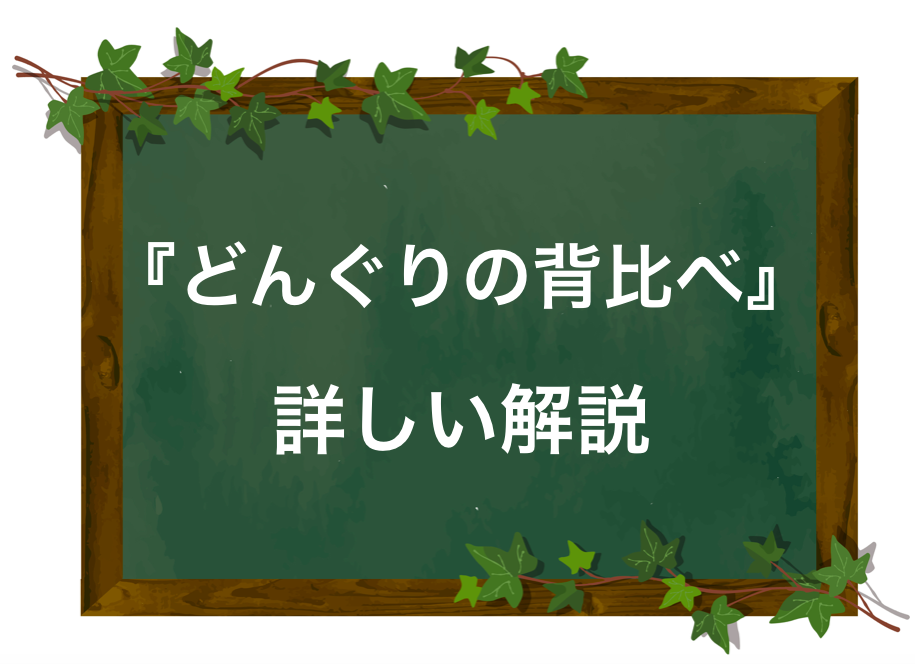 ことわざ・慣用句の詳しい解説
ことわざ・慣用句の詳しい解説「どんぐりの背比べ」という言葉を聞いたことがありますか? どんぐりをコマにして遊んだことがあるけれども、並べて背比べなんてしたことがないよという方・・・、「どんぐりの背比べ」は遊びを表現した言葉ではありません。 それでは...
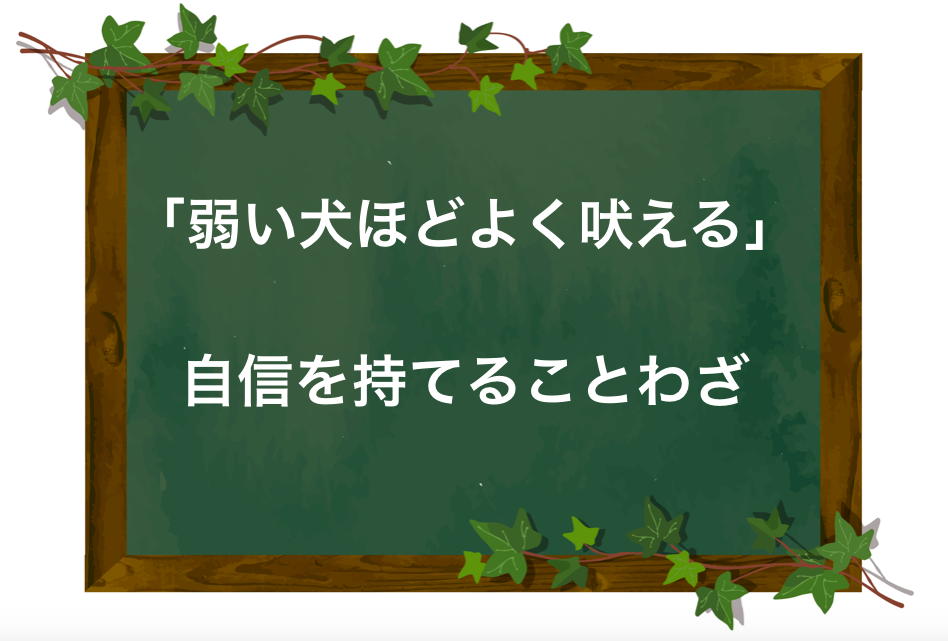 ことわざ・慣用句の詳しい解説
ことわざ・慣用句の詳しい解説「弱い犬ほどよく吠える」ということわざを耳にしたことがあるでしょうか? 「弱い犬ほどよく吠える」のただしい意味をご存じでしょうか? 「弱い犬ほどよく吠える」の意味を知り、弱い犬の立場から物事を考えると、生きることや働くこ...
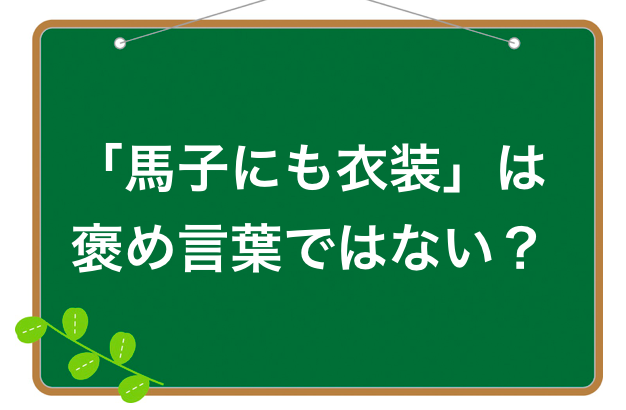 ことわざ・慣用句の詳しい解説
ことわざ・慣用句の詳しい解説みなさんは、「馬子にも衣装」という言葉をご存じでしょうか。 この言葉は、「まごにもいしょう」と読みます。 という方がいらっしゃるかもしれません。 自分の孫はどんな服を着ても世界一かわいい、孫を目に入れても痛くない親ばかな...
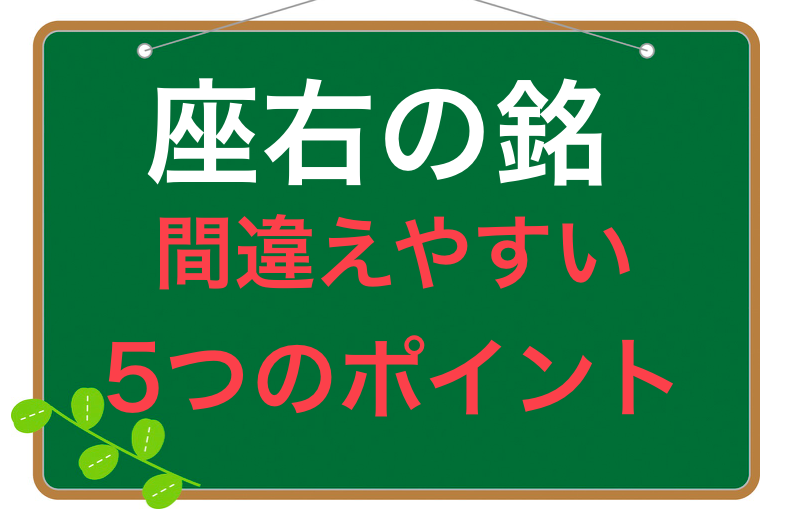 ことわざ・慣用句の詳しい解説
ことわざ・慣用句の詳しい解説ビジネスやスポーツで成功した人がたびたびインタビューで尋ねられる「座右の銘」。 新学期に自己紹介をするときに「僕の座右の銘は・・・」なんていう人も多いのではないでしょうか。 胸に秘めた「座右の銘」のおかげで、挫折すること...
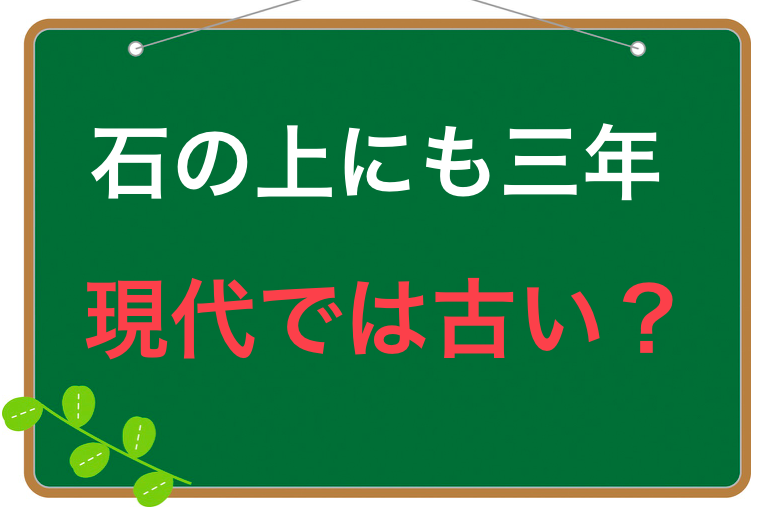 ことわざ・慣用句の詳しい解説
ことわざ・慣用句の詳しい解説「石の上にも三年」、よく耳にすることわざじゃないですか? 入社した会社が合わなくて辞めたいと思っているとき、 といわれたり、 という風に使います。 ここからは、石の上にも三年の意味や語源を見ていきましょう。 「石の上にも...
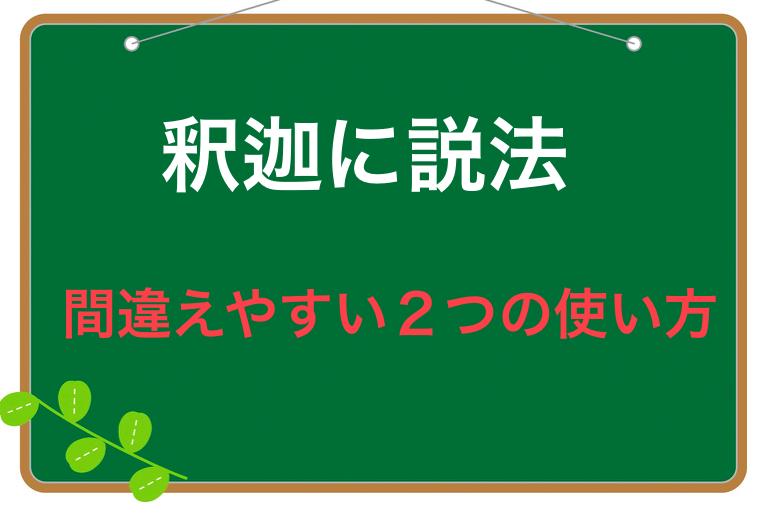 ことわざ・慣用句の詳しい解説
ことわざ・慣用句の詳しい解説突然ですが、みなさんは「釈迦に説法」という言葉を聞いたことがありますか? といった風に使います。 聞いたことがありましたか? 聞いたことがある、知っているよという方には「釈迦に説法」かもしれませんが、この言葉の意味をご紹...
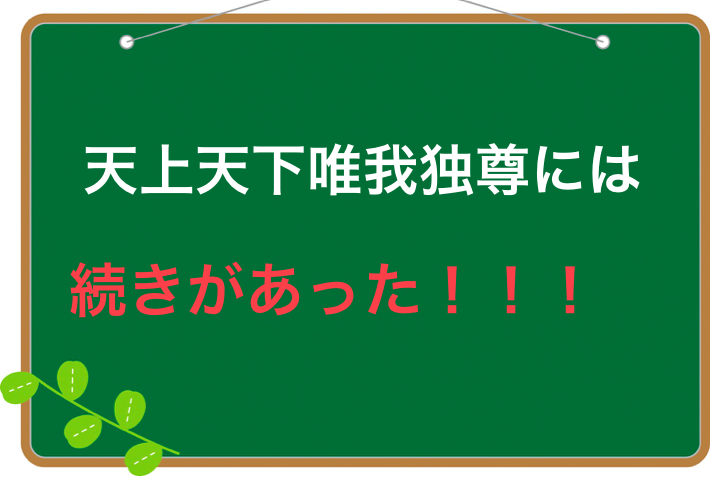 ことわざ・慣用句の詳しい解説
ことわざ・慣用句の詳しい解説皆さんは、「天上天下唯我独尊」という言葉をご存じでしょうか。 ちなみにこちらは、「てんじょうてんげゆいがどくそん」と読みます。 バスケットボール部員を描いた伝説的有名漫画の流川何某君が、N長君に「天上天下唯我独尊」なあい...
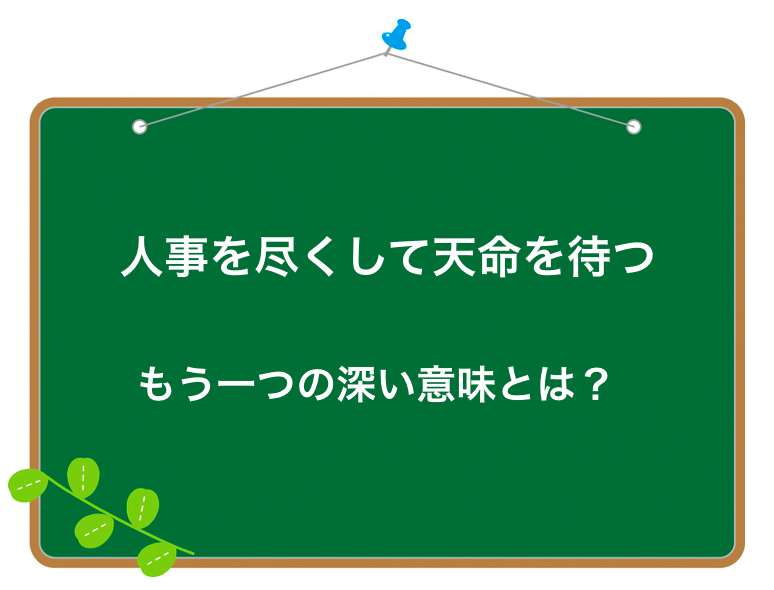 ことわざ・慣用句の詳しい解説
ことわざ・慣用句の詳しい解説「人事を尽くして天命を待つ」ということわざを聞いたことがありますか? というような会話を耳にしたことがある方が結構たくさんいらっしゃるのではないでしょうか。 ここからは、皆さんご存じかもしれませんが、「人事を尽くして天命...
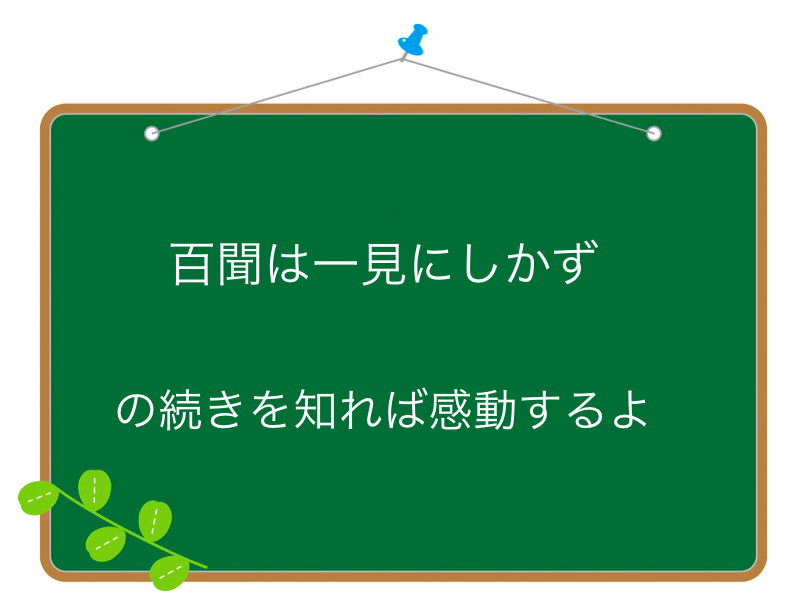 ことわざ・慣用句の詳しい解説
ことわざ・慣用句の詳しい解説「百聞は一見にしかず」ということわざ。聞いたことがあるよという人は多いと思います。けれども、この言葉に続きがあることはご存じでしょうか? ここでは「百聞は一見にしかず」の意味とその続きを紹介します。 「百聞は一見にしかず...
 ことわざ・慣用句の詳しい解説
ことわざ・慣用句の詳しい解説突然ですが・・・、 という会話を聞いたことはないでしょうか? 「的を射る」、「的を得る」一体どちらが正しいのでしょうか。 両者に違いはあるのでしょうか。そもそも「的を射る」ってどういう意味なんだろうと思う方もいるかもしれ...
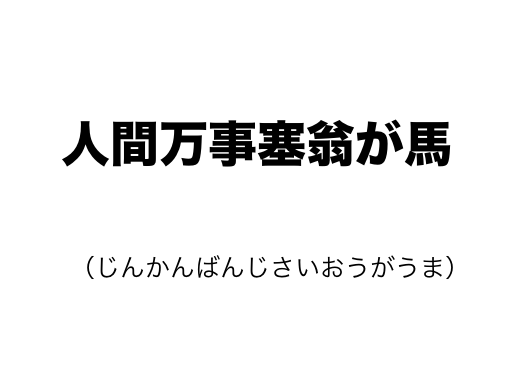 ことわざ・慣用句の詳しい解説
ことわざ・慣用句の詳しい解説人間万事塞翁が馬ということわざを聞いたことがありますか? そういえば、「気にするなよ。人間万事塞翁が馬というじゃないか。きっと次はいいことがあるさ。」と友達に言われたことがあるな。 意味は分からなかったけれども、なんだか...
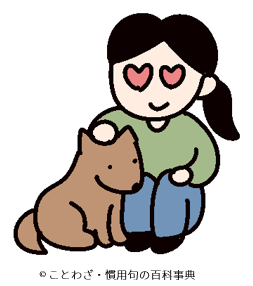 「わ」で始まることわざ
「わ」で始まることわざ【ことわざ】 我を愛する者は我が犬をも愛す 【読み方】 われをあいするものはわがいぬをもあいす 【意味】 真剣に人を好きになると、その人の家族やその他すべてに好感がもてるということ。 「我を愛する者は我が犬をも愛す」の使...
 「わ」で始まることわざ
「わ」で始まることわざ【ことわざ】 我が家に勝る所無し 【読み方】 わがやにまさるところなし 【意味】 自分の家ほどくつろげる場所はないということ。 【語源・由来】 アメリカの劇作家ジョン・ペインの叙情詩「ホーム・スイート・ホーム」より。 「...
 「り」で始まることわざ
「り」で始まることわざ【ことわざ】 悋気は女の七つ道具 【読み方】 りんきはおんなのななつどうぐ 【意味】 焼きもちを焼くことは女の武器のひとつであり、男性を操縦する武器ともなる。 【類義語】 ・悟気嫉妬は女の常 「悋気は女の七つ道具」の使い...
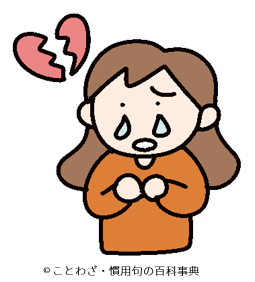 「り」で始まることわざ
「り」で始まることわざ【ことわざ】 悋気嫉妬も正直の心より起こる 【読み方】 りんきしっともしょうじきのこころよりおこる 【意味】 やきもちをやいたり嫉妬をするのも、相手を心の底から思っているからであっていい加減な気持ちではないということ。 ...
 「り」で始まることわざ
「り」で始まることわざ【ことわざ】 離別の後の悋気 【読み方】 りべつののちのりんき 【意味】 離婚した夫婦のどちらかが、あとから嫉妬することをいった言葉。未練の深いことにたとえる。 「離別の後の悋気」の使い方 「離別の後の悋気」の例文 もう...
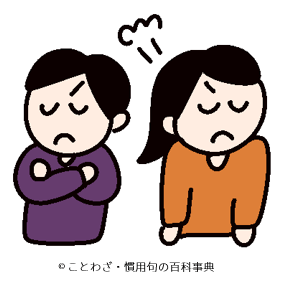 「よ」で始まることわざ
「よ」で始まることわざ【ことわざ】 良い仲の小いさかい 【読み方】 よいなかのこいさかい 【意味】 親密な間がらの者や仲の良い者には、かえって小さな争いごとがあるということ 【類義語】 ・思う余りの小諍い ・思う仲の小諍い ・思う仲のつづり諍...
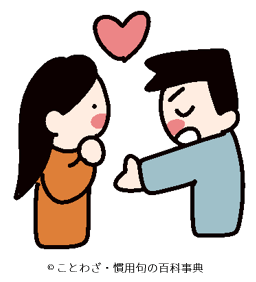 「よ」で始まることわざ
「よ」で始まることわざ【ことわざ】 弱気が美人を得た例はない 【読み方】 よわきがびじんをえたためしはない 【意味】 美人を得るには押しが肝心ということ。 「弱気が美人を得た例はない」の使い方 「弱気が美人を得た例はない」の例文 身の程知らず...
 「や」で始まることわざ
「や」で始まることわざ【ことわざ】 焼き餅焼くとて手を焼くな 【読み方】 やきもちやくとててをやくな 【意味】 嫉妬も度を過ごせば災いを招くから、ほどほどにせよという戒め。 【類義語】 ・焼き餅焼くなら狐色 「焼き餅焼くとて手を焼くな」の使い...
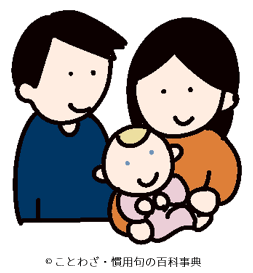 「も」で始まることわざ
「も」で始まることわざ【ことわざ】 物種は盗むとも人種は盗まれず 【読み方】 ものだねはぬすむともひとだねはぬすまれず 【意味】 作物の種を盗むことができても人の子種は盗めない。血筋は争えないもので生まれた子は親に似てしまうものだということ。...
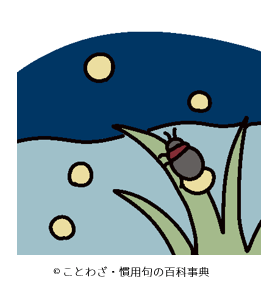 「み」で始まることわざ
「み」で始まることわざ【ことわざ】 水に燃えたつ蛍 【読み方】 みずにもえたつほたる 【意味】 水の上を燃えんばかりに光りつつ飛ぶ蛍。「水」と「見ず」をかけ、「燃えたつ」に、感情が激しくわき上がる意をかけて、相手に会うことなく恋い焦がれること...
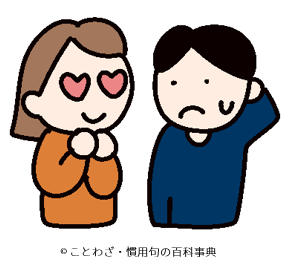 「ほ」で始まることわざ
「ほ」で始まることわざ【ことわざ】 惚れられたが不祥 【読み方】 ほれられたがふしょう 【意味】 どうしても好きになれない相手に惚れられてしまうという不幸も、前世からの因縁と思ってあきらめるしかないということ。 「惚れられたが不祥」の使い方 ...
 「ほ」で始まることわざ
「ほ」で始まることわざ【ことわざ】 惚れた病に薬なし 【読み方】 ほれたやまいにくすりなし 【意味】 恋患いは病気のようなものであるが治す薬はなく、どうしようもないということ。 【類義語】 ・恋の病に薬なし ・恋の山には孔子の倒れ ・四百四病...
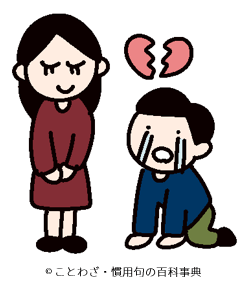 「ひ」で始まることわざ
「ひ」で始まることわざ「美女は命を断つ斧」の意味(類義語) 【ことわざ】 美女は命を断つ斧 【読み方】 びじょはいのちをたつおの 【意味】 美女の色香に溺れると、不摂生を招いて寿命を縮めたり身を滅ぼしたりすることになるので、美女は男の寿命を縮...
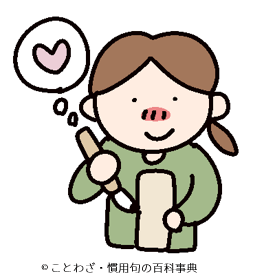 「ひ」で始まることわざ
「ひ」で始まることわざ「貧の盗みに恋の歌」の意味 【ことわざ】 貧の盗みに恋の歌 【読み方】 ひんのぬすみにこいのうた 【意味】 貧しければ人の物を盗むようになり、恋をすれば歌を詠むようになるように、人は必要に迫られればどんなことでもすること...
 「ひ」で始まることわざ
「ひ」で始まることわざ「日陰の豆も時が来ればはぜる」の意味(類義語) 【ことわざ】 日陰の豆も時が来ればはぜる 【読み方】 ひかげのまめもときがくればはぜる 【意味】 日当たりの悪い場所で育った豆でも、時が来れば自然とさやからはじけ出るように...
 「に」で始まることわざ
「に」で始まることわざ「憎い憎いは可愛いの裏」の意味(類義語) 【ことわざ】 憎い憎いは可愛いの裏 【読み方】 にくいにくいはかわいいのうら 【意味】 男女間で、憎いという気持ちは可愛いと思う気持ちの裏返しで、可愛いと思うからこそ憎いと思うの...
 「な」で始まることわざ
「な」で始まることわざ「無くてぞ人は恋しかりける」の意味 【ことわざ】 無くてぞ人は恋しかりける 【読み方】 なくてぞひとはこいしかりける 【意味】 付き合っていたり、一緒に暮らしている間はそれほど思わなかった相手でも、いざ別れたり死別したり...
 「と」で始まることわざ
「と」で始まることわざ「遠ざかる程思いが募る」の意味(類義語) 【ことわざ】 遠ざかる程思いが募る 【読み方】 とおざかるほどおもいがつのる 【意味】 人を思う気持ちは、遠く離れたり仲を引き裂かれたりすると、かえって強くなることをいう。 【類...
 「と」で始まることわざ
「と」で始まることわざ「遠くなれば薄くなる」の意味(類義語) 【ことわざ】 遠くなれば薄くなる 【読み方】 とおくなればうすくなる 【意味】 親しかった者でも、遠く離れてしまうと親しみが薄れていくということ。 【類義語】 ・去る者は日日に疎し...
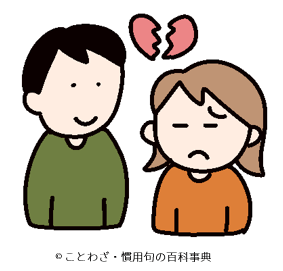 「ち」で始まることわざ
「ち」で始まることわざ「近惚れの早飽き」の意味(類義語) 【ことわざ】 近惚れの早飽き 【読み方】 ちかぼれのはやあき 【意味】 熱しやすく冷めやすいこと。ほれっぽい人は飽きやすいということ。 【類義語】 ・恋いた程飽いた ・惚れた腫れたは当...
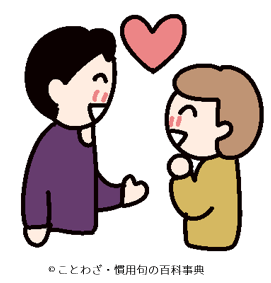 「そ」で始まることわざ
「そ」で始まることわざ「添わぬうちが花」の意味(類義語) 【ことわざ】 添わぬうちが花 【読み方】 そわぬうちがはな 【意味】 家庭をもつと互いの欠点が目につくもので、楽しいのは一緒になるまでであるということ。 【類義語】 ・待つうちが花 ・...
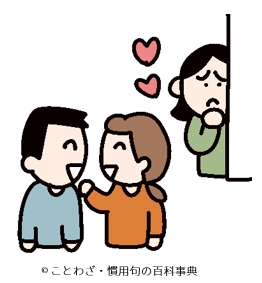 「せ」で始まることわざ
「せ」で始まることわざ「堰かれて募る恋の情」の意味(類義語) 【ことわざ】 堰かれて募る恋の情 【読み方】 せかれてつのるこいのじょう 【意味】 誰かに恋をする思いは、他人から邪魔をされるとますます激しくなるものであるということ。 【類義語】...
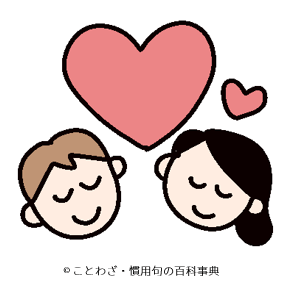 「す」で始まることわざ
「す」で始まることわざ「好いた水仙好かれた柳」の意味 【ことわざ】 好いた水仙好かれた柳 【読み方】 すいたすいせんすかれたやなぎ 【意味】 相思相愛の男女の様子のたとえ。 「好いた水仙好かれた柳」の解説 「好いた水仙好かれた柳」の使い方 「...
 「そ」で始まることわざ
「そ」で始まることわざ【ことわざ】 賎に恋なし 【読み方】 しずにこいなし 【意味】 恋は貴人のすることであって、身分の低い者がすることではないということ。 【対義語】 ・恋に上下の隔てなし ・低いも高いも色の道 「賎に恋なし」の使い方 「賎...
 「さ」で始まることわざ
「さ」で始まることわざ「山路が笛」の意味(語源由来) 【ことわざ】 山路が笛 【読み方】 さんろがふえ 【意味】 山路が吹いた草刈り笛。恋心を寄せる道具とされる。 「山路が笛」の解説 「山路が笛」の使い方 「山路が笛」の例文 山路が笛を吹いて...
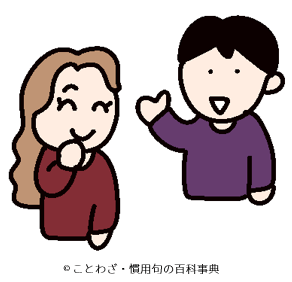 「ふ」で始まることわざ
「ふ」で始まることわざ「触れなば落ちん風情」の意味 【ことわざ】 触れなば落ちん風情 【読み方】 ふれなばおちんふぜい 【意味】 男が誘えばすぐに応じそうな様子であること。色っぽい女のさま。 「触れなば落ちん風情」の解説 「触れなば落ちん風情...
 「さ」で始まることわざ
「さ」で始まることわざ「魚は海に幾らでもいる」の意味 【ことわざ】 魚は海に幾らでもいる 【読み方】 さかなはうみにいくらでもいる 【意味】 機会を一度逃がしても落胆してはいけないということ。 「魚は海に幾らでもいる」の解説 「魚は海に幾らで...
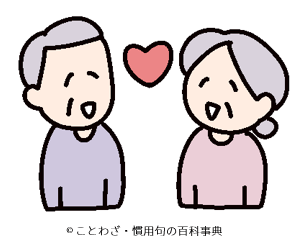 「こ」で始まることわざ
「こ」で始まることわざ「五十なれば五十の縁あり」の意味 【ことわざ】 五十なれば五十の縁あり 【読み方】 ごじゅうなればごじゅうのえんあり 【意味】 恋や縁談には年齢による制限はないこと。 「五十なれば五十の縁あり」の解説 「五十なれば五十の...
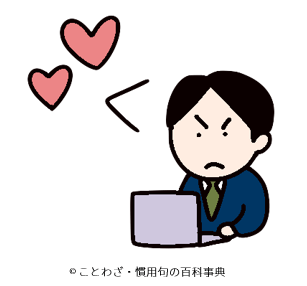 「こ」で始まることわざ
「こ」で始まることわざ「恋をするより徳をしろ」の意味(類義語) 【ことわざ】 恋をするより徳をしろ 【読み方】 こいをするよりとくをしろ 【意味】 先行きのわからない不安定な恋にうつつをぬかすよりは、世の中に役立つことを行なう方が有益であり確...
 「こ」で始まることわざ
「こ」で始まることわざ「恋の山には孔子の倒れ」の意味(類義語) 【ことわざ】 恋の山には孔子の倒れ 【読み方】 こいのやまにはくじのたおれ 【意味】 孔子のような聖人でさえも色恋に迷うことがあり、その結果、政治や人生に失敗することがあるという...
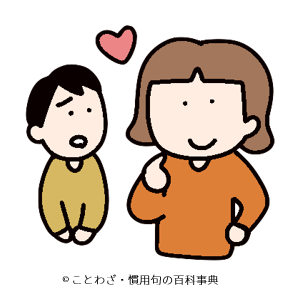 「こ」で始まることわざ
「こ」で始まることわざ「恋の道には女が賢しい」の意味(語源由来) 【ことわざ】 恋の道には女が賢しい 【読み方】 こいのみちにはおんながさかしい 【意味】 恋に関しては、男よりも女の方が知恵が働き、判断力や行動力においてすぐれているということ...
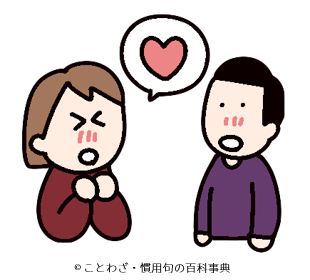 「こ」で始まることわざ
「こ」で始まることわざ「恋と願いはよくせよ」の意味 【ことわざ】 恋と願いはよくせよ 【読み方】 こいとねがいはよくせよ 【意味】 恋をするならば大胆に行い、望みを抱くならば大きく抱く必要があるということ。 「恋と願いはよくせよ」の解説 「恋...
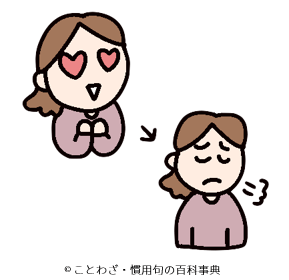 「こ」で始まることわざ
「こ」で始まることわざ「恋いた程飽いた」の意味 【ことわざ】 恋いた程飽いた 【読み方】 こいたほどあいた 【意味】 恋が激しければ激しいほど、其の分早く燃焼してしまい飽きてしまうのも早いということ。 「恋いた程飽いた」の解説 「恋いた程飽い...
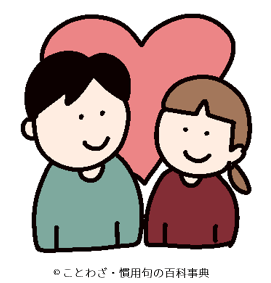 「こ」で始まることわざ
「こ」で始まることわざ「恋路は縁のもの」の意味(語源由来) 【ことわざ】 恋路は縁のもの 【読み方】 こいじはえんのもの 【意味】 男女が知りあったり一緒になったりすること。 【語源・由来】 恋が実ったり生まれたりするのは、二人の間に不思議な...
 「こ」で始まることわざ
「こ」で始まることわざ「恋に師匠なし」の意味 【ことわざ】 恋に師匠なし 【読み方】 こいにししょうなし 【意味】 恋の道は人に教えられなくても、時が来れば誰もが自然と覚えるものであるということ。 「恋に師匠なし」の解説 「恋に師匠なし」の使...
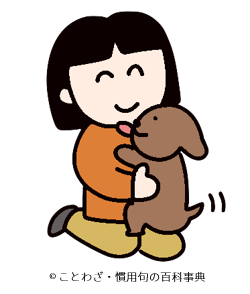 「か」で始まることわざ
「か」で始まることわざ「叶わぬ恋に心を尽くすより犬猫を飼え」の意味 【ことわざ】 叶わぬ恋に心を尽くすより犬猫を飼え 【読み方】 かなわぬこいにこころをつくすよりいぬねこをかえ 【意味】 叶わぬ恋にいろいろ思い悩んで心をわずらうより、飼い主の...
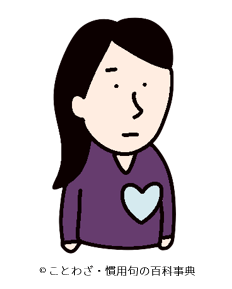 「か」で始まることわざ
「か」で始まることわざ「顔に似ぬ心」の意味 【ことわざ】 顔に似ぬ心 【読み方】 かおににぬこころ 【意味】 美しい顔をしているが心は冷たい人はいるもので、 鬼のような顔をしていても心の良い人はおり、顔と心は一致しないものだということ。 「顔...
 「お」で始まることわざ
「お」で始まることわざ「女は目の天国、財布の煉獄、魂の地獄」の意味 【ことわざ】 女は目の天国、財布の煉獄、魂の地獄 【読み方】 おんなはめのてんごく、さいふのれんごく、たましいのじごく 【意味】 女性は美しく、見ている分には素晴らしいが、付...
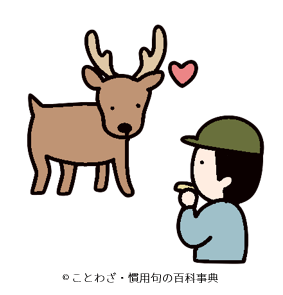 「お」で始まることわざ
「お」で始まることわざ「女の足駄にて造れる笛には秋の鹿寄る」の意味(語源由来) 【ことわざ】 女の足駄にて造れる笛には秋の鹿寄る 【読み方】 おんなのあしだにてつくれるふえにはあきのしかよる 【意味】 女の色香の魅力は強烈であり、男はその魅力...
 「お」で始まることわざ
「お」で始まることわざ「思うに別れて思わぬに添う」の意味 【ことわざ】 思うに別れて思わぬに添う 【読み方】 おもうにわかれておもうにそう 【意味】 好きな人とは結ばれず、好きでもない人とは結ばれること。恋は思い通りにならないということ。 「...
 「お」で始まることわざ
「お」で始まることわざ「鬼の女房に鬼神がなる」の意味(類義語) 【ことわざ】 鬼の女房に鬼神がなる 【読み方】 おにのにょうぼうにきじんがなる 【意味】 鬼のような冷酷な夫には、それと釣り合う同じような女が女房になるということ。似たもの夫婦の...
 「う」で始まることわざ
「う」で始まることわざ「浮気と乞食は止められぬ」の意味 【ことわざ】 浮気と乞食は止められぬ 【読み方】 うわきとこじきはやめられぬ 【意味】 浮気も乞食も一度その味をしめるとやめられないということ。悪癖であってもその誘惑から抜けられないこと...
 「い」で始まることわざ
「い」で始まることわざ「いらつは恋の癖」の意味 【ことわざ】 いらつは恋の癖 【読み方】 いらつはこいのくせ 【意味】 恋をしていると、次に恋人に会うまでの時間が非常に長く感じられて、いらいらしたり、あるいは、恋人に会いたくても思うように会え...
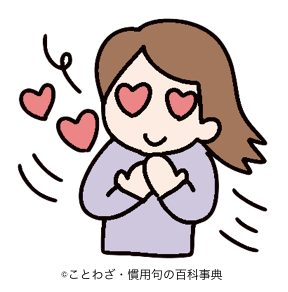 「あ」で始まることわざ
「あ」で始まることわざ「網の目にさえ恋風がたまる」の意味 【ことわざ】 網の目にさえ恋風がたまる 【読み方】 あみのめにさえこいかぜがたまる 【意味】 綱の目には普通、風は吹き抜けてたまったりすることはないが、恋の風なら通り抜けることなくたま...
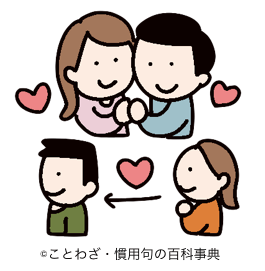 「あ」で始まることわざ
「あ」で始まることわざ「相惚れ自惚れ片惚れ岡惚れ」の意味(語源由来・類義語) 【ことわざ】 相惚れ自惚れ片惚れ岡惚れ 【読み方】 あいぼれうぬぼれかたぼれおかぼれ 【意味】 人が誰かを好きになるのは、それぞれ様々であるということ。 【語源・由...
 「あ」で始まることわざ
「あ」で始まることわざ「愛想尽かしは金から起きる」の意味(類義語) 【ことわざ】 愛想尽かしは金から起きる 【読み方】 あいそづかしはかねからおきる 【意味】 女が男につれなくなるのは金銭が原因である場合が多いという意味。 【類義語】 ・金の...
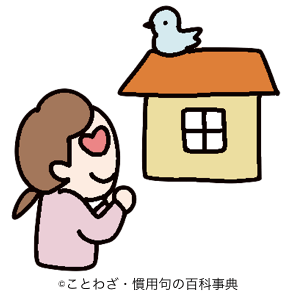 「あ」で始まることわざ
「あ」で始まることわざ「愛、屋烏に及ぶ」の意味(類義語・対義語) 【ことわざ】 愛、屋烏に及ぶ 【読み方】 あい、おくうにおよぶ 【意味】 人を愛すると、その愛する人が住んでいる家の屋根に留まっている烏をも愛するようになるように、愛する相手自...
 「い」で始まることわざ
「い」で始まることわざ「一生添うとは男の習い」の意味 【ことわざ】 一生添うとは男の習い 【読み方】 いっしょうそうとはおとこのならい 【意味】 結婚して一生君と添い遂げるというのは、男性が女性を口説く時の決まり文句であるということ。 「一生...
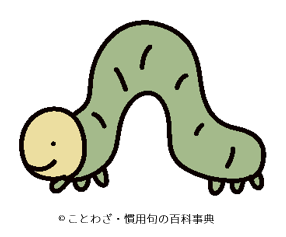 「せ」で始まることわざ
「せ」で始まることわざ「尺蠖の屈するは伸びんがため」の意味(出典・語源由来) 【ことわざ】 尺蠖の屈するは伸びんがため 【読み方】 せっかくのくっするはのびんがため 【意味】 将来の成功のために一時の不遇に耐えることのたとえ。 【出典】 「易...
 「わ」で始まることわざ
「わ」で始まることわざ【ことわざ】 禍も三年経てば用に立つ 【読み方】 わざわいもさんねんたてばようにたつ 【意味】 災害のようなものでも、三年も時がたつと何かの役に立つ。あるいは幸福の原因になるという意味。不用なものはないというたとえ。 【...
 「ろ」で始まることわざ
「ろ」で始まることわざ【ことわざ】 櫓三年に棹八年 【読み方】 ろさんねんにさおはちねん 【意味】 櫓が便いこなせるようになるには三年かかり、棹ともなれば八年の修業を要するということ。 【類義語】 ・櫂は三年櫓は三月 ・首振り三年ころ八年 ・...
 「ろ」で始まることわざ
「ろ」で始まることわざ【ことわざ】 櫓櫂の立たぬ海もなし 【読み方】 ろかいのたたぬうみもなし 【意味】 どんなに困難なことでも努力すればなんとかなるものだというたとえ。 【語源・由来】 どんなに広い海でも櫓や櫂が使えないということはない。同...
 「る」で始まることわざ
「る」で始まることわざ【ことわざ】 瑠璃の光も磨きから 【読み方】 るりのひかりもみがきから 【意味】 瑠璃が美しいのは磨くからである。素質があっても修練を積まなければ大成しないことのたとえ。 「瑠璃の光も磨きから」の使い方 「瑠璃の光も磨き...
 「り」で始まることわざ
「り」で始まることわざ【ことわざ】 利は天より来たらず 【読み方】 りはてんよりきたらず 【意味】 利益は、天から降ってくるものではない。自らが努力して得るしかないということ。 【出典】 『塩鉄論』 「利は天より来たらず」の使い方 「利は天よ...
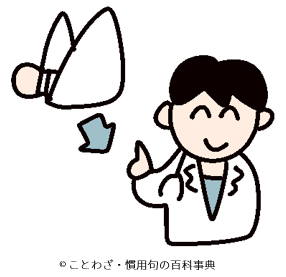 「み」で始まることわざ
「み」で始まることわざ【ことわざ】 三度肘を折って良医となる 【読み方】 みたびひじをおってりょういとなる 【意味】 自分の肘を何度も折ることで苦痛を味わい、治療する経験を積んだ後に、はじめて優れた医師になれるという意味。 「三度肘を折って良...
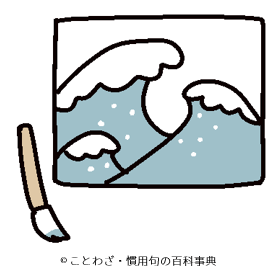 「ほ」で始まることわざ
「ほ」で始まることわざ【ことわざ】 ぽつぽつ三年波八年 【読み方】 ぽつぽつさんねんなみはちねん 【意味】 日本画ではぽつぽつした苔が描けるようになるにも三年の修業が必要で、波だと八年もかかるということ。日本画の難しさを言った言葉。 【類義語...
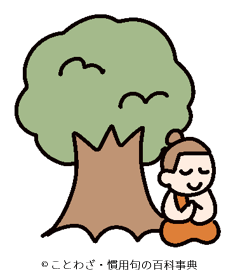 「ほ」で始まることわざ
「ほ」で始まることわざ【ことわざ】 仏も昔は凡夫なり 【読み方】 ほとけもむかしはぼんぷなり 【意味】 釈迦も最初は煩悩に苦しむ普通の人間だったが、修行を積み重ねることによって悟りを開いた。そこから、誰でも精進すれば仏になれるという教え。 「...
 「ほ」で始まることわざ
「ほ」で始まることわざ【ことわざ】 細き流れも大河となる 【読み方】 ほそきながれもたいがとなる 【意味】 小さな川がたくさん集まれば大きな川になるように、小さな努力でも長く続けていれば、やがて大きな成果を得ることができることのたとえ。 【類...
 「は」で始まることわざ
「は」で始まることわざ「肺肝を砕く」の意味(語源由来・類義語) 【ことわざ】 肺肝を砕く 【読み方】 はいかんをくだく 【意味】 心力のあるかぎりを尽くして考える。心を尽くす。非常に苦心する。 【語源・由来】 杜甫の「垂老別」より。「肺肝」は...
 「つ」で始まることわざ
「つ」で始まることわざ「釣瓶縄井桁を断つ」の意味(語源由来) 【ことわざ】 釣瓶縄井桁を断つ 【読み方】 つるべなわいげたをたつ 【意味】 微力でも根気良く続ければ大きな成果を得ることができるというたとえ。 【語源・由来】 井戸の井桁が、水を...
 「た」で始まることわざ
「た」で始まることわざ「玉琢かざれば器を成さず」の意味(出典・類義語) 【ことわざ】 玉琢かざれば器を成さず 【読み方】 たまみがかざればうつわをなさず 【意味】 生まれつきすぐれた才能を有していても、学問や修養を積まなければ立派な人間になる...
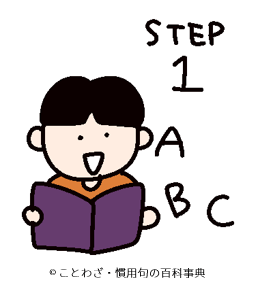 「た」で始まることわざ
「た」で始まることわざ「高きに登るは必ず低きよりす」の意味(出典) 【ことわざ】 高きに登るは必ず低きよりす 【読み方】 たかきにのぼるはかならずひくきよりす 【意味】 物事の進行には一定の順序があり、手近な所から始めねばならないということ。...
 「た」で始まることわざ
「た」で始まることわざ「斃れて後已む」の意味(出典・類義語) 【ことわざ】 斃れて後已む 【読み方】 たおれてのちやむ 【意味】 死ぬまで一生懸命努力して、途中でやめることをしないということ。 【出典】 『礼記』「表記」 【類義語】 ・死して...
 「せ」で始まることわざ
「せ」で始まることわざ「生は難く死は易し」の意味 【ことわざ】 生は難く死は易し 【読み方】 せいはかたくしはやすし 【意味】 苦しみに耐えて生きるのは、苦しみに耐えられず死を選ぶよりもむずかしい。 「生は難く死は易し」の解説 「生は難く死は...
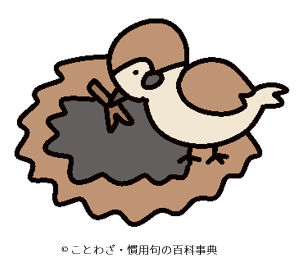 「す」で始まることわざ
「す」で始まることわざ「雀の巣も構うに溜まる」の意味 【ことわざ】 雀の巣も構うに溜まる 【読み方】 すずめのすもくうにたまる 【意味】 雀が材料を少しずつ運んできて巣を作り上げるように、少しずつ貯蓄をしても積もり積もれば大きな額になるという...
 「し」で始まることわざ
「し」で始まることわざ「上手昔より上手ならず」の意味(類義語) 【ことわざ】 上手昔より上手ならず 【読み方】 じょうずむかしよりじょうずならず 【意味】 何事においても始めから上手な者はいるわけではなく、それぞれに苦労と努力を重ねた結果であ...
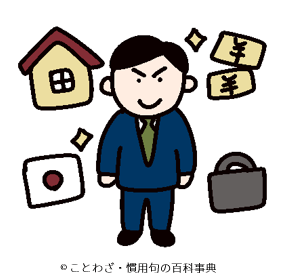 「し」で始まることわざ
「し」で始まることわざ「修身斉家治国平天下」の意味(出典) 【ことわざ】 修身斉家治国平天下 【読み方】 しゅうしんせいかちこくへいてんか 【意味】 自分の行ないを正しくし、家庭もととのえ、国家を治め、天下を平らかにする。儒教においてもっとも...
 「さ」で始まることわざ
「さ」で始まることわざ「山中の賊を破るは易く心中の賊を破るは難し」の意味(語源由来) 【ことわざ】 山中の賊を破るは易く心中の賊を破るは難し 【読み方】 さんちゅうのぞくをやぶるはやすくしんちゅうのぞくをやぶるはかたし 【意味】 自分の心を律...
 「さ」で始まることわざ
「さ」で始まることわざ「歳寒の松柏」の意味(語源由来・出典) 【ことわざ】 歳寒の松柏 【読み方】 さいかんのしょうはく 【意味】 節操が堅く、困難にあっても屈しないことのたとえ。 【語源・由来】 松や柏が厳寒にも葉の緑を保っているところから...
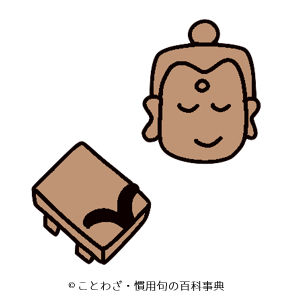 「け」で始まることわざ
「け」で始まることわざ「下駄も阿弥陀も同じ木の切れ」の意味(類義語) 【ことわざ】 下駄も阿弥陀も同じ木の切れ 【読み方】 げたもあみだもおなじきのきれ 【意味】 人の足に踏まれる下駄も、人から頭を下げて拝まれる阿弥陀の像も、どちらも同じ木で...
 「け」で始まることわざ
「け」で始まることわざ「芸は道によって賢し」の意味 【ことわざ】 芸は道によって賢し 【読み方】 げいはみちによってかしこし 【意味】 物事はその道にある人が一番よくわかっている。商売は道によって賢し。 「芸は道によって賢し」の解説 「芸は道...
 「く」で始まることわざ
「く」で始まることわざ「首振り三年ころ八年」の意味 【ことわざ】 首振り三年ころ八年 【読み方】 くびふりさんねんころはちねん 【意味】 尺八を吹くのに、首を振って音の加減ができるようになるのに三年、さらに細かい指の動きによってころころという...
 「き」で始まることわざ
「き」で始まることわざ「狂瀾を既倒に廻らす」の意味(出典・語源由来) 【ことわざ】 狂瀾を既倒に廻らす 【読み方】 きょうらんをきとうにめぐらす 【意味】 形勢がすっかり悪くなったのを、再びもとに返すたとえ。回瀾を既倒に反すともいう。 【出典...
 「き」で始まることわざ
「き」で始まることわざ「今日の一針明日の十針」の意味(語源由来) 【ことわざ】 今日の一針明日の十針 【読み方】 きょうのひとはりあすのとはり 【意味】 処置が遅れるほど負担がかさむことのたとえ。 【語源・由来】 今日であれば一針縫うことで繕...
 「き」で始まることわざ
「き」で始まることわざ「騏驥も一躍に十歩すること能わず」の意味 【ことわざ】 騏驥も一躍に十歩すること能わず 【読み方】 ききもいちやくにじゅうほすることあたわず 【意味】 よく走るすぐれた馬でも、一回の跳躍で十歩の距離を進むことはできないと...
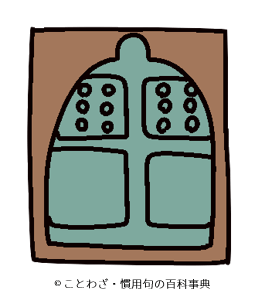 「か」で始まることわざ
「か」で始まることわざ「鐘鋳るまでの土鋳型」の意味 【ことわざ】 鐘鋳るまでの土鋳型 【読み方】 かねいるまでのつちいがた 【意味】 目的を達成するまでの手段として用いるだけのもののこと。また、成功するまでは粗末なもので我慢することをいう。 ...
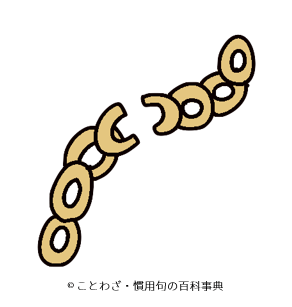 「か」で始まることわざ
「か」で始まることわざ「金の鎖も引けば切れる」の意味 【ことわざ】 金の鎖も引けば切れる 【読み方】 かねのくさりもひけばきれる 【意味】 意志の強い人でも誘惑に負けることがあるというたとえ。また、努力すればできないことはないというたとえ。 ...
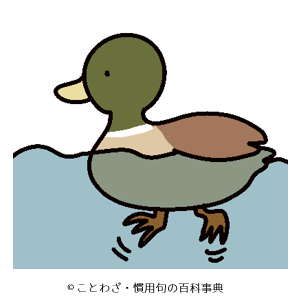 「か」で始まることわざ
「か」で始まることわざ「鴨の水掻き」の意味 【ことわざ】 鴨の水掻き 【読み方】 かものみずかき 【意味】 のんびりと水に浮かぶ鴨も、水面下では絶えず足で水を掻き続けている。転じて、人知れない苦労があるということのたとえ。 「鴨の水掻き」の解...
 「か」で始まることわざ
「か」で始まることわざ「櫂は三年櫓は三月」の意味 【ことわざ】 櫂は三年櫓は三月 【読み方】 かいはさんねんろはみつき 【意味】 櫓の使い方に比べて櫂の使い方の難しいことをいう。櫂と櫓のように、似たようなものであっても習得にかかる時間には差が...
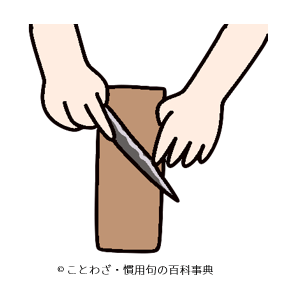 「お」で始まることわざ
「お」で始まることわざ「斧を研いで針にする」の意味(類義語) 【ことわざ】 斧を研いで針にする 【読み方】 おのをといではりにする 【意味】 斧を針の細さにまで研ぐというのは大変なことだが、やる気になれば不可能なことではない。転じて、どんなに...
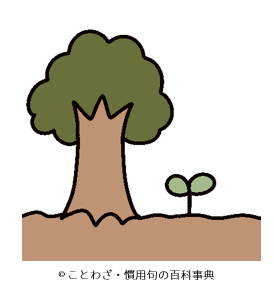 「お」で始まることわざ
「お」で始まることわざ「大木の下に小木育たず」の意味(類義語・対義語) 【ことわざ】 大木の下に小木育たず 【読み方】 おおきのしたにおぎそだたず 【意味】 大きな木の下は日光が遮られ、小さな木は育たない。転じて、権勢のある者の庇護を受けてい...
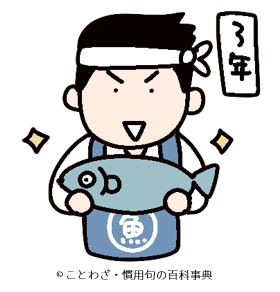 「う」で始まることわざ
「う」で始まることわざ「売り出し三年」の意味(類義語) 【ことわざ】 売り出し三年 【読み方】 うりだしさんねん 【意味】 商売を始めて最初の三年間、しっかりとした商売をすればあとはうまくいくということ。 【類義語】 ・商い三年 「売り出し三...
 「う」で始まることわざ
「う」で始まることわざ「生まれながらの長老なし」の意味(類義語) 【ことわざ】 生まれながらの長老なし 【読み方】 うまれながらのちょうろうなし 【意味】 生まれつき人格や学問のすぐれた人はいない。名僧と呼ばれる人であっても生まれつきの名僧で...
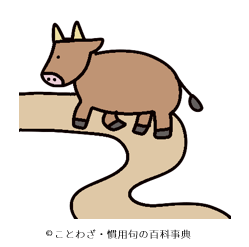 「う」で始まることわざ
「う」で始まることわざ「牛の歩みも千里」の意味(語源由来・類義語) 【ことわざ】 牛の歩みも千里 【読み方】 うしのあゆみもせんり 【意味】 努力を怠らなければ、大きな成果を上げることができるというたとえ。 【語源由来】 牛のような速度でゆっ...
 「い」で始まることわざ
「い」で始まることわざ「一芸は道に通ずる」の意味(類義語) 【ことわざ】 一芸は道に通ずる 【読み方】 いちげいはみちにつうずる 【意味】 一つの芸道について極めた者は、他の分野にも通じる道理を身につけているということ。 【類義語】 ・一芸は...
 「あ」で始まることわざ
「あ」で始まることわざ「鞍上人なく鞍下馬なし」の意味 【ことわざ】 鞍上人なく鞍下馬なし 【読み方】 あんじょうひとなくあんかうまなし 【意味】 馬術の名人が馬を巧みに乗りこなす様子。乗り手と馬の呼吸がぴたりと合っているので、馬は鞍の上に人の...
 「あ」で始まることわざ
「あ」で始まることわざ「粟一粒は汗一粒」の意味 【ことわざ】 粟一粒は汗一粒 【読み方】 あわひとつぶはあせひとつぶ 【意味】 小さな粟一粒であっても、その収穫のためには汗一粒にも当たる労力がかけられているのだから、無駄にしてはいけないという...
 「あ」で始まることわざ
「あ」で始まることわざ「網無くして淵にのぞむな」の意味(語源由来・出典・類義語) 【ことわざ】 網無くして淵にのぞむな 【読み方】 あみなくしてふちにのぞむな 【意味】 十分な準備や用意をしていなければ、成功しないということ。 【語源・由来】...
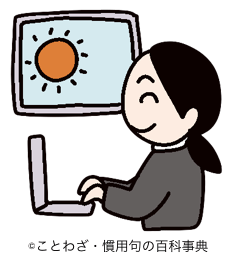 「あ」で始まることわざ
「あ」で始まることわざ「朝の一時は晩の二時に当たる」の意味(類義語) 【ことわざ】 朝の一時は晩の二時に当たる 【読み方】 あさのひとときはばんのふたときにあたる 【意味】 朝は仕事がはかどるので、夜に仕事をするよりも二倍も能率が上がるという...
 「あ」で始まることわざ
「あ」で始まることわざ「朝起き千両夜起き百両」の意味(類義語) 【ことわざ】 朝起き千両夜起き百両 【読み方】 あさおきせんりょうよおきひゃくりょう 【意味】 朝早く起きて働く方が、夜遅くまで起きて仕事をするよりも効率がよく十倍の価値があると...
 「あ」で始まることわざ
「あ」で始まることわざ「商い三年」の意味(類義語・英語) 【ことわざ】 商い三年 【読み方】 あきないさんねん 【意味】 商売で利益を上げるまでには三年かかる、三年は辛抱せよということ。 【類義語】 ・石の上にも三年 ・顎振り三年 ・売出し三...
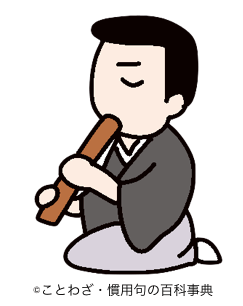 「あ」で始まることわざ
「あ」で始まることわざ「顎振り三年」の意味(語源由来・類義語) 【ことわざ】 顎振り三年 【読み方】 あごふりさんねん 【意味】 何事も身につくようになるまでには、年月を要すること。 【語源由来】 尺八を習得する場合、顎を振って調子をとるコツ...
 「わ」で始まることわざ
「わ」で始まることわざ【ことわざ】 吾日に吾が身を三省す 【読み方】 われひにわがみをさんせいす 【意味】 一日に何度も自分の言行をふりかえってみて、過失のないようにすること。三省。 【出典】 「論語」にある孔子の弟子のことば。「吾日に吾が身...
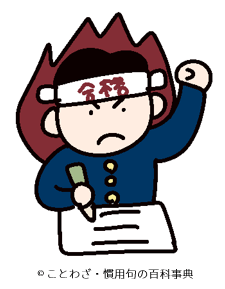 「わ」で始まることわざ
「わ」で始まることわざ【ことわざ】 吾十有五にして学に志す 【読み方】 われじゅうゆうごにしてがくにこころざす 【意味】 十五歳の時に学問に志しを立てた。「有」は又の意味。十五は大学に入る年。「志学」は学問に志すこと、十五歳の異称。 【出典】...
 「わ」で始まる慣用句
「わ」で始まる慣用句【慣用句】 我関せず 【読み方】 われかんせず 【意味】 自分には関係ない、自分の知ったことではないということ。 「我関せず」の使い方 「我関せず」の例文 クラス中がざわざわしていても、ともこちゃんだけは、我関せずという...
 「わ」で始まる慣用句
「わ」で始まる慣用句【慣用句】 割を食う 【読み方】 わりをくう 【意味】 割に合わない目にあうという意味で、損な立場に立たされる。 「割を食う」の使い方 「割を食う」の例文 いつだって、割を食うのは、健太くんではなく私の方なのです。 健太...
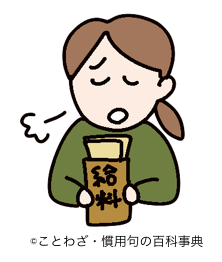 「わ」で始まる慣用句
「わ」で始まる慣用句【慣用句】 割に合わない 【読み方】 わりにあわない 【意味】 損になる。 【類義語】 ・間尺に合わない 【対義語】 ・割に合う ・間尺に合う 「割に合わない」の使い方 「割に合わない」の例文 彼女だって同罪のはずなのに...
 「わ」で始まる慣用句
「わ」で始まる慣用句【慣用句】 割に合う 【読み方】 わりにあう 【意味】 努力や苦労に見合うだけの利益がある。 【類義語】 ・間尺に合う 【対義語】 ・割りに合わない ・間尺に合わない 「割に合う」の使い方 「割に合う」の例文 その職には...
 「わ」で始まる慣用句
「わ」で始まる慣用句【慣用句】 割がいい 【読み方】 わりがいい 【意味】 ほかと比べて得である、有利である。 【対義語】 割が悪い 「割がいい」の使い方 「割がいい」の例文 時給千円と割がいい夜九時くらいから十二時までの夜番のアルバイトを...
 「わ」で始まる慣用句
「わ」で始まる慣用句【慣用句】 わびをいれる 【読み方】 わびをいれる 【意味】 謝罪を申し入れる。あやまる。 「詫びを入れる」の使い方 「詫びを入れる」の例文 主人の部屋に入ると、彼は書類に向かっていたので、私は仕事の邪魔をしたと思い、詫...
 「わ」で始まる慣用句
「わ」で始まる慣用句【慣用句】 渡りを付ける 【読み方】 わたりをつける 【意味】 話し合いなどをするために、前もって連絡をとっておく。「渡り」は、二つの間にかけ渡すもの。 「渡りを付ける」の使い方 「渡りを付ける」の例文 彼は、友人の国会...
 「わ」で始まることわざ
「わ」で始まることわざ【ことわざ】 我が田へ水を引く 【読み方】 わがたへみずをひく 【意味】 物事を自分の利益になるように強引に取り計らうこと。 【語源・由来】 自分の田に水を引くという意味から。 【同義語】 我田引水 「我が田へ水を引く」...
 「わ」で始まる慣用句
「わ」で始まる慣用句【慣用句】 我が意を得たり 【読み方】 わがいをえたり 【意味】 ものごとが自分の考えや気持ちとぴったり合っているということ。自分の思い通りになって気分をよくするようすをいう。 「我が意を得たり」の使い方 「我が意を得た...
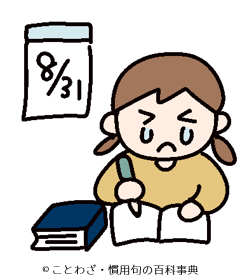 「わ」で始まることわざ
「わ」で始まることわざ【ことわざ】 若い時の辛労は買うてもせよ 【読み方】 わかいときのしんろうはこうてもせよ 【意味】 若い時に苦労することはよい経験であり、将来きっと役に立つから、買って出ても苦労したほうがよいという教え。 【類義語】 ・...
 「ろ」で始まる慣用句
「ろ」で始まる慣用句【慣用句】 論を俟たない 【読み方】 ろんをまたない 【意味】 論じるまでもなく、明白である。言うまでもない。 「論を俟たない」の使い方 「論を俟たない」の例文 彼が世界一腕のいい医者であることは、論を俟たないので、安心...
 「ろ」で始まることわざ
「ろ」で始まることわざ【ことわざ】 論陣を張る 【読み方】 ろんじんをはる 【意味】 論理を組み立てて議論を展開すること。 「論陣を張る」の使い方 「論陣を張る」の例文 公文書の「書き換え」か「改ざん」かで、政府擁護の論陣を張る新聞と、そうで...
 「ろ」で始まることわざ
「ろ」で始まることわざ【ことわざ】 露命を繋ぐ 【読み方】 ろめいをつなぐ 【意味】 露のようにはかない命をやっと繋いでいるという意味で、困窮しながらもどうにかこうにか生活しているたとえ。 【類義語】 ・粥をすすって露命を繋ぐ 「露命を繋ぐ」...
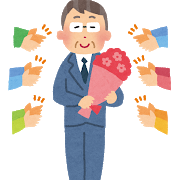 「ろ」で始まる慣用句
「ろ」で始まる慣用句【慣用句】 労を多とする 【読み方】 ろうをたとする 【意味】 相手の働きや骨折りに感謝する言葉。「多とする」は労力や好意がふつう以上であるという意味で、感謝するときに用いる。 「労を多とする」の使い方 「労を多とする」...
 「ろ」で始まる慣用句
「ろ」で始まる慣用句【慣用句】 労を惜しまない 【読み方】 ろうをおしまない 【意味】 努力を苦にせず、一生懸命に取り組むこと。 「労を惜しまない」の使い方 「労を惜しまない」の例文 得点力はあまり高くないもののチームのために労を惜しまない...
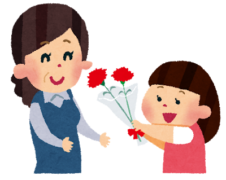 「ろ」で始まる慣用句
「ろ」で始まる慣用句【慣用句】 労に報いる 【読み方】 ろうにむくいる 【意味】 他人からしてもらった物事に対して、それに見合うようなお返しをする。 「労に報いる」の使い方 「労に報いる」の例文 一年頑張ってくれた社員の労に報いるために、毎...
 「ろ」で始まることわざ
「ろ」で始まることわざ【ことわざ】 労して功無し 【読み方】 ろうしてこうなし 【意味】 苦労したのに報われず、何の得もないということ。 【出典】 荘子 【類義語】 ・労あって功なし ・労多くして功少なし ・灯心で竹の根を掘る ・骨折り損のく...
 「れ」で始まる慣用句
「れ」で始まる慣用句【慣用句】 歴とした 【読み方】 れっきとした 【意味】 みんなから認められて、はっきりとしていること。 【語源由来】 「歴(れき)とした(=はっきりした)」が変化したことば。 「歴とした」の使い方 「歴とした」の例文 ...
 「れ」で始まることわざ
「れ」で始まることわざ【ことわざ】 例によって例の如し 【読み方】 れいによってれいのごとし 【意味】 いつものとおりである。相変わらずのありさまである。 「例によって例の如し」の使い方 「例によって例の如し」の例文 着替えを済ませて居間に行...
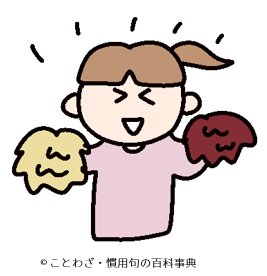 「る」で始まることわざ
「る」で始まることわざ【ことわざ】 坩堝と化す 【読み方】 るつぼとかす 【意味】 熱く激しい気分がみなぎっている。興奮が高まっている。 【語源・由来】 「坩堝(るつぼ、かんか)」とは化学実験などで、物質を溶融し、または焙焼する場合に用いる耐...
 「り」で始まる慣用句
「り」で始まる慣用句【慣用句】 両肌を脱ぐ 【読み方】 りょうはだをぬぐ 【意味】 ①衣の上半身全部を脱いで、両肌を現す。 ②全力を尽くし、事に当たる。 【類義語】 ・諸肌を脱ぐ 「両肌を脱ぐ」の使い方 「両肌を脱ぐ」の例文 足腰が弱ってい...
 「り」で始まることわざ
「り」で始まることわざ【ことわざ】 梁上の君子 【読み方】 りょうじょうのくんし 【意味】 泥棒のこと。転じて、鼠のこともいう。 【出典】 後漢書 【故事】 中国、後漢の陳寔が梁の上に隠れている泥棒をさして、「人間は悪を行うことが癖になると、...
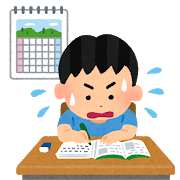 「り」で始まる慣用句
「り」で始まる慣用句【慣用句】 理の当然 【読み方】 りのとうぜん 【意味】 理屈から見て確かにそうであること。当たり前のこと。 「理の当然」の使い方 「理の当然」の例文 今までの彼の生活態度から言って、両親に信用してもらえないのは理の当然...
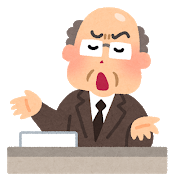 「り」で始まる慣用句
「り」で始まる慣用句【慣用句】 理に落ちる 【読み方】 りにおちる 【意味】 話が理屈っぽくなる。 「理に落ちる」の使い方 「理に落ちる」の例文 二人の会話がいつの間にか、理に落ちてしまってつまらなくなったので、今日はお開きにすることにしま...
 「ら」で始まる慣用句
「ら」で始まる慣用句【慣用句】 濫觴 【読み方】 らんしょう 【意味】 流れの源。転じて、物事の起源のこと。 【語源・由来】 「濫」はあふれること。「觴」はさかずき。孔子が弟子の子路を戒めて、「揚子江も源までさかのぼればさかずきにあふれる程...
 「ら」で始まることわざ
「ら」で始まることわざ【ことわざ】 らっぱを吹く 【読み方】 らっぱをふく 【意味】 大きな事を言う。ほらを吹く。大言壮語する。 【類義語】 ・ほらを吹く ・大きな口をきく ・大言壮語 ・大風呂敷を広げる 「らっぱを吹く」の使い方 「らっぱを...
 「ら」で始まる慣用句
「ら」で始まる慣用句【慣用句】 埒も無い 【読み方】 らちもない 【意味】 筋道が立ってなく、まとまりがない。くだらない。 「埒も無い」の使い方 「埒も無い」の例文 ともこちゃんは、そんな埒も無いうわさを信じるような人ではないので大丈夫だと...
 「よ」で始まることわざ
「よ」で始まることわざ【ことわざ】 夜を日に継ぐ 【読み方】 よをひにつぐ 【意味】 夜の時間を昼の時間に継ぎ足してということで、一日中通して。 【出典】 『孟子』 【類義語】 ・昼夜兼行(ちゅうやけんこう) ・不眠不休(ふみんふきゅう) 「...
 「よ」で始まる慣用句
「よ」で始まる慣用句【慣用句】 夜を徹する 【読み方】 よをてっする 【意味】 一晩中寝ないで物事をする。徹夜する。 「夜を徹する」の使い方 「夜を徹する」の例文 夜を徹して、白熱した議論が交わされると思うから、今日は、そのまま会場のホテル...
 「よ」で始まる慣用句
「よ」で始まる慣用句【慣用句】 世を憚る 【読み方】 よをはばかる 【意味】 世間に遠慮するという意味で、ひっそりと目立たずに生活する。 「世を憚る」の使い方 「世を憚る」の例文 長年、世を憚って一人暮らしをしていたため、独り言が癖になって...
 「よ」で始まる慣用句
「よ」で始まる慣用句【慣用句】 世を忍ぶ 【読み方】 よをしのぶ 【意味】 世間に知られないようにする。人目を避けて隠れる。 「世を忍ぶ」の使い方 「世を忍ぶ」の例文 その女優は、晩年は田舎で世を忍び、農業をしながら暮らしていたそうです。 ...
 「よ」で始まる慣用句
「よ」で始まる慣用句【慣用句】 弱音を吐く 【読み方】 よわねをはく 【意味】 弱気なことや、意気地のないことを言う。 【類義語】 音を上げる 「弱音を吐く」の使い方 「弱音を吐く」の例文 頑張り屋のともこちゃんが弱音を吐くのを今まで聞いた...
 「よ」で始まる慣用句
「よ」で始まる慣用句【慣用句】 夜の帳 【読み方】 よるのとばり 【意味】 夜の闇のこと。「帳」は、室内を隔てるのに垂らす布。「夜の帳が下りる」の形で使われることが多い。 「夜の帳」の使い方 「夜の帳」の例文 目が覚めて外を見て見ると、日は...
 「よ」で始まることわざ
「よ」で始まることわざ【ことわざ】 寄ると触ると 【読み方】 よるとさわると 【意味】 いっしょに集まればいつでも。 「寄ると触ると」の使い方 「寄ると触ると」の例文 もちろん知っていますわ、東京中どこへ行っても、寄ると触るとこの噂で持ち切り...
 「よ」で始まることわざ
「よ」で始まることわざ【ことわざ】 夜も日も明けない 【読み方】 よもひもあけない 【意味】 夜も昼も過ごすことができないということで、あることがらに夢中になり、そのことなしではいきていけないほどである。 「夜も日も明けない」の使い方 「夜も...
 「よ」で始まる慣用句
「よ」で始まる慣用句【慣用句】 呼び水になる 【読み方】 よびみずになる 【意味】 ある物事を引き起こすきっかけとなる。 【類義語】 ・誘い水になる 「呼び水になる」の使い方 「呼び水になる」の例文 すっかり忘れていた一連の事柄が、一つの出...
 「よ」で始まる慣用句
「よ」で始まる慣用句【慣用句】 呼び声が高い 【読み方】 よびごえがたかい 【意味】 評判が高い。うわさされる。 「呼び声が高い」の使い方 「呼び声が高い」の例文 彼が世界記録を持っていた400mでは、大会前から優勝候補の呼び声が高かった。...
 「よ」で始まる慣用句
「よ」で始まる慣用句【慣用句】 世の習い 【読み方】 よのならい 【意味】 世間一般によくあること。 「世の習い」の使い方 「世の習い」の例文 あの時代は、跡を継ぐ者がいなくなれば、養子をもらって店を継がせるのが世の習いでした。 年収が倍に...
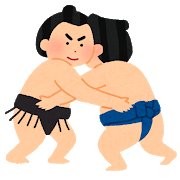 「よ」で始まる慣用句
「よ」で始まる慣用句【慣用句】 四つに組む 【読み方】 よつにくむ 【意味】 相撲で力士が両手を指し合って組む、ということから、双方が正面から堂々と勝負をいどむ。また、ある問題にまともに取り組むこと。 「四つに組む」の使い方 「四つに組む」...
 「よ」で始まる慣用句
「よ」で始まる慣用句【慣用句】 寄ってたかって 【読み方】 よってたかって 【意味】 大勢が一つのことに取りかかるようす。 「寄ってたかって」の使い方 「寄ってたかって」の例文 あんなちっぽけな仕事に五十人の人間が寄ってたかってやるなんて、...
 「よ」で始まることわざ
「よ」で始まることわざ【ことわざ】 与太を飛ばす 【読み方】 よたをとばす 【意味】 でたらめを言う。ふざけてくだらないことを言う。よたる。 【語源由来】 「与太」は、「与太郎」の略で、芸能界で間抜け・うそ・でたらめなどの意味に使われることば...
 「よ」で始まる慣用句
「よ」で始まる慣用句【慣用句】 横を向く 【読み方】 よこをむく 【意味】 拒絶したり、無視したりする。相手にしない。 【類義語】 ・そっぽを向く ・背を向ける 「横を向く」の使い方 「横を向く」の例文 新しく作ったノートが、学生に横を向か...
 「よ」で始まる慣用句
「よ」で始まる慣用句【慣用句】 善かれ悪しかれ 【読み方】 よかれあしかれ 【意味】 よくても悪くても、どちらにしても、絶対に。 「善かれ悪しかれ」の使い方 「善かれ悪しかれ」の例文 自分以外の人間への干渉は、善かれ悪しかれすべて暴力になり...
 「よ」で始まる慣用句
「よ」で始まる慣用句【慣用句】 世が世なら 【読み方】 よがよなら 【意味】 世の中が、その人にとって都合のよい時代だったなら。 【出典】 『史記』 「世が世なら」の使い方 「世が世なら」の例文 あのお方にあんなことをするなんて、世が世なら...
 「よ」で始まる慣用句
「よ」で始まる慣用句【慣用句】 要領を得ない 【読み方】 ようりょうをえない 【意味】 だいじな点がはっきりしなくて、わかりにくい。 【出典】 『史記』 「要領を得ない」の使い方 「要領を得ない」の例文 ともこちゃんの欠席の理由を健太くんに...
 「よ」で始まる慣用句
「よ」で始まる慣用句【慣用句】 要領がいい 【読み方】 ようりょうがいい 【意味】 ①ものごとの処理の方法がうまく、手ぎわがいい。 ②自分が有利になるように巧みに立ち回ることができる。 【対義語】 ・要領が悪い 「要領がいい」の使い方 「要...
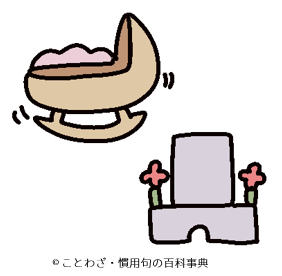 「ゆ」で始まることわざ
「ゆ」で始まることわざ【ことわざ】 揺り籠から墓場まで 【読み方】 ゆりかごからはかばまで 【意味】 人の一生を言い表すことば。生まれてから死ぬまで。 【語源・由来】 1941年に経済学者のベバリッジによって提唱され、イギリスの社会保障政策の...
 「ゆ」で始まることわざ
「ゆ」で始まることわざ【ことわざ】 弓折れ矢尽きる 【読み方】 ゆみおれやつきる 【意味】 力が尽きて、もうどうすることもできない。 【語源・由来】 武器の弓も矢も使えなくなってしまうということから。 【類義語】 ・刀折れ矢尽きる ・万策尽き...
 「ゆ」で始まることわざ
「ゆ」で始まることわざ【ことわざ】 指一本も差させない 【読み方】 ゆびいっぽんもささせない 【意味】 指で差されて、あれこれ言われるようなことをしないということで、人からの非難や干渉はいっさい許さないたとえ。 「指一本も差させない」の使い方...
 「ゆ」で始まることわざ
「ゆ」で始まることわざ【ことわざ】 油断も隙もない 【読み方】 ゆだんもすきもない 【意味】 少しも油断することはできない。油断がならない。 「油断も隙もない」の使い方 「油断も隙もない」の例文 油断も隙もない世の中なので、厳重な金庫を購入し...
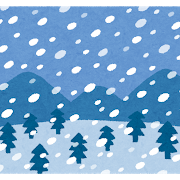 「ゆ」で始まる慣用句
「ゆ」で始まる慣用句【慣用句】 雪を欺く 【読み方】 ゆきをあざむく 【意味】 極めて白いようす。雪と見間違うほど白い。主に女性の肌の白さを雪の白さにたとえていう。 「雪を欺く」の使い方 「雪を欺く」の例文 女優をしている彼女の肌の白さは、...
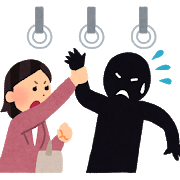 「ゆ」で始まる慣用句
「ゆ」で始まる慣用句【慣用句】 勇を鼓す 【読み方】 ゆうをこす 【意味】 勇気を奮い起こす。「鼓す」は太鼓を叩いて勇気などを奮い起こす意味。 「勇を鼓す」の使い方 「勇を鼓す」の例文 偶然、彼女と三度目に会った時、彼は、勇を鼓して彼女とデ...
 「や」で始まる慣用句
「や」で始まる慣用句【慣用句】 刃に掛かる 【読み方】 やいばにかかる 【意味】 刃物で切り殺される。「刃」は、刃物。 「刃に掛かる」の使い方 「刃に掛かる」の例文 江戸時代、武士より身分が低いとされた農民は、武士の刃に掛かっても文句が言え...
 「や」で始まることわざ
「や」で始まることわざ【ことわざ】 遣らずぶったくり 【読み方】 やらずぶったくり 【意味】 人に何も与えないで、取り上げるだけであること。 「遣らずぶったくり」の使い方 「遣らずぶったくり」の例文 その地域の利益を考えず、デベロッパーの利益...
 「や」で始まる慣用句
「や」で始まる慣用句【慣用句】 遣らずの雨 【読み方】 やらずのあめ 【意味】 帰ろうとする人や出かけようとする人を引き止めるかのように降る雨。 「遣らずの雨」の使い方 「遣らずの雨」の例文 そろそろおいとましようかと席を立ったら、雨が降っ...
 「や」で始まる慣用句
「や」で始まる慣用句【慣用句】 止むを得ない 【読み方】 やむをえない 【意味】 そうするよりほかに方法がない。しかたがない。 「止むを得ない」の使い方 「止むを得ない」の例文 介護や自身の病気など、止むを得ない事情がある場合以外は、原則P...
 「や」で始まる慣用句
「や」で始まる慣用句【慣用句】 止むに止まれぬ 【読み方】 やむにやまれぬ 【意味】 やめようとしても、やめられない。そうしないではいられない。 「止むに止まれぬ」の使い方 「止むに止まれぬ」の例文 このような結果になることを十分承知してい...
 「や」で始まる慣用句
「や」で始まる慣用句【慣用句】 やぶさかでない 【読み方】 やぶさかでない 【意味】 努力を惜しまない。喜んでする。「やぶさか」は、物惜みするようす。 「やぶさかでない」の使い方 「やぶさかでない」の例文 自分の誤りが明らかであればそれを認...
 「や」で始まることわざ
「や」で始まることわざ【ことわざ】 矢でも鉄砲でも持って来い 【読み方】 やでもてっぽうでももってこい 【意味】 どんなことをしてでもかかって来い、負けないぞ。覚悟したときや、やけになったときに使うことば。 「矢でも鉄砲でも持って来い」の使い...
 「や」で始まる慣用句
「や」で始まる慣用句【慣用句】 易きに付く 【読み方】 やすきにつく 【意味】 楽で易しいほうを選ぶ。「易き」は、たやすいこと。 「易きに付く」の使い方 「易きに付く」の例文 一度、易きに付くことを覚えたものは、決して、困難な道を歩もうとは...
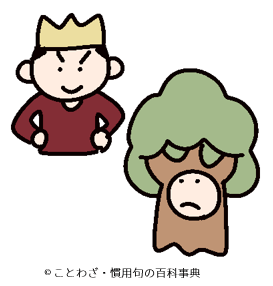 「や」で始まることわざ
「や」で始まることわざ【ことわざ】 役者が一枚上 【読み方】 やくしゃがいちまいうえ 【意味】 人物・知略・駆け引きなどにおいて、一段とすぐれていること。 【語源・由来】 芝居の番付や看板では上位から役者名が記されるところから。 【類義語】 ...
 「や」で始まることわざ
「や」で始まることわざ【ことわざ】 焼き餅を焼く 【読み方】 やきもちをやく 【意味】 嫉妬する。嫉妬 (しっと) するという意味の「妬く」に「焼く」を掛けて、餅を添えていった言葉。 「焼き餅を焼く」の使い方 「焼き餅を焼く」の例文 私の彼氏...
 「も」で始まることわざ
「も」で始まることわざ【ことわざ】 もんどりを打つ 【読み方】 もんどりをうつ 【意味】 とんぼ返りをする。宙返りをする。もんどりうつ。「もんどり」は「翻筋斗(もどり)」の音が変化したもの。空中でからだを1回転させること。とんぼ返り。宙返りの...
 「も」で始まる慣用句
「も」で始まる慣用句【慣用句】 門外漢 【読み方】 もんがいかん 【意味】 その部門のことを専門にしていない人。そのことに直接関係のない人。 「門外漢」の使い方 「門外漢」の例文 デザインについて門外漢の僕にも、店員の表情が曇ったことから...
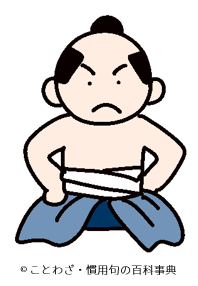 「も」で始まることわざ
「も」で始まることわざ【ことわざ】 諸肌を脱ぐ 【読み方】 もろはだをぬぐ 【意味】 着物の両方の袖を脱いで自由に動け、力が十分出せるようになるということから、全面的に協力することのたとえ。 「諸肌を脱ぐ」の使い方 「諸肌を脱ぐ」の例文 会社...
 「も」で始まる慣用句
「も」で始まる慣用句【慣用句】 物を言う 【読み方】 ものをいう 【意味】 いざというときに効果を表す。 【類義語】 ・物を言わせる 「物を言う」の使い方 「物を言う」の例文 肩書きが物を言う世界だから、彼一人じゃ出来ないことも社長の肩書き...
 「も」で始まる慣用句
「も」で始まる慣用句【慣用句】 物は言いよう 【読み方】 ものはいいよう 【意味】 同じことでも、言い方によって相手の受け取り方が違う。話し方が悪いと、まとまるべき話もまとまらない場合などにいう。 【類義語】 ・丸い卵も切りようで四角 ・物...
 「も」で始まる慣用句
「も」で始まる慣用句【慣用句】 物の用 【読み方】 もののよう 【意味】 なんらかの役。 「物の用」の使い方 「物の用」の例文 集まってきた人たちは、口々に騒ぐだけで、何の手助けもしてくれなくて、物の用をなさなかった。 今日乗ってきたのは、...
 「も」で始まる慣用句
「も」で始まる慣用句【慣用句】 物ともしない 【読み方】 ものともしない 【意味】 問題にもしない。なんとも思わない。 「物ともしない」の使い方 「物ともしない」の例文 祖父という人間は、周囲の反対を物ともしないでひたすら意志を通した格好い...
 「も」で始まる慣用句
「も」で始まる慣用句【慣用句】 物心が付く 【読み方】 ものごころがつく 【意味】 幼児期を過ぎて、世の中のいろいろなことがなんとなくわかりはじめる。 「物心が付く」の使い方 「物心が付く」の例文 お兄ちゃんとは12歳も年が離れているので、...
 「も」で始まる慣用句
「も」で始まる慣用句【慣用句】 物が分かる 【読み方】 ものがわかる 【意味】 人情や道理を心得ている。 「物が分かる」の使い方 「物が分かる」の例文 おじいちゃんは、若いころ苦労したらしく、物が分かるので、道に逸れたことをしない限りは、い...
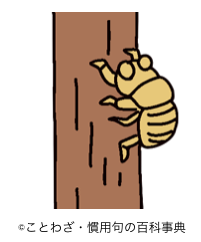 「も」で始まる慣用句
「も」で始まる慣用句「もぬけの殻」の意味 【慣用句】 もぬけの殻 【読み方】 もぬけのから 【意味】 人が逃げ出した後の寝床や家。「もぬけ」は脱皮すること。また、その皮。 「もぬけの殻」の解説 「もぬけの殻」の使い方 「もぬけの殻」の例文 ...
 「も」で始まる慣用句
「も」で始まる慣用句【慣用句】 元を取る 【読み方】 もとをとる 【意味】 それまでに費やした金銭を回収すること。元金を取り返すこと。 「元を取る」の使い方 「元を取る」の例文 あのスーパーは安いけれども年会費が掛かるので、元を取るには、た...
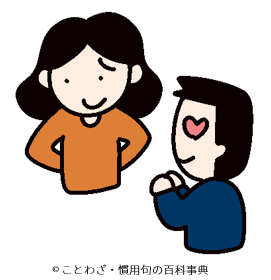 「も」で始まることわざ
「も」で始まることわざ【ことわざ】 勿体を付ける 【読み方】 もったいをつける 【意味】 何かありそうな気配やそぶりを見せ、相手をじらす。必要以上に重々しい態度をとる。「勿体」は、本来は「物体」で、物の本体の意味。態度などが重々しいこと。 【...
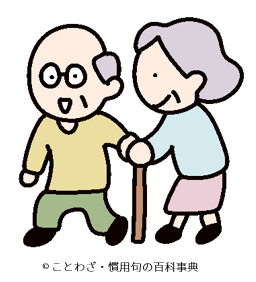 「も」で始まることわざ
「も」で始まることわざ【ことわざ】 持ちつ持たれつ 【読み方】 もちつもたれつ 【意味】 互いに助け合って、両者が成り立つこと。 「持ちつ持たれつ」の例文 「持ちつ持たれつ」の例文 持ちつ持たれつの関係で商売をしている間は、両者の関係はうまく...
 「も」で始まる慣用句
「も」で始まる慣用句【慣用句】 藻屑となる 【読み方】 もくずとなる 【意味】 海中の藻などのくずとなるということで、海で死ぬことをたとえたことば。 「藻屑となる」の使い方 「藻屑となる」の例文 泳げないのに海水浴に行きたいだなんて、海の藻...
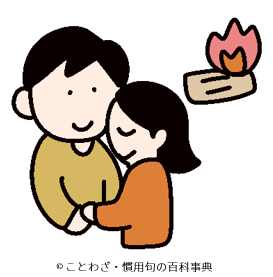 「も」で始まることわざ
「も」で始まることわざ【ことわざ】 燃え杭には火が付きやすい 【読み方】 もえぐいにはひがつきやすい 【意味】 燃え残りの杭は簡単に火がつくことから、一度途絶えた関係はもとに戻りやすいというたとえ。多く、男女関係に使う。 【語源・由来】 「燃...
 「も」で始まることわざ
「も」で始まることわざ【ことわざ】 蒙を啓く 【読み方】 もうをひらく 【意味】 知識がなく道理を知らない者を教え導く。啓蒙(けいもう)する。 【語源・由来】 「啓蒙(けいもう)」を訓読したもの。 「蒙を啓く」の使い方 「蒙を啓く」の例文 こ...
 「め」で始まることわざ
「め」で始まることわざ【ことわざ】 面目次第も無い 【読み方】 めんぼくしだいもない 【意味】 申し訳が立たず顔向けできない。めんぼくない。「面目次第」は「面目」を強めた語。世間に対する体面や名誉のこと。 「面目次第も無い」の使い方 「面目次...
 「め」で始まる慣用句
「め」で始まる慣用句【慣用句】 目を遣る 【読み方】 めをやる 【意味】 視線をその方に向ける。その方を見る。 「目を遣る」の使い方 「目を遣る」の例文 振り返って母に目を遣ると、まだソファで横になっていたので、頭の痛みがひいていないようで...
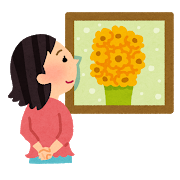 「め」で始まる慣用句
「め」で始まる慣用句【慣用句】 目を養う 【読み方】 めをやしなう 【意味】 良し悪しを判断する力を付ける。 「目を養う」の使い方 「目を養う」の例文 幼稚園に通うお母さんたちをたくさん見て、目を養ってきた園の先生の洞察力には、思わず脱帽し...
 「め」で始まる慣用句
「め」で始まる慣用句【慣用句】 目を伏せる 【読み方】 めをふせる 【意味】 視線をそらして下を向く。伏し目になる。 【類義語】 目を落とす 「目を伏せる」の使い方 「目を伏せる」の例文 ともこちゃんは、僕のことをチラリと見て目を伏せる仕草...
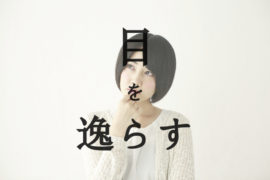 「め」で始まる慣用句
「め」で始まる慣用句【慣用句】 目を逸らす 【読み方】 めをそらす 【意味】 ①別の方向に視線を向ける。 ②直面している事柄を見ないようにする。 「目を逸らす」の使い方 「目を逸らす」の例文 健太くんは、私の質問には直接答えず、やや困ったよ...
 「め」で始まる慣用句
「め」で始まる慣用句【慣用句】 目を背ける 【読み方】 めをそむける 【意味】 ①見ていられなくて、視線をそらす。 ②関わり合いになることを避ける。逃避する。 【対義語】 目を注ぐ 「目を背ける」の使い方 「目を背ける」の例文 人間誰だって...
 「め」で始まる慣用句
「め」で始まる慣用句【慣用句】 目を掠める 【読み方】 めをかすめる 【意味】 人に見つからないように、すきを見てこっそりと行う。 【類義語】 目を盗む 「目を掠める」の使い方 「目を掠める」の例文 敵の目を掠めて、敵が大事にしていた黄金の...
 「め」で始まる慣用句
「め」で始まる慣用句【慣用句】 目端が利く 【読み方】 めはしがきく 【意味】 その場に応じてよく才知が働く。機転がきく。 【類義語】 目先が利く 「目端が利く」の使い方 「目端が利く」の例文 ともこちゃんは目端が利く女性だから、彼女にすべ...
 「め」で始まる慣用句
「め」で始まる慣用句【慣用句】 目の覚めるような 【読み方】 めのさめるような 【意味】 眠気を覚ますようなという意味で、鮮やかさや目新しさにはっと驚くようす。 「目の覚めるような」の使い方 「目の覚めるような」の例文 目の覚めるような美人...
 「め」で始まる慣用句
「め」で始まる慣用句【慣用句】 目に物を言わす 【読み方】 めにものをいわす 【意味】 目つきで人に気持ちを伝える。 【類義語】 ・目で物を言う ・目が物を言う 「目に物を言わす」の使い方 「目に物を言わす」の例文 店内で騒いでいる子供たち...